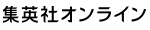1970年代よりマンガ界の最前線で活躍した一条ゆかり、もりたじゅん、池田理代子、秋本治、そしてちばてつやとの温かな交流。マンガ家・里中満智子が自身の半生を振り返った『漫画を描く 凜としたヒロインは美しい』より一部抜粋、再構成してお届けする。
#1
#3
少女マンガ家仲間のこと
『有閑倶楽部』や『砂の城』の一条ゆかりさんは、ずっと「りぼん」で作品を描かれていましたが、最初、私のアシスタントになりたいといって講談社にいらしたのです。
だけど作品を見たらとても上手で、アシスタントどころじゃない。「これはもう、即デビューだ、アシスタントのレベルじゃない」と思い、お断りしました。だけど彼女は未だに冗談で「アシスタントにしてくれなかった」と言うのです。
一条さんは、私よりひとつ年下なのですが、若いときからおしゃれで元気いっぱいでした。『クレオパトラ』を描いているとき、電話がかかってきたのですが、私は締切間際でもう眠くてヘロヘロでした。「じゃあ手伝いに行くよ」とバイクを飛ばして来てくれたこともあります。彼女は月刊誌連載だったから、月のうち半分は集中して描いて、残りは気分転換できていたようです。
他社で描いている人たちとも知り合ったのが、25歳頃でした。池田理代子さん、木原敏江さん、もりたじゅんさんなどです。作品をよく知っている人だと、初めて会った気がしないし、ワクワクしたものですね。
池田さんと初めて会ったときは「うわあ!」と興奮して、「あれを描いたいきさつはどうだったの?」なんて質問し合って、そのまま延々と朝の4時くらいまでお喋りし続けました。最初は喫茶店に行くのですが、そのうちお店が閉まってしまうので、うちに来て話し込んで。当時は本当に元気でしたね、朝まで喋って、そのまま仕事をしていましたから。
同じ出版社で描いていると何かとつながりが多く、同世代と仕事のことを話すのが良い刺激になります。青池保子さん、大和和紀さんが上京してきてからは、よくお喋りしていました。会って話すだけでは飽きたらず、夜中の長電話もしょっちゅうでした。若かったあの頃は本当に体力があり、徹夜で疲れていてもお喋りしていると目が覚めたものです。
編集部に顔を出していたことで、思い出すことがもうひとつあります。
「別冊少女フレンド」だったでしょうか、編集長が「これどう思う? すごく新感覚でいいだろ? この子、ほかの編集部に渡したくないから、ちょっと口説いてよ」と言うのです。家に電話するから、本人が出たら私が電話に代わって「この雑誌で描くのが良い」と誘ってくれと。それが吉田まゆみさんでした。
私もすごくドキドキして、「怖がられたらどうしよう、どういう風に言ったら、いい感じで来てくれるかしら」なんて考えていました。そのときはご自宅にいらっしゃらなくて、お話はしなかったのですが。
編集者は、有望な新人が連載をはじめると、「先輩に挨拶しなさい」なんて連れてくることがありました。先輩だなんて偉そうなのはいやなのですが、地方から出てくると心細いですよね。私もそうだったからよく分かります。それでお話ししたり、「新人賞の読み切り見たよ、頑張ってね」と励ましたりはしました。私も先輩方からそうやって言ってもらいましたから。
『こち亀』の秋本治先生からのファンレター
庄司陽子さんとも同じ雑誌で描いていたので、なにかとお喋りすることが多いです。
はじめて会ったときから明るくて元気いっぱいな庄司陽子さんと今話すのは、お互いに「あそこがいたい、ここが苦しい」と、病気の話がメインになってしまいました。「年とっちゃったわねぇ」「私より長生きしてね」などなど話し合っています。
昔は「どこの編集部が待遇がいい」とか「個々の契約でこんなことを言われた」なんて仕事、特に契約に関する情報交換が多かったものです。一条ゆかりさんやもりたじゅんさん、池田理代子さんあたりの集英社系のマンガ家さんとは、ガス抜きというか、他社情報を交換していました。
週刊誌だと、急いで決断しなければいけないことも多いのですが、同じ雑誌でネタやキャラクターの名前がかぶるといけないので、そんな調整もしていました。「この名前をつけようと思って」「あ、それ予告に入れちゃった」なんて話し合うのです。
80年代はどんどん雑誌ができて、大人向けのレディースマンガができてきた頃ですから、創刊された雑誌に描くか相談したり、「みんな重たい話が多いよね、ちょっと軽いのがあったほうがよくない?」なんて編集が調整するべき内容を心配してみたり。
誰だってしんどいときはありますが、みんな、しんどいとか辛いとか言いませんでした。やっぱり自分で選んだ仕事ですから、肝が据わっているのです。口では「好きでやってるんじゃない」なんて言いながら、努力しているんですよね。
それから『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の秋本治さんがデビュー当時にファンレターをくださったそうです。
「自分もマンガ家を目指そうと思いました」という手紙を読むと、すごく嬉しくて、私はお返事も出したらしいんですけど、覚えていなくて。秋本さんからずっとあとになってビッグになってお目にかかったとき、「僕ね、ファンレター出してお返事もらったんですよ」と教えていただきました。
女子の気持ちを誰より理解していた、ちばてつや先生
19歳になる頃、同好会で一緒に映画をよく観ていた高校時代からの親友が、大阪から上京しました。周囲にいるすべての人を明るい気持ちにする天使のような存在でした。一緒に住むことにしたのですが、彼女は仕事を決めていなかったので、アルバイト先に講談社の「少女フレンド」編集部を紹介しました。
やがて彼女は、仕事でちばてつや先生のお宅に出入りするようになり、弟さんと結婚します。『キャプテン』『プレイボール』などの名作を残したマンガ家、ちばあきおさんです。一緒にマンガを読んでいた彼女が、まさか将来ちば先生を「お義兄さん」と呼ぶようになるとは思わなかったので、羨ましかったですね。
この2人のデートに、くっついていったことがあります。高級車のベンツに初めて乗りました。ちなみに私は、ちばてつや先生を、長い間女性だと勘違いしていたのです。
ちば先生は少女マンガ雑誌でデビューなさって、ずっと少女マンガを描いていらっしゃいました。当時の男の人が考える女の子は、か弱くて、守ってあげたくて、すぐ泣いて、悲しいさだめにシクシク泣いて、ひたすら我慢して耐えるようなヒロインばかりでした。
昔の少女マンガには、継母にいじめられたヒロインがメソメソ泣くというパターンがあって、私はそれが嫌いでした。もう、シンデレラだらけ。でもちば先生の少女マンガのヒロインは、生き生きして、素晴らしかったのです。男に負けずに堂々と自分の道をいく少女を描いていらした。
私は「女子の本音を誰より理解しているから、作者は女性」「ちばてつやってかっこいい名前だからきっとペンネームだろう」「男性のペンネームを使った女性のマンガ家だろう」と思い込んでいました。昔は情報が全然なくて、雑誌に載っているのも切手大の自画像くらい。自画像なんてどうにでも描けますから、参考になりません。
中学1年生の頃、「少女クラブ」の片隅にちば先生の写真が載ったことがありました。当時の新聞の写真はすごく目が粗かったのですが、目を細めて一生懸命見ても、何かおじさんっぽい。おかしいな……と思いました。
当時、美輪明宏さんが丸山明宏という名前で、シャンソンを歌ってデビューなさいました。お人形のように美しい、美少年というか美少女というか。キャッチフレーズは「シスターボーイ」でした。だから私は、ちば先生はシスターボーイなのだろうと。
「丸山明宏さんは、体つきも細くて顔もきれいで、絵に描いたような美しさだけれども、ちば先生は身体は男で心が女なのだろう」と勝手に思っていたのです。
そうしたら、マンガページの隅に「ちばてつや先生が結婚なさいました」という情報が出たのです。おかしいなと思って。世を忍ぶ仮の姿で結婚する人も、子どもが欲しくて結婚する人もいるし、それかもと納得させました。我ながらしつこいですね。
私自身がデビューして、ちば先生とお目にかかれるようになって、かなり親しくなってようやく言えました。
「昔、私、先生のことをシスターボーイだと思っていたのです。だって、先生の描く少女マンガの中の女の子がものすごくリアルで本当に嬉しくて、これは女の子の気持ちを体験した人じゃないと描けないと思ったのです」と言ったら、
「ははは、そう。まあ多少その気はあるかもね、皆少しずつあるからね」と言われました。「そうですね、私はかなり男入ってますし」と言ったら「そうだね」って。
ちば先生とは、今では家族ぐるみのお付き合いをする仲になりました。父同士が親しくて、しばしばゴルフをご一緒させていただきました。
ご本人は『紫電改のタカ』『ハリスの旋風』『あしたのジョー』などの大ヒット作からも伝わるとおりの、優しくて、まっすぐな方です。私は「歩く性善説」と呼んでいます。
文/里中満智子
#1 「なぜ自分が少女マンガなんかの担当に」マンガ家・里中満智子が目撃した1970年代の現場…編集者はおじさんばかりで、マンガが下に見られていた時代
#3 なぜ少年マンガからメガヒットが生まれるのか? マンガ家・里中満智子が、男性読者の傾向に笑ってしまった瞬間「みんな戦いに勝ったシーンを気に入る」
『漫画を描く 凜としたヒロインは美しい』(中央公論新社)

「すべてのマンガ文化を守りたい」との想いを胸に走り続けてきた75年の半生を自ら振り返り、幼少期から現代、そして未来への展望までを綴る。
高校生にしてプロの漫画家デビューを果たした著者だが、決して順風満帆ではなく、ジェンダーギャップで叱責をあびたり、読者からの抗議を受けたり、がんを患ったり、まるで朝ドラを見ているような半生が、これでもかと詰められている。顔の広かった著者ならではの、レジェンドのマンガ家たちとのやりとりも、多数収録。
当時を知る人には共感を、当時を知らない世代には新しい発見をもたらす1冊。