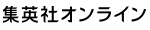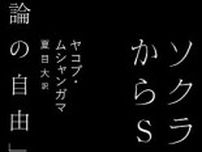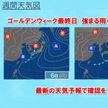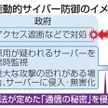ノンフィクション本の新刊をフックに、書評のような顔をして、そうでもないコラムを藤野眞功が綴る〈ノンフィクション新刊〉よろず帳。今回は、元判事のジェド・S・レイコフによる『なぜ、無実の人が罪を認め、犯罪者が罰を免れるのか』(中央公論新社)を紹介する。
内容の核心は、タイトルの通り。少なからぬ読者がぼんやりイメージする「どういうわけだか、金持ちとセレブは罰を受けない国」の司法の歪みを、これでもかと抉り出す。もちろん、話はそこにとどまらず……。
法律と道徳
法律は「正しさ」を担保する、のではない。法律の許す範囲と正しさの範囲が寸分の狂いなく重なるなら、法改正という行為は存在し得ないからである。
もしも法律に間違いがないのなら、人間を奴隷として所有する行為は責められるようなものではなく、両手の親指の先、ふっくら盛り上がった桃色の肉と爪の間にゆっくり、深く、容赦なく裁縫針の先を押し込んでいく拷問も悪くない。違う。そうはならない、というのであれば、つまり我々の眼前にはしばしば「誤った法律」が現れていることになる。
しかし、法律における「誤り」とは何だろう。一瞬でもその点に思いを致せば、「法律と道徳は別物である」と単純に決めつけてしまうことは虚しい。両者の関係はまだらに重なっている程度だが、法律が道徳的な正しさ(を実現することへの欲求や信頼)を背景として一般国民に遵守されている実態を、真向うから否定する専門家は少ないのではないか。
司法は独立しているか
近代民主国家を支える骨格は三権分立と呼ばれるが、国民がその権力を付託する三者は必ずしも対等な権力を有しているわけではない。いわゆる三権のうち、行政権を付託された内閣と、立法権を付託された国会はともに高度な自律性を持つが、司法権を付託されているはずの裁判所には同等の自律性が備わっているとは言い難い面がある。
裁判所そのものはどの省庁にも属していないが、代表的な「司法機関」(法秩序の維持や実践に携わる実力組織)である警察は総務省、検察は法務省といずれも行政機関の傘下に置かれ、司法府の予算も行政府に握られているからだ。これはアメリカも同様で、連邦警察や連邦検察はいずれも司法省の管下にある。
こうした権力の偏在によって生じた司法の機能不全が、ついに行きつくところまで行ってしまったアメリカの状況を詳らかにした1冊が邦訳された。『なぜ、無実の人が罪を認め、犯罪者が罰を免れるのか』(中央公論新社)【1】。著者のジェド・S・レイコフは、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所の元判事である。
本書によれば、ハリウッド映画やドラマの大好物、正義をもたらす舞台装置として描かれる陪審裁判は〈幻想〉に過ぎない。
〈今日のアメリカの刑事司法制度は、建国の父たちが考えていたこと、メディアが描く姿、あるいは平均的なアメリカ人が信じているものとの関連をほとんどとどめていない。建国の父たちにとって、この制度における重要な要素は陪審裁判であった。陪審裁判は、真実を追求するメカニズムとして、また公正さを実現する手段としてだけでなく、専制政治に対する盾としても機能していた(…しかし…)こうした保障に内在するドラマは、映画やテレビ番組では定期的に、裁判官や陪審員の面前の、公開の場で繰り広げられる戦いとして描かれる。しかし、これはすべて幻想だ。実際のところ、アメリカの刑事司法制度は、ほぼ全面的に、密室で交渉され、司法の監督もない司法取引のシステムである〉【2】
日本における司法取引は組織犯罪や経済犯罪、薬物や銃器など特定の犯罪に限られるが、アメリカではすべての犯罪が取引の対象となる。その結果、アメリカでは過去20年間にわたって起訴された連邦刑事事件のうち90%近くが司法取引によって〈解決〉されてしまっているという【3】。
司法取引の闇
では、重大な刑事事件のほとんどを〈解決〉してしまう司法取引の何が問題なのか。レイコフが強調するのは〈起訴の決定という名の下、量刑権を事実上行使する〉のが〈裁判官ではなく検察官〉になってしまっている点である【4】。
1960年代以降に犯罪率が急速に上昇し、警察官の数も検察官の数も、そして裁判官の数も不足したアメリカでは、事件を最終的に〈解決〉する前に、別件に対する処罰で「解決したことにしてしまう」手法が広がりを見せた。簡単にいえば、拷問で自白を取るのと同じだ。
〈例えば、連邦薬物事件で、司法取引を行う場合、検察官は、必要的な最短収容刑期がなく、二年未満のガイドラインの範囲であるヘロイン数オンスの個人売買についてのみ被告人は有罪を認めればよいと弁護人と合意することができる。しかし、もし被告人が有罪を認めなければ、彼の密売量はごく一部であったにもかかわらず、最低一〇年の最短収容刑期と二〇年以上のガイドラインの範囲に該当し得る何キロものヘロインの薬物密売の共謀で起訴されることになる〉【5】
こうして、アメリカでは約220万人以上もの人間が刑務所および拘置所に収容されるに至った。世界のすべての国の刑務所人口の25パーセント近くを、アメリカのそれが占めているのである【6】。
金持ちは逮捕されない、捕まらない、罰を受けない
その一方、不正に手を染めた企業の経営者や幹部として、多額の金銭を蓄財した連中は塀の内側に放り込まれないどころか、訴追すらされず、分厚い財布はそのまま、ぴっちり矯正された不自然な歯列をテラテラと白く塗りたくり、訓練された動物かフィギュア人形のような型通りの笑みを浮かべて、慈善パーティでグラスを掲げている。
ほとんど価値のないクズ同然の金融派生商品を売り続けて大儲けした連中……2008年の〈リーマンショックに関連して見事に訴追された真に高い地位にある重役は一人もおらず、適用可能なすべての犯罪の時効が到来していることを考えると、今後も起訴されないことは明らかである。なぜ、このような事態になったのか、また、長期的かつ超党派的な傾向として、重役を刑事訴追の対象から外そうとする動きがあるのか〉【7】。
レイコフは、このような事態を招いている原因を、警察および検察の捜査手法の変化に見出している。変化というより、怠慢と書くべきか。
企業を舞台としておこなわれた詐欺的事件について、問われてしかるべき個人の責任を突き止める方法は、麻薬王の追跡と似ている。捜査の端緒は、底辺から中堅クラスの構成員を抱き込むことから始まり、何年にも亘って粘り強く証拠を集め、抱き込む対象をだんだんと上層階級に上げ、最終的に親玉を捕まえる【8】。
ところが近年、この熱意と手間と金がかかる社会的正義の追求は放棄され、ホワイトカラーの重大犯罪者たちはぬけぬけと自由を謳歌できるようになってしまった。その新しく、お手軽な手法においては、手間のかかる構成員の「抱き込み」など、始めから実施されないからだ。
儲かるのは、悪者と弁護士だけ
〈【もしも、あなたが検察官だとしたら/評者註】捜査の初期段階であなたは会社を訪ね、詐欺の疑いがある理由を説明する。すると担当者は、会社は協力し、正しいことを行いたいと考えており、そのために元連邦検察官で、現在は著名な法律事務所のパートナーである弁護士を雇い、内部調査を行わせると回答する。会社の顧問弁護士は、会社自身の内部調査の結果をあなたと共有することを条件に、内部調査が終わるまで、あなたの捜査を延期するよう要請する。時間と資源を節約するため、あなたは同意する。
半年後、会社の顧問弁護士が、会社は過ちを犯したが、現在それを是正する意向であることを示す詳細な報告書を持って、戻って来る。そしてあなたと会社は、会社が、経費のかかる内部的な予防措置の強制と、即時の制裁金の支払いと結びついた訴追延期合意を結ぶことで合意する。現実的に、この事件はこれで終結する。あなたは将来の犯罪防止に役立ったと思うのでハッピーだし、会社は壊滅的な起訴を免れたのでハッピーだ。そしておそらく最もハッピーなのは、実際に発端となる不正行為を働いたにもかかわらず、無傷のままに置かれた重役や元重役たちであろう〉【9】
レイコフは、このような手法を〈ハッピー〉とは考えない。本書では他にも、目撃証言やDNA鑑定を代表とする科学捜査に潜む矛盾や問題点、テロとの戦いがもたらした法解釈の歪みなど、さまざまな角度からアメリカの法制度や運用、解釈の異常性を訴えている。
都合のいい武器
では、かの国の法制度が――1周遅れて追随することも少なくない、日本も含めて――正義と公正を取り戻すためには何が必要なのだろうか。レイコフは、行政権と立法権に正面から対抗できる実際的権限を求め、司法にかかわる専門家たちを信頼してほしいと切望する。
その気持ちは理解できる一方、少なからぬ専門家たちが司法を「自らに都合のよい武器」として取り扱っている実態も捨て置けない。近年の注視すべき具体例としては、師岡康子(弁護士)を始めとした司法の専門家たちによる「ヘイト・スピーチ」をめぐる議論の手口が挙げられるだろう。
彼らはしばしば言う。「『米軍出ていけ』という言葉は、ヘイト・スピーチには当たらない」。この手口には、二重の不誠実さがある。ひとつは恣意的な比較だ。
先に触れた師岡は著書『ヘイト・スピーチとは何か』(岩波新書)の中で、自身が共感を寄せる在日朝鮮人という存在に対して向けられた言語表現の一例として〈ゴキブリ朝鮮人〉【10】を挙げる。このフレーズを読んだ者は誰しも、胃の底がむかつくような憤りの感情を覚えるに違いない。それは酷く、醜い言葉であるからだ。
その一方で師岡は、自身が共感を覚えない在日米軍や政治的関係者に向けられた言語表現の一例として〈米軍出ていけ〉【11】というフレーズを挙げる。〈ゴキブリ朝鮮人〉と〈米軍出ていけ〉。誰がどう見ても、悪質なのは前者だという印象を受けるだろうが、これは文字通りの印象操作である。
言葉のすり替え
師岡らは〈米軍出ていけ〉と叫ぶ人々が、同時に〈人殺し〉【12】や〈お前らは犬だから言葉は分からない〉【13】とも叫んでいることを知りながら、知らぬふりを決め込む。〈ゴキブリ朝鮮人〉と〈お前らは犬〉。ゴキブリにも犬にも礼を失した愚かな比喩だが、双方の愚かさと醜さは、これなら釣り合いがとれるかもしれない。
ふたつめの不誠実さは、この同じ穴のむじなの論点をズラし、〈お前らは犬〉だけをなかったことにする手口を指す。似た者同士だと双方を非難する者に対して、師岡らは「日本における米兵や機動隊員はマイノリティではないので、彼らへの非難はヘイト・スピーチには当たらない」【14】と主張するのだ。
これは、言葉のすり替えとしか思えない。そもそも、両者を非難する者たちが使っている「ヘイト(・スピーチ)」は、法律用語としてのヘイト・スピーチを指すのではなく、一般表現としての「憎悪に基づく言葉/尊厳を傷つける醜い言葉」を意味している。その道徳的問いかけに対して、師岡らは法的解釈のみを回答しているからだ。
誤解ではなくすり替えという形で、師岡らはヘイト(・スピーチ)という言葉に付随する「一般表現としての側面」を捨象し、ヘイト(・スピーチ)という言葉を「法律用語としてのヘイト・スピーチ」だけに限定し、特権化しようと試みている。その狙いが、ヘイト(・スピーチ)という言語表現の独占にあるとしか考えられない実態に、評者は危機感を覚える。
権力を欲するのであれば
司法に携わる者は言うだろう。評者の言い分もまた、単なる「道徳的非難」に過ぎない、と。
そんなときは『なぜ、無実の人が罪を認め、犯罪者が罰を免れるのか』の問いかけに立ち戻って考えていただきたい。司法は要件を絞り込み、社会を統治するシステムを効率化するためだけに存在しているのではない。正しさを担保するためにこそ在る。
言論を用いた憎悪の氾濫から、法の権力でもって片一方の者だけを免責するのは、差別からの救済ではなく、検閲だ。評者は、人間社会を構成する根本的価値として「表現の自由」を尊重する立場から、たとえ憎悪に基づく恥ずべき言説であっても、原則として法的規制には反対の立場をとる【15】。
もしも司法の専門家たちが「正義と公正を実現するための権力」を欲するのであれば、「法の許す範囲」と「道徳の許す範囲」をいかにして近接させられるか、その不断の議論を続けることだけが、付託の説得力を醸成するだろう。一体化ではなく、法と道徳の同衾こそ、およその国民が司法に期待する役回りなのだから。
文/藤野眞功
【1】訳者は、川崎友巳+佐藤由梨+堀田周吾+宮木康博+安井哲章。
【2】『なぜ、無実の人が〜』より引用。
【3】『なぜ、無実の人が〜』を参照。司法取引の数字は、1998年から2018年までのもの。〈〉は引用。
【4】『なぜ、無実の人が〜』より引用。
【5】『なぜ、無実の人が〜』より引用。
【6】『なぜ、無実の人が〜』を参照。
【7】『なぜ、無実の人が〜』より引用。
【8】『なぜ、無実の人が〜』を参照。
【9】『なぜ、無実の人が〜』より引用。
【10】師岡康子『ヘイト・スピーチとは何か』(岩波新書)より引用。
【11】「米軍出ていけ」はヘイトスピーチか―沖縄でのヘイトスピーチ規制条例制定を考える(安田菜津紀)
【12】2016年、米軍基地と契約する民間企業の社員である元米兵の男(妻は日本人)が、沖縄県うるま市の女性を強姦・殺害した事件を受けておこなわれたデモにおける言語表現。当該の元米兵は日本の司法によって裁かれ、無期懲役の判決が確定した。
【13】石垣市議会『高江現場における不穏当発言に抗議し警備体制の改善を求める意見書』より引用。当該の現場(ヘリパット建設予定地)では、機動隊員がデモ隊に発した「土人」という言語表現だけがクローズアップされた。
【14】前掲『ヘイト・スピーチとは何か』を参照。
【15】言語表現のみならず、絵画や楽曲による表現についても評者は同様の立場である。また、ここで示す表現とは憎悪に基づくものだけでなく、暴力や性表現等の万象を含む。