ベルリオーズ「イタリアのハロルド」のソリストを務める、東京交響楽団首席ヴィオラ奏者の青木篤子。2010年5月には前音楽監督ユベール・スダーンの指揮で同曲ソリストを務め、今回は現音楽監督ジョナサン・ノットの指揮で14年ぶりに臨む。ヴィオラ奏者にとって特別な存在である本作についてのほか、ノット監督や東響への思いなどを語ってもらった。
――2010年、当時の音楽監督のユベール・スダーンさんとの「イタリアのハロルド」はすばらしい演奏で、最後のパフォーマンスも強く印象に残っています。
東響で初めてソロを弾かせていただいたのがこの「イタリアのハロルド」でした。どんどんソロの出番が減っていく曲で、第4楽章になると10分近く弾かない時間があります。ストーリー的にも最後死んでしまうので、あの世から聞こえるような最後のフレーズはコントラバスの後ろで弾くのはどうでしょうとスダーンさんに提案をして、最後は倒れるようなお芝居もしました(笑)。今回改めて取り組むにあたっては、視覚的なことはせずに、譜面に書いてあることを素朴に再現したいと考えています。ベルリオーズの書いたスコアの奥行き、遠近感が本当にすばらしく、耳で聞くだけでシアターピースとして伝わるものと再認識しています。台本であれば主人公のセリフは少なく、最後はほぼ「……」になってしまうような内向的な曲で、難しいけどやりがいがあります。全体にはオーケストレーションが非常に素晴らしく、いろいろな風景を楽しめるのが魅力です。
――特に好きな場面はありますか?
私が一番好きな場面は、第2楽章の巡礼の場面の最後です。ここは「カント・レリジオーソ」(宗教的な歌)という指示があり、主人公は巡礼には加わらず傍観していますが、気持ちは共感していて、風が吹くようなアルペジオをスル・ポンティチェロ(駒寄りで弾くことで特殊な音色が出る奏法)で演奏します。第2楽章以降はもう依頼者のパガニーニを意識せずに、ベルリオーズが心の赴くままに書いていったかのようで、華やかな超絶技巧みたいなものが全然ないのです。本当に純粋な音楽ですし、室内楽を書くような感覚だったのかもしれません。
――今回の「イタリアのハロルド」は、ほとんどベルリオーズを取り上げてこなかったノット監督からの提案だったそうですね。しかもヴィオラのソリストが2人で、青木さんがフランスのベルリオーズ、フランス人のサオ・スレーズ・ラリヴィエールが酒井健治作品という、かなりレアなプログラム。
ノット監督の提案でこの曲をやると知ったとき、「ドッキリ?!」というくらい驚きました(笑)。ラリヴィエールさんとお会いするのは初めてで、とても楽しみです。酒井健治さんはフランスで学ばれた方で、ノットさんは「日本とフランスの架け橋がいくつもあるプログラム」と語っていたそうです。ヴィオラが2人も出てきて……と思われそうですが(笑)、この楽器は本当に一人ひとりが違う音色をもっていますし、全然違う音響世界を楽しんでいただけると思います。さらに、最後にイベールの「寄港地」で華やかに締めるのもいいですね。地中海の各地を巡る旅を楽しめる作品で、ノットさんも含めてオーケストラ全員で「旅をしよう!」という気持ちにもなれそうです。フライヤーの「2人のヴィオラ奏者、地中海を往く。」というキャッチコピーもいいですよね!
(C)Junichiro Matsuo
――ノット監督はどのような存在でしょうか?
サウンドもフレージングも、いかに音楽を自然な状態に近づけていくかということを大切にされています。彼は協奏曲であっても全員で作り上げる意識で、絶妙なバランス感覚でオーケストラを背景に回さないのです。
以前ノット監督の指揮で「ドン・キホーテ」でヴィオラ・ソロを務めたとき、サンチョ・パンサの語りのようなソロが結構難しいのですが、最初のリハーサルで私のソロを聴いて「一回、私が振るみたいに弾いてみて?」と軽い感じで(笑)一度だけ振ってくれて、それを見ながら弾いたら楽器の都合も忘れて、ごく自然なオペラのレチタティーヴォみたいな演奏になったのです。自分が一番驚いたほどの忘れられない体験ですが、そういう魔法をオーケストラ全体にもかけられる人なのです。
ノットさんとの仕事は本当に楽しいです。誰もいない山に咲く小さい花を守るような作業を音楽家はしなきゃいけない、ピュアな気持ちを保ち続けたい、と考えているのですが、彼は率先してそれをできる温かい人で、深く尊敬しています。
――東響はどんなオーケストラですか?
いい意味でなんでもやるオーケストラで、みんな自分の得意分野をいつでも発揮できて、とても柔軟。“オーケストラは大きな室内楽”といわれますが、そういう親密な対話ができていると思います。あと、私は関西弁しか喋れませんが(笑)、音楽を通せば言語も関係なく、言葉を超越したしたすばらしいコミュニケーションができることも実感しています。常に新鮮な気持ちになれますし、音楽ってすごいなと日々感じています。
取材・文=林昌英(音楽ライター)

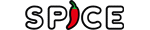


































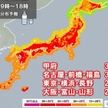

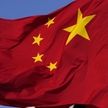

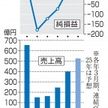














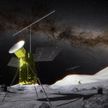




































































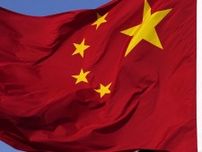














![[連載]イーストスタッドブログ・第7回 新種牡馬、レッドルゼルについて](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33395.jpg)


