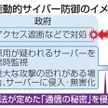ブランド力<2>
1973年発売のロングセラー「明治ブルガリアヨーグルト」は昨年、発売50周年を迎えた。
東京都内で12月に開かれた記念イベントで、明治の松田克也社長は「正統こそが、未来をつくる」との新ブランドビジョンを掲げ、100周年に向けて進化を続けていく考えを示した。
ヨーグルトの正統――。明治は商品パッケージにこう記載する。ヨーグルトといえばブルガリア。強固なブランドイメージを作り上げた自負がにじむ。
ヨーグルトの定番商品が誕生したきっかけは1970年。明治の社員が大阪万博のブルガリア館で本場のプレーンヨーグルトを試食したことだった。独特の酸味と香りに魅了され、日本の食卓に本場の味を届けようと商品化に着手した。
課題は当時の日本のヨーグルトは寒天などで固めた甘いデザートの位置づけだったこと。なじみがないプレーンヨーグルトの良さをどう広めるか。それには酸味がある方が「本物」だという証しがいる。そのアイデアがブルガリアという国名を入れた商品名だった。
だが、ブルガリア政府に断られてしまい、当初は「明治プレーンヨーグルト」の商品名で発売した。明治はその後も粘り強く交渉を続けること1年あまり。国名使用の許可を得て商品名の変更にこぎつけた。
調査会社インテージによると、2023年の固形ヨーグルト市場の規模は3256億円に上る。プレーンヨーグルト需要は堅調で、「ブルガリアヨーグルト」は森永乳業や雪印メグミルクの競合商品をリードする。
発売から半世紀。衰えないブランド力はどこからくるのか。明治の樋口靖夫グローバルデイリー事業本部長は「お客様に『変わってないね』と思われる変わり方を中身やパッケージで50年間続けたこと」と話す。
明治は今もブルガリアから乳酸菌を取り寄せ、「正統」の位置づけを守る。一方で消費者が「ちょっと酸っぱい」と感じる微妙な味のバランスを探ってきた。
食生活の変化に伴い「ちょっと酸っぱい」と感じる味は時代とともに変わっている。発売当初の商品を今食べるとかなり酸っぱいという。常にちょっと酸っぱいの定位置を守るため、あえて味を変えてきた。
パッケージも2年に1回程度の頻度で変える。白と青の基調は守りつつ、デザインは横線から斜めにしたり円にしたり。消費者に古くさい印象をもたれないよう腐心する。
それでも単身世帯が増え、食べきれないとの声も出てきた。機能性ヨーグルトの攻勢も受ける。ブランドをどう管理するか。悩みは尽きない。
ロングセラーが直面する問題が顧客層の高齢化だ。いかに新しい世代を取り込むか。1958年発売の日清食品の「チキンラーメン」の取り組みは目を引く。
た・ま・ご ポケットに た・ま・ご おとせ――。ラップ調の軽妙なリズムに乗せて、ひよこのキャラクターが麺にくぼみをつけて卵をのせやすくした「たまごポケット」を紹介する。このユニークなアニメ動画は公式ユーチューブやX(旧ツイッター)などで拡散し、話題を集める。
そのままかじって食べる「0秒チキンラーメン」といった派生商品を投入したり、アレンジレシピの情報発信に力を入れたり。いずれも即席麺の消費が多い若者世代との接点を増やす試みだ。神奈川県内の大学生、増井梨々花さん(19)は「SNSで話題になったつけ麺風のレシピを再現しようと思った」と購入理由を話す。
チキンラーメンは今も袋麺ではトップブランドだが、即席麺の主流はカップ麺だ。創業者の安藤百福氏の発明から66年。画期的だったがゆえ、社内で聖域化され、「いじりにくい」面があったことは否めない。リブランドに取り組む土岡洋平ブランドマネジャーは言う。
「100年ブランドを目指すためにもっと若い人にアプローチしていきたい。それには今までと違った一面を出すべきだと思う」
革新性と独自の価値がカギ
ロングセラーとなったブランドは、高度経済成長期の1950年代からバブル経済が崩壊した90年代にかけて続々と誕生した。
切りの良い年だけでみても60年発売の「のりたま」(丸美屋食品)、70年発売の「ほんだし」(味の素)、80年発売の「ポカリスエット」(大塚製薬)、90年発売の「一番搾り」(キリン)など、すぐ目に浮かぶ商品が多い。
ロングセラーになる条件とは何か。ブランド戦略に詳しい学習院大学の青木幸弘教授は、発売時に〈1〉革新性がある〈2〉独自の価値、カテゴリーを作る――ことを挙げる。その上で長寿命化には「特徴など守るべきを守り、環境の変化に応じて変えるべきところを変えていくブランド管理が重要になる」と指摘する。
近年は大手コンビニが毎週100商品前後の新商品を投入するなど商品の入れ替わりが激しい。結果的にロングセラーがさらにロングセラーになっている。