数々の名勝負に名を刻み、規格外の大きさからプロレスに縁のない人にもその名が知られたアンドレ・ザ・ジャイアント(1946〜1993)。46歳の若さで旅だってから31年になります。リングの上では荒々しいファイトを見せていたアンドレが人知れず抱えていた悩みとは何か。朝日新聞の編集委員・小泉信一さんが様々なジャンルで活躍した人たちの人生の幕引きを前に抱いた諦念、無常観を探る連載「メメント・モリな人たち」。今回はアンドレの知られざる素顔に迫ります。
おならも「必殺技」
アナウンサーの古舘伊知郎さん(69)が「人間山脈」「1人民族大移動」「現代のガリバー旅行記」などと絶叫したのが懐かしい。その本質は、あまりにも大きな肉体にあるのだろう。
「1人と呼ぶには巨大過ぎ。しかし、2人と呼ぶには人口の辻褄が合わない」
とも言っていたが、けだし名言である。
「大巨人」という異名で世界中の人々を湧かせたプロレスラー、アンドレ・ザ・ジャイアント(本名アンドレ・レネ・ロシモフ)である。父の葬儀に出席するため母国フランスに帰国中の1993年1月27日、心臓発作を起こしてパリのホテルで急逝。46歳という若すぎる死だった。
訃報を速報したAP通信によると、アンドレの身長は223・5センチ、体重は235・5キロとなっていた。でも、実際はもっと大きかったのではないか。
特に体重。田鶴浜弘・著「プロレス大研究」(講談社・1981年)によれば、なんと270キロとなっていた。ちなみに、足の長さは40センチもあったらしい。
いずれにせよ、「世界8番目の不思議」と呼ばれ、プロレス界でも常識を覆す桁外れの巨体。遠征先の北海道札幌市では、サッポロビール園で生ビールを大ジョッキで78杯も飲み、同園から追い出されたとか。伝説は数々ある。
フランス出身のアンドレが日本のリングに初めて上がったのは1970(昭和45)年1月。国際プロレスの試合だった。当時のリングネームは「モンスター・ロシモフ」。やがてカナダに転戦し、「アンドレ・ザ・ジャイアント」に改名した73年、ニューヨークを本拠地とするWWWF(現WWE)と契約。たちまち全米ナンバーワンの売れっ子レスラーとなった。その人気は「年収世界一のプロレスラー」としてギネスブックに掲載されたほど。しかも、そのころから「フォール負けなし、ギブアップ負けなし」の無敵のレスラーとして君臨した。
74年、アントニオ猪木(1943〜2022)が率いる新日本プロレスのリングに上がる。だが、猪木以外のレスラーでは試合にならないため、日本人レスラー3人が一斉にアンドレに挑むというハンディキャップマッチも組まれた。
ところで、アンドレは日本人が大嫌いだったそうである。それは、日本人が彼をあからさまに化け物(モンスター)扱いし、見せ物小屋の異形物のような奇異の目で見たからであろう。たしかに、アンドレには異界から来た者のオーラのようなものがあった。
驚くべきことに、アンドレは来日するたびに身長も体重も大きくなっていった。ゆで卵を一度に20個も食べていたからだろうか。試合中でも大爆音とともにおならを放ち、鼻がひん曲がるほど臭かったそうである。その悪臭はリングサイドにも漂ったことだろう。巨体を生かしたボディープレスやヒップドロップのほかに、おならまでもが必殺技になるとは何ともすごい話である。
そんなアンドレではあったが、亡くなったとき作家の夢枕獏さん(73)が記した追悼文が興味深かった。
「異人の集団であるプロレス界の中にあっても、なお、彼は異人であった。彼自身が嫌いであった自分の肉体の特異性が、自分の人気を支えているという矛盾を、常に胸の中に抱え込んでいなければならなかったレスラーである」(朝日新聞:93年2月24日夕刊文化面)
たしかに、日本での関心事は、どのレスラーがアンドレを持ち上げるか、誰がフォール勝ちを奪うかに集約されていた。いわば、アンドレは一方的に「やられ役」というか「汚れ役」を背負っていたようにも思える。規格外の巨人にとって、日本という国は住みにくかったに違いない。
アンドレの孤独を理解していた馬場
アンドレが亡くなった6年後には「東洋の巨人」ことジャイアント馬場(1938〜1999)が亡くなったが、かつて馬場を見ると指をさし、「アッポー、アッポー」とはやし立て、笑い転げる子どもたちがいた。カメラでも持っていようものなら、それは大変。レンズを無遠慮に向け、シャッターを押し続けるのである。「ガリバー物語」で描かれた小人国の兵士らの弓矢攻撃のようなものだった。
馬場は終始無言。私も高校生のとき、川崎の体育館で子どもたちに囲まれている馬場を見たことがあるが、その眼は限りなく静かで、悲しみさえたたえているようでもあった。
だからなのだろうか。馬場はアンドレの孤独を理解していた人物と言われている。
90年4月、全日本プロレス、新日本プロレス、WWEの3団体合同興行「日米レスリングサミット」(東京ドーム)で、馬場はアンドレとタッグを結成(通称「大巨人コンビ」)。すでにリング上では往年のような動きができなくなっていたアンドレを引き取るような形で、全日本の試合に参戦させた。
馬場が率いた全日本はアンドレが最後にたどり着いた安住の地だったとも言えるだろうが、全盛期のアンドレが闘ったらどんな試合になっただろうか。想像するだけでウキウキする。
話を戻そう。
プロレスがショービジネスの一種であるとするなら、リングの内と外とを問わず衆人から高貴の眼で見られることは歓迎すべきことなのに、じろじろ見られるのはやはり苦痛だったのだろう。「俺だって人間だ」という思いをアンドレはいつも抱いていたに違いない。
「ゲラウェイ!(出ていけ)」
控室でプロレス記者に声を荒らげたことも何度かあったというが、いつも不機嫌だったアンドレは徹頭徹尾、孤独だったのかもしれない。
忘れられない「あの試合」
孤独といえば、こんな話もある。日本にやってくる外国人レスラーは泊まる宿が決まっていたが、アンドレだけは昔からなじみにしていたホテルに泊まっていた。アンドレにとっては本当にひとりぼっちになって心を休めることができた空間。ほかのレスラーと一緒のホテルに泊まるより、余計な気を遣わなくて済むと思ったに違いない。
だが、晩年のアンドレはかなり丸くなり、日本からやってきた報道関係者の取材を自宅で受けたりしていたという。
アンドレといえば忘れられない試合がある。否、「謎に包まれた不穏試合」と言ったほうがいいだろう。86年4月29日、三重県津市体育館で行われた前田日明(65)と対戦である。
動画を見たが、試合開始後、アンドレは不敵な笑みを浮かべながらリング中央で仁王立ち。アンドレはプロレスの攻防に付きあう気は全くなかったのだろうか。異変を感じた前田が距離をとってのローキック攻撃に転換。何度も蹴りを繰り返したが、アンドレはまったく仕掛けて行こうとしない。業を煮やした古舘アナが「果てしない凡戦」とマイクに向かってしゃべっていた。
この試合は、アンドレが前田のプロレスに一切付き合わず、潰しにかかった「セメントマッチ」だったともいわれる。やがてアンドレは大の字に寝転がり試合を放棄。アンドレは自身の商品価値を下げてしまったが、一方の前田は「アンドレを戦意喪失に追い込んだ男」として人気上昇。だが、イメージが先行してしまったことは否めないだろう。
まあ、これ以上は書くのをやめておく。いずれにしても、アンドレが活躍した昭和のプロレスは、まさに「夢の世界」だった。呪われた悪の権化のようなレスラーが繰り返す非道な反則、ラフ・ファイトの地獄絵は、いまも脳裏に焼き付いている。その一方で華麗なファイトを見せ、悪役レスラーをことごとくなぎ倒したレスラーも記憶に新しい。
古舘アナはプロレスを「闘いのワンダーランド(御伽の国)」と表現したが、「御伽の国」はアンドレ・ザ・ジャイアントという唯一無二の存在によって形成されていた面もあった。
次回は浅草芸人の関敬六(1928〜2006)。あの渥美清(1928〜1996)が心から頼りにしていた親友で、映画「男はつらいよ」シリーズでは寅さんのテキヤ仲間などを演じた。決して演技はうまくはなかったが、浅草らしい泥臭さを持った味わい深い芸人だった。
小泉信一(こいずみ・しんいち)
朝日新聞編集委員。1961年、神奈川県川崎市生まれ。新聞記者歴36年。一度も管理職に就かず現場を貫いた全国紙唯一の「大衆文化担当」記者。東京社会部の遊軍記者として活躍後は、編集委員として数々の連載やコラムを担当。『寅さんの伝言』(講談社)、『裏昭和史探検』(朝日新聞出版)、『絶滅危惧種記者 群馬を書く』(コトノハ)など著書も多い。
デイリー新潮編集部




















































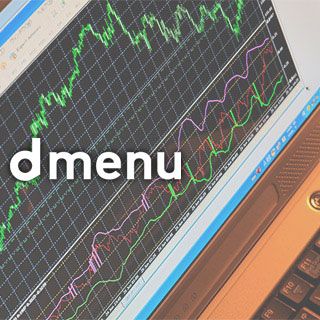











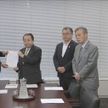






























































![大坂なおみ、全仏OP前哨戦で世界45位に快勝し2回戦進出[イタリア国際]](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/tennisclassic/s_tennisclassic-6158.jpg)






















![[ブルーノ・ユウキ]『パンサラッサの人』になって、変わったこと、変わらなかったこと](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33278.jpeg)


