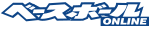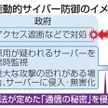誰もが順風満帆な野球人生を歩んでいくわけではない。目に見えない壁に阻まれながら、表舞台に出ることなく消えていく。しかし、一瞬のチャンスを逃さずにスポットライトを浴びる選手もいる。華麗なる逆転野球人生。運命が劇的に変わった男たちを中溝康隆氏がつづっていく。
ドーム野球の申し子
巨人時代の勝呂
「プロ野球選手は公式戦に出てこそなんぼなんです。それがいくら待っても上(一軍)にいかせてもらえないことほどつらいものない」
オリックスで日本一になった秋、彼は前所属チームでの自分が置かれた状況をそう振り返った。気がつけば、巨人からトレード移籍して5年が経過していた。勝呂壽統 (博憲)は、千葉商の在学時に阪神からドラフト外で誘われるも断り、社会人の日本通運でプレー。遊撃のレギュラーをつかむのに時間はかかったが、1年だけ一緒にプレーした辻発彦とよく比較され、「辻以上の素質」と評価するプロのスカウトの声もあった。
「辻さんは、ほんとにいいお手本でした。守備のうまさは強烈な印象となって残ってますね。特にスタートの速さ。ボクはいつも2、3歩遅れをとってました」
プロ入り後に『週刊ベースボール』で先輩・辻の印象をそう語った勝呂は、1986(昭和61)年11月のドラフト会議で巨人から5位指名を受けるも、「まだまだ会社に義理があるから」と都市対抗野球に出場したのち約1年後に入団する。契約金5000万円、年俸540万円という下位指名では異例の好待遇で、日通の野球部員全員に一着5万円のスーツをプレゼントしてみせた。入団発表と同時に87年11月10日から始まる宮崎秋季キャンプのメンバーに追加招集され、東京ドーム開業元年の“ドーム野球の申し子”は脚力とセンスを買われると、1年目の春先にはスイッチヒッターの練習にも励んだ。
88年の巨人は開幕から鴻野淳基や岡崎郁らが遊撃のポジションを争っていたが、守備でミスの続いた鴻野に代わり、4月20日にはイースタン・リーグ2位の打率.407を記録していた勝呂が初昇格。いきなり代打で2打席連続安打と結果を残し、4月30日の広島戦では「二番・遊撃」で初スタメン。3打数2安打1四球と存在感を見せると、翌日以降も一・二番で起用され、5月6日現在で22打数11安打の打率5割と打ちまくる。
「社会人出だから、すぐやれると思っていた。幅広い使い方ができる選手だ」と王貞治監督は喜び、土井正三守備コーチも「フットワークがいいね。こちらからの指示がなくても、バントの構えをしてピッチャーを牽制したり、研究熱心だし、野球に取り組む姿勢がいい。教えがいのある選手だよ」(週刊読売88年5月22日号)と実戦派ルーキーを高く評価した。
新人時代に数々の武勇伝
実は新人時代の勝呂は、いくつかの武勇伝を残している。春季キャンプでは、槙原寛己に対して、「おい槙原、トス・バッティングしようや」とおもむろに声をかけ、周囲を驚かせた。お互い同じ1963年生まれだが、かたや1年目のドラフト5位入団の新人、一方の槙原はプロ7年目のエース格である。その度胸のよさは開幕直後にも、巨人ナインを驚愕させた。
ある日、勝呂は戸田でヤクルトとのファームの試合に出場する予定だったが、寝坊して他の二軍選手を乗せたバスが出発してしまう。すると乗り遅れたルーキーは、なんとそのまま歩いて一軍が練習しているジャイアンツ球場へ向かい、「二軍の試合に間に合わなかったので一軍に来ました」と姿を現したという。しかも、すでに一軍の練習が終わりかけているところにひょっこり顔を出したのだ。この前例のない行動には首脳陣も怒ることを忘れて絶句。ベテラン捕手の山倉和博はのちに週べの自身の連載で、「二軍がダメなら一軍があるさという発想が出来る男に、私は初めてお目にかかった」なんて笑い話として振り返っている。「こいつはとんでもない大物か、とんでもない大馬鹿かどっちかだな」と山倉は24歳の強心臓男に期待したという。
そして、88年5月28日の広島戦。その時点で6勝0敗、防御率0.91、被本塁打0という絶対的エースの大野豊から、勝呂は延長10回にプロ初の決勝1号ソロアーチを放つのだ。それは大野がシーズン257人目で初めて打たれた本塁打でもあった。スポーツ各紙は伏兵のまさかの一発に「“不沈艦”大野が沈んだ」と大々的に報じ、無名の背番号38は監督賞の10万円も手にして、いちやく時の人となる。当時のゴールデンタイムに地上波テレビ中継していた巨人戦には、それだけのニュースバリューがあったのだ。
『週刊現代』88年6月25日号ではOBの堀内恒夫が、「第二の高田繁になれる!」と断言。グラウンド上で先輩たちに臆することなく対等の立場でプレーする勝呂の堂々たる態度と、アイドル化した最近の巨人選手らしくないひたむきなプレーを褒め、「これから10年、巨人の理想のトップバッターとして定着できる要素を備えた数少ない選手だと思う」とまで絶賛している。6月12日現在、3割5分近いハイアベレージに、勝利打点3つの勝負強さ。『週刊文春』では、日通浦和の中村国勝監督が勝呂の快進撃を語る。
「これぞというチャンスをものにしようという気の強さは、他の選手にないものがあった。日通浦和で初めてスタメンで出した試合も、よく打ったからね。今も、ここで打てなけゃ明日はないんだという目をしてバッターボックスに入っている。うちでレギュラーをとった時と同じような目をね」(週刊文春88年6月23日号)
単独で表紙を飾った週ベ88年6月20日号では、松本匡史との「新旧トップバッター対談」に登場。「一番ほしいのはゴールデングラブ賞。ああいうのを続けてとりたいですね」と明るい未来を語り、ともに遊撃を守る中日の立浪和義との新人王争いも話題となる。当時、勝呂と同い年で、よく食事に誘ったくれた吉村禎章がプレー中に味方野手と激突して重傷を負いチームに衝撃が走るが、“アジアの大砲”呂明賜や勝呂といった若い力が首位争いをする王巨人を牽引した。
移動中はお気に入りの爆風スランプをウォークマンで聴きながら、週刊誌を読んで気分転換。さすがに夏場には失速するも89試合で打率.283、3本塁打、11打点、10盗塁の成績を残し、9月26日には内輪だけでささやかな結婚式をあげた。オフはサイン会にも引っ張りだこのニュースター候補は、89年シーズンは「二番・遊撃」で初の開幕スタメン。すべてが怖いくらいに順調だった。
チームで居場所を失いオリックスへ
王監督に代わり、藤田元司監督が復帰した新チームでも、当初は勝呂が遊撃レギュラーと見られていたが、グアム・キャンプから続けてきた打撃フォーム改造が結果的に失敗。打撃の悩みが守備にも悪影響を及ぼし、開幕4戦目には川相昌弘に遊撃のポジションを明け渡す。しばらく併用されるも、やがて川相は堅実な守備としぶとい打撃で、藤田野球の申し子として一気にブレイク。さらに若いスピードスター緒方耕一の台頭もあり、勝呂は89年に70試合、90年はわずか20試合の出場とリーグ連覇したチームの中で居場所を失っていく。
同世代に先を越され、年下にも追い抜かれる。要はライバルたちとのポジション争いに負けたわけだ。右打ちを意識するあまり感覚が狂ったバッティングは打率1割台と低迷。プロ4年目の91年はわずか3試合の出場に終わり、1本のヒットも打てなかった。そして、勝呂はオフに熊野輝光とのトレードでオリックスへ移籍するのである。いわば、28歳で巨人に見切られた形となった。
オリックスでは巧打の内野手としてリーグ連覇に貢献した
だが、男の運命なんて一寸先はどうなるか分からない――。このとき、オリックスの監督は、勝呂が最も輝いていたプロ1年目にコーチとして接した土井正三だった。92年は守備中に味方野手と衝突して、右頬骨骨折で手術をするアクシデントに見舞われるも、移籍2年目の93年は心機一転「壽統」に改名。遊撃のレギュラーを掴み、96試合で打率.254と一時期のスランプからは復調する。
94年から就任した仰木彬監督も使い勝手のいい勝呂を重宝した。延長戦で緊急時のオプションとしてキャッチャーの準備を命じられると、「中学1年までは捕手だったし、(リトルリーグの)船橋リトルでは全国制覇もしてますからね」と嫌な顔ひとつ見せず出番を待った。試合出場に飢えていた勝呂は、仰木マジックの選手起用にハマり、「がんばろうKOBE」の95年は自己最多の117試合に出場。優勝チームの遊撃を守り、開幕戦ではロッテの伊良部秀輝から決勝アーチを放っている。リーグ3位の27犠打を記録するが、九番打者として「一番イチロー」につなぐのが勝呂の仕事だった。翌96年は日本シリーズで古巣の巨人と対戦。4勝1敗でオリックスが日本一に輝くが、勝呂は全5試合に途中出場。同じく高田誠や四條稔ら巨人二軍でくすぶっていた男たちが、古巣に対して意地を見せた。彼らは「元・巨人」ではなく、オリックス初の日本一メンバーになったのである。
97年からは近鉄でプレー。99年限りでユニフォームを脱いだ
だが、チームの若返りの方針もあり、33歳の勝呂は96年オフに内野手不足で悩む近鉄へ金銭トレードで移籍。大阪ドーム元年の97年は72試合で打率.275といぶし銀の働きを見せ、99年限りで12年間のプロ生活に別れを告げた。
巨人を「出された」のではなく、野球を続けるために「出ていく」。悲しんでいるヒマなどなかったと、勝呂はのちに語っている。
「巨人時代のことなんか振り返りたくもないですよ。確かに人気球団ではあったが、オリックスだってすごい人気があるでしょう。もし、あのまま巨人にいたらユニフォームを着ていられたかどうか……。トレード通告された時、とうとうくるべきものがきたという感じがした。もうあとがないというか、オリックスでやらなきゃ野球人生は終わってしまう、と……」(週刊ベースボール96年11月9日増刊)
文=中溝康隆 写真=BBM