文化人類学者による怪異報告書
超自然的な力を利用して望みを叶え、憎い相手に不幸を与える……。そんな呪術はフィクションの中だけのもの、と思うかもしれないが、世界各地でまだ信じられているのみならず、実際に効力を発揮しているらしい。9人の文化人類学者が調査地で体験あるいは見聞きした怪異をレポートする、奥野克巳監修『世界ぐるぐる怪異紀行 どうして“わからないもの”はこわいの?』(河出書房新社)を読むと、そのことがよく分かる。
病気や事故などを引き起こす西アフリカのベナン共和国の妖術師、川に潜む人間を襲うパナマの悪霊アントミャ。目には見えないそれらの存在は、人々の生活と密接に関わり、悲しみや苦しみといった感情の受け皿となっている。外国人が押し寄せたことで古来の精霊が観光の目玉になったり(ネパール)、キリスト教伝来によって呪術や霊が時代遅れになったりと(ヴァヌアツ)、価値観の移り変わりとともに怪異もまた変化しているのが興味深い。
最終章において民族誌映画が専門のルーマニア人研究者イリナ・グリゴレは、「怪異」という言葉は「strange:理解し難い他者」と「mystery:神秘的」の二つのニュアンスを含むと述べている。受け入れがたいものと、受け入れられるもの。前者から後者への転換が、怪異を研究するうえでは大切だというのだ。好奇心から本書を手にした読者も、気づけば呪術の実在する世界を受け入れているに違いない。
身近なマジナイから本格的な作法まで紹介
オカルト・宗教・民俗学などに詳しく、現在公開中の映画『陰陽師0』では呪術監修を務めている作家の加門七海。『呪術講座 入門編』(KADOKAWA)は、身近なマジナイから本格的な呪術の作法までをトータルに紹介した入門書だ。呪いやマジナイには効力がある、霊や神仏・妖怪は実在する、というスタンスで書かれているのが特徴で、豊富な実践やフィールドワークを下敷きにした記述には、類書にはない説得力とかすかな怖さが漂っている。
有名な陰陽師・安倍晴明が使役したとされる「式神」、エンタメ作品にもよく登場する「結界」などについて詳しく解説される一方で、目や指などを使った簡単なマジナイも取り上げられており、その気になればすぐにでも呪術のある生活をスタートすることが可能。というよりも、日本人の生活自体が呪術と切っても切れないものであることが、本書を読むと明らかになる。
運動会の前夜に吊す「てるてる坊主」や、日常的に使用する印鑑、お盆や節句などの年中行事にも、呪術的な意味合いが込められているのだ。『世界ぐるぐる怪異紀行』で紹介されている国々に負けず劣らず、日本もマジカルな国だということを再認識する。
歪んだ呪術がもたらすおぞましい災厄
3冊目はフィクション。芦花公園『極楽に至る忌門』(角川ホラー文庫)は、独自の民間信仰が伝わる村を舞台にしたホラー長編だ。大学の友人・匠の帰省に同行し、四国の山村を訪れた隼人は、匠の一家が村人たちに避けられていることに気づく。匠の実家に着いたその晩、外を見てくると出かけた匠はそのまま失踪。唯一の家族である匠の祖母も急死し、隼人は途方に暮れる。相次ぐ異変はどうやら、裏山に祀られている「ほとけ」と関係があるらしい。やがて隼人の夢に現れた匠は、大切なものを捧げるよう要求してくる……。
そもそも呪術とは「人間を超えた力に働きかけ、望ましい結果を手に入れようとする作法のこと」(『世界ぐるぐる怪異紀行』)。本書では人と人ならざるものとの間で交わされた契約が、長い年月の間に変容し、おぞましい災厄を招き寄せていく。閉鎖的な村にわだかまる闇の濃さと、関わった村人たちの業の深さに思わずぞっとさせられる、著者渾身の民俗ホラーだ。
隼人視点の第一章、人生に絶望して帰郷した女性が主人公の第二章、祖父母の家に遊びにきた男の子が中心の第三章。三つのパートからなる物語は、いずれも“触れてはいけないものに触れてしまった”という感覚に満ち満ちており、恐怖度はかなり高い。どんなに科学が進んでも、人間には太刀打ちできないものがあるらしい。呪術をよく知ることは、分をわきまえて生きるということにも繋がるはずだ。




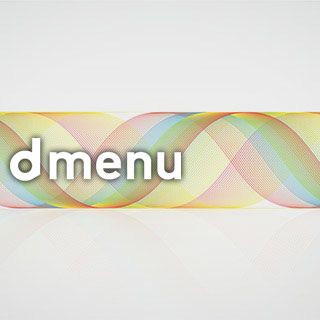




































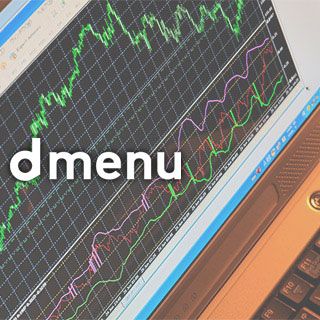






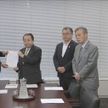




































































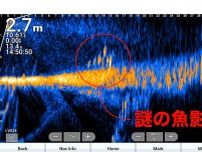







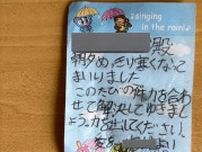


















![[ブルーノ・ユウキ]『パンサラッサの人』になって、変わったこと、変わらなかったこと](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33278.jpeg)





