石橋凌(67)がミュージシャンとしての活動に心血を滾らせている。45周年を記念したライブツアー「KEEP IN TOUCH!2024」が6月30日の北國新聞赤羽ホール(金沢市)まで開催中。「自分の思いや考えを音に乗せて伝える」――。その思いを、バンド時代からソロに至るまで常に貫いてきた45年だ。
幼少時からロックに共感
「ジョン・レノンやボブ・ディラン……。幼少の頃からその歌詞を読んで、個人の意見を音に乗せて言ってもいいんだ、というのを知ったんですよ」
石橋は男ばかり5人兄弟の末っ子として生を受けた。4人の兄が聴く音楽のジャンルはバラバラだったが、その中にあったロック音楽に共感し、こんな考えを育んでいったという。
そんな頃、すぐ上の兄がアマチュアバンドを組んでボーカルを務めていた。ビートルズやローリング・ストーンズ、クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル(CCR)などの曲を歌う兄の姿を見て、音楽をやりたいというより「バンドをやりたい」という思いにまずは突き動かされた。
「家族や兄弟でもない他人が集まって一つのものを創ることに憧れ、すごく魅力を感じた」と述懐し、高校に入ると音楽研究会に所属。同級生・先輩とバンドを組んだのが音楽人生のスタートとなった。「ずっとバンドをやっていきたい」という思いが胸中を占めていた。
シェフの道に進む?
「バンドでプロを目指していきたい」
バンドを続けるうちにそんな思いが芽生えたのも当然だろう。だが高卒後、プロデビューへの道が見えそうでなかなか見えない中、シェフの道に足を踏み入れそうになった経験もある。
バンドと並行して、アルバイトをしていたイタリアンレストラン。シチリア島で修業したという店長の下で精を出す石橋に、店長は新たに博多に出す支店を任せようと、「シチリアで勉強しておいで」と勧めてきたのだ。
「もうミュージシャンを断念し、8割方、シェフになるのかなと思っていた」
そんなときに連絡をくれたのが、地元で組んでいたバンドで出演したKBCラジオの番組「歌え!若者」のディレクター、岸川均氏だった。
岸川氏は「ARB」のボーカルオーディションを受けないか、という連絡を電話でくれた。石橋が19歳のときだ。そのチャンスをつかみ、念願のプロミュージシャンの道が開けた。
理想と現実のはざまで
1978年にシングル「野良犬」でデビューし、翌年にはアルバム「A.R.B.」を発表したが、そこには石橋がやりたかったことと現実との乖離が生じていた。
「ロックというのは、自分の思いや考えを歌に乗せて伝えられるものだ」
という“原点”を持つ石橋に対し、当時の事務所は「社会的、政治的な歌を入れるな」との考えだったため、相容れなかった。ファーストアルバムの1曲「喝!」は、経済大国になりながら自殺者の多い日本を歌ったものだが、「これが事務所の逆鱗に触れた」ため、事務所を退所。その後は「中古のワンボックスカーで日本中のライブハウスを回る活動となった」。
だがそれは、「それまで思っていたことができるようになった」ことの裏返しでもあり、徐々にではあるが、それを支持するファンも増えていった。
デビューから10年となった88年には、日本武道館ライブを敢行。多くのファンが熱狂したライブは、ARBの足取りが確かであったことを証明していたが、それでも「茶の間には入っていけなかった」と石橋。
「欧米のミュージシャンはテレビでも(社会的、政治的なメッセージを含む歌を)プレイしているのに、それができなかった」
松田優作の影響
ARBが武道館に到達する2年前、石橋は松田優作が監督した映画「ア・ホーマンス」で本格的な役者デビューを果たし、キネマ旬報の新人男優賞を獲得する。
「自分の夢もここまでだな、と思ったときに必ず誰かが登場して俺を救ってくれたんですよ」
石橋は松田との出会いをこう振り返る。プロデビューのきっかけをくれた岸川氏との出会いと同様だ。
当時の石橋は20代半ば。徐々に浸透してきていたとはいえ、コンサートの動員やレコード売り上げの伸びなどに悩み、「分厚くて高い壁」にぶち当たっていた。出会いを得た松田に対し、相談に乗ってもらう中で、松田が自身の監督作「ア・ホーマンス」に出ないかと持ち掛けてくれたのだという。
「これはバンドを売るチャンスだ」
オファーを受け、石橋の頭をよぎったのはこんな考えだった。それを包み隠しもせず、「バンドを茶の間に売る宣伝でいいですか」。殴られる覚悟すらしながらも、ストレートに松田にこう尋ねたという。
「それでいいよ」
4秒ほどの間があって、松田からこんな答えが返ってきて、出演が決まった。
映画の現場では、それまで歌ってきた中で培ってきたフィーリングや感性が「間違っていなかった」と実感できたという。
だからこそ、撮影終了後、松田から「お前、これからどうするんだ」と尋ねられた際、「(悩みも吹っ切れて)また歌えるようになりました。もう一回バンドを立て直して、頑張ります」と答えた。
一方で役者稼業については「もし自分にできるようなものがあれば、やるかもしれません」という程度の答えだった。
遺志を継げないかと俳優業に専念
だが、石橋が見せた可能性を、演技の世界が放っておくこともなく、88年にはNHK大河ドラマ「武田信玄」に織田信長役で出演。様式美なども大きく異なる時代劇に「戸惑いはもちろんあった」というが、「自分がやるのならリアルにやらせてほしい」と、自身なりのリアルな武将像を求めて表現した。「今、見るとやはり表現力も当時は稚拙だった」と苦笑する。
ただ「ア・ホーマンス」の現場で松田に叩き込まれた映画における表現の基礎として「映ったときに、医者なら医者、やくざならやくざ、そのものでいなくてはいけない」という教えを心に刻み、多くの役を演じてきた。
松田は89年、40歳で早世したが、このとき石橋は33歳。行き詰まっていた自分をよみがえらせてくれた恩人として、「自分なりのやり方で優作さんの遺志を継げないか」と考え、俳優業に専念するため、音楽活動を34歳で休止した。
松田が生前よく言っていた、米国との合作映画で日本人を演じるのが日本人でないこと、米国の映画俳優組合「SAG」に日本人俳優が入れていないこと、露骨ではないけれども差別・偏見と闘うこと――などを胸に役者業に邁進。東映ビデオが米ハリウッドと組んで作ったシリーズ「Vアメリカ」の作品に参加するなどの経験を積み、95年にSAGの会員となった。松田には線香をあげて、そのことを報告したという。
カメレオンが頭の上に…
その後、ラブストーリーや社会派ドラマ、あらゆるジャンルに臨んだ石橋。
「押しなべて言えば、テレビより映画の方がいい」というものの、映画であろうがテレビドラマであろうが、その存在感を十二分に発揮してきた。
映像から発せられる部分では笑いとは遠い役柄も多いが、2010年のNHK大河ドラマ「龍馬伝」ではこんな裏話もあった。
演じた長崎奉行・朝比奈昌広はカメレオンを飼っており、坂本龍馬(福山雅治)と謁見する際も、肩にカメレオンを抱きかかえていた。
「セリフをしゃべりながら、抱きかかえていたんですけどね。やり取りしているうちに、どこかに行ったなあとは思っていて」
龍馬のセリフが終わり、カットがかかった瞬間、福山をはじめ、出演者、スタッフ一同が大爆笑。なんとカメレオンがかつらの上に乗っており、「丁髷が2本あるみたいになっていた。かつらの中は鉄板なので、俺は全く気付かなかったけど…」と、今思い出しても笑える出来事だったという。
自分を見せる仕事と嘘をつく仕事
「言葉は悪いけど、俳優業は嘘をつく仕事。片やミュージシャンは本当のことを言っていく仕事。全く違いますよね」
俳優業が軌道に乗った後、98年にARBを復活させ、脱退する2006年まで続けた。バンドを復活させた後の2002年にはソロデビューも果たし、音楽と俳優業を並行してきた。
「バンド時代はいいこともたくさんあったが、嫌なことも経験したし、自分の嫌な部分も出さなければいけない。それもあって卒業したかったというのもある」とソロへの転身を説明する。原点こそ「バンドをやりたい」だったが、今は音楽をやりたいという、より純な気持ちに突き動かされて活動を続けている。
ただ、俳優業との両立は傍から見ているほど楽ではないという。
「俳優業は、恐山のイタコと同じで、自分ではない人間を降霊させる作業。特に自分は悪党の役も多いので、そういう役を身体から抜けさせてから、音楽へ行くなど、数日間でもいいから切り替える期間を設けている」と明かす。
かつて、ショーン・ペン監督の「クロッシング・ガード」でゲイの役を演じたこともあるが、その役を抜けさせるのに苦労した経験もあるという。
そうした切り替えに奏功しているのがサウナ。サ道は50年以上といい、新陳代謝を図るとともに、役の男を排出して、初めて“整う”のだという。
現在、進行中のツアーでは、最新アルバム「オーライラ」からの曲も多く歌う。「Dr.TETSU」はアフガニスタンやパキスタンで医療活動に従事し、アフガンの銃撃事件で死去した中村哲医師を歌った歌。2017年のアルバム「may Burn!」収録で、戦争や核兵器反対をストレートに歌った「ピカドンの詩」など、大事に歌い続ける曲も多い。
「アマチュア時代を含め、50年以上歌ってきて、最新のアルバムは自分の音楽人生の中でも最高傑作といえる」と胸を張り、進行中のライブを「ぜひ見に来てほしいね」と訴える。
俳優業で海外へ進出したことと同様に、「チャンスがあれば将来的には海外で歌ってみたい」となお意気盛ん。今回のライブは、そんな石橋の姿を生で感じるチャンスと言えそうだ。
デイリー新潮編集部















































































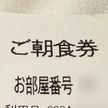



























































![[重賞回顧]自分らしくありのままに。絶妙なペース配分で美しく逃げ切ったアリスヴェリテが重賞初制覇〜2024年・マーメイドS〜](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33680.jpeg)


