ノンフィクションライター・長谷川晶一氏が、異業種の世界に飛び込み、新たな人生をスタートさせた元プロ野球選手の現在の姿を描く連載「異業種で生きる元プロ野球選手たち」。第9回に登場して頂くのは、北海道日本ハムファイターズ、東京ヤクルトスワローズで活躍した鵜久森(うぐもり)淳志さん(37)。愛媛・済美高校時代、センバツ高校野球で初出場・初優勝をはたしてプロ入りした鵜久森さんに立ちはだかった“プロの壁”とは――。前編では、長打を武器にプロ入りから引退するまでを振り返ってもらいます(前後編の前編)。
ダルビッシュ有と同期で、北海道日本ハムファイターズに入団
2004(平成16)年のセンバツ(選抜高等学校野球大会)において、愛媛代表・済美高校は初出場・初優勝をはたした。1988(昭和63)年センバツで、同じく愛媛代表の宇和島東高校を初出場・初優勝に導いた上甲正典監督を招聘したことが奏功したのである。
「やれば出来る」は 魔法の合いことば
ユニークな歌詞を持つ済美高校の校歌は一躍有名となった。その中心にいたのが四番打者として2本のホームランを放った鵜久森淳志である。さらに夏の甲子園では3本塁打も記録し、同校の準優勝に大きく貢献した。この年のドラフトで、東北高校・ダルビッシュ有とともに北海道日本ハムファイターズに入団。鵜久森の前途は明るく、希望に満ちたスタートとなった。
「バッティングに関してはすごく自信はありましたね。やっぱり結果を残したかったですし、プロの世界でもホームランをたくさん打ちたいとか、理想の将来像があったので、生意気だったと思います(笑)」
この年のファイターズはドラフト1巡目がダルビッシュで、鵜久森は8巡目だったが、本人は球団や世間からの評価に関しては、何も気にしていなかった。
「とりあえず、まずはプロに入らないことには何も始まらないので、ダルビッシュと比べて、ドラフトの順位が高いとか低いとか、その点は気にしていなかったです。だけど、今から考えると、すごく妥当な評価だったと思います(苦笑)」
長打力には非凡な才能を誇っていた鵜久森だったが、守備に関してはまったく自信がなかった。足が速いわけでもない。彼が誇るものは、誰にも負けない長打力。ただこの一点にあった。
「僕にはバッティングしかなかった。それは自分でもよくわかっていました。守備に関しては不安しかなかったですから。だから、そこだけを見れば、“当然上位指名はないな”と思いますよね。やっぱり、《走攻守》の三拍子とは言わなくても、最低でも二拍子そろっている人が、上位指名されますから。だから球団としても、僕の指名はある意味では賭けだったのかもしれないですね。自分でも、長打力しか武器がないと思っていましたから」
いわゆる「即戦力ルーキー」としてではなく、秘めたる可能性が魅力の選手として、鵜久森のプロ生活はスタートしたのである。
同期・ダルビッシュからの気遣い
プロ入り後、ファイターズは鵜久森を「強化指定選手」とし、ファームでひたすら試合に出場させる育成方針を採用した。試合後には連日の特守 も行われた。試合においては、生きた投手のボールに慣れること。練習においては、最低限の守備力を身に着けることを目的としたのである。それでも、雌伏の時期は続いた。
「最初の数年間はずっと結果が出ずに、焦りしかなかったです。自分は守れない分、打つしかない。だけど、全然ボールが前に飛ばないし、三振も多い。だからといって、単打を狙って当てにいくタイプのバッターではないので打率も残らない。毎日悩んでいました」
同期のダルビッシュはすでに一軍の主力投手として活躍していた。一軍本拠地の札幌ドーム(当時)で躍動する同期の姿を、二軍のある千葉・鎌ケ谷の選手寮で応援する日々。しかし、ダルビッシュもまた鵜久森のことを陰で支えていた。
「あるとき、ダルビッシュから食事に誘われました。聞けば、当時の西武の中心選手だった中島(裕之/現・宏之)さんと栗山(巧)さんも一緒にいるということで、“せっかくの機会だから、いろいろ質問すればいいじゃん”って、僕のことを気遣ってくれたんです。でも、あまりにも緊張しすぎて、何を聞いたのか、どんなことを話したのか何も覚えていません(笑)。だけど、ダルビッシュの気持ちはすごく嬉しかったです」
同期でありながら、ダルビッシュに対しては「ずいぶん遠くに行ってしまったな」という思いを抱いていた。だからこそ、その気遣いがかえって心に沁みた。それでも、なかなか結果が出ない日々が続いた。プロ7年目に待望の初ホームランを打ったものの、その後もブレイクを果たせず、次第に活躍の場は減じていく。気がつけば後輩の陽仲壽(現・岱鋼)、 中田翔の後塵を拝することとなっていた。
「当時はいつも、“そろそろ戦力外通告を受けるかも……”という思いでした。現在のように育成制度があればとっくにクビになっていたはずです。だから、日本ハム球団には感謝の思いしかありません。期待されているのはわかっているのに、その思いに応えることができない。今から思えば、日本ハム時代はずっとそんな感じでしたね……」
そして、ついに「そのとき」が訪れる。15年オフ、鵜久森は戦力外通告を受けた。プロ11年目、28歳の秋の日のことだった。
「報恩謝徳」の思いで駆け抜けた14年間のプロ野球人生
それでも現役を続けるつもりでいた。迷いなく合同トライアウトを受験すると、「右の代打候補」を探していた東京ヤクルトスワローズが獲得に名乗りを挙げた。首の皮一枚ではあるが、鵜久森に現役続行のチャンスがもたらされたのである。
「今から思えば、このときから野球に対する考え方が変わりました。それまでは、“自分のため”に野球をしていました。でも、ヤクルトに拾ってもらってからは“人のため”という思いが強くなりました。せっかくチャンスを与えてもらったのに、また同じ失敗をするわけにはいかない。自然と、“監督のために、ファンのために、家族のために”という思いが強くなっていったんです」
この頃、鵜久森は「ある言葉」に出会っている。
「たまたまネットを見ていたら、《報恩謝徳》という言葉を見つけました。自分が受けた恩に対して、最大限の努力をして報いたい。そんな感謝の思いを込めた言葉です。それは、当時の自分にすごくフィットした言葉でした。ヤクルト時代は、常に《報恩謝徳》の気持ちで打席に入っていました」
スワローズ移籍初年度には46試合、翌年には45試合に出場した。17年4月2日の横浜DeNAベイスターズ戦では、4対4で迎えた延長10回裏、1死満塁の場面で代打で登場すると、須田幸太からサヨナラ満塁本塁打を放った。
「あのとき、左ピッチャーのエスコバーから右の須田に代わりました。それでも、真中(満)監督は僕をそのまま起用してくれました。それはやっぱり、意気に感じますよね。あのホームランは忘れられない一発となりました」
結果的にこれが、鵜久森にとってのプロ生活最後のホームランとなった。18年オフ、再び戦力外通告を受けた。プロ生活14年で256試合出場、放ったヒットは111本、ホームランは11本。通算打率は2割3分1厘だった。再びトライアウトを受験したものの、どこからもオファーはなかった。こうして鵜久森は、31歳での現役引退を決めた。
「二度目のトライアウトは、自分でも“受からないだろうな”と思っていました。だけど、“これまで応援してくれたファンの方々に最後のユニフォーム姿を見てもらいたい”という思いで臨みました。野球人生に別れを告げるつもりでした。改めて、これからどうするかを決めるつもりでした」
そして、このトライアウト会場での出会いが、鵜久森の第二の人生に向けての指針となる。彼が選んだのはソニー生命、ライフプランナーとして生きる道だった――。
(文中敬称略・後編【「プロ野球時代より責任は重い」「死ぬ気で頑張れば…」元ヤクルト選手がソニー生命社員になって思うこと】に続く)
長谷川 晶一
1970年5月13日生まれ。早稲田大学商学部卒。出版社勤務を経て2003年にノンフィクションライターに。05年よりプロ野球12球団すべてのファンクラブに入会し続ける、世界でただひとりの「12球団ファンクラブ評論家(R)」。著書に『いつも、気づけば神宮に東京ヤクルトスワローズ「9つの系譜」』(集英社)、『詰むや、詰まざるや 森・西武 vs 野村・ヤクルトの2年間』(双葉文庫)、『基本は、真っ直ぐ――石川雅規42歳の肖像』(ベースボール・マガジン社)ほか多数。
デイリー新潮編集部


































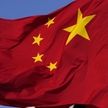











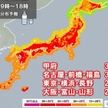



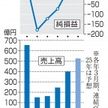














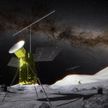




















































































![[連載]イーストスタッドブログ・第7回 新種牡馬、レッドルゼルについて](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33395.jpg)


