“生みの親”はアイデアマン「近藤貞雄監督」
打力や投手力が売りのチームは珍しくないが、盗塁でひたすら走りまくるチームは、なかなかお目にかかれない。そんななかで、1980年代半ば、1チームで3人が史上初の40盗塁以上を記録する快挙が実現した。大洋(現・DeNA)のスーパーカートリオである。【久保田龍雄/ライター】
1番・高木豊、2番・加藤博一、3番・屋鋪要の3人からなるスーパーカートリオは、1985年に大洋の監督に就任した近藤貞雄が“生みの親”になる。
近藤監督は1966年の中日コーチ時代、まだ先発完投が当たり前だったときに「投手の肩は消耗品」と日本で初めて投手分業制を導入し、中日監督時代(81〜83年)にも試合の前半を攻撃主体、後半を守備主体にメンバーをガラリと入れ替える“アメフト野球”を用いるなど、無類のアイデアマンだった。
その柔軟な発想力は、大洋でもいかんなく発揮される。川崎球場時代から「打線が打てば勝ち、打てなければ負け」という大味なチームを、足をフルに使ったスピード型のチームへと大改造したのだ。
前年の盗塁王・高木を1番、俊足巧打の加藤を2番に据え、3番にはプロ野球運動会の100メートル走で3年連続優勝した“快速男”屋鋪を入れた。3番は「強打者、もしくは好打者」が常識とあって、前年8番を打っていた屋鋪の抜擢には、敵将からも驚きの声が上がった。
だが、近藤監督は「球場などを考えた場合、屋鋪がピッタリなんです。なぜかといえば、両翼94メートル、しかもフェンスが4メートル以上もある。ホームランは後楽園なんかに比べたら、はるかに出にくい。そういうところで3番というのはね、シングルを二塁打、二塁打を三塁打にできる男。これだと思うんです。1番から3番まで足を使える男を並べる。これが横浜球場に合った打線なんです」(『週刊ベースボール』85年8月12日号)と力説した。
「50個アウトになってもいいから、100個走れ」
屋鋪の3番起用は当たり、85年は打率.304、15本塁打、78打点を記録。まさに「立場が人を育てる」だった。8番時代は塁に出ても、次打者の投手が送りバントをするケースが多く、盗塁数も伸びなかったが、3番に定着すると、水を得た魚のように、高木、加藤とともに走りまくった。
近藤監督も3人に「50個アウトになってもいいから、100個走れ」と厳命した。どんな場面でも「とにかく走れ」で、帰塁したら罰金というから、徹底している。
三者三様、走り方にも個性があった。トリオの一人、加藤は「高木君は都会的なセンスで走るという感じだし、屋鋪君は野性味のある走り、そして私は庶民的な(?)走りだった」(自著『生き抜いた21年』青谷舎)と回想している。
高木は中央大時代の1979年6月、全日本大学野球選手権決勝、早稲田大戦で、“神走塁”を披露している。0対0の3回2死満塁、4番・小川淳司の中前安打で一塁から一気に本塁を突き、捕手の落球に乗じて、あっと驚く3点目をもたらしたのだ。190センチ近い巨体のチームメイトと相撲を取って勝ったという話も伝わっており、抜群の身体能力を持っていた。
最年長の加藤は、投手の癖を見抜くのがうまく、高木が“足のスランプ”に陥ったときは、エンドランの形でアシストする良き兄貴分。屋鋪はスタートが遅れても、強引に二盗を成功させてしまう野性味に溢れ、足の速さでは、トリオの中で文句なしの1番だった。
3人で計148盗塁を記録
この3人が足でかき回し、一発のあるレオンや田代富雄がポイントゲッターになる。そんな作戦が見事にハマったのが、85年6月16日の阪神戦だった。
1回に岡田彰布のタイムリー、3回に掛布雅之の2ランで3点を先行され、打線はゲイルの前に6回まで3安打無得点に抑えられていた。
だが、大洋はゼロ行進を続けながらも、加藤、高木がバント安打、屋鋪と加藤が二盗を成功させるなど、序盤から足で揺さぶり、ゲイルを心身ともに消耗させていく。
そして7回、ゲイルの疲れに乗じて四球とエンドランでチャンスを広げ、代打・高木由一が中前タイムリー。さらに2死後、加藤、屋鋪の連打で一挙同点に追いつくと、8回に田代の決勝2ランが飛び出した。
この結果、首位・阪神は2位に転落し、大洋は首位・広島に3ゲーム差の3位に浮上。7月以降、黒星が先行し、V争いから脱落したものの、足で魅せる積極果敢な野球は、チームを活性化し、ファンを楽しませた。
近藤監督は3人で最低100盗塁、できれば120盗塁を期待していたが、同年は高木が42、加藤が48、屋鋪が58と3人で計148盗塁を記録。盗塁王こそ「73」の広島・高橋慶彦に譲ったが、同一チームの3人が40盗塁以上を記録したのは、現在でも“唯一無二”の快挙である。
「スーパーカー」か、「スポーツカー」か?
ところで、スーパーカートリオは、当初は“スポーツカートリオ”と呼ばれていた。評論家時代の長嶋茂雄氏が最初にスポーツカートリオと命名したが、後に近藤監督が「今流行りのスーパーカーに」と改名したとされている。高木豊や屋鋪も同様の証言をしているが、その一方で、長嶋氏が「スーパーカー」と言い間違えたのがきっかけで定着したという正反対の異説も伝わっている。
ちなみに、「週刊ベースボール」では、1986年3月31日号まで「スポーツカー」、同年4月の開幕カードで大洋が前年の覇者・阪神を3タテした直後の4月28日号以降から「スーパーカー」に変わっている。「スポーツカー」も意外に長く用いられていたことがわかる。
だが、86年後半以降は、加藤が右足首の故障でほとんど出場できず、トリオも半ば解散状態に。近藤監督も同年限りで退任した。
3人のスピードスターが一世を風靡したのは、85年の開幕から86年前半戦までの実質1年半ながら、今もスーパーカートリオの呼称に郷愁のような懐かしさを覚えるファンは少なくないはずだ。
久保田龍雄(くぼた・たつお)
1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。
デイリー新潮編集部













































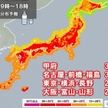

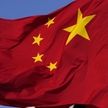

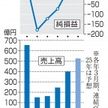














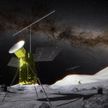



































































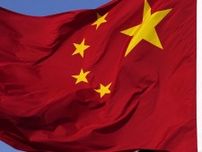














![[連載]イーストスタッドブログ・第7回 新種牡馬、レッドルゼルについて](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33395.jpg)


