日本の火葬率は99.99%(2022年度衛生行政報告例、厚生労働省)。「故人を火葬場で火葬する」のが、ほぼ必須の国だ。
私はかつて『葬送の仕事師たち』(新潮社)を書くにあたって、火葬場を取材した。遺族にとって故人と最後のお別れとなる、悲しみのピークの場だし、働くスタッフにとってもデリケートな働きが必要な場だ。
「火葬開始」のボタンを押せば、遺体はすべて自動的に焼かれると思われがちだが、火葬炉の担当者は、いわく「きれいに焼く」ために、燃焼具合を小窓から目視し、炉温の調整に余念がない。もっと言えば、小窓から鉄の棒を差し込んで遺体の部位の位置を動かすこともある。
人間は心臓が止まった時点で、即物的にはモノになる。しかし、感情的には割り切れないものがあるから、遺族も葬送の仕事人も一所懸命に故人と向き合っている――。
そんな感想を持ったことを、このほどインドのガンジス川の川岸に位置する町、バナーラス(バラナシ、ベナレスとも)で思い出さずにはいられなかった。そして、ところ変われば「しきたり」も変わる、とつくづく思った。報告したい。【ノンフィクションライター/井上理津子】
(前後編の前編)
***
ヒンドゥー教徒なら“バナーラスで火葬”
首都・デリーから南東に約800キロ、空路2時間弱。バナーラス空港に着くと、赤や黄などカラフルな色の花々に迎えられ、「南国に着いた」と心躍った。デリー郊外に在住して10年の親戚、前田くんが同行してくれた今回のバナーラス旅は、日本語ガイドのSさん(38)と空港で会い、始まった。
「ようこそ。バナーラスは日本で言うと京都です。3000年の歴史あるヒンドゥーの聖地ですから、インドに来たからには絶対に来てほしい町。大歓迎します」
「ガンガー(ガンジス川)の雄大な流れに身を置ける。あなたたちは幸せ」
「絹織物の産地です。金銀銅をあしらった厚手のバナーラスシルクがスペシャルです」
などと、Sさんは立て続けにバナーラスの町をアピールする。「なんでも聞いてください」とおっしゃるので、さっそく質問してみた。「あなたもヒンドゥーですか?」と。
「もちろんです」
「あのー、ご両親はご健在?」と婉曲に問いを重ねた私の本当に知りたかったことをすぐさま察してくれ、
「いいえ。父は亡くなり、バナーラスで火葬しました」
「バナーラスで火葬、が意味するのは、ガンジス川の川岸にある野外火葬場で火葬することですよね?」
「はい、もちろん。私自身もいずれバナーラスで焼いてもらうつもりですよ」
そんなSさんとのやりとりと、前田くんが「仕事仲間のヒンドゥー5人にヒアリングしたら、全員が『自分もバナーラスで火葬を望む』と言っていた」と話してくれたことが、今回の旅の最大の目的である火葬場見学の伏線となった。
ガンジスでの水ごりは朝が多い
車で移動し、1時間ほどで旧市街の中心地に着く。道という道に人があふれ、犬もあふれ、時おり牛が寝そべっている。そんな光景も、迷路のような路地に小さな店がひしめく光景も堪能。夕方からプージャ(ヒンドゥーの礼拝儀式)を見に行き、東京ドーム5つ満杯になるくらいの人数(あくまで私の感覚です)が、200メートル四方(同)の中で蠢く人熱に圧倒され……の後だから、夜の8時半過ぎだった。ガートが連なり、チャイや花の売り子が数多いるガンジス川の川岸をそぞろ歩いて、火葬場へ行き着いたのは。
ガートとは、岸辺から階段状に川水に没している堤のことで、バラーナスには84カ所あり、そのほとんどが沐浴場となっている。夜なのに水ごりする人たちがちょこちょこいた。
暗いので、水はきれいとも汚いとも、いまひとつ分からなかったが、「赤ん坊の死体や牛の死体がどんどん流れてきて、悪臭が漂っている」などと言われるのは、ずいぶん誇張があると思うに十分で、少なくとも悪臭はしなかった。
「ガンガーでの水ごりはヒンドゥーにとって最も尊いこと。インド全土から来ていますね、ま、朝の方が多いですが」と説明してくれた後、Sさんがあまり喋らなくなり、歩みが重くなった。その先に煌々と炎が上がる火葬場があった。
あちらにもこちらにも橙色の炎が
「2か所ある野外火葬場のうちの1か所、マニカルニカー・ガートのようだね。運ばれてきた死者はまずシヴァ神を祀る寺院に安置され、それからここへ来る。ここでの火葬は肉体から魂を解放して、輪廻転生するための儀式なんだって」
と、前田くんがスマホをさくさく調べ、伝えてくれる。
火葬場内に立ち入ることに、Sさんも前田くんも積極的でなかったようで、私は一人で近づいて行ったのだが、「うわー」と何度声を上げたことか。階段上の通路の両側、あちらにもこちらにも橙色の炎が「ごおー」と音をたてて上がっていて、呆気にとられた。炎(すなわち火葬中の遺体)を取り囲む、遺族らしき人たちも相当数いる。あ、鉄の棒を手に、遺体がよく焼けるように働いている(と直感した)スタッフさんたちも。遺体を担架で運んできて、「これから焼く」感じのグループもいた。
スマホで写真を撮っていると、男の人がやってきて、
「写真ノー」
と怒られた。「ごめんなさい。つい」と応じると、なぜかその人は、「OK。いいよ」とすぐさま許してくれて、
「24時間焼いている。1体3時間、1日200体」と言った。
「もっと知りたいなら、私にお金を」
「もっと知りたいなら、私にお金を。私はすぐそこのホスピスのスタッフ。ここは普通の人を焼く場所だけど、私にお金を払うと金持ち用の火葬場も見せてあげる」と営業トークをなさった。
私はまだそういうのに慣れていなかったから、怪しい、と思って断って、その夜はただただ静かに見学して、火葬場のエリアをあとにした。火葬場から100メートルほど離れた階段のところに、サリーを着た6、7人の女の人がかたまって座り、全員に涙の痕跡があった。遺族だ、と思った。
「Sさんはお父さんを見送ってからまだ日が浅いから、火葬場が苦手なのでは。バナーレスで火葬できたことは誇りだけど、リアルを思い出すと辛い。そんな感じみたい」
と、待っていてくれた前田くんが、Sさんが去った後で言う。「Sさんの気持ち、なんとなく分かるよねー」と言い合いながら、ホテルに戻る(仕事とはいえ、しんどい思いをさせて、Sさんごめんなさい)。
***
インドのヒンドゥー教徒が誇りとする「バナーレスでの火葬」。お墓の概念がない地域ではどのように遺骨を扱うのか? また「女性遺族は立ち入り禁止」の理由とは? 後編では火葬の具体的な手順などをお伝えする。
後編【遺体は裸でテカテカ、女性遺族は立ち入り禁止、なぜか水牛のお乳が…インド・ガンジス川の野外火葬場で見た驚きのしきたり】へつづく
井上理津子(いのうえ・りつこ)
ノンフィクションライター。著書に『さいごの色街 飛田』、『葬送の仕事師たち』(ともに新潮社)、『絶滅危惧個人商店』(筑摩書房)、『師弟百景』(辰巳出版)などがある。
デイリー新潮編集部

















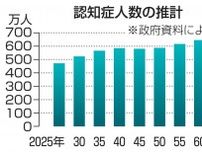











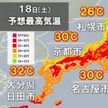





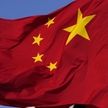

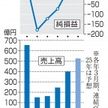













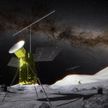



















































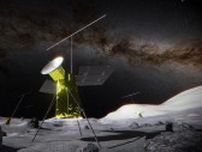












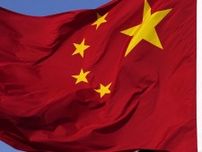
















![[連載]イーストスタッドブログ・第7回 新種牡馬、レッドルゼルについて](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33395.jpg)


