中国では不動産バブルの崩壊が長期化し、デフレに突入する懸念も強まっている。習近平政権は国内外で強権的な政治を進めていることもあり、国際投資アナリストの大原浩氏は、経済が長期低迷する「失われる50年」になってもおかしくないと指摘する。それでは中国に代わって急成長する国はどこなのか。
◇
1978年に鄧小平氏が始めた改革開放路線は目覚ましい成果を上げた。北朝鮮よりも貧しいといわれていた国が、米国に次ぐ国内総生産(GDP)世界第2位の経済大国に上り詰めたのだ。
しかし、97年の鄧氏の死後四半世紀以上を経て、習主席は「悪夢の毛沢東時代」への回帰を鮮明にしている。中国の経済状況が今後も悪化するのは明白で、「失われる50年」に向かっているといえるだろう。
「失われた30年」と呼ばれた日本のバブル崩壊以後よりも状況が厳しいと筆者が考えるのは、「中国共産党一党独裁」が抱えるリスクによるものだ。
シンガポールも強権的な政治を行っているが、建国の父リー・クアンユー氏から引き継がれる政策が、1人当たりGDPでは米国を上回り世界第5位という豊かな国に浮上させた。したがって国民は政府を支持し、政治も安定している。
逆に言えば「貧しくなりつつある国が、強権政治を強める」ことがどのような結果を招くのか、火を見るより明らかだ。
それでは、中国に代わる世界経済の牽引(けんいん)役はどこになるのであろうか。
人口で中国を抜いたインドが取り沙汰されているが、筆者はそうは思わない。2014年の製造業振興策「メーク・イン・インディア」によって当時GDPに占める割合が15%程度だった製造業の比率を22年までに25%に増やす目標だった。だが、20年度は18.8%、21年度は18.7%、22年度は17.7%と大きな変化がない。
中国の場合、改革開放の初期には鄧氏自身が頭を下げ、華僑や日本など海外の企業・政府に協力を依頼した。毛沢東時代に「走資派」を始めとする資本主義や市場を理解できる人々を放逐したこともあり、資金もノウハウも国外から導入するしかなかったのだ。
証券市場の整備には日本の大手証券会社が全面協力した。松下幸之助を始め多くの財界人が改革開放を手助けした。
現在のインドも、資金やノウハウが不足しているが、海外からの参入障壁は極めて高い。しかも、製造業にとって重要なインフラを積極的に整備しようとする気配もないのが実情だ。
むしろ、あまり注目されないが、米国に次ぐ世界第4位の人口大国であるインドネシアの方が発展の可能性が高いかもしれない。
特に、首都を現在のジャワ島に所在するジャカルタから、カリマンタン(ボルネオ)島のヌサンタラに移転するという壮大な計画が発展の決め手になると考える。
ジャワ島のジャカルタは地盤沈下や慢性的な洪水、渋滞、人口過密など多数の問題を抱えており、首都移転を成功させれば「新たな道」が開けそうだ。移転費用の8割を民間や海外に頼る手法には危うさもあるが、外部からの協力が必要不可欠であることは、インドネシア政府も十分認識しているはずである。
幸いにして、「インドネシア建国の父」であるスカルノ氏は親日家だった。現在も日本のアニメなどの後押しもあってインドネシアはかなりの親日国だといえる。
今後、われわれが協力するのならば、「親日国・インドネシア」を選ぶべきではないだろうか。
【おおはら・ひろし】 人間経済科学研究所執行パートナーで国際投資アナリスト。仏クレディ・リヨネ銀行などで金融の現場に携わる。夕刊フジで「バフェットの次を行く投資術」(木曜掲載)を連載中。

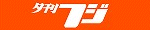










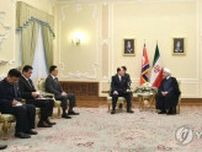














































































































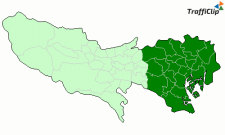

![[連載・片目のサラブレッド福ちゃんのPERFECT DAYS]登録者数2000名突破!(シーズン1-7)](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33426.jpg)





