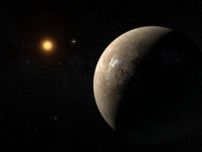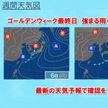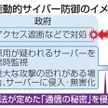世界最大規模の峡谷であるグランドキャニオン。数十億年分の地層が刻まれた赤褐色の岩肌がむき出しになり、砂漠が広がる。この峡谷のあるアリゾナ州は、地質学上、重要な地域とされ、宇宙研究もさかんに行われてきた場所だ。
2月下旬、アリゾナ大の建物の一室にあるスクリーンで、生きたクマムシがうごめく姿が顕微鏡から映し出されていた。高温や低温などさまざまな条件でも増殖できる、極限環境微生物の一種。同じような環境下で生きうる地球外生命体を理解する足掛かりになるとみられている。
アリゾナ大は、アポロ11号の月面着陸計画も支えた天文学で先駆的な大学だ。近年の研究から宇宙に生命体がいる可能性が現実味を帯び始め、宇宙生物学や地球外生命体への関心の高まりと研究の進展もあって、昨年10月、アリゾナ・アストロバイオロジー(宇宙生物学)センターを発足させた。
この日は、地球外生命体に関心をもつ学部生や院生の有志が集まって、3月中旬に大学で予定されていたイベントの出し物の目玉として、この生きたクマムシの展示をしようと準備中だった。「いまの地球上にいる『地球外生命体に近いもの』と見てもらえたら」と、博士課程のソーサン・ウェビさんは話す。
センターは学部横断型で、3月時点で14の研究領域から40人以上の研究者らが参加する。科学だけでなく、アート、言語学や哲学の領域の専門家も参加し、幅広く地球外の生命体について考える枠組みが作られた。
タブーだった議論をオープンに
UFOや宇宙人を想起させる地球外生命体は、長く科学界が本気では扱わないテーマだった。だが1990年代の太陽系外惑星の発見で、次第にこうした研究に光が当たるようになった。地球以外にも、水など一定の条件が整えば、極限環境微生物などもふくめ、生き物はいるのではないかという見方は近年、広がっている。それでもまだ地球外生命体のなかで、人間とコミュニケーションをとれる知的な生命体や、そうした存在がもち得る技術について、話しやすい環境にはないという。
この学際的なセンターを立ち上げたアリゾナ大惑星科学部のダンテ・ローレッタ教授は、知的な地球外生命体も研究対象にしていくと明言する。
「ここはだれもが参加できる場所で、生命や意識など、様々なテーマについて話せることを目指しています。特に若い人たちがどんなテーマでもタブーなく対話ができるような環境づくりに努めています」
そう考えるのは、ローレッタ氏自身、学生時代に地球外生命体への思いが芽生えた時の経験があるからだろう。学費を自分で納めていたローレッタ氏は、1992年、NASAが出す学部生用の研究助成金を取った。地球外知的生命体の出す電波などをキャッチする「地球外知的生命体探査(SETI)」だった。やりたいことが見つかった! そう思ったが、当時は、SETIや地球外生命体の研究は真剣には受け止められず、「キャリアの自殺になる」とさえ言われるほどだった。
そこで、「地球でなぜ生物が暮らせるようになったか」を研究テーマに据え、隕石の研究もした。2002年の南極大陸の調査に参加したとき、大気圏をとおり、太陽にも照らされて化学変化を起こしたと見られる隕石からだけでは宇宙の実態は見えない、と感じた。やはり宇宙に行き、物質をとってこなければ─。2004年からの7年間でNASAに3本の提案書を出し、「米国版はやぶさ」といわれる探査機「オシリス・レックス」の企画を通した。
小惑星から物質を採取する探査は、米国では初めてだった。
生命の起源を知る手がかりに
ローレッタ氏の研究室のある同じ建物には、NASAの委託を受け、このオシリス・レックスで採取してきた砂などの一部を解析するラボがある。ラボで見せてもらった透明の小さなボトルの内側には、漆黒の細かい粉状の砂が、スプレーをかけたように広がっていた。
いまはラボの最新施設を使って、この砂にどんな物質がどんな割合で入っているか解析している。今後こうした研究は10年単位で深められていくだろうとみられている。
ローレッタ氏は言う。
「小惑星がどう生物の起源にかかわり、どんな環境で生物が絶滅し、また別の生物が誕生したかを探る機会にしたい。宇宙生物学につながる研究だ」
私たちは宇宙で孤独な存在なのか─。はるかギリシャ神話の時代から人が問うてきたこの問いに、センターでは文系を含めたさまざまな学問分野を巻き込み、取り組もうとしている。
アートを通じて私たちの存在を伝える?
アート分野もその一つだ。同大芸術学部副学部長のエレン・マクマン氏も参加する一人。生物学を専攻した後、アートも学び、科学領域のイラストやデザインも手掛けてきた。アートは、従来と違った視点で見たり、発想したりすることを求められ、宇宙生物学のような学際的なテーマに役立つと考えている。2月中旬には、天文学に造詣(ぞうけい)の深いアーティストと連携し、ワークショップも企画した。
今後は、宇宙の生物、地球外知的生命体がいるとすれば、人間側としてどうコミュニケーションをとるかも、アートを通じて探りたいと考えている。
「(たとえば壁画のように)私たちが時代を超えて歴史の文明を知るのは、アート作品から。アートは、時空を超えて地球外生命体に私たちのことを伝えていく手段になるとも考えています」
日本にも宇宙生物学の研究拠点
実は、日本にも宇宙生物学を学際的にすすめる動きはある。
自然科学研究機構(東京都)の中に、「アストロバイオロジーセンター」が2015年に設立された。太陽系外惑星や、宇宙にいるかもしれない生物について学際的な研究をすすめることが目的で、現在は、系外惑星探査プロジェクト室、宇宙生命探査プロジェクト室、アストロバイオロジー装置開発室の三つで、研究を進めている。研究員の多くは、国立天文台(東京都)と基礎生物学研究所(愛知県)と併任したりしている。
このセンターを設立した当時の自然科学研究機構長だった東京大の佐藤勝彦名誉教授(宇宙物理学)は「生命、知的生命体は宇宙の作りだした最高の創造物だ。生命を考えるとき、他分野との共同研究は非常に重要になってくる。日本の大学のなかで、宇宙生物学の研究をできればと思って立ち上げた」と話す。
佐藤教授自身も当時から、文系分野との連携は視野に入っており、監修した「科学者18人にお尋ねします。宇宙には誰かいますか?」(2017年、河出書房新書)では、自ら人類学者らと鼎談した。「この宇宙で自由意思を持ち、物理法則を知り尽くしたような生命体が生まれた不思議は、物理学者にとって究極の課題。より深い理解のためには物理学者、人類学者、そして哲学者との協働が不可欠だ」との思いがあるからだ。
日本のアストロバイオロジーセンターも文系分野にも関わる可能性はあるのか。センター長の田村元秀・東京大教授は、同センターにおける文系分野との協働は将来的には「発展的にできる」とした上で、「現在でもある公募研究は文系分野にも開かれており、これを通して協力できると思う」とも話した。