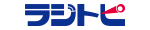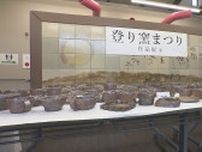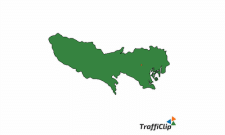乗客106人が亡くなり、562人が重軽傷を負ったJR福知山線脱線事故は4月25日、発生から19年を迎えた。この事故で、当時大学生だった次女が重傷を負った三井ハルコさん(兵庫県川西市)がラジオ関西の取材に対し、「次世代に何を語り継ぎ、伝えるか」を語った。
三井さんをはじめ、事故の負傷者と家族らの有志は、事故から約2か月経った2005年6月、思いを話し、共有する「語りあい、分かちあいのつどい」をスタートさせた。
そして事故の2年後、2007年7月から「補償交渉を考える勉強会」を開催。その後、補償(賠償)交渉などが個別では対処しきれなくなったため、2008年2月に「JR福知山線事故・負傷者と家族等の会」を設立した。また負傷者やその家族らの「空色の会」も生まれた。
この19年間、心が折れそうになったことは何度もあった。あくまでも事故現場にいたのは次女であり、自身はあの場にはいなかった。「当事者ではないが、負傷した家族としての立ち位置」はどうあるべきかを問い続けている。
「事故の教訓をどう伝えるか、負傷者と家族の何を伝えるか」。19年という月日は、それを精査することの重要性を与えてくれた。事故を知らない世代にも、心の片隅に留めてほしい、風化していく流れをどう緩めていくのかを考えている。
「安心・安全な社会は、人任せでは成立しない」。これは三井さんが訴え続けているテーマだ。「この事故をめぐっては、専門家も、遺族も、負傷者も、加害企業であるJR西日本も、それぞれの立場で発信すべきものがある」という考えは変わらない。
しかし、時間がすべてを解決してくれるわけではない。事故によって一度壊れた心、傷んだ身体は、そう簡単に元に戻らない。むしろ目に見えぬ“しこり”、無言の“苦しみ”として、重くのしかかる。
だからこそ、三井さんは次女と事故の話を持ち出さないようにしている。昨今議論されている、事故車両のあり方については特にそうだ。
1985年に起きた日本航空ジャンボ機墜落事故は、JR福知山線脱線事故と同じく、人々の安全神話を根底から覆した大惨事だった。羽田空港の日航安全啓発センターで見た事故機体は、あまりにもインパクトが大きかった。
機体を見ることは、社会的な出来事として、安全への意識を喚起させるには“語る教科書”になり得るかも知れないが、その車両を目にすることによって、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に苦しむ人もいる。拙速に進めるものではなく、議論を尽くすことが重要だと三井さんは話す。
日航ジャンボ機事故をめぐっては、事故の教訓を伝えるため、羽田空港にある日航の社員研修施設「安全啓発センター」で事故機体の一部や乗客の遺品が展示されている。それは事故から21年後のことだった。
JR西日本は、社員研修センター(大阪府吹田市)の敷地内に整備し、2025年度中に完成する見通しだ。社員教育の一環として、事故車両を保存することを検討しているが、一般公開については、「車両を直視することができない」という遺族の意見を踏まえて展示方法を見直すなどしており、これからの課題となっている。
最も恐れるべきは、無関心。特に今年は、元日から能登半島地震が起き、海外でも戦乱が収まらない。さまざまな問題が国内外を取り巻いている。
こうした中、三井さんは感覚が鈍麻(どんま)してしまい、世の中の出来事に何も感じなくなることの恐ろしさを危惧している。
今年も、4月25日がめぐってきた。三井さんは「一定程度、記憶が薄らぐことは仕方ない。しかし、『こんなものだ』と諦めてはいけない」と願う。
ペイフォワード(Pay it forward)という言葉がある。自分が受けた善意をつないでいくことを意味し、三井さんは「恩送り」と訳している。
阪神・淡路大震災の前年(1994年)、三井さんは脚の手術のために緊急入院した。その時、ある女性が身の回りの世話をしてくれた。嬉しさの反面、申し訳ない気持ちでいっぱいになった。「何もお返しができない…」かえって気を遣っていた。それを察した女性は「そんなこと、気にしないで。私に何かを返そうとするから気持ちがしんどくなる。全快して気持ちが落ち着いたら、どなたかに返してくれたら」と声をかけてくれた。救われた気がした。
1年後に起きた震災の時も、手術後、完全に復帰できなかった三井さんは「恩送り」ができなくて悲しい思いをした。そして10年後、脱線事故が起きた。次女が負傷したからではなく、今度は負傷者とその家族のケアを考え、今度こそはと、19年にわたる「恩送り」を続けている。
そして、「JR西日本の社内体質が、『お互い(乗務員、従業員)どうしをいたわりあう』ものだったら、この事故は起きなかったかも知れない」と話す。過密なダイヤの中、オーバーランなどで遅延を招いてしまうと、当時のJR西日本では「日勤教育」という懲罰が待っていた。
恩を送り、互いを尊重する社会。「時代の潮目を迎えているような気がする。安心・安全な社会を本当に構築するのはこれから」。節目となる20年を前に、何をすべきかを見出した三井さんの優しい笑顔の奥に、鋭い視線が見えた。