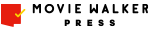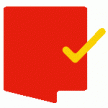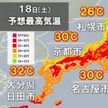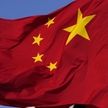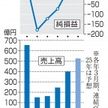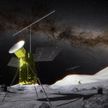リバウンドとは、ミスをチャンスに変え、失敗を成功へ導くこと。現在公開中の『リバウンド』は、王道スポ根ものながら、世界を虜にする韓国エンターテインメントの底力を感じられる作品だ。監督・脚本を手掛けたチャン・ハンジュン監督(『記憶の夜』(17))、選手役のチョン・ジヌン(2AM)に話を聞いた。
■「“負け犬の物語”が今だからこそ響くテーマになる」(チャン・ハンジュン監督)
釜山の弱小高校バスケットボール部を任された未経験新任コーチが、その破天荒なリーダーシップでチームをまとめあげ、強豪校を次々と打破していく…という、どこのスポ根漫画ですか?というような物語。だが、これは2012年に実際に釜山であった実話で、チャン・ハンジュン監督は、実際のコーチから全国大会を終えて釜山に戻る際に、すでに話を聞いていたそうだ。「今作のプロデューサーがコーチと話をして、すぐに私に電話がかかってきました。それから5年後、完成した脚本が私の元に届いたのです」。ところが、撮影に向けて選手役のオーディションを行なっていると、出資会社の経営状況により製作が中断してしまう。「それから2年が経ち、ようやく製作が再始動しました。つまり、この映画の出で立ちがすでに“リバウンド”だったのです。という意味で、私もこの物語と同じ経験をしたと言えますね(笑)」と、チャン・ハンジュン監督は自嘲する。
数多くあるスポーツを題材にした映画の中で、今作の特異なる点はなにか?と考えたとき、チャン・ハンジュン監督は、“負け犬の物語”が今だからこそ響くテーマになるのではないかと考えたそうだ。「今の世の中、誰もがチャンスを与えられるわけではありません。だからこそ、絶対に諦めない精神、どんな小さな可能性も見逃さないような粘り強さが人々を勇気づけ、映画を観た人たちに希望を与えられたらと思ったのです」と語る。
■「『リバウンド』での経験は、勇気という大きな贈り物をくれました」(チョン・ジヌン)
名選手だったが、怪我でバスケットボールを諦めたペ・ギュヒョク選手を演じたチョン・ジヌンは、「新しいことに飛び込める力」こそがリバウンドなのではないかと言う。バスケットボールの経験があり、今作にも真っ先にキャスティングされていた彼は、「脚本を読んで、重要な役を演じるプレッシャーや恐怖を感じずに、直感で『やりたい』と思った役でした。そして、恐怖心を克服し再びバスケットボールコートに立ったペ・ギュヒョク選手を演じたことで、失敗を恐れずに、常に自分自身と向き合って人生を選択していけるようになったと思います。『リバウンド』での経験は、勇気という大きな贈り物をくれました」と思い返す。
チョン・ジヌン、イ・シニョンを含む選手役6人は、撮影の3ヶ月前からバスケットボールの猛特訓を開始した。バスケットボール経験のある俳優たちが練習プログラムを作り、チームメイト役を演じる俳優たちの結束が固くなっていったという。チャン・ハンジュン監督は、「役者間のケミストリーが生まれているのを感じ、時にカットをかけるのをためらうこともありました。それくらい、みんなが輝き始めていたんです」と語る。さらに、実際の釜山中央高校バスケットボール部のメンバーも映画にカメオ出演しているのだそうだ。実在する人物を演じるために監督が最も重視したのは、同じ身長・体型の役者を揃えること。そして記録映像などから、各選手の仕草や動きを完璧にコピーしたそうだ。そのおかげで、撮影終了後に実在の元選手・コーチと会った際には、本人たちとかなり似ている状態だったという。コーチのカン・ヤンヒョンを演じたアン・ジェホンは、本人に似せるために体重を10kg以上増量して撮影に臨んだ。アン・ジェホンは、「体重をコントロールするなんてたやすいことですよ」と言い、撮影が終わるとすぐに体重を落とすことができたそうだ。「それが怪優アン・ジェホンの秘密兵器なのです(笑)!」と、チャン・ハンジュン監督は笑う。
ちなみにチャン・ハンジュン監督と、ドラマシリーズ[キングダム」(Netflix)などの人気脚本家キム・ウニは夫妻。『リバウンド』の脚本にもキム・ウニが参加している。「彼女の作風とはまったく異なるので驚かれたかもしれません。私の元に脚本が届いたときに妻が読み、『この企画はやったほうがいい。そして、脚本に少し手を入れてみたい』と言いました。彼女が描く脚本は、とても強いイメージを観客や視聴者に与える、独特な筆致があります。『リバウンド』の後半、ドラマが動き出す部分でその威力が発揮されています」。
実話を基にした力強い脚本と、テーマを明確に浮き彫りにする演出。役に近づくために努力を惜しまない俳優たちと、体型を自在にコントロールできる怪優の存在。『リバウンド』には、韓国エンターテイメントが世界に示してきた粘り強さが現れている。笑いと涙が同時に訪れ、観賞後には元気や活力が漲るような今作を、ぜひ劇場で楽しんでほしい。
取材・文/平井伊都子
「小さな可能性も見逃さない粘り強さが人々を勇気づける」チャン・ハンジュン監督&チョン・ジヌンが語る『リバウンド』の力

関連記事
おすすめ情報
MOVIE WALKER PRESSの他の記事もみるあわせて読む
-

賀来賢人、岡田将生ら豪華共演!柄本時生、今井隆文がドラマ初プロデュース「錦糸町パラダイス」
テレ東プラス5/18(土)6:00
-

飲み屋で語った「夢」が実現!賀来賢人、柄本時生、落合モトキ、岡田将生がテレ東連続ドラマのメインキャストに
スポーツ報知5/18(土)6:00
-

TXドラマ24『君が獣になる前に』出演の深水元基が所属するブレスが新人を募集『2024春ドラマ特別オーディション』
ORICON NEWS5/17(金)22:00
-

「顔隠れてもカリスマ」「面影消えた?」 イケメン俳優が演じたマンガ実写版の強烈悪役
マグミクス5/17(金)20:25
-

TBS金曜ドラマ『9ボーダー』出演の箭内夢菜が所属するアービングが新人を募集『2024春ドラマ特別オーディション』
ORICON NEWS5/17(金)20:00
-

細田佳央太主演『七夕の国』、謎めいた物語が動き出すティザー予告解禁 山田孝之ら追加キャストも発表
クランクイン!5/17(金)19:30
-

来場者特典は“映画フィルム風クリアしおり”に!『好きでも嫌いなあまのじゃく』劇場限定版Blu-rayも発売決定
MOVIE WALKER PRESS5/17(金)19:00
-

ドラマ『ダブルチート 偽りの警官 Season1』出演の松本若菜が所属するトリプルエーが新人を募集『2024春ドラマ特別オーディション』
ORICON NEWS5/17(金)19:00
-

山田裕貴に加え小日向文世、早見あかりらが参加!『Ultraman: Rising』キーアート&本予告もあわせて公開
MOVIE WALKER PRESS5/17(金)17:30
-
-

『ヒーローではないけれど』チャン・ギヨンの底なし沼に浸るおすすめの出演韓ドラ3選【ハングクTIMES Vol.155】
ORICON NEWS5/17(金)16:00
-

大久保桜子がビキニ姿でエキゾチックな雰囲気を漂わせる デジタル写真集『射抜くように美しい』誌面カット3点を解禁
SPICE5/17(金)13:20
-

Netflix映画「ウルトラマンライジング」吹替キャストに立木文彦ら 山田裕貴、小日向文世、早見あかりのコメントも
アニメ!アニメ!5/17(金)13:15
-

草彅剛「白い布に血が滲んでいくような変化にゾクゾクした」白石和彌監督最新作で“復讐に燃える男”に
Walkerplus5/17(金)12:00
-

Netflixで大人気!『ヒーローではないけれど』ストーリー解説!
韓ドラ時代劇.com5/17(金)11:00
-

<七夕の国>不気味な球体が日本を襲う予告映像公開&藤野涼子、上杉柊平、山田孝之ら追加キャスト発表
WEBザテレビジョン5/17(金)10:00
-

Netflix『Ultraman: Rising』映像公開 吹き替えキャストにフジ・アキコ隊員の桜井浩子ら
ORICON NEWS5/16(木)23:00
-

Netflixアニメ『Ultraman:Rising』本予告&日本語吹替え追加キャスト解禁 山田裕貴らのコメントも到着
クランクイン!5/16(木)23:00
-

木曜ドラマ『Believe−君にかける橋−』出演の山本舞香が所属するインセントが新人を募集『2024春ドラマ特別オーディション』
ORICON NEWS5/16(木)20:00
-
エンタメ アクセスランキング
-
1

木村拓哉『Believe』“人気女優”演じるキャラがまさかの豹変…「期待外れ感」に視聴者ガッカリ「マジで怖い」
女性自身5/17(金)20:10
-
2

滝沢秀明氏「TOBE」6人組新グループ「DeePals」結成発表、いきなり有明デビューも決定
日刊スポーツ5/17(金)22:34
-
3

「ビリギャル」小林さやかさん「コロンビア大学教育大学院を卒業しました!」美しいガウン姿…12日に離婚公表
スポーツ報知5/17(金)20:30
-
4

84歳志茂田景樹氏「要介護5」告白 17年に関節リウマチ発症、車椅子生活も励ましの声相次ぐ
日刊スポーツ5/17(金)20:39
-
5

博多大吉 相方・華丸にも35年間黙っていた秘密を告白 五輪表彰台の夢も
デイリースポーツ5/17(金)23:01
-
6

草なぎ剛、SMAP時代“どん底”救われた高倉健さん 自身が救った香取慎吾…デビュー35年の驚がく秘話
ORICON NEWS5/17(金)20:42
-
7

肺気胸で療養の長渕剛「健康について緊急報告」の動画公開 4週間の療養必要との診断も
デイリースポーツ5/17(金)20:55
-
8

泉房穂氏が元TBS記者と生放送でバトル「間違いなんですよ!」「自民党の言いなりだ」
東スポWEB5/17(金)20:26
-
9

有吉弘行 ドラマ版バカボン役演じた芸人の心中推察「腹立ってるんじゃ?」 マツコは絶賛「当たり役」
スポニチアネックス5/17(金)21:11
-
10

「顔隠れてもカリスマ」「面影消えた?」 イケメン俳優が演じたマンガ実写版の強烈悪役
マグミクス5/17(金)20:25
エンタメ 新着ニュース
-

徳光和夫さん、ラジオ生放送で日テレ・水卜麻美アナの管理職昇進を絶賛「後輩たちに慕われている…将来的にはアナウンス部長」
スポーツ報知5/18(土)7:16
-

三浦翔平 妻・桐谷美玲とのバイクデートで大恥かいた大失敗…河北麻友子が思わずツッコミ「ダサっ…」
スポニチアネックス5/18(土)7:05
-

【ギャグ漫画】医者から「余命3ヶ月」の衝撃的な事実!?患者の痛快なボケにめちゃ笑える!【作者インタビュー】
Walkerplus5/18(土)7:00
-

今夜放送『with MUSIC』Kep1erダヨンの特技に松下洸平「すごい!」 HY仲宗根泉は驚きの行動
ORICON NEWS5/18(土)7:00
-

『クレヨンしんちゃん』×『わんだふるぷりきゅあ!』コラボ回が本日放送 しんのすけ、プリキュア変身
ORICON NEWS5/18(土)7:00
-

いぎなり東北産・吉瀬真珠、3rdアルバム「東北産万博」は東北産らしさ感じる曲ばかり
日刊スポーツ5/18(土)7:00
-

NHK鈴木奈穂子アナ、木梨憲武の生き方や考え方に「憧れます」
サンケイスポーツ5/18(土)7:00
-

Kep1er「with MUSIC」登場! 最新曲「Straight Line」の注目してほしい歌詞は?マシロが明かす
日テレTOPICS5/18(土)7:00
-

徳光和夫さん、ラジオ生企画で番組史上最高額「91万6640円」馬券的中…リスナー1名にプレゼント「興奮しております」
スポーツ報知5/18(土)6:58
-

和装挙式のみちょぱも美しい!「わあああ素敵すぎる…」「和装も世界一きれいで似合いますね」の声
スポーツ報知5/18(土)6:41
総合 アクセスランキング
-
1

木村拓哉『Believe』“人気女優”演じるキャラがまさかの豹変…「期待外れ感」に視聴者ガッカリ「マジで怖い」
女性自身5/17(金)20:10
-
2

滝沢秀明氏「TOBE」6人組新グループ「DeePals」結成発表、いきなり有明デビューも決定
日刊スポーツ5/17(金)22:34
-
3

5月17日が「大谷翔平の日」に LAが制定…グレースーツで市庁舎訪問、球団発表
Full-Count5/18(土)3:45
-
4

「ビリギャル」小林さやかさん「コロンビア大学教育大学院を卒業しました!」美しいガウン姿…12日に離婚公表
スポーツ報知5/17(金)20:30
-
5

世界ランク1位シェフラー緊急事態 警察に拘束、手錠かけられ囚人服姿に 全米プロゴルフ選手権
日刊スポーツ5/17(金)22:10
-
6

【阪神】青柳晃洋3敗目 岡田監督辛口「目も当てられんわな。ボール、ボールなる」
日刊スポーツ5/17(金)23:04
-
7

84歳志茂田景樹氏「要介護5」告白 17年に関節リウマチ発症、車椅子生活も励ましの声相次ぐ
日刊スポーツ5/17(金)20:39
-
8

大谷翔平が米ファンを泣かせる行動 突然現れたと思いきや…「よくやった。本当に…」と米感動
THE ANSWER5/17(金)21:03
-
9

博多大吉 相方・華丸にも35年間黙っていた秘密を告白 五輪表彰台の夢も
デイリースポーツ5/17(金)23:01
-
10
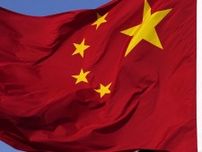
中国、日本水産施設を停止 5月から税関当局の登録
共同通信5/17(金)23:41
いまトピランキング

東京 新着ニュース
-

つばさの党の行為は「表現の自由」? 逮捕に踏み切った警視庁はどう判断したか 候補者ら立件の前例はなく
東京新聞5/18(土)6:00
-

選挙カー囲み「出てこい、クズが」 「米国の犬、ばばあ」とまで…各陣営が訴えた「つばさの党」妨害の内容
東京新聞5/18(土)6:00
-

重要人物が異論!「井上尚弥VS“最狂”デービスは現実離れし過ぎている」“モンスター”陣営のアラムCEOがサウジ王族提言のドリームプランを疑問視
RONSPO5/17(金)21:41
-

旧岩淵水門が「重要文化財」指定へ 荒川と隅田川の分岐点で水害防ぎ100年 「誇りだ」住民ら喜び
東京新聞5/17(金)21:15
-

シラサギの群れが舞った 浅草・三社祭が開幕「まるで別世界」 「宮出し」は最終日の19日
東京新聞5/17(金)20:42
東京 コラム・街ネタ
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright (c) MOVIE WALKER Co., Ltd.