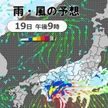テレビドラマ作品全体を通した物語の魅力がある一方で、キャラクターを演じる俳優自身が醸し、物語るストーリーというのもある。その意味で川口春奈とは、まさに物語る人だと思うのだ。
毎週金曜日よる10時から放送されている『9ボーダー』(TBS)では、10歳ずつ年がはなれた三姉妹が、それぞれの世代ごとに悩める人生を考える。中でも川口扮する次女の悩みは尽きない。
イケメン研究をライフワークとする“イケメン・サーチャー”こと、加賀谷健が物語る人であり、食べる人であったりもする本作の川口春奈について解説する。
◆金子ありさ脚本世界が「最後の砦」だと思う理由
主人公が、雄弁かつボソボソぼやきで心中を吐露するモノローグ表現がテレビドラマのトレンドとして多用されるここ数年、『中学聖日記』(TBS、2018年)や『恋はつづくよどこまでも』(TBS、2020年)などの金子ありさ脚本世界が、最後の砦だとぼくは思っている。金子作品の主人公たちは、繊細に絡まった感情の襞を簡単には解こうとせず、慎重になりながら、心中をやすやすとぼやかない。そのためモノローグの使用は第1話冒頭程度。必要最低限の文字数だからしみるものがある。
川口春奈主演の『9ボーダー』では、冒頭すぐ主人公・大庭七苗のモノローグが流れる。本作のメイン舞台となる銭湯「おおば湯」前、「そのあまりに唐突で……」という川口トーンがしみる、しみわたる。それが単なるぼやきではなく、格別のモノローグがさりげなく使用されるのは、金子作品と川口の関係性を考えればわかること。
横浜流星との共演作『着飾る恋には理由があって』(TBS、2021年、以下、『着飾る恋』)の最終話がやっぱり忘れがたい。「頑張れ」という短いフレーズで川口が極限の吐息まじりにふるわせるつややかな情感と質感は、どんなに饒舌で文学的なモノローグ表現でもたぶん及ばない。その上で『9ボーダー』冒頭のモノローグ自体がパンチラインとなる。作品間を越境して響き合う川口春奈の豊かな表現性にぼくらはどこまでも感動してしまう。
◆“風通しがいい”川口春奈
そう考えると、『9ボーダー』は、『着飾る恋』の姉妹編的なドラマとして捉えられる。時代の先をいくインテリアメーカーでチャキチャキ働く頼れる広報担当だった川口が、今度はプロデュース会社の副部長になる。この出世は見逃せない。同じ脚本家の作品に再度出演し、役柄を通じてステップアップする。うん、風通しがいい。さすがは、我れらが川口春奈である。
でもどうやらキャラクターの内面世界はそうでもないよう。『9ボーダー』の大庭七苗(川口春奈)は、『着飾る恋』の真柴くるみ同様に相変わらず、人生にモヤモヤぎみだ。職場での活躍が期待されるのは嬉しいが、「貫禄あるな」といって部長の新浜良則(岩谷健司)からは、29歳のところを30歳だと逆サバ読みされるし、プロデュースする現場店舗でばったり会った元彼(塩野瑛久)からは、「仕事ばっかりじゃ寂しいもんな」といわれてしまう。元彼が待ち合わせていたのが結婚したばかりの妻で、七苗は思わず、別の指につけていた指輪を左手の薬指につけかえる。出世はするが、ぶかぶかの指輪を婚約指輪だと偽り、強がる七苗の人生には、寒風が吹いている。
そんなキャラクターを風通しのいい川口が演じるから味わいがうまれる。元彼の妻がすかさず指輪を見て結婚してるのかと尋ねてくる。七苗は、「まだではありますが、そろそろ近いような、そうでもないような……」となんとも曖昧な返答をする。なるほど、この曖昧な心地よさが、川口の持ち味なのかもしれない。
◆“物語る人”であることが魅力の一つに
川口春奈という俳優の魅力はなんだろう。ぼくは、彼女が絶えず物語る人であることだと思っている。キャラクターのバックグラウンドをさまざまな仕草で丁寧に織り込むだけでなく、キャラクターを演じる川口の背景にも物語る意思があって、それがオーラみたいに広がっている。
川口がちょっと歩きだしただけで、その一歩ずつがポイントとなり、振り返れば、そこにはひとつのプロット(筋)が流れている。みたいな人だと思う。だから、ぼくらはドラマ全体としての物語を楽しみながら、同時に川口の演技レベルで物語られるストーリーを適宜オーバーラップしながら見ている。川口が演じる役柄の味わい深さはおそらく、そのため。
象徴的なのは、共演者である松下洸平の存在。元彼の言葉を気にしてぷらぷら歩いていると、ふと川辺から歌い声が聞こえる。声の持ち主は、謎の雰囲気を醸すコウタロウ(松下洸平)。松下もまた物語る人の代表格みたいな人だ。2008年にシンガーソングライターとしてデビューし、歌心としての気持ちを乗せることに長けている彼は、歌を歌うように台詞を吐く。背景に物語が広がる川口に対して、ボーカルでもある彼の完璧なフレージング感が、マイクに向かわせて常に前へ前へ物語ろうとする。ストーリーとは別に、もうひとつの松下洸平物語を紡ぐのだ。
アサヒ生ビールのCM「出張とおつかれ生です。」篇を見ると、カウンター席の松下がビールを一口飲んで「はぁぁぁ〜」ともらす一言というか、一音の持続だけでもうなんかドラマを感じてしまう。ならば川口が出演するビールCMはどうかというと、これが短編小説の切れ味みたいな痛快さで、エールビールの喉越しを伝えてくれる。川口が歩いてきてすでに物語は静かにたちあがり、それを松下がキャッチして歌い継ぐ。それぞれの特性を活かして物語る俳優同士が共振する瞬間が素晴らしいのだ。
◆“食べる人”として類似するロマコメ作品は…
ちょうど10歳ずつ年がはなれた3姉妹が夜毎集うおおば湯の休憩室で、真ん中を陣取ってビールを飲む七苗から再びモノローグがもれる。さわやかな孤独として響くのは、物語る人の白眉といえるワンシーンだからだろう。
というわけで、仕事の人であり、物語る人であり、ビールを飲む人でもある川口だが、もうひとつ彼女は、食べる人でもある。休憩室で2本目のビールを飲みながら、七苗が食べているのが、牛丼。その食べっぷり(!)。
『着飾る恋』でも川口の食べっぷりが話題だった。同作第2話、横浜扮する藤野駿が作った料理を一口。広いシェアハウスの天井まで「んっま」が響く。この一言に集約されるその食べっぷりが、食べる人としての川口春奈を揺るぎないものにしている。川口が食べ物を口に運ぶときの大胆さを見て思い出すのは、『食べて、祈って、恋をして』(2010年)のジュリア・ロバーツだ。
かたことのイタリア語を頼りに現地のポモドーロを一息に頬張るジュリア・ロバーツの解放感が川口春奈にも息づき、まさか日本の銭湯を舞台にしても似たような生命力ある食の場面が見られるとは思わなかった。七苗の姉・成澤六月(木南晴夏)が、イタリアで食べたパスタについてたわいもなく話す場面は、偶然の目配せと理解しつつ、ロマコメ作品の主人公同士が食べる人として類似する、こんな贅沢で国際的なドラマの楽しみ方をどう享受したらいいんだろ……。
◆“炭鉱のカナリア”になることができる俳優、川口春奈
国際的だなんてちょっと飛躍が過ぎるかと思いながら、本作が提示する身近で切実なテーマにグッとくる。耳に優しい川口のモノローグがあり、松下洸平の心地いい歌声があって、次にどうも耳慣れないワードが入ってくる。
ハラスメントはハラスメントでも、上司が部下の負担を減らし、ハラスメントに過剰に対応し過ぎるとホワイトハラスメントになるらしいのだ。良かれと思ったことが、こんな裏返しになる時代の新しいハラスメント概念。七苗は、後輩の西尾双葉(箭内夢菜)にコンプライアンス室に駆け込まれ、新浜から注意を受ける。プロデュース店の一周年記念パーティー会場に入るとき、七苗がぶつぶつ「ホワハラって何。何でも、ハラハラハラ……」というのだが、否が応でも社会の変化を感じてしまう。上下ふたつの世代のちょうど間にはさまれる七苗のようなアラサー世代はどうふるまうべきなのか。
「まだではありますが、そろそろ近いような……」という台詞が象徴していた川口の曖昧さなら、うまく余白を作りながら前に進めるかもしれない。SEKAI NO OWARI「陽炎」のサビが流れ、三姉妹それぞれの孤独が浮き彫りになる第1話クライマックスを見て思う。『着飾る恋』の「頑張れ」の必殺フレーズ発動の瞬間も星野源による主題歌「不思議」のR&Bフレイバーなメロウネスが川口のエモーションを高めていた。一方の「陽炎」では、こぼれたビールを右手親指と人差し指だけでつまむように飲む川口の清濁ないまぜのワンショットが際立つ。この場面を見て、アラサーの葛藤を体現し、時代の変化を身をもって察知する“炭鉱のカナリア”になることができる俳優は、川口春奈しかいないと強く思った。
<TEXT/加賀谷健>
【加賀谷健】
コラムニスト・音楽企画プロデューサー。クラシック音楽を専門とするプロダクションでR&B部門を立ち上げ、企画プロデュースの傍ら、大学時代から夢中の「イケメンと映画」をテーマにコラムを執筆。最近では解説番組出演の他、ドラマの脚本を書いている。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業。Twitter:@1895cu