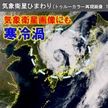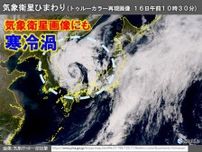メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平の連日の活躍が日本人を喜ばせている。MLBを観察し、取材してきたライターの内野宗治氏はその圧倒的な力でさまざまな障壁や閉塞した世界を変えた「ゲームチェンジャー」だと評する。そんな大谷に湧き上がったのが、前通訳の水原一平容疑者の賭博疑惑に端を発した「英語を会見で話さない」問題だ。アメリカでの大谷に対する批判をこう解釈する。
※本稿は、内野宗治著『大谷翔平の社会学』(扶桑社新書)の一部を抜粋、再編集したものです。
◆大谷翔平に苦言を呈したアメリカ人コメンテーター
「野球が国際的なスポーツだということはわかっている。しかし、観客を放送局や球場に引き寄せるための顔としてナンバーワンである選手が、やりとりに通訳が必要だというのは、いいことだとは思えない」
米スポーツ専門局「ESPN」のコメンテーター、スティーブン・A・スミスは2021年7月13日、今やメジャーリーグの顔となった大谷翔平が「やりとりに通訳が必要」な選手であるという事実に苦言を呈した。
スミスは「この男(大谷)は特別だ。そこは間違えてはいけない」と前置きしたうえで、以下のように持論を展開した。
「だが、英語を話さず、通訳を必要とする外国人選手のいることが──真偽はともかく──興行面でプラスに働くとしたら、それは野球にとってある程度マイナスだ。(野球界の顔となるのは)ブライス・ハーパー(フィリーズの強打者)やマイク・トラウト(エンゼルスの強打者)のような選手でなくてはならない」
ハーパーとトラウトは、いずれも白人のアメリカ人選手だ。前年、黒人差別に抗議する「ブラック・ライブズ・マター」運動が勃発し、人種差別に対して極めてセンシティブになっていたアメリカでこのコメントは当然のごとく批判され、後日スミスは謝罪した。この件について大谷は、自身が表紙を飾ったアメリカの有名ファッション誌『GQ』のインタビューで、同誌の記者であるダニエル・ライリーから話を振られてこう答えている。
◆「英語はもちろん話したい」だが……
「英語はもちろん話したいし、話せても損はなく、いいことしかない。でも、僕は野球をするためにここに来ました。そして、フィールドでの僕のプレーが、多くの人たち、ファンとのコミュニケーションの手段になると感じています。あの件で僕が考えたのは、そういうことでした」
2024年がメジャー7年目のシーズンとなる大谷は、日常会話程度の英語力に問題はないと言われており、チームメイトたちと通訳を介さずおしゃべりする姿なども頻繁に見られる。ただほかの日本人選手と同様、試合中の重要なコミュニケーションやオフィシャルな記者会見の場では、通訳の力を借りている。微妙なニュアンスが間違って伝わってしまうことや、誤解を招く表現をしてしまうことを防ぐためだろう。
メジャーで19年プレーし、現在はシアトル・マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターを務めているイチローも、あるいは2024年がメジャー13年目となるダルビッシュ有も、オフィシャルな場では基本的に通訳をつけている。彼らが通訳をつけるのは「英語ができないから」ではなく、プロフェッショナルとしての責任を果たすためだろう。
◆フィールドでのプレーこそが「多くの人たち、ファンとのコミュニケーションの手段になる」
公の場で英語で話したほうがアメリカのファンに親しみを持たれるだろうが、それ以上にプロとして仕事を全うすることを優先しているはずだ。チームメイトとのミスコミュニケーションが原因で試合に負けたり、自分の発言が不適切なかたちでメディアに取り上げられたりするリスクを冒す必要はない。大谷が言う通り、プロ野球選手にとって何よりも重要なのは、人前で英語を話すことではなく、プレーで結果を残すことだ。そして大谷は、フィールドでのプレーこそが「多くの人たち、ファンとのコミュニケーションの手段になる」という自身の考えを口にしている。
確かに僕らは、大谷がインタビューで語る言葉よりもまず、彼の特大ホームランや剛速球に魅了される。大谷の超人的なプレーの前では、言葉が随分とちっぽけなものに思える。僕らが大谷の言葉に感動したり感心したりするとしたら、それはまず彼のプレーがあるからだ。スーパースターの言葉だからこそ、みんながありがたがる。言葉そのものに価値があるのではなく、プレーあってこその言葉なのだ。
◆マイケル・ジャクソンのダンスと大谷翔平の本塁打
たとえば20世紀後半、マイケル・ジャクソンの音楽とダンスは人種や国籍を超えて人々に感動を与えたが、トップアスリートのプレーにもそれに似たパワーがある。スポーツは単なる競争やゲームではなく、エクストリームな身体表現だ。フィギュアスケートや体操など、芸術性の高い競技は身体表現としてわかりやすいが、野球やサッカーといった競争性の高い競技にも芸術性を見いだすことはできる。
大谷にはきっと、自身が野球というスポーツを通じた表現者、あるいはアーティストであるという自覚があるだろう。
大谷は日本語でも英語でも、あまり多くを語らない印象がある。マスコミやスポンサーのインタビューには答えるが、大谷が発する言葉は当たり障りのない、優等生的な内容に終始することが多い。「チャンスで打てたのは良かったかなと思います」「明日も頑張りたいと思います」といった具合だ。ハッキリ言って、コメント自体はあまり面白くない。
◆アメリカ人記者がみた取材対象としての大谷翔平
ロサンゼルス・エンゼルスの地元紙『オレンジ・カウンティ・レジスター』の記者として、エンゼルスを10年以上取材しているジェフ・フレッチャーは著書『SHO-TIME 大谷翔平 メジャー120年の歴史を変えた男』で、取材対象としての大谷についてこう書いている。
「そして仮に話したとしても、大谷は囲み取材でお決まりの言葉しか口にしないという定評ができあがっていた。あまりにも感情がこもっていないインタビューが続いたので、『ロボット』呼ばわりする記者までいた」
同じ日本人メジャーリーガーでも、たとえばイチローは現役時代、個性的な表現や独特の言い回しで注目を集めたり、とんちんかんな質問をする記者に「逆質問」して困惑させることもあった。ダルビッシュ有は公式の記者会見でもSNSでも、球界に対して「もっとこうした方がいい」「これはよくない」といった意見を積極的に述べ、賛否両論を巻き起こしてきた。新庄剛志はワールドシリーズ出場後に「五右衛門風呂に入りたい」とコメントして通訳を困らせるなど、毎回のインタビューが一発芸のようだった。
こうした先人たちの個性溢れる言葉遣いに比べると、大谷が発する言葉は極めて平凡で、まるでAIが回答しているかのように機械的だ。ChatGPTのほうがより気の利いたコメントを返すかもしれない。でも、その言葉の平凡さこそが大谷の、プレーの非凡さをさらに際立たせているという印象もある。
◆プレーで賛否両論を巻き起こしてきた大谷
大谷はダルビッシュのように、歯に衣着せぬ発言によって賛否両論を巻き起こすことはしないが、「二刀流」というプレースタイルそのものが賛否両論を巻き起こしてきた。大谷のプレー自体が強烈なメッセージ性を有しているからこそ、彼は言葉で強いメッセージを発する必要がない。大谷はマイクを向けられたときではなく、野球のフィールドにいるときこそ最も雄弁なのだ。
【内野宗治】
(うちの むねはる)ライター/1986年生まれ、東京都出身。国際基督教大学教養学部を卒業後、コンサルティング会社勤務を経て、フリーランスライターとして活動。「日刊SPA!」『月刊スラッガー』「MLB.JP(メジャーリーグ公式サイト日本語版)」など各種媒体に、MLBの取材記事などを寄稿。その後、「スポーティングニュース」日本語版の副編集長、時事通信社マレーシア支局の経済記者などを経て、現在はニールセン・スポーツ・ジャパンにてスポーツ・スポンサーシップの調査や効果測定に携わる、ライターと会社員の「二刀流」。著書『大谷翔平の社会学』(扶桑社新書)