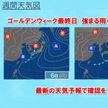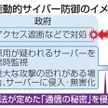40歳での鮮烈なFA宣言、巨人へ電撃移籍した落合博満……1993年12月のことだった。
あれから30年。巨人にとって落合博満がいた3年間とは何だったのか? 本連載でライター中溝康隆氏が明らかにしていく。連載第17回(前編・後編)、1995年シーズンを最後に原辰徳が現役引退した。いよいよ落合博満vs松井秀喜、約20歳差の“新4番争い”がスタートする。【連載第17回の前編/後編へ】
◆◆◆
「ボクなんか、アルバイトみたいなもん」
「運転手サン、巨人勝ってる?」
大学時代、記者とタクシーに乗った原辰徳は、少年のような屈託のない表情で運転手にそう聞いたという。原はプロ入り前から大の巨人ファンで、長嶋茂雄ファンでもあった。そして、ドラフト1位で巨人入りすると4番を打ち、1995年限りで現役を引退したが、ユニフォームを脱ぐ際に自身の後継者として21歳の松井秀喜の名前を挙げた。
「最後の試合の時、まぁ、あまり個人的に言ったらいけないのかもしれないけど、松井にはとにかく打って欲しかったですね。松井、打ってくれ、打ってくれって、そう願ってました」(週刊文春1995年10月19日号)
巨人の4番は貰うものではなく、奪い取るものだ――。そんなメッセージを残した原とは対照的に松井秀喜は子どもの頃から阪神ファンで、長嶋茂雄が現役を引退した1974年生まれということもあり、ミスタープロ野球の勇姿をリアルタイムでは見ていなかった。プロ3年目の1995年シーズン、落合博満が故障欠場した8月25日の阪神戦(甲子園)でプロ初の4番に座ったが、松井本人も「ボクなんか、アルバイトみたいなもんですよ」と認める、あくまで代役の4番バッターだった。
42歳直前の異変「絶対に邪魔しません」
この年の松井は打率.283、22本塁打、80打点という成績でチームは3位に終わり、最後は自分が凡退して目の前でヤクルトの優勝が決まる屈辱を味わった。秋が深まり、野村ヤクルトとイチロー擁するオリックスが激突した日本シリーズも遠い世界の出来事だった。だが、同時にこの屈辱が背番号55の反骨心に火をつける。オフは自費で北野明仁打撃投手と契約して徹底的に打ち込んだのである。長嶋監督もそれに呼応するかのように秋季キャンプで松井をキャプテンに指名する。
「本人に自覚を持ってもらうためには、肩書きを付けるのが一番なんですね。昔から地位は人を変え、向上させるというではありませんか。松井にとっても集大成の秋ですから、必ずやってくれるでしょう。ええ、やらせますよ」(週刊ベースボール1995年11月20日号)
長嶋監督はプロ4年目の来季こそ勝負の年と位置付け、“4番1000日計画”の仕上げに入ろうとしていた。だが、その1995年の秋季キャンプである異変が起きる。
20代の若手選手たちに混じり、なんともうすぐ42歳になる落合博満が志願参加したのである。「絶対に邪魔はしませんから」と3週間に渡り、1日2〜3時間もカーブマシンをじっくり打ち込むオレ流調整。シーズン中、真ん中から外に逃げる変化球が見えなくて打撃が狂ってしまったので、その狂いを見つけ修正したかったのだという。先のシーズンで、リーグ4位の打率.311と史上最年長の打率3割を記録した男が、さらなる進化を求めてバットを振る理由を長嶋監督はこう見ていた。
「カーブの打ち方について、あるテーマを持って秋季キャンプに臨んでいた。松井に対して、4番はやすやすとは譲れないという強い気持ちがあるんでしょうね。松井のほうも、落合が衰えたからというんじゃなくて、力で奪ってやろうという気持ちが前面に出てきたことがうれしいんだよね」(週刊現代1996年1月1日・6日号)
落合が苦言「若手は練習をやらされている」
日に日に周囲も過熱する4番争いに対して、これまで表向きは「特別な意識はまったくない」、「ボクは別に何番でもいいんですけど」と興味を示さなかった松井の言動にも徐々に変化が現れる。元阪神の4番打者・田淵幸一との対談企画では、はっきりとオレ流への宣戦布告を口にしたのだ。
「正直にいいます。4番は、落合さんのいるうちにとりたい。きっちり結果を出して、絶対に実力で4番をとりたいという気持ちです。王さんや長嶋監督を筆頭に、これまでの巨人の4番打者というのは、あまりにも偉大でした。落合さんにしても、過去に3度も三冠王になったという実績がある。(中略)落合さんを尊敬する気持ちは強いけど、その落合さんから4番の座を奪えたら、という気持ちも同時にある」(週刊現代1996年2月24日号)
もちろん数々の修羅場をくぐり抜けてきた落合も黙っちゃいない。
年末には、当時まだ珍しかった酵素ドリンクからだけ栄養補給するファスティング(断食)療法を敢行。その様子を報じる『週刊ベースボール』によると、ミネラル・ウォーターを大量に飲み新陳代謝を促すウォーター・ローディングや、日常生活で良質のタンパク質を多く含む落花生を意識的に食べるようにしたりと最新のスポーツ医学や栄養学を貪欲に試す大ベテランの姿があった。故障を抱えていた前年とは違い、万全の体調で迎えた1996年の春季キャンプでは、恒例のエアテント内での打撃練習だけでなく、背番号6は守備のフォーメーションプレーにも参加するなど精力的に動いてみせた。
2月19日に宮崎の清武町で行われた「交通安全のつどい」のゲストに呼ばれた落合は、300人を超える警察官を前に「今の若手は練習をやらされている。その間は負けない」なんて巨人の甘えの体質をチクリ。松井に対しても、「4番を打つと言うべき」とあらためて言及した。
長嶋監督「非常に不気味ですよ(笑)」
長嶋監督は、そんなオレ流を「非常に不気味ですよ(笑)。自分の力を見せないでおいて、今に来るときが来たらオレの番だというね、あの不気味さなんて若い連中じゃとても太刀打ちできませんね」(週刊ベースボール1996年4月16日号)と冗談交じりに肯定したが、ここぞとばかりにマスコミは落合と松井の不仲を煽った。当時のチームメイトですら、「落合さんが松井と話していた記憶はあまりない。で、これは僕の勝手な憶測ですが、落合さん、松井の力を認めて意識しているのかなと思っていました」(長嶋巨人 ベンチの中の人間学/元木大介・二宮清純/廣済堂新書)と指摘する声があったのも事実だ。
だが、実は昭和と平成を代表する“最強のふたり”の大打者の関係性は、周囲が知らない意外な場所で繋がっていたのである。その場所とは――。
<続く>
文=中溝康隆
photograph by ベースボール・マガジン社