2000年代オリックスが採用した契約金0円の選手たち。彼らはその後、どのような野球人生を歩んだのか。前編の「高橋浩司」編に引き続き、『オリックスはなぜ優勝できたのか』(光文社新書、2021年12月14日発売)より一部を抜粋してお届けします。(全3回の第2回/前回はこちら ※肩書、成績はすべて刊行当時)
毎年のドラフト候補、社会人の好選手
高見澤考史は、高橋と同じ2000年ドラフトで、6位指名を受けた。
社会人の東京ガスに所属していた外野手は、社会人野球の最高峰・都市対抗野球でも、補強選手を含めて3度出場。1999年(平成11年)には、4カ国国際大会の日本代表にも選出されるなど、毎年のようにドラフト候補として名前の挙がる好選手だった。
ただ、プロが目をつけるプレーヤーだけに、チームでは大黒柱だ。高見澤のような選手がプロ入りすることで、社会人側のチーム力が落ちるのも困るのだ。
「もう1年残ってくれ」といった会社側の意向を受けてプロ側が指名を避けたり、指名順位が低過ぎるのは会社の体面上好ましくないと、上位指名以外なら残留といった条件をプロ側に出しているところも多いという。
高見澤も、プロ側のアプローチが「僕のところまで届いていなかったのが、どうも2、3年くらい、続いていたみたいです」と、その裏事情を明かしてくれた。
年齢的にも、そろそろラストチャンスかもしれない。そんな焦りが募り出していた頃、思わぬオファーが舞い込んできた。
そんなん、どうでもええ
「年々、自分の順位が落っこちているのも知っていました。最後の最後に来ていただいたのが、オリックスだったんです」
その時点で「契約金0円」という新制度の方針も伝えられていた。
「契約金0って、どういうこと? あ、そういう感じか、と。いや、そんなん、どうでもええ。なんか、ホント、プロに入って勝負したいという感じでした」
それでも、東京ガスといえば、業界でも超一流企業の一つだ。
夢を追うか、大企業に残るという安定を取るか。
契約金というのは、退職金の前払いともいわれる側面がある。リスクの大きい世界で、それこそ何十年と現役生活を続けられるわけでもない。
なぜ「契約金0円」でプロの世界に飛び込んだ?
そこへ「契約金0円」で、飛び込むのか?
「東京ガスは大きい、っていうのが、僕には今ひとつ、働いている時には分からなかったんですね。何ていうのかな、その先のことを一切、考えていなかったというのもありましたね。東京ガスにいてどうのこうのとか、プロに行ってダメだったとか良かったとか、何か考えて、プロに入ったかといったら、そういうのがなかったんです。プロで、という声をいただいて、チャンスをいただいたことに対して、僕は嬉しくて、そんな声をもらえるのであれば、ありがたいという思いをオリックス側に伝えた、という感じでした」
25歳の選手を獲る。球団側にしても、ここから大幅に実力が伸びるということは期待しづらい。ただ、社会人での実績を考えれば、数年なら一軍で働いてくれるかもしれない。
見知らぬ男性から電話が…
つまり、そこそこの実力者を「契約金0円」で獲っておくことは、仮に思惑が外れたとしても、ダメージは小さい。そんな打算が、球団側にはあるのも事実だろう。
高見澤にしてみれば、そうした“企業の論理”も承知の上だった。
高見澤は、プロ入りの決断と同時に、入籍もしている。
新たなる人生のスタートを切った高見澤のもとに、見知らぬ男性から電話が入った。
「車を売った、という記事を見ました」
演出家を名乗る男性「どうやって球場に行くんですか?」
知り合いのツテをたどり、高見澤の連絡先を入手したという男性は「演出家」を名乗った。
「どうやって球場に行くんですか?」
「いや、何も考えていないんです。多分、歩きか自転車か、ですね」
「じゃあ、私が自転車を用意します。メーカーでこういうところを知っているので、自転車で行ってみたらどうですか?」
社会人時代の愛車を売却して、高見澤は神戸に引っ越してきていた。
おカネがないという態でいこう
「こっちの作戦だったんですけど、とことん、おカネがないという態(てい)でいこうと。中途半端だけはなくして、とりあえず、チャリンコでいいんじゃねえ、っていう話で」
ちなみに高見澤は、この縁をきっかけに、その演出家との付き合いが今も続いていると教えてくれた。
メーカーとタイアップした自転車が、高見澤のもとに本当に送られてきた。
新居は本拠地・グリーンスタジアム神戸(当時)からおよそ3キロ。自転車で走る距離としてはちょうど手頃だった。
高級車の隣に自転車を置く
漕いできた愛車を、高級車がずらりと並ぶ駐車場の片隅に置く。
そのコントラストは、もちろんテレビやスポーツ紙で大きな話題となった。
「あれはありがたかったですけどね。でも、プロのイメージじゃない。ホントは、切なかったですよ。くそー、車買うぞ、っていうのはありましたけどね」
社会人で主軸を張っていた男だから、ファームのレベルでは早々に目立ち始めた。
だから、高見澤は「契約金0円選手」の中で、最初にインセンティブの1000万円を手にすることになる。
仰木監督から「みんなにご飯でもご馳走せい!」
1年目の監督は、仰木彬だった。
球界のマジシャンと呼ばれた知将は、そういう演出にもたけている。
「あと3日やな」「あと2日やな」。にやりと笑って、毎日のように高見澤に声を掛ける。
神戸の試合前、仰木に「高見澤!」と大声で呼ばれた。
「お前、これで今日、1000万円の出来高、ゲットするんやから、みんなにご飯でもご馳走せい!」
仰木流の祝福に合わせ、ベンチ内が沸いた。
「ご馳走様でーす」
おどけた声で田口壮が言うと、ベンチ内に爆笑が起こり、拍手が湧いた。
高見澤は最終的に、満額の2000万円を獲得することになる。
2年目は打率.279、4本塁打、26打点。
自力で契約金をつかみ取った男が輝いたのは、2年目の2002年だった。
2000年オフにイチロー、翌01年には田口壮がFA権を行使して、かつてのオリックスの看板選手の2人が、メジャーへと戦いの場を移していた。
その穴は簡単に埋まらない。8年間の長きにわたってオリックスを率いた仰木も、2年連続の4位に終わった2001年を最後に勇退していた。
後を継いだのは、西武で遊撃手として活躍。高いリーダーシップで、その黄金期を支えた石毛宏典だった。
その石毛が、高見澤のガッツと実力を高く評価してくれた。
62試合に出場、打率.279、4本塁打、26打点。
これだけの結果を残せた選手が「契約金0円」ならば、それこそ、スカウト陣の見る目は高く評価されてもいい。仕入れ価格0円から、一軍で稼げる選手を生んだのだ。
プロ初安打は松坂大輔からのホームラン
その“0円選手”だからこそ、騒がれたシーンがあった。
4月19日、鹿児島・鴨池球場(当時)での西武戦。
プロ初安打は、あの西武の若きエース・松坂大輔からのホームランだったのだ。
平成の怪物を、「契約金0円」の男が打った。
このコントラストは、痛快なドラマでもある。
「たまたま。ホントたまたま。僕からしたら、行き当たりばったりのタイミングで、ポーンとぶつかったのが、パーンと行っただけ。何ともないんですけど、それを今でも言ってもらえるんで、本当にありがたいです。でも、そういうのがなかったら、今、何していたんだろう、とも思いますね」
ああ、俺、クビだな
しかし、翌3年目。社会人時代から痛めていた右肘が、とうとう悲鳴を上げる。
いかに痛くないように投げるか。ごまかし、探りながら、外野を守っていた。自分の立場が分かっていた。ダメなら、すぐに切られる。だから必死だった。
2年目のシーズン終了後に右肘を手術。だから3年目のキャンプインは、ファームでのリハビリでのスタートだった。
夏頃になると、FA権を取得した他球団の外野手を、獲得に乗り出すというまことしやかな噂が耳に入り、スポーツ新聞でも、それが事実のように報じられていた。
「ああ、俺、クビだな、そんな感じでしたね」
医者から「もう野球は無理でしょう」
28歳、右肘の怪我、契約金0円。球団は待ってくれない。言い方は悪いが、元手がかかっていないから、クビにするのにも躊躇がない。
わずか3年。怪我に泣かされた、短いプロ野球人生だった。
オリックス退団後、高見澤は無給のまま古巣・東京ガスの練習生に復帰、韓国や台湾のプロリーグで、数カ月の短期契約を結べるという話が持ち込まれ、それに向けた準備で練習を続けていたという。
その矢先に、再びアクシデントが起こった。
「今度は、腰でした」
今も、その時のボルトが入っているという。「もう野球は無理でしょう」と医者からも言われ、手術を決断すると同時に、自らの現役引退も決めた。
妻から渡された1枚のチラシ「正社員って書いてあるよ」
そんな時だった。
新聞に入っていた1枚のチラシを、妻から渡されたという。
「野球だよ、これ。正社員って書いてあるよ」
埼玉に居を移していた高見澤は、東京ガスの練習に車で通う途中に、バッティングドームがあるのを、毎日のように見ていた。
さいたま市岩槻区にある「アーデルバッティングドーム」の求人募集だった。
高見澤君、野球塾ってどうかな?
正社員としての勤務が始まった。希望者には高見澤自ら打撃指導も行っていた。
仕事が軌道に乗り始めた頃、ドームの社長から思わぬ提案があった。
「高見澤君、野球塾ってどうかな?」
勉強の塾と同じように月謝制。子供たちに本格的に野球を教えてみるのはどうだろうという新ビジネスのアイディアだった。
高見澤は、惹かれるものがあった。
野球は危ない。ボールが当たったら、怪我をする。
公園でも、キャッチボール禁止の看板が掛けられるような時代になった。
野球をやりたくてもできない。その環境の制限が、都会ではさらにきつくなった。
「公園だとか、危ない、やったらダメというところが多くなっているし、親の方もどうせやるんだったら、そういうプロの人たちに見てもらったらとか、その辺、熱の入れようも変わってきているんですね」
やるなら、きっちりと教えます。そうしたコンセプトで「野球塾」を名乗る施設やシステムは、2000年代序盤には「調べてもなかったんですよ」と高見澤は明かしてくれた。
「子供を見るのも大好きだし、やってみても面白いかな、と思ったんです」
<つづく>
文=喜瀬雅則
photograph by JIJI PRESS















































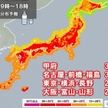



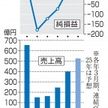




























































































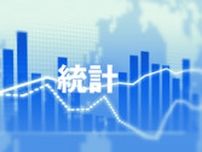











![[連載]イーストスタッドブログ・第7回 新種牡馬、レッドルゼルについて](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33395.jpg)


