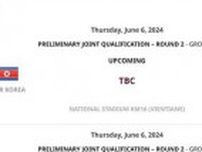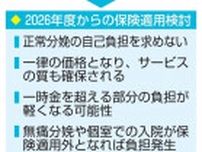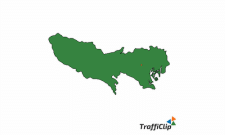今夏に迫ったパリ五輪への出場を目指す山本有真(24歳)。多くのメディアから注目を集め、日本代表として輝く山本には、じつは順風満帆ではない学生時代の苦難があった。インタビュー第1回では、大学時代に一度陸上をやめた日、そして亡き母への思いを聞いた。《NumberWebインタビュー/全3回》
高い競技力と美意識を兼ね備えたアスリートがスポーツ界に増えつつある。
トラックを颯爽と走る姿はそれ自体、美しいが、そこに個人の美意識が加わると華やかになり、見ている人の目をより引き、憧れの対象にもなる。
山本有真は、そういうアスリートのひとりだ。
メイクし、ヘアスタイルを整え、最小限のアクセサリーを身に着ける。山本にとって、それは気持ちを高め、トラックやロードで戦うための「戦闘服」だ。
インターハイは「私には縁も関係もない世界だと…」
山本が陸上を始めたのは、中学の時だった。
バスケットボール部を希望したが弱小ゆえ、足が速かったので陸上部を選んだ。800mで全中(全国中学校体育大会)を狙ったが、「かすりもしなかった」という。高校でも陸上部に入り、高2の時には800mでインターハイに出場、高3時には1500mと3000mの2種目でインターハイに出場した。
「インターハイには出たんですけど、ほんと一応です(苦笑)。レベル的には全国の下っ端で、800mの時はズタボロの予選落ちでした。ちゃっかり出ちゃったみたいな感じで、私には縁も関係もない世界だと思いました」
全国のトップとの差を身に染みて感じた山本だが、同期の藤中佑美からは大きな刺激を受けていた。藤中は、高1から頭角を現し、高2の全国高校駅伝一区8位で走り切り、高3の都大路では1区2位の快走を見せた。その際、山本は2区で藤中から襷を受けたが、区間13位に終わった。
「佑美とは、毎日登下校を一緒にしていたぐらい仲が良かったです。ただ、私とは違って、めちゃくちゃ速かったんですよ。佑美にレースで勝ったことはほとんどないですし、練習でラスト1本(400m)でダッシュするんですけど、毎回負けていました。それでもライバル意識があって、佑美が私の1歩前にいてくれたから頑張ることができたんです」
大学時代の葛藤「なんで走っているんだろう…」
高3になり、進路を決める際、山本は高校で陸上をやめようと思っていた。
「実業団で働いて走ろうという気はまったくなかったですし、大学に行って陸上を続けたいとも思っていなかったです。どっちかというと普通の女子大生としてキャンパスライフを送って、友人とはっちゃけて遊びたいと思っていました(笑)。でも、たまたま名城大学から声が掛かったんです。そんな強い大学から声がかかると思っていなかったので、じゃあ頑張ろうって行くことに決めました」
名城大は全国でも屈指の駅伝強豪校。山本も厳しい練習に打ち込むことになる。
「高校の時は、遊び半分、本気半分みたいな感じで陸上をやっていたんです。でも、名城は駅伝の日本一の大学なので、集まってくる子が日本のトップレベルなんですよ。最初は、そういう子たちと一緒に練習するのが新鮮だったんですけど、慣れてくると……」
山本は入学前から陸上部に染まらない環境を望んでいた。スポーツ推薦で入学した学生は、練習場が近い法学部を選択することが多い。だが、山本は、人間学部を選択し、市内中心部にあるナゴヤドーム前のキャンパスに通っていた。そこで部活とはまったく関係がない一般の学生と交友関係を広げていった。
「みんなと授業を受けている時は普通に楽しいんですよ。でも、授業が終わったら、友人はバイトや遊びに行くんですけど、私は部活。『カラオケ行こう』と誘われても『ごめん、行けないわ』と断ってばかり。『バイバイ』と笑顔で別れた後、みんながめちゃめちゃ羨ましくて、いつも泣きそうになっていました。陸上に価値を見出せなくて、なんで走っているんだろうと思うこともありました」
「遊びたいので、もうやめたい」監督に伝えた日
それでも、競技面では1年生の時から主力だった。全日本大学女子駅伝(杜の都)では4区区間賞、大学女子選抜駅伝(富士山女子)は4区区間賞でチームの優勝に貢献した。
「大学に入った時は、4年間で一度、駅伝を走れたらいいなって思っていたんです。そうしたら1年目で2つの駅伝を走れて目標を達成し、個人種目もインカレの1500mで3位に入れたんです。それで、かなり満足しちゃいました(笑)。大学2年の時もやる気はあったんですけど、両足が足底筋膜炎になってしまって……。もう、死ぬほど足が痛くて、どうにもならなかったです」
足底筋膜炎は朝、床に足を付けただけで激痛が走る等の症状が出るランナーに多い故障だ。両足ともなると普通に歩くことさえ厳しくなり、テーピングなどを施さないと走れない。そういう中、山本は日本インカレ1500mで予選を突破したが、決勝は痛みで出走できなかった。駅伝出走も危ぶまれたが、痛みを我慢しながら練習をこなし、杜の都2区2位、富士山女子は4区区間賞でともに優勝に貢献した。
「足がギリギリの状態で、駅伝を走って優勝できたので、やり切ったな、もう陸上はいいやって思いました。それで駅伝が終わった翌年の1月に監督とコーチのところに行って、『遊びたいので、もうやめたい』と伝えました」
山本は「ダメだ」と言われても実家に帰る覚悟だった。米田勝朗監督は山本の頑固さと意志の強さを理解しており、あえて何も言わずに山本の離脱を受け入れた。
山本を変えた“亡き母の存在”「お母さんの分まで陸上を」
山本は実家に戻り、友人と旅行に出かけたり、カラオケに行ったり、出来なかった「遊び」を楽しんだ。2月、陸上部が合宿に入る際、電話がかかってきたが、「行かない」と伝えた。しかし、遊んでばかりいると、最初は新鮮だが、やがて飽きてくる。「遊びの毎日」が「単調な日々」に変わり始めた3月、学生ハーフで小林成美(住友海上)と荒井優奈(積水化学)がユニバーシアード出場の切符を手にしたことが耳に入った。
「それを聞いて、すごいなぁと思ったんです。ふたりとは同年代でずっと一緒にやってきたし、ライバルみたいな意識もあったんです。そのふたりが結果を出して、日本代表として世界に行く、上のレベルに行くのは羨ましい。私も行きたいって思ったんです」
ライバルの躍進によって陸上への気持ちに火がついた。だが、それ以上に山本の気持ちを陸上に駆り立てたことがあった。
姉から聞いた亡き母のことだった。
山本の母親は、3歳の時に亡くなった。当時、13歳だった姉は、母のことをよく覚えており、山本にどんな母親だったのか、教えてくれた。
「お母さんは私を産む際、障害を持っていたので、産まない方がいいと医者に言われたらしいんです。でも私を産んでくれて、その3年後に亡くなりました。自分がいなければ今も元気だったんじゃないのかな、自分のせいで亡くなったんじゃないのかなってすごく考えました。でも、お姉ちゃんに、『お母さんは水泳とかスポーツが好きだった。お母さんの分まで陸上をがんばってほしい』と言われて……。確かに、そうだな。今、健康でスポーツができていることってありがたいこと。お母さんの分まで頑張って走ろうと思ったんです」
競技人生のターニングポイント
3月、山本は米田監督に部に戻る意思を伝えた。監督は、山本の申し出を1月の時と同じく、何も言わずに受け入れた。
「ここで陸上に戻って来れたのは、私の競技人生の中で大きなターニングポイントになりました。そこからちゃんとやろうっていうのは失礼かもしれないけど、ただ駅伝を走れればいいとかではなく、日本インカレで優勝したい、日本選手権に出たいとか、目標がどんどん高くなっていったんです」
陸上に戻ってきた山本は、2カ月ほどで自分の走りを取り戻し、3年の時は日本選手権1500mで6位、日本インカレ1500mは2位。杜の都は1区区間賞、富士山女子は4区区間賞で優勝に貢献した。4年時は、日本インカレ5000mで優勝、杜の都3区区間賞、富士山女子5区区間賞でチームの優勝に貢献し、有終の美を飾った。
「大学はいろいろありましたけど、4年間やり切ったと思います。駅伝はすべて優勝できたのですが、得るものが大きかったです。追われる立場で勝ち続けるのはすごく難しくて、さらに勝ち続けるためには勝った時以上の走力や強さが求められます。大学で追われる側にいて、そこで打ち勝つためのノウハウを学べたのは、いい経験になりました」
「駅伝女」として、多くの記録と記憶を残し、個人としても強さを発揮した山本は、卒業後、実業団の強豪・積水化学に入社することになる。《インタビュー第2回に続く》
(撮影=杉山拓也)
文=佐藤俊
photograph by Takuya Sugiyama/JIJI PRESS