2023ー24年の期間内(対象:2023年12月〜2024年4月)まで、NumberWebで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。MLB部門の第4位は、こちら!(初公開日 2024年2月24日/肩書などはすべて当時)。
大谷翔平投手と山本由伸投手が加入したロサンゼルス・ドジャースが注目を集めている。日本人メジャーリーガーのパイオニアである野茂英雄投手の通訳を務めた奥村政之氏(現・ヤクルト編成部参事、国際グループ担当部長)が振り返る「NOMOフィーバー」。後編は通訳にまつわる珍事件や、ドジャースの知られざる伝統とチームカラーについて聞いた。〈全2回の後編/第1回も配信中〉奥村が見た「妥協しない真摯な姿勢」
奥村氏が野茂の通訳を務めたのはメジャー初年度の1995年から97年の3年間。まさに「NOMOフィーバー」真っ只中の輝かしい時間だった。95年はシーズン通算13勝6敗で、最多奪三振(236)のタイトルを獲得。翌96年は9月17日のロッキーズ戦で初のノーヒットノーランを達成する歓喜の瞬間も味わい、チーム最多の16勝を挙げた。97年には当時のメジャー最速記録で通算500奪三振に到達するなど破竹の勢いで突き進んだ。
奥村氏が3シーズンを共にして感じた右腕の凄みは、いかなる時も気を抜かず妥協しない真摯な姿勢と、その集中力の高さだという。例えばメジャー3年目の97年8月28日、この年から導入されたインターリーグ(交流試合)のオークランド・アスレチックス戦でのことは忘れられない。当時のアスレチックスは黄金期の選手がごっそりと抜け低迷期にあった。試合の1カ月前の7月末には強打者のマーク・マグワイアも放出しており、ドジャースにとっては楽勝のカードに思えた。
「アメリカン・リーグの打者はフォークボールにも慣れていないし、私も軽口のつもりで『ガンガン三振を取るチャンスですよ』なんてことを言ったんです。そうしたら野茂は『思い通りに行っているように見えるかもしれないけど、メジャーはそんなに甘くないんです。どんなチーム相手にも絶対に気を抜いたらダメ。それを毎日痛感しながらやっています』と言っていた。中4日で投げ続けて、気候の変化や移動も大変そうでしたが彼が手を抜くようなところは一度も見なかったです」
三振の数は全く気にしていない
この試合、ドジャースは7-1と完勝した。野茂は8回途中まで投げて被安打4の1失点。三振を9つ奪い、デビューから3年連続となるシーズン200奪三振に到達した。試合後はいつものポーカーフェイスに戻り、「三振の数は全く気にしていない」と振り返った。浮かれることなく淡々と、次の登板に向けた入念な準備をしていたという。
野茂が日本人メジャーリーガーのパイオニアであるように、奥村氏は日本語通訳として初めてMLBの球団職員となった草分けだった。今でこそ日本人選手に通訳やトレーナーが付くのは当たり前だが、当時は異色の存在。野茂に先駆けてドジャースで活躍していた朴贊浩(チャンホ)も韓国語の通訳はチームに帯同しておらず、英語が話せない中南米の選手は、困ったら地元局のスペイン語が話せるアナウンサーをグラウンドに呼んで対処していたのだという。
当時はメディア側とギクシャクした部分も
「アメリカのメディアにとって、あくまでチームの中心選手は(マイク・)ピアッツァや、(ラウル・)モンデシー、(トム・)キャンディオッティーであって、野茂は彼らにとって面白い記事を書かせてくれる“お客さん”のような存在だったと思います。悪いことを書かれたことはありませんでしたが、インタビューを巡っては揉めることもありました。僕は野茂が野球に集中できることを優先に殺到する取材をキャンセルすることもあったのですが、よく吊し上げられましたよ(笑)。今、大谷選手の水原(一平)通訳はメディアとの関係をすごく上手くやっていますが、当時はギクシャクした部分もありました」
ラソーダ監督「いいことを思いついたぞ」
当時、通訳は試合中のベンチ入りを許可されなかった。奥村氏は野茂の登板日にはロッカールームに待機して、ベンチへ続くドアから時折顔を覗かせて状況を把握していたのだという。当然、投手コーチとのやりとりなどでは不都合もある。チームでは、ユーモアたっぷりの“奇策”を講じたこともあった。
「ラソーダ監督が突然『いいことを思いついたぞ。今からバットボーイのユニフォームを着ろ。お前は今日から英語と日本語を喋るバットボーイだ!』って言い出したんです。実際に野茂が登板する公式戦でドジャースのバットボーイの制服を着てベンチの横に待機したことがありました。審判に気づかれないようにずっと下を向いて、バット引きをしてはダッシュで戻る。こっそりと野茂のサポートもして……(笑)。3、4試合くらいでしたかね。最後はメディアに気づかれて書かれてしまって、その後は出来なくなりました」
ファミリー色が強かった1990年代のドジャース
野茂がメジャーリーガーとして一歩を踏み出したドジャースにはその後、石井一久や斎藤隆、前田健太、ダルビッシュ有ら多くの日本人選手が所属。今季からは大谷、山本もユニフォームに袖を通し、再び注目度が高まっている。球団職員として3年間所属した奥村氏から見て、そのチームカラーや伝統的な球団の気質はどのようなものなのだろうか。
「当時はオマリー会長のファミリー経営だったので、選手や選手の家族、職員に対して温かく“ファミリー色”が強かった。一方で現場の選手たちは仲が良くても勝負への厳しさをきっちり持っていました。試合後に、あのプレーはおかしくないか? というような怒鳴り合いはしょっちゅうあったし、シャワールームで取っ組み合いが起きていたことも。チーム経営に大きな資本が入り、変わってきているでしょうけど、絆を大切にするというカラーや勝負への厳しさという気質は今も残っていると思います」
「コントロール養成マシン」も
ロサンゼルスという土地柄もあり、新しいことをどんどん取り入れる進取の気性も特徴だ。奥村氏の在籍時には、一般にパソコンが普及する前だったにも関わらず、早々にITを駆使し、最新の機材を導入していたという。
「ドジャースには95年当時から映像をベースにした最新のデータシステムがありました。スカウトも自分でプログラミングしたソフトを作っていて、驚いたことを記憶しています。チームには『コントロール養成マシン』もありました。パソコンを使って一点に向かう集中度を高めるゲームのようなものですが、視覚の集中力が高まってコントロールが良くなるということで選手は全員、毎日それをやらなければいけなかった。当時でそんな状況でしたから、今ではさらに凄いシステムや最新の機械が導入されていると思いますよ」
エンゼルスとドジャースの違い
大谷はエンゼルスからドジャースへの移籍となった。同じロサンゼルスを本拠地とするチームでも、ファンの気質は大きく異なるという。
「エンゼルスのファンは一言で言えばお上品なんです。地理的にもアナハイムから下の方はサンディエゴまで高級住宅エリアが続いていく。一方でダウンタウンのてっぺんにあるドジャースは熱狂的で、ノリが良くて“ガヤ”が凄いという印象があります。ロサンゼルスはヒスパニック系が多くてみんな地元のドジャースが大好き。彼らはファミリーも子供も多いので、大人数で球場に来てワイワイと野球を観て楽しむ印象があります。日本の野球の知識も深いので野茂もすごく愛されていましたし、その後ドジャースでプレーした日本人選手も応援されてきた。大谷選手や山本投手の加入は、おそらく日本人以上に喜んでいると思います」
夏場のナイターはボールが飛ばないという印象
奥村氏は現在、ヤクルトの国際担当グループのトップとして、外国人選手の獲得に関わっている。メジャーリーグとも太いパイプを持つ立場から、大谷や山本の挑戦をどのように見ているのか。
「本拠地のドジャースタジアムはピッチャー優位の球場で、特に昼夜の寒暖差がある夏場のナイターはボールが飛ばないという印象があります。山本投手はもちろん、大谷選手も来年以降は投手としてマウンドに立つでしょうし、そう考えると立地的にもアドバンテージのある球場だと思います。野茂が入った時は年俸10万ドル(当時約980万円)でしたから、特に大谷選手はその1万倍からのスタートになる。1球の重みという意味で大きな責任を背負っていると思いますし、これは本当に大変なことです。“野球を楽しみたい”というだけでは片付けられない重みがあると思うので、その中でどんな活躍をするのか注目しています」
29年の時を経て再び日米を熱狂させるドジャーブルーの旋風。日本人メジャーリーガーが刻む新たな歴史を奥村氏も楽しみにしている。
<「メジャー1年目」編とあわせてお読みください>
文=佐藤春佳
photograph by Koji Asakura
































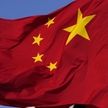












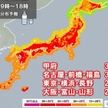


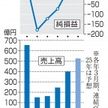















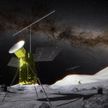

































































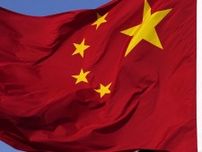












![[連載]イーストスタッドブログ・第7回 新種牡馬、レッドルゼルについて](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33395.jpg)


