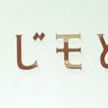プレミアリーグのルートン・タウンFCへ電撃移籍――。驚きのニュースから3カ月が過ぎた。サッカー日本代表・橋岡大樹(24歳)は世界最高峰の舞台で懸命にもがいている。来季の行方を占う激しい残留争いに身を置く中で、着実に掴みつつある手応え、そして微かに芽生えた自信とは…。積み重ねてきた思いをNumberWebインタビューで打ち明けた。〈全2回の1回目/後編に続く〉
おそらく、橋岡大樹は世界で唯一のプレーヤーだ。プレミアリーグの大舞台で、怪物が至近距離から全力で振り抜いたシュートを顔面で受け止め、それが自軍のゴールネットを揺らす。そんな貴重で、地獄の体験をした選手なんて他にいない。
必死に体を投げ出す金髪の日本人
4月13日、プレミアリーグ第33節。橋岡が所属するルートンは、アウェーでマンチェスター・シティと戦った。その開始わずか2分のことだった。カウンターのピンチで、こぼれ球がシティの大エースの頭上へ飛んだ。すかさずアーリング・ハーランドは体をねじり、左足でのジャンピングボレーを狙った。
ここに、橋岡が飛び込んだ。シュートコースを塞ぐために、必死に体を投げ出した。ところが大谷翔平の打球のごとき豪速球は、金髪の日本人の顔面を直撃し、そのままルートンのゴールへと吸い込まれた。
エティハド・スタジアムが、いきなり揺れた。5万人を超える大観衆の大半を占めるシティサポーターたちは、プレミア残留争いを続けるルートンの選手とファンに、上から目線で罵声を浴びせた。
「お前らは、チャンピオンシップ(イングランド2部リーグ)のチームだ!」
一方、アウェーチームのサポーターは毛色が異なる。計5点を奪われても、野次を飛ばすことはない。後半36分に一矢報いるゴールが決まれば、懸命に手を叩き、特大の声で愛する選手たちを称えた。
ルートン・タウンFCは人口約21万人の街に本拠を構える。29年ぶりに国内トップリーグを戦うこのクラブを支持するファンたちは、辛抱強く、温かく、そして目ざとい。
試合後、ある初老のサポーターは、ルートン応援席に見慣れない顔があることに気が付いた。
「おい! 君は、ハシのファミリーだろ?」
声をかけられたのは、この記事の写真を撮影してくれたカメラマン・延命悠大さん。橋岡の従兄弟である。旅行と仕事を兼ねて、イングランドに滞在していた。延命さんが笑顔で頷くと、おじさんはがっちり肩を抱いてきた。
「顔が似ているから、すぐわかったよ。俺は20年以上、ルートンを応援しているんだ。ハシは最高の選手だよ! 今日のオウンゴールは仕方がない。アンラッキーだっただけだ。大丈夫だよ」
クラブと橋岡への愛を熱弁すると、首に巻いていたマフラーを差し出した。オレンジと白のニット地に、ルートンの街の紋章をモチーフにしたエンブレムが描かれていた。
「これを受け取ってくれ。ハシにもぜひ、見せてあげてほしい」
「この日本人、鬱陶しい」
試合終了から1時間半が経った。エティハド・スタジアムの駐車場で待機していた車の助手席に、橋岡が乗り込んできた。アウェー戦の場合、普段はチームメイトとともに現地のホテルに宿泊することが多い。でも、「試合の日の夜は、どうせ眠れないから」と、車で4時間かけて自宅へ帰ることにしていた。
ハンドルを握る延命さんが、ちらりと横を見た。助手席の日本代表DFは、意外とすっきりとした顔をしていた。5失点して敗れたショックを引きずっている様子はない。かつては自身も名門高校サッカー部でプレーしていた延命さんは、少し安心して、試合の感想をぶつけてみた。
「オウンゴールは不運だったけど、あの後のプレーは良かったと思う。どう?」
橋岡は、静かにうなずいた。
「うん。実は俺も、そう思ってる。やられてしまったものは仕方ないから。切り替えはすぐにできたし、そもそも普段からあれぐらいでは落ち込まないよ。手応えは少なからず感じていたし、試合中、ハーランドも『この日本人、鬱陶しい』って嫌がっていたからね」
確かに。オウンゴールのショックも、顔面の傷みも、どこ吹く風。先制を許した後も、ハーランドにしつこく、激しく、粘っこく体を寄せ続けて、クロスとシュートをはね返し続けた。
マンチェスターからのロングドライブを終えて、あの初老のサポーターからもらったマフラーを手渡すと、橋岡は嬉しそうに笑った。従兄弟の目から見ても、この3カ月で随分たくましくなったと思った。
「ハシ、君はバックラインなら、どのポジションでも全部できるだろ?」
これは橋岡が今年1月にルートンへ加入した当初、ロブ・エドワーズ監督からかけられた言葉だ。守備陣に怪我人が続出する中、41歳の青年監督はその期待どおりに橋岡をピッチに送り出してきた。本職の右ウイングバックだけでなく、3バックの右でも左でも。
この指揮官が採用する戦術は特殊である。基本コンセプトは、とにかく人を捕まえろ。各選手が受け持つ相手を決めて、マンマークで徹底的に張り付く。そうしてボールを刈り取り、一気に相手ゴールへ迫る。言葉にすればシンプルだが、実行するのはかなり過酷だ。その負荷を、橋岡はこう表現する。
「ディフェンスの選手が走る量、スプリントの数はほかのクラブと段違いだと思います。特に3バックの選手は。うちの場合、自分がマークするFWがボールをもらうために自陣のペナルティエリア付近へ下がったとしたら、そこまで付いていきますからね。それをプレミアのプレースピードの中でやるから、頭の中も疲れます。加入当初は、どこまで相手についていくのか、周りがマークを剥がされたときにどう動くべきか、理解するのに時間がかかりました」
敵陣深くでボールを奪えば、大チャンス。一方、ひとたびマークを剝がされれば、大ピンチ。プレミアリーグ第36節を終えた時点で、ルートンはリーグワースト2位の78失点を喫している。当然、橋岡が失点に絡んだ場面もある。
「絶対に下を向かない」
そのとき、DFはどう振る舞うべきか。欧州へ渡って3年を迎えた男には、流儀がある。
「絶対に、下は向かない。自分に失点の責任があるとわかっていても、そうは見せない。すぐに上を向いて、手を叩いて、周りを鼓舞して指示を出す。周りから見れば、『あれ? こいつのせいじゃないのかな』って思うかもしれないですね」
失点に動揺していたら、相手に付け込まれる。仲間と指揮官の信用も失う。メディアは容赦なく批判の矛先を向ける。ならば、たとえマークを外されても、たとえ顔面でオウンゴールをしても、強気で、強気で。
この姿勢は2018年、浦和レッズの新人時代に培われた。浦和ユースからトップチームへの昇格が決まり、開幕前のキャンプに参加したときのことだ。世代別代表の常連ではあったが、当時の橋岡は、まだ弱気な少年だった。
周りには日本代表クラスの選手がずらり。高校生の自分が本当にプロで通用するんだろうか。そんな不安がプレーに表れていた。これじゃダメだと、自分でも認識していた。だから勇気を出して、ある先輩のもとへ向かった。チームの中でとびきり明るくて、声がでかいその人に、本音を打ち明けた。
「俺、ちょっと縮こまってプレーしてる部分があるんですよね。自分でもそれはわかっているんですけど……」
そんな橋岡を見て、槙野智章は豪快に笑った。
「縮こまる必要なんて、まったくないやん! だってお前が今、ミスをしても何も失うものないだろ。まだ何も得てないし、何も失うものはないんだから、自分がやりたいように、思いっきりプレーすればいいんだよ」
アドバイスは、試合中のコミュニケーション術にも及んだ。
「ピッチに入ったら、名前を呼び捨てにしても全然いいから。年齢に関係なく、対等だと思ってガンガン指示を出して、思いっきりプレーすりゃいいよ」
素直なルーキーは、その後の練習試合で、さっそく行動に移した。
「青木! もっと前に出ろ!」
ユースのときと同じように、積極果敢にプレーした。先輩にも、堂々とコーチングした。プロとしての覚悟が、ようやく決まった。
「お前、呼び捨てにしただろ」
試合後、青木拓矢に冗談交じりでお説教されたのは、18歳の甘酸っぱい思い出だ。以来、プロの舞台でも縮こまることなく自分らしさを表現するようになった。
転機となったウイングバック起用
ポジティブなオーラを放つ選手には、チャンスが舞い込む。2018年4月、リーグ開幕からわずか1カ月あまりの段階で、浦和の監督が交代した。
大槻毅。オールバックの髪型と鋭い眼光により、「組長」と呼ばれた新指揮官は橋岡に、いきなりこう言った。
「今、怪我でウイングバックをできる選手が誰もいない。お前、ちょっとやってみろ」
当時、橋岡はセンターバックを主戦場としていた。でも、失うものは何もない。「とにかく明るい槙野」の言葉にも背中を押され、右のタッチライン際で躍動した。4月11日のヴィッセル神戸戦で初めて先発起用されると、4日後の清水エスパルス戦では初アシストを記録。終わってみれば、プロ1年目でリーグ戦25試合に出場し、1得点。迷いと遠慮を捨てた若者は千載一遇のチャンスを逃さず、右のウイングバックとサイドバックのポジションを自分のものにした。
〈後編に続く〉
文=松本宣昭
photograph by Yudai Emmei