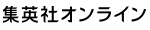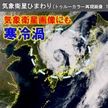生殖医療の光と影を描いた桐野夏生の小説『燕は戻ってこない』が、NHKドラマ10で映像化される。自分の遺伝子を残したいと願う元トップバレエダンサーを演じたのは稲垣吾郎。役柄とは対照的に「自分の遺伝子を残すことにこだわりを持ったことがない」と語る元トップアイドルの本音と、あるものを通して思いがけず発動された父性に迫る。
生殖医療をはじめ、深刻な問題がテーマに
──『燕は戻ってこない』は、貧困から抜け出すために代理母になる派遣社員、自分の子どもを残すことを熱望する夫、代理出産に積極的になれない妻の3人の心の揺れを鮮烈に描いた物語です。原作を読まれた印象は?
稲垣吾郎(以下、同) 『OUT』をはじめ、桐野夏生さんの作品はこれまでも読んできましたし、対談をさせていただいたこともあったんです。やっぱり一線を超えた人々の描き方はすごいですよね。人によって共感できるところもあれば、まったく受けつけない部分もある。それでいて、登場人物はどこか憎めないキャラクターとして描かれていて。人によっていろんな解釈ができる作品だと思いました。
──小説だからこそ描けたデリケートなテーマを、どう映像化するのか期待が高まります。
挑戦だなと思いましたね。生殖医療はもちろん、地方社会のちょっとした息苦しさであったり、若者の貧困であったり、深刻な問題がテーマとしてありますから。この物語を必要としているひとりでも多くの方に届けられたらいいなと思っています。
──稲垣さんが演じた草桶基(くさおけもとい)については、どんな印象を持ちましたか?
自分の遺伝子を受け継ぐ子どもをなんとしてでも生み出したいという欲望、これは人間の本能でもありますが、そこに本当にこだわりを持っている人物ですよね。その姿が滑稽に見えたりコミカルに見えたりもする。このドラマに決して悪人は出てこないけど、基に共感できるかというと、ちょっとよくわからないかも。
──産む側の性であるふたりの女性の葛藤や苦悩が浮き彫りになるぶん、基が無意識に放つ言葉の無責任さや傲慢さが際立つ場面もあります。
男から発言するのがすごく難しい物語だなと思っていて。原作や台本を読んで「愛する人に対してこんな行動をとるはずがない」と感じても、実際にはやってしまう可能性もある。誰にでも心当たりはあると思うし、僕自身もハッとする瞬間がありました。
でも男女の関係性には時として、男性の無邪気さや無神経な行動が必要な瞬間もありますよね。お互い考えすぎて前に進めないときに、男の無邪気さによって扉が開いたり。まあ、まったく逆もありますけど(笑)。
男としては基のことを責められないと思いました。男性にもぜひ見ていただきたいし、カップルで見て考える機会になってほしいなとも思います。
子どもがいたら
めちゃめちゃかわいいだろうな
──稲垣さんは自分の子どもがほしい基の思いを理解できますか?
僕は遺伝子を残すことに対して強いこだわりを持たずに生きてきました。ただ、もしも基のように両親ともにバレエダンサーという環境で育っていたら、自分の遺伝子を残さなきゃいけないというような、責任感や義務感が生まれたのかもしれない。
でも僕の場合は、ちょっと特殊な芸能の世界に身を置いてきた立場なので(笑)。それが僕の人生だし、後悔はしていません。だからこそ、基を僕に演じさせたらおもしろいと思ってオファーをしていただけたのかもしれませんね。
──役で父親を演じることもありますが、「もしも父親になったら?」と空想したことは?
うーん。なくはないけど、具体的な想像ができなかったんです。娘がいたらすごくかわいがるだろうなということは、うっすら想像がついたけど、男の子だとどう接していいかわからなそうだなとも思っていました。
ただ、飼っているオス猫を見ていて「男の子がいたらこういう感じ?」と思ったりもして。ちょっと自分の子どもの分身のような感覚で見ていることに気づいたんです。
もちろん動物と人間は違うし正しい例えではないかもしれないけど、最近はそんなことを思ったりしたかな。
──猫を通して父性が発動される瞬間があったんですね!
そうですね。当たり前だけど、めちゃめちゃかわいいんだろうなって、今になって思っています。
愛猫は子どもではなく、むしろ恋人だと思っている
──猫は2匹飼ってらっしゃるんですよね?
今は3匹います。
──にぎやかですね。猫と稲垣さんの関係性は、子どもと父親という感覚?
いや、なんかそれがすごく抵抗があって。ペットショップにメスの子猫を迎えに行ったときに、店員さんが「ほら、パパが来たよー」って言ったんです。その瞬間「いや、パパじゃないし」って思っちゃって。
僕としては同志や一緒に暮らしているパートナー、むしろメスに対しては恋人ぐらいに思っていたから、ちょっとショックを受けちゃって(笑)。なんか違和感があったんですよ。
でも、オスに対してふと親目線になっている自分がいたように、「パパ」と呼ばれるのもわからなくないなと、最近は思いはじめているところです。
──猫との生活は、想定外の出来事も多い気がしますが。
全然思い通りにならなくていいんです。ワンちゃんはよくしつけをしたりするけど、厳しめに言うことを聞かせようとする人を見ると、もういいじゃんって思っちゃう(笑)。そこが親っぽくないのかもしれない。猫なんか言うことをきくわけがないしね。
彼らも僕のことをペットだと思っているかもしれないし、同じ空間に住んでいるだけの存在だと思っているかもしれない。コントロールできないことが心地よくておもしろいから、僕は猫を飼っているんだと思います。
取材・文/松山梢
撮影/石田壮一
ヘアメイク/金田順子
スタイリスト/黒澤彰乃
〈文庫版〉燕は戻ってこない