
関東や近畿などの公立中学校で本格的な修学旅行シーズンが始まる中、「バスの運転手が確保できず、貸し切りバスが手配できなかった」とのSNS投稿が議論になっている。修学旅行先の京都でバスが突然キャンセルとなり、在来線で移動することになったという。背景には、運転手の長時間労働などを規制する「2024年問題」があるとみられるが、修学旅行のあり方を見直すべきだとの意見は相次ぐ。
【映像】総額6万2200円 中学修学旅行費用の内訳
一方で話題となったのが、東京都港区。2024年度から、区立中学校の修学旅行先をシンガポールに決めた。「子どもにとって素晴らしい体験になる」との声もあるが、区議会では費用の高さや、海外渡航が適切なのかとの指摘も。様々な問題をはらむ昨今の修学旅行について、『ABEMA Prime』で考えた。
■修学旅行が抱える根本的な問題
教育学を専門とする千葉工業大学の福嶋尚子准教授は、形骸化した修学旅行はやめるべきだとし、3つのポイントを挙げる。まず「教育的意義」に対する疑問で、旅行会社が提案したプランにのっかるなど、教育としての意味が薄くなったこと。2つ目が、交通費・宿泊代・見学料・保険料などのために修学旅行積立金を支払う上、バッグ・衣類など家庭で用意するものも用意する必要があり、「費用」が高すぎる点。3つ目が「教師の負担」で、現地下見の交通費や入館料、当日の飲食代などが自腹のケースもあるほか、天候ごとのシミュレーション、生徒らのトラブル回避やアレルギー対策などの安全管理に24時間体制で取り組む必要があることなどだ。

教育評論家の石川幸夫氏は「修学旅行はどんなものでもやったほうがいい」という立場だが、福嶋氏の指摘には同意する。「単純に賛否を取る問題ではない。今の子どもたちには経験値が欠けていて、修学旅行によって人生が変わることもある。そのためには、修学旅行が抱える根本的な問題を解決しなければいけない」。
日本修学旅行協会「教育旅行年報データブック2023」によると、国公立中学校の修学旅行費用は、交通費や宿泊費、体験活動費などを合わせて総額6万2200円となっている(抽出校まとめ)。リディラバ代表の安部敏樹氏は、「コストが本当に高いかは、整理して議論したほうがいい」と指摘。体験コンテンツを提供する立場から、「教育旅行はまとめて行けるので、コストが一般向けの3分の1〜4分の1になる。宿も、大きな会社はまとめ買いしているから安く、個人で同じものをやると高くなる」と説明する。
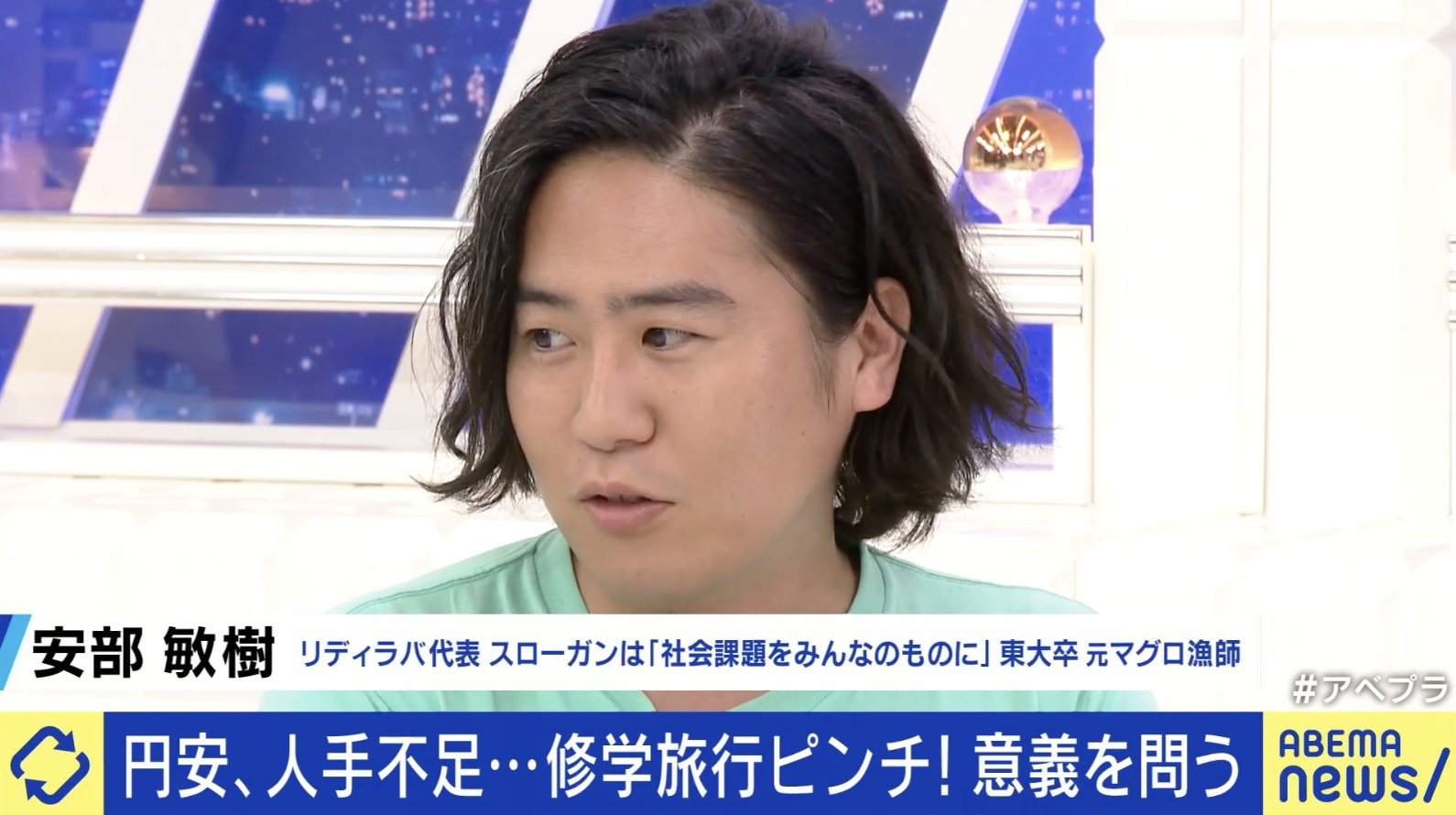
その上で、「体験活動が子どもの主体性やコミュニケーション能力に影響を及ぼしそうだと、研究でわかってきた。かつては無償提供されていた体験が、今は資金的理由でできない人もいる。それが将来の所得に影響を及ぼすと考えると、経済状況が厳しい家庭も含めて学校が安く体験を提供するメリットはある」と、修学旅行の意義を語った。
費用面について福嶋氏は「ジャンボタクシーや大型バスを貸し切るのは、安全性を重視して、昭和期に生まれた手法だ。6人でジャンボタクシーに乗ると、1日だけで8000〜1万円。安全性の確保が、公共交通機関よりも高額な交通手段を取る理由になり得るかは疑問だ」とした。
■港区立中学はシンガポールへ 体験格差に是非も
港区立中学校のシンガポールへの修学旅行は、中学3年生の全生徒760人を対象に、6月から9月にかけて各校3泊5日で渡航する。事業費は約5億1200万円で、港区が1人あたり約40万円を負担。保護者負担としては交通費や食費、宿泊費の一部として一律5万円(パスポート代や現地活動費などで+1万7000円程度)がかかる。複数の候補地を比較した結果、公用語の1つが英語で、移動時間・時差が少なく、治安が比較的良いシンガポールが選ばれた。この修学旅行の目的は「英語教育の集大成」に位置づけられている。

石川氏は「英語教育だけでなく、『日本を離れる』という体験に教育的価値がある」と考えている。「税関を通り外国に足を踏み入れる感覚は、日本国内では味わえないもので、行くだけで大きな価値がある。またコミュニケーション力を発揮して、言葉を使わなければ、食事にありつけない可能性もある。中学生においての経験値としては相当大きい」。
港区では現在、4割が私立の中学校に進学している。安部氏は「そういう私立校と競争する状況がある中で、区としては公立校を魅力的に維持する必要がある。子どもが私立へ行くような家庭では、それ以前に何百万円も塾の費用をかけているだろう。なので、家庭負担を当たり前にしないことも大事だ」との考えを述べる。
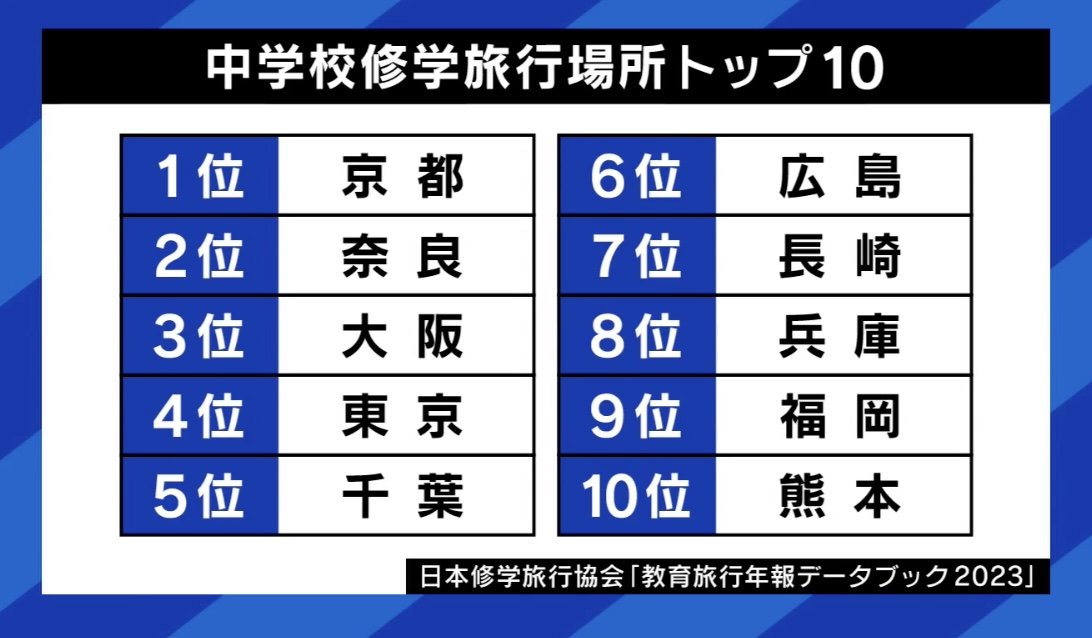
福嶋氏は「前例踏襲ではなく、『港区の子どもにはこれが必要だ』と目的を持っているのは、きっちり決断した結果だ」と評価しつつ、後の検証で「行った意義があったと、子どもや保護者、区民に説明できないといけない」と指摘する。
一方、安部氏は「旅行というロジックだと税金を投入する意義は説明できないので、教育であるべきだと思う。経験というものは定量化して評価しづらいが、共感してくれる人が過半数を超えれば、税金を投入すればいい。体験価値を中長期的に測るにはまだ研究の余地があるが、非日常の体験介入は伴走型より持続効果が長いという研究結果も出ている。意外と資本効率が良い可能性はある」と述べた。(『ABEMA Prime』より)









































































































































![[重賞回顧]自分らしくありのままに。絶妙なペース配分で美しく逃げ切ったアリスヴェリテが重賞初制覇〜2024年・マーメイドS〜](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33680.jpeg)


