昨年、ある大手ゼネコンの幹部と食事する機会があった。2人で和食を食べながら話題はさまざまな方面に及んだ。どんな流れだっただろうか。語り合ううちに「忖度」の話になった。
そのゼネコン幹部はしばらく黙ったあと、眼に涙を光らせた。
「うちの会社は、在職中に夫が亡くなったとき専業主婦だった奥さんを必ず正社員として採用するんです」
長い勤務歴で思い出すことどもがあるのだろう。あの上司が死んだときも、あの同期が死んだときも、あの部下が死んだときも、会社はその家族に手を差し伸べてくれたと。その潤む眼を見ながら私も感無量になっていた。
「実は……」と私は言った。「僕がいた中日新聞社もそうなんです。在職中に夫が死ぬと誰が言い出すわけでもなく奥さんに声をかけて雇うんです」と。
2人で驚きながら話した。もしかしたら歴史の古い日本企業の多くに同じような風(ふう)があるのではないか。
誤解する読者がいるかもしれないので書くが、これは殉職や労務災害の話ではない。若くして癌に冒されたり、心筋梗塞などで突然死した社員たちについての話だ。会社側が微塵も引け目を感じる事例なんかではない。
それでも彼が死んだことを聞いた社員たちはみな俯き加減に廊下を歩き、眉間に浅く皺を寄せ、残された家族のことを考える。
やがて社規に書いてあるわけでもないのに、自然に奥さんを雇う方向へと向かう。「まだ子供が小さいよな」「専業主婦がこの年齢で良い職に就くのは難しいだろう」。皆が胸の内に思うそんな気持ちが、言葉にならぬまま温かい風となって社内に拡がっていくのだ。普段は辞令ひとつで鬼のように大鉈を振るう人事部や、社規違反するやつはいないかと憲兵よろしく眼を光らせる労務部の人たちも同じだ。四十九日法要をすませた奥さんが子供2人の手を引いて「夫がお世話になりました」と挨拶に来ると、人事部員も労務部員もみな両膝を床につけ、子供たちの眼線にまで降りて手のひらで頭を撫でる。
「君のお父さんは立派な人だったんだよ」
亡くなったその人と一緒の部署で働いたことはない。言葉をかわしたこともない。顔すら知らない。それでも子供たちに言うのだ。
「お父さんのような人になれるように頑張りなさい」
彼らがこのように言うのは彼らにも親がいて、子供もいるからだ。だからさまざま忖度してくれる。このような風土が日本の古い企業にはまだ残っている。
お父さんが云々とか専業主婦が云々などと言ったのですでに怒り心頭に発している若者がいるかもしれない。しかしこれはそこにフォーカスした話ではない。妻が在職中に癌で逝き、専業主夫が代わりに雇われる時代にもこれからなっていく。男女は半々で存在するのだから当然だ。そもそも結婚制度だって性別だっていずれ戸籍から無くなるだろう。
私が言いたいのはまったく違う話だ。日本には人の立場を忖度する風がかつてよりあり、今も残っているということだ。それでも「増田さんの言うことは古いよ」と今の10代、20代の人たちは怒るだろうか。そうさ。私はあと2年で還暦になるのだから。だけど1つだけ教えてあげよう。君のお父さんも立派な人だった。お母さんも立派な人だった。私は彼ら彼女らと一緒に働いてきたからよくわかるんだ。
思春期になると誰もが親を疎ましく感じるようになる。私もそうだった。自分の未来には永遠が拡がっていると思っているのに、彼らがその考えを否定するようなことを口やかましく言うからだ。だから時間さえあれば外へ逃げ出て友人たちと遊んでいた。いま思えばほんとうは父のことも母のことも大好きだったくせに、それを上手に表現できなかった。
今の社会には変えていかねばならないことが多々あるのは承知している。しかし忘れてはならないこともある。日本人が持つ忖度の心もそのひとつだ。過去数百年をかけて日本人が育んできた人を思いやる気持ちは忘れてはならない。まずは今日、老いた父と母に御礼を言おう。饅頭でも買って実家へ寄るつもりだ。




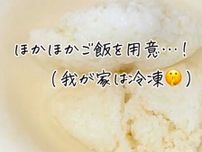

















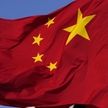












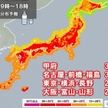


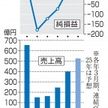















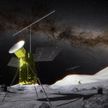



































































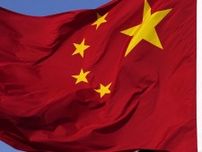


















![[連載]イーストスタッドブログ・第7回 新種牡馬、レッドルゼルについて](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33395.jpg)


