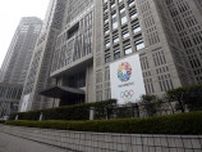第二次世界大戦後の「極東国際軍事裁判」、いわゆる「東京裁判」は1946年5月3日に開廷した。A級戦犯として起訴された日本人被告は28人。約2年半後の11月12日、免訴・病死の3人を除く25人に絞首刑(7人)や終身禁固刑(16人)、禁錮20年(1人)、禁錮7年(1人)が言い渡された。
裁判官は連合国側11カ国の11人、裁判長は豪州のウイリアム・ウェッブ。検察側の国際検察局も連合国側各国の出身者で構成され、首席検察官は米国のジョセフ・キーナンが務めた。弁護にあたったのは鵜澤總明 を団長とする「極東国際軍事裁判日本弁護団」や米国人たちである。
開廷から今年で78年を迎えるこの裁判については、現在も様々な議論が存在する。関係者の人数が膨大だったことも、研究本やドキュメンタリー映画などから見て取れるだろう。だが、そうした記録には残りにくい“裏方”として、最初から最後まで東京裁判を見続けた者たちがいた。裁判記録の作成に従事した衆議院の速記者たちである。法廷の中央で速記符号を書き続けながら、彼らは何を見ていたのか。
(前後編記事の前編・「新潮45」2010年12月号掲載「稀少資料入手! 国会速記者たちが語っていた『東京裁判』裏話」をもとに再構成しました。文中の年齢、役職、年代表記等は執筆当時のものです。文中敬称略)
***
速記者たちが東京裁判を語り合う
〈戦争裁判ははたして“首祭り”かどうかの論議はさておき、世紀の国際裁判と言われた東京裁判の法定記録はいかにしてつくられたか、当時秘せられた事実を明らかにしつつ、日本語コート・リポーターの世話役を勤められた人々に、その回顧をしていただこう。〉
これは、衆議院速記者養成所の卒業生でつくる「衆友会」の会報誌「衆友」の第13号に掲載された座談会の序文だ。当時の衆議院の男性速記者たちが、その数年前に法廷速記者(コート・リポーター)として執務した極東国際軍事裁判(東京裁判)について語り合う内容になっている。
“首祭り”などという表現にどぎつさが漂うが、何しろ発行日は56年前の昭和29(1954)年4月25日だ。サンフランシスコ講和条約の発効から2年後で、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)による占領時代の記憶がまだ生々しいころである。
私は今年9月下旬(編集部注:2010年)、先ごろ刊行された『速記者たちの国会秘録』(新潮新書)を著すため2年ほど前から取材で接触してきた元衆議院速記者たちを通して、東京裁判の座談会記事が掲載された「衆友」の現物を入手することができた。同養成所の教授、生徒らが編集し、ガリ版刷りでごく少数、印刷されたものだ。
裏方たちの息遣いや本音、戸惑い
目玉の特集記事は「東京裁判速記秘話」と銘打ち、計17ページにわたる。座談会に出席したのは、終戦直後に中軸を担った男性衆議院速記者10人。いずれも戦後、東京裁判に駆り出され、裁判記録の作成に従事させられたのだ。資料に乏しい東京裁判の裏方たちの息遣いや本音、戸惑いが窺える貴重な一次資料である。
座談会の本文の冒頭、出席した速記者の1人は、こう述懐している。
〈事の起りは、今の西沢衆議院法制局長(当時議事課長)のところに友人の太田三郎(外務省)さんが来て、実は東京裁判の速記をお願いしたい、ということだつた。(略)太田さんと私が司令部に行つて、(略)「どうかこの裁判の速記を衆議院速記者の手でやつてもらいたい。翻訳が間に合わなければ参議院の速記者をも使って、早くやつてもらいたい」ということなので、私は「両院は困る、一つにまとまつているわけでないので、衆議院の人を全部使うようにしたい」と申し入れた。〉
衆議院に頼み込んだ外務省
東京裁判は、ポツダム宣言受諾に基づき、連合国による戦後処理と占領政策を担うGHQの最高司令官である米国のマッカーサー元帥の命令の下、太平洋戦争での日本の戦争犯罪人を対象に行われた。
被告は元陸海軍幹部、元閣僚などA級戦犯28人。豪州から来たウイリアム・ウェッブ裁判長、各国判事、検事らが任命され、昭和21年5月、東京・市ヶ谷の旧陸軍士官学校を舞台に開廷し、23年11月の判決言い渡しまで続いた。
裁判記録作成のための速記は、GHQの占領政策の日本側窓口である終戦連絡中央事務局の要請を受ける形で、衆議院速記者が担当した。座談会出席者が述壊するように、発端は、GHQの意向を受けた外務省の担当者が、衆議院の事務方の幹部に対し、「とにかく急いで体制を整えてほしい」と頼み込んできたことにある。
当初は、衆議院、参議院(21年当時は貴族院)の速記者が協力してでもやり遂げてほしい、との要望だったが、座談会記事を読み進むと、衆議院側は「どうしてもうちでやらせてほしい」と“独占”を主張したことが分かる。

衆議院だけでやるぞ、との決意
そして、「衆議院速記者だけによる担当」にこだわった根拠として、時代背景を感じさせる次のような説明が続く。
〈当時(二十一年初め)われわれ(原文はくノ字点)の月給が八十円か百円、とても食えない。ほかに収入もない。その時分、インフレーションがそろそろ(原文はくノ字点)進行しかかつているときで、みんな困つていたんだ。だからこの仕事を何とか衆議院の方に持つて来れば、新円であろうが、旧円であろうが、とにかく手当は出るに違いない。そんなところからこれに食いついたわけです。〉
戦後の混乱期、とりあえず収入を確保したいという事情もあったわけだ。36年から約40年間、衆議院記録部の速記者や記録部幹部として勤務した浅水信昭さん(69歳)=東京都大田区在住=は、この冒頭部分に興味を抱いた。
「戦後間もなくは、国会の前庭に畑を作ってイモを植えていたほどの食糧難でしたからね。22年の新憲法施行に伴う帝国議会から国会への移行期とも重なっていて、てんやわんやだったはずですよ。ただ、激務ながらも、衆議院だけでやるぞ、との決意が感じられます。衆議院と参議院とでは、速記符号や文化、気風が違ったことも独占した理由でしょう」
国会と東京裁判の「二足の草鞋」
当時は戦争などのため人手不足が深刻で、現場に出る速記者は現在の3分の1ほどの30数人しかいなかった。衆院事務局は慌てて速記者の大量養成を開始し、23年には60数人に倍増している。国会と東京裁判の「二足の草鞋」は、名誉ではあっても現場の速記者にとってかなりの重労働になったのだ。
速記者席が設置されたのは法廷の中央で、中堅やベテランの「主」任速記者と補佐役を勤める「副」担当の2人1組ずつ、30分ごとに次の番の者と交代して執務した。
裁判が始まってしばらく後、日米の速記者、日系米国人を中心とした通訳、通訳のまとめ役のモニターらが執務するガラス張りのブースが法廷内に設置され、速記者は「主」が法廷中央、「副」がブース内に配置されるようになった。座談会では、法廷で協力し合った通訳、モニターについて触れられている。
〈モニターは伊丹、林、小野寺などが、フィリッピンの本間裁判を終えてから来た。(略)伊丹という人は、日本語が日本人と同じようにしやべれたね。ジョージ・長野というのがいたが、これがむつつり屋で、人づきが悪い。ところがあとで服部ハウスに入つたら、こんなにいい人間だつたか、と驚いたくらいだ。〉
『二つの祖国』主人公のモデルも
「本間」とは、日本軍のフィリピン占領時の最高司令官で、BC級戦犯として現地で銃殺刑に処せられた、本間雅晴 陸軍中将と思われる。彼の指揮の下、米兵、フィリピン兵を虐待したとされる「バターン死の行進」事件は、東京裁判でも問題視された。
さらに「伊丹」とは、日米開戦により数奇な運命を辿ることになった日系米国人たちを描いた山崎豊子の小説『二つの祖国』で、主人公・天羽賢治のモデルになったとされる人物だ。戦時中は高い日本語能力を買われ、米陸軍情報部で、日本の軍事暗号を解読する任務に就いていたといわれる。
「ジョージ・長野」については、詳細は不明だが、日系米国人の通訳だったらしい。
「服部ハウス」とは、速記者の代表5人、通訳、法学者らが過ごした東京都内の住宅を指す。23年4月、裁判の審理を終えて休廷に入った後、裁判の言語担当部署の命により、判決文作成のために百日余もここに監禁されたのだ。
部下には「黙して語らず」
現在の衆議院事務局記録部や年配の元速記者たちに尋ねると、10人の座談会出席者は全員、既に鬼籍に入っているとのことだ。ただ、この場にいた唯一の存命者と思われる人が東京都中野区内に住んでいる。座談会を速記した元衆議院速記者の角田恵弘さん(77歳)だ。
「まだ養成所の生徒でした。先輩たちに呼ばれて速記したんです。東京裁判についてようやく話せるようになったということで座談会が企画され、リラックスした雰囲気で3時間ほど語り合っていました。でも、まだ速記が追いつかなくて、後で本人たちに直してもらったのを覚えています。私自身、服部ハウスを含めて、東京裁判の速記のことはこのときに初めて知りました。“ご褒美”は、近所のそば屋で、きつねそば一杯だけでした」
こう苦笑いしながら振り返るのだが、この座談会の後、「大仕事」だったはずの東京裁判が衆院速記者の間で語られることはほとんどなかった。元衆議院速記者の宮田雅夫さん(79歳)=東京都渋谷区在住=は証言する。
「ここに出てくる速記者のうち4人の部下を経験しましたが、東京裁判の話は一切、聞いたことがありませんでした。『黙して語らず』だったのです。やはり軍事法廷という性格上、秘密にすべきことが多かったからだと思います。その意味でも、彼らが仲間内で、本音で語った『衆友』の記事は貴重な資料ですね」
「読み返し要求 」に四苦八苦
東京裁判は、検察側立証、弁護側反証、論告、最終弁論と進み、国内外からの重要証人も続々と登場。検察側、弁護側双方が激しく論戦を繰り広げている。
座談会では、最も苦労したことの一つが「読み返し要求」だったと述懐している。日本人の証言が聞き取りにくかったり、通訳がもたついたりした場合、ウェッブ裁判長やモニターから、イヤホーンを通して再読を求められる。日本の国会の議事進行と異なるため、即座に答えられなくて困ったというのである。
〈ときたまうつかりしているところを突然モニターからマイクで「日本語の速記者の方、今のところ、もう一度読んでください」と声をかけられる。あちらの速記者ならあたりまえのことかもしらぬが、日本の速記者としては初めての経験だから、法廷中モニターの声がとどろきわたつたように感じた。(略)国際的な場所で間違つたことも読みたくないし、あれには脅威を感じた。まあ毎回適当に読んで何とか切り抜けたがね。(笑)〉
21年3月に戦後の女性一期生として衆議院速記者養成所を卒業し、東京裁判での速記も担当した元衆議院速記者の寺戸満里子さん(83歳)=東京都中野区在住=も、座談会記事に出てくる発言者名を目にして「懐かしい名前ばかり。みなさん大先輩です」と声を上げつつ、肝を冷やした体験を語った。
「確かに『読み返し』は大変でした。『副』でしたので、ブースの中でのんびりしてると、モニターに『今のところ読んでください』とやられるんです。アメリカ人の速記担当者はいつも悠然とタイプを打ってこなしていたのに、こちらはばたばたと手作業でしたからね。『アメリカは進んでいるな』と思いました」
「ダンコク」は「ダンガイ」
前述の宮田さんは、「国会では、発言を読み返すことはおろか、聞き返す場面も、まずなかった」という。
「東京裁判は発言者が頻繁に変わるので大変だったと思います。米国式だと、速記者や裁判官が聞き取れなければ、その場で確認するのが普通だったようですが、日本の国会ではそんな中断はなかった。速記者が発言についていくのは当たり前、との風潮がありましたから。聞き取れなければ、後で議員に確認するしかなかったのです」
日系米国人通訳の日本語が直訳的で滑らかではなかったため、速記がしにくかった、と振り返った座談会出席者もいた。なかなか完璧とはいかなかったようなのだ。こんな発言も見える。
〈ぼくのやつでは通訳が「ダンコク」と盛んに言うんだ。聞きに行つて「ダンコク」というのはどういう字なんだといつたら「弾劾」(ダンガイ)のことなんだ。「ダンコク」では、こつちは何のことかわからない。〉
***
「黙して語らず」の速記者たちがついに語った「東京裁判という仕事」。つづく後編では、座談会の後半で語られた裁判官や検察官、被告といった“登場人物“たちのエピソードをお届けする。法廷での濃厚な人間ドラマを見続けた彼らが、「肩書きや肩章をもぎとられた人間の姿」に抱いた複雑な思いとは。
後編【東條英機を見て感じた人情のつれなさ、日本人の便所に来たパール判事…速記者たちが語った「東京裁判」秘話】へつづく
菊地正憲(きくちまさのり)
ジャーナリスト。1965年北海道生まれ。國學院大學文学部卒業。北海道新聞記者を経て、2003年にフリージャーナリストに。徹底した現場取材力で政治・経済から歴史、社会現象まで幅広いジャンルの記事を手がける。著書に『速記者たちの国会秘録』など。
デイリー新潮編集部