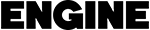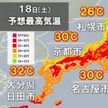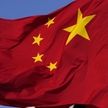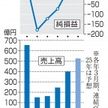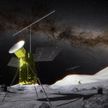ついに発表された新型フェラーリ。その車名は実に驚くべきものであり、時代にあらがうようなネーミングには、フェラーリの決意と自信がに滲み出ていた。正式発表に先立ってイタリアのマラネロで行われたジャーナリスト向けの特別な内覧会に立ち会ったエンジン編集長の村上が、その名前に込められた熱い想いをリポートする。
シンプルにして大胆不敵
「エンツォ・フェラーリ」や「ラ・フェラーリ」という、初めて聞いた人が思わず仰け反ってしまうようなシンプルにして大胆不敵な車名を、飛び切り重要なモデルに与えてきたメーカーのことである。もはや、どんな名前のクルマが現れても驚かないが、それにしても、まさかここまでストレートにくるとは! 
5月3日、フェラーリのアメリカ上陸70周年を記念して、グランプリ・ウィークのマイアミで開催されたイベントに登場したニューモデルの名は「12Chirindori」。イタリア語を無理やりカタカナにすると「ドーディチ・チリンドリ」。英語ならば「トゥエルブ・シリンダー」。すなわち、日本語では「12気筒」ということになる。
この車名に、多くのクルマ好きはどんな印象を抱くだろうか。もちろん、意外ではあるだろうが、イタリアには、文字通り4枚ドアを意味するマセラティの「クアトロポルテ」という名を持つ名車もあるし、戦前の栄光の時代のアルファ・ロメオは「6C」とか「8C」とか、まさに気筒数に由来する名前を持っていた。それを考えれば、決して突拍子なネーミングではない。いや、それ以上に、なによりも「いま・ここ」で、あえて「12気筒」という大看板を掲げたことに、私は、フェラーリがこのクルマに託した熱い想いがそのまま伝わってくるように思ったのだ。
発表に先立ち、イタリアのフェラーリの本拠地マラネロで、ジャーナリスト向けの特別な内覧会が開かれた。そこでの説明によれば、実際にこのクルマを開発し始めたのは4年前だという。すなわち、まさに内燃機関に対して世間の逆風が強まり、多くの自動車メーカーが急ピッチで電気シフトに取り組む中で、フェラーリはあえて「12気筒」を全面に押し出した、言うなれば時代の流れに逆行するようなモデルを世に問うことを決断し、その開発をその後のコロナ禍の数年の間、コツコツと進めていたということになる。
その意気やよし。もはや確信犯と言うべきだろう。ひょっとすると最後になるかも知れない自然吸気12気筒をフロント・ミドシップに搭載する後輪駆動モデル。それは、1947年に登場した145S以来、フェラーリのプロダクト・カーのメイン・ストリームはフロントV12エンジンの2シーター・ベルリネッタにあったのだ、ということを強烈に印象づける、いわば集大成のモデルでもある。以下に、その中味を詳しく見ていくことにしよう。
365GTB4デイトナを想起
12チリンドリの開発コンセプトは極めてシンプルで、「パフォーマンスとコンフォートの完璧なバランス」にあったという。リアではなくフロント・ミドシップにエンジンを置くことにより、十分にコンフォートなキャビンのスペースを確保する一方で、リア・アクスル上にギア・ボックスを置くトランス・アクスル・レイアウトを取ることで、パフォーマンスに大きく影響する重量配分も、前48.4、後51.6%という極めて理想的な数字を得ている。ちなみに、車両乾燥重量は1560kg。12気筒モデルとしてはかなり軽く、徹底的な軽量化が図られたことが窺える。 
スポーツカー・ドライバーを対象とするモデルを左側に、レーシング・パイロットを対象とするモデルを右側に配置した現行フェラーリのプロダクション・モデルのポートフォリオの中では、12チリンドリはちょうど中間に位置するという。すなわち、一番左側にいるのがローマとローマ・スパイダーで、その右隣がプロサングエ。逆に一番右側にいるのはSF90とSF90スパイダーで、その左隣が296GTB&GTS。そして、プロサングエと296の間に入るのが12チリンドリというわけだ。こう説明されると、「パフォーマンスとコンフォートの完璧なバランス」という開発コンセプトが良く分かる。
別の言い方では、「パワフルでアグレッシブ、けれど洗練されていてミ二マル」とも表現していた12チリンドリのデザインは、まさにそれをそのまま表現したものになっている。フロント・マスクを見て誰もがすぐに想起するのは、1965年の365GTB4デイトナだろう。フェラーリ自身が、1950から60年代の伝説的グランド・ツアラーをインスピレーションとしていることを謳っているのだから、それも当然のことだと思うが、リアに視線を移すと、まるで違った印象の極めて未来的な後ろ姿が現れる。ローマに似た宝石のようなテール・ランプに、コーダ・トロンカの現代的解釈とも言えそうな下部のディフューザーに向けてグッと切れ込んだリア・エンド。 
とりわけ特徴的なのは、ほとんどまっ黒と言っていいくらいにダークなリア・スクリーンからリア・エンドに向けて、三角形に拡がっていく「デルタ・ウィング・シェイプ」とデザイナーのフラヴィオ・マンゾーニ氏が呼ぶ造形だ。リアの両側部分はフラップになっていて、速度や走行状況に応じて上下するという。このデルタ・ウィング・シェイプはルーフからリア・クォーター・ガラスにかけても反復されており、マンゾーニ氏は「ダブル・デルタ・ウィング・シェイプ」と表現していたが、まるで宇宙船みたいだと私は思った。
このアイデアがマンゾーニ氏はよほど気に入ったらしく、さらにインテリアにも同じ造形が反復されていることを、後から知ることになった。運転席と助手席の間にあるコンソールに、同じ造形のフローティング・ブリッジがあしらわれているのだ。 
インテリア全体のデザインは、ローマのダブル・コクピット・デザインをさらに推し進めたものだ。助手席側にもモニターがあるので、まるで運転席と変わらない印象で、ふたつのコクーン(繭)がほぼ左右対称に並んだようになっている。洗練されていてミニマルなデザインとは、まさにこういうものを言うのだろう。
スパイダーも登場
さて、このクルマの主役である12気筒エンジンについても、しっかりと見ていくことにしよう。ドライサンプ式を採用し、フロント・ミドシップに深く低く押し込まれた赤い結晶塗装を持つ自然吸気6.5リッターV12エンジンのコード・ネームはF140HD。番号からわかる通り、これまでの12気筒エンジンの最新進化版である。どうやら、一番近いのは812コンペティツィオーネに搭載されたそれで、エンジンに限らず、シャシーなども同車から引き継がれたものが多いようだ。最高出力は830psで最大トルクは678Nm。チタン製コンロッドの採用により回転質量を40%低減するなどして、最高回転数はなんと9500rpmというからまさにレーシングカー並だ。そんなとてつもない高回転型エンジンであるにもかかわらず、最大トルクの80%を2500rpmから発揮する実用的な性能も兼ね備えているのである。
そのパワー&トルクは、前述のようにリア・アクスル上に配置される8段デュアルクラッチ・トランスミッションを介して21インチの大径タイヤを履く後輪に伝えられる。
シャシーはアルミニウム製で、ホイールベースが812スーパーファストより20mm短縮されているのも、12チリンドリの特徴である。パフォーマンスを重視してのことだというが、さらに12チリンドリには812コンペティツィオーネゆずりの4輪独立操舵システム(4WS)が装備されている。これは左右後輪が別々に操舵可能で、前輪と同位相や逆位相にステアするのはもとより、状況に応じてトーアウトやトーインの姿勢も取るというから、パフォーマンスの面でも安定性の面でも、大いに貢献するであろうことが予想される。
また、最新技術のひとつとしてブレーキ・バイ・ワイヤー・システムが導入されていることが発表されたが、気になったのはサスペンションについての説明がまったくなかったことだった。前後ダブルウィッシュボーンなのはともかく、パフォーマンスとコンフォートの完璧なバランスを求めたというのならば、なぜプロサングエに採用したプロアクティブ・サスペンション・システムを採用しなかったのだろうか? この問いに対するチーフ・エンジニアのダビデ・ラニエリ氏の答えはこうだった。第1に、パフォーマンスを重視した12チリンドリでは軽量化が重要だったこと。第2に、プロアクティブ・サスペンションは48Vの電源に加えて独自の冷却システムを必要とするが、そのためのスペースが無かったこと。第3に、もともと車高の低い12チリンドリには、車高を上下させるシステムが必要なかったことから、従来の可変ダンパーを採用したというのである。 
ところで、12チリンドリの登場には、もうひとつサプライズがある。クーペと同時にスパイダーも発表されたのである。時速45km/hまでなら走行中でも14秒で開閉できるリトラクタブル・ハードトップを備えたスパイダーは、コクピットの背後に左右ふたつのフィンを備えたスタイルを持っているクーペの未来的なデルタ・ウィング・シェイプが小さくなってしまうのは残念だが、こちらの方がスタイリッシュで好ましいと思う人も少なからずいるのではないか。とはいえ、どちらを選ぶかを悩めるのはとても幸運な人というべきだろう。なにしろ、クーペのイタリア価格が39万5000ユーロというから、日本では7000万円前後になるだろう。むろん、スパイダーはさらに高くなる。それでも欲しいという人は悩む前に即刻オーダーを入れるべきだ。どちらも一瞬で売り切れる可能性が高い。
文=村上 政(ENGINE編集長)
(ENGINE Webオリジナル)
【エンジン音付き!】新型フェラーリ発表! その名も「12チリンドリ」 830馬力の自然吸気6.5リッターV12の最高回転はなんと9500rpm!!

関連記事
あわせて読む
-

ホンダ「“2シーター”軽量スポーツカー」登場! 鮮烈レッド&MT採用の超スポーティ仕様! 約35年前の「CR-X」米で高額落札
くるまのニュース5/18(土)7:40
-

ヤマハの電動アシスト自転車が体感できるショールーム! みなとみらいに「Yamaha E-Ride Base」がオープン
バイクのニュース5/18(土)7:10
-

トヨタのEV、bZシリーズに2つのニューモデルが登場 北京モーターショー2024でお披露目
ENGINE WEB5/18(土)7:00
-

低カロリー&グルテンフリーの「こんにゃく焼きうどん」「玉こんにゃくのアヒージョ」が食べ放題!
BCN+R5/18(土)6:30
-

「巨人の手で押されるような4.4リッターV8ツインターボのトルク感は最高」 モータージャーナリストの小沢コージがBMWアルピナXB7など5台の輸入車に試乗!
ENGINE WEB5/18(土)6:00
-

「Summer Game Fest 2024」パートナー企業55社発表―カプコン、バンダイナムコ、Deep SilverやEA、UBI…
Game*Spark5/17(金)22:30
-

中古車の値段が上がるのはイヤなので内緒にしたい! 4リッター自然吸気並みの大トルクを発揮する3リッター直6ターボをぶち込んだ135iクーペは、どんなBMWだったのか?
ENGINE WEB5/17(金)21:00
-

シドニー観光のためのモデルコース完全ガイド|3日間で巡る絶景と文化
YOKKA5/17(金)20:30
-

【コスプレ】『NIKKE』紅蓮の美クビレが織りなすS字カーブ!いくらなんでも腰が細すぎ【写真8枚】
インサイド5/17(金)20:00
-
-

水無しでメイクが落とせるクレンジング「セラクレンズ」にミニサイズが出るよ〜!防災・アウトドア・旅行で便利。
東京バーゲンマニア5/17(金)20:00
-

今夏は185系の臨時列車が激減! 一般の臨時列車はわずか2つのみに、今後どうなる?
鉄道コム5/17(金)19:25
-

ヤマハのナイトミーティング「The Dark side of Japan Night Meeting 2024」 来場者数は約700名 次回開催は?
バイクのニュース5/17(金)19:10
-

9月に日本デビュー&夏にジャパンホールツアー決定! RIIZE初のファンコンが大盛況
ananweb5/17(金)19:00
-

新型iPad Proは史上最高峰だけど「何でもできる」わけではない
Gizmodo Japan5/17(金)19:00
-

【6/1】世羅町のFlower village 花夢の里「あじさいとタチアオイの丘」がオープン
ひろしまリード5/17(金)17:48
-

セルジュ・ルタンスの24年夏フレグランス、“目覚めの時”をイメージした爽やかな香り
ファッションプレス5/17(金)17:45
-

【6/24〜9/15】岡山県倉敷市の「倉敷アイビースクエア SUMMER NIGHT BEERGARDEN 2024」開催!今年もビアガーデンの季節が到来!
ひろしまリード5/17(金)17:23
-

メルセデスAMGの「超高性能モデル」サーキットでの印象は? ルックスは迫力満点!“闘争心あふれる走り”も新型「GTクーペ」の持ち味です
VAGUE5/17(金)17:10
-
トレンド アクセスランキング
-
1

「家事は妻の役目!」【超亭主関白な父】が → ある日『風呂掃除担当』に! 父を変えた出来事とは?
ftn-fashion trend news-5/17(金)21:01
-
2

世界初の「2階建て」ミニバン! 斬新すぎる「屋根裏部屋」付きのマツダ車が凄い!「車中泊」が最高に楽しめる「面白ミニバン」に注目!
くるまのニュース5/17(金)20:10
-
3

「笑いが止まりませんでした」 自販機で缶コーヒーを1本買った結果→まさかの〝大当たり〟で困惑
Jタウンネット5/17(金)20:00
-
4

「可愛くなった?」褒められるかも♡【30・40代】周りと差がつく「ふんわりショートヘア」
ftn-fashion trend news-5/17(金)20:45
-
5

朝イチのコーヒー、胃腸が弱い… 「どんどん老ける人」の特徴と対策
ananweb5/17(金)20:30
-
6

パッと目を引く!【しまむら】大人の可愛さ♡ 高見え「花柄アイテム」
ftn-fashion trend news-5/17(金)21:05
-
7

しまラー、リアルバイ♡【しまむら】真似して買いたい!「2,000円以下アイテム」
ftn-fashion trend news-5/18(土)3:05
-
8

60歳代おひとりさまの「平均貯蓄額」はいくら?
All About5/17(金)21:20
-
9

40・50代も【ユニクロ】がおしゃれ! 上品 & 高見え! 「優秀カーディガン」
ftn-fashion trend news-5/18(土)5:05
-
10

温泉に入って10秒でお肌がトロリ!? 関東初スノーピークのキャンプ場が生まれた「鹿沼の日帰り旅が予約なしでも楽しい」ワケとは?
VAGUE5/17(金)20:10
トレンド 新着ニュース
-

ホンダ「“2シーター”軽量スポーツカー」登場! 鮮烈レッド&MT採用の超スポーティ仕様! 約35年前の「CR-X」米で高額落札
くるまのニュース5/18(土)7:40
-

今年も重宝する予感♡【ハニーズ】激かわです!「クリアバッグ」
ftn-fashion trend news-5/18(土)7:35
-

「今日はどうだった?」「もうやめてよ!」【小学生の娘】を傷つけてしまい母、大反省。そのワケは?
ftn-fashion trend news-5/18(土)7:31
-

【マッジョーレ】錦糸町で見つけた、石臼引き手打ち生パスタを楽しめるイタリアン
cocotte5/18(土)7:30
-

近所にできたらうれしい定食チェーンランキング!3位 やよい軒、2位 大戸屋ごはん処、1位は…
gooランキング5/18(土)7:30
-

金の価格はどこまで上がるのか…「ミステリアスラリー」の背景に「ドルからの脱却」?
ABEMA TIMES5/18(土)7:30
-

「首都圏横断」の異色特急が運転へ 土浦を出ると次は立川! 豪華なグリーン車も連結
乗りものニュース5/18(土)7:12
-

「図々しいんだよ!!」【産後すぐに乗り込んできた義姉家族】 → 非常識な言動の連続に激怒!
ftn-fashion trend news-5/18(土)7:11
-

ヤマハの電動アシスト自転車が体感できるショールーム! みなとみらいに「Yamaha E-Ride Base」がオープン
バイクのニュース5/18(土)7:10
-

1泊3千円!?「高速道SA」にホテル存在ッ!? 「一般道に降りずに寝るのサイコー!」 注目の”飲み放付き”の施設、連休は混んだ?
くるまのニュース5/18(土)7:10
総合 アクセスランキング
-
1

木村拓哉『Believe』“人気女優”演じるキャラがまさかの豹変…「期待外れ感」に視聴者ガッカリ「マジで怖い」
女性自身5/17(金)20:10
-
2

滝沢秀明氏「TOBE」6人組新グループ「DeePals」結成発表、いきなり有明デビューも決定
日刊スポーツ5/17(金)22:34
-
3

5月17日が「大谷翔平の日」に LAが制定…グレースーツで市庁舎訪問、球団発表
Full-Count5/18(土)3:45
-
4

「ビリギャル」小林さやかさん「コロンビア大学教育大学院を卒業しました!」美しいガウン姿…12日に離婚公表
スポーツ報知5/17(金)20:30
-
5

世界ランク1位シェフラー緊急事態 警察に拘束、手錠かけられ囚人服姿に 全米プロゴルフ選手権
日刊スポーツ5/17(金)22:10
-
6

【阪神】青柳晃洋3敗目 岡田監督辛口「目も当てられんわな。ボール、ボールなる」
日刊スポーツ5/17(金)23:04
-
7

84歳志茂田景樹氏「要介護5」告白 17年に関節リウマチ発症、車椅子生活も励ましの声相次ぐ
日刊スポーツ5/17(金)20:39
-
8

大谷翔平が米ファンを泣かせる行動 突然現れたと思いきや…「よくやった。本当に…」と米感動
THE ANSWER5/17(金)21:03
-
9

博多大吉 相方・華丸にも35年間黙っていた秘密を告白 五輪表彰台の夢も
デイリースポーツ5/17(金)23:01
-
10
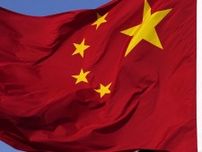
中国、日本水産施設を停止 5月から税関当局の登録
共同通信5/17(金)23:41
東京 新着ニュース
-

つばさの党の行為は「表現の自由」? 逮捕に踏み切った警視庁はどう判断したか 候補者ら立件の前例はなく
東京新聞5/18(土)6:00
-

選挙カー囲み「出てこい、クズが」 「米国の犬、ばばあ」とまで…各陣営が訴えた「つばさの党」妨害の内容
東京新聞5/18(土)6:00
-

重要人物が異論!「井上尚弥VS“最狂”デービスは現実離れし過ぎている」“モンスター”陣営のアラムCEOがサウジ王族提言のドリームプランを疑問視
RONSPO5/17(金)21:41
-

旧岩淵水門が「重要文化財」指定へ 荒川と隅田川の分岐点で水害防ぎ100年 「誇りだ」住民ら喜び
東京新聞5/17(金)21:15
-

シラサギの群れが舞った 浅草・三社祭が開幕「まるで別世界」 「宮出し」は最終日の19日
東京新聞5/17(金)20:42
東京 コラム・街ネタ
-

本田圭佑、FIFA議会に初出席 「初めて出席したけど、良いところも悪いところも大体イメージは掴めた」
Qoly5/18(土)7:30
-

ブライトン三笘薫、日本で実戦復帰か デゼルビ監督が可能性示唆
Qoly5/18(土)7:10
-

22歳鈴木唯人、マンチェスター・ユナイテッドも争奪戦に参戦 移籍金は42億円か
Qoly5/18(土)6:55
-

伊藤洋輝、今夏にプレミアリーグ移籍も?シュトゥットガルトが格安の50億円でも売却するワケ
Qoly5/18(土)6:45
-

オセールFWオナイウ阿道、最終戦でハットトリック!「今季15得点のなかで間違いなくベストゴール」と現地賞賛
Qoly5/18(土)6:30
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
(C) 2024 SHINCHOSHA Publishing Co.,Ltd.