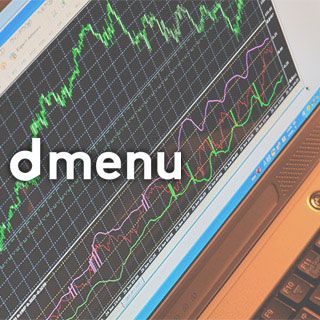姪・こま子を妊娠させ、フランスに逃げた藤村は、『桜の実の熟する時』を書いたのち帰国します。そして主人公と姪の不倫を書いた告白小説『新生』を発表するのです。世に言う「新生事件」として世間を騒がせた藤村。自然主義文学はなんでも洗いざらい書けば許されると思っているとしたら大間違いです。
文=山口 謠司 取材協力=春燈社(小西眞由美)
懺悔すれば許されるのか
前回を読んでいただいた方は、藤村は純粋でシャイな人物のように思うかもしれませんが、その実態は違いました。
『桜の実の熟する時』でも藤村は若い頃の不幸な恋愛経験を吐露しましたが、自然主義文学だからといって、洗いざらい書けばいいというものではありません。
明治の後半になって興った自然主義という文学運動は、人間の生活を直視し、ありのままの現実を飾ることなく描写するというものですが、二葉亭四迷などは「近頃は自然主義とか云って、なんでも作者の経験した愚にも附かぬ事を、聊(いささ)かも技巧を加えず、有(あり)の儘に、だらだらと、牛の涎(よだれ)のように書くのが流行(はや)るそうだ」と明治40年の連載小説『平凡』に書き、批判的な目を向けていました。
藤村と並んで自然主義文学の代表作とされる田山花袋の『布団』も、実体験に即して中年作家・竹中が美しい弟子の芳子に恋心を抱き、嫉妬にかられる様子を赤裸々に描いた作品です。芳子の使っていた布団と夜着の匂いを嗅ぐシーンは、今だったら変態扱いでしょう。なんでもかんでも事実を書けばいいというものではありません。
藤村の場合、キリスト教徒だったということも影響していると思います。
キリスト教では自分の罪を悔いて告白する「懺悔」をすることで、罪を許され、救いになります。洗いざらいすべて明かして、懺悔のような気持ちで綺麗な世の中を作っていくんだという、理想的な世界を藤村は求めているように思えますが、実は小説のモデルとなった輔子や恒子、こま子など、他人の苦労を何とも思わない、ずる賢いところがありました。
作家になってからも「僕はこんなに惨めなんだ」と女性を油断させておいて、「ねえ、慰めて。僕の奥さんは体が弱くて何もしてくれないんだよ」というようなことを言って女性に言い寄り、ついには妻が死んだ後、その寂しさから家事を手伝いに来ていた21歳の姪のこま子に手を出すのです。この時藤村は41歳。そしてこま子が妊娠したことがわかると「これはヤバい!」と、自分だけフランスに逃げるという、とっても卑怯な男だったのです。
そして大正5年(1916)7月に帰国すると、その2年後にこま子との一部始終を描いた『新生』第1部を発表(第2部は1919年8〜10月)しました。登場人物の岸本捨吉が藤村、節子がこま子です。節子が岸本に妊娠を告げる場面は次のように描写されています。
ある夕方、節子は岸本に近く来た。突然彼女は思い屈したような調子で言出した。
「私の様子は、叔父さんには最早(もう)よくお解(わか)りでしょう」
新しい正月がめぐって来ていて、節子は二十一という歳(とし)を迎えたばかりの時であった。丁度二人の子供は揃(そろ)って向いの家へ遊びに行き、婆やもその迎えがてら話し込みに行っていた。階下(した)には外に誰も居なかった。節子は極く小さな声で、彼女が母になったことを岸本に告げた。
避けよう避けようとしたある瞬間が到頭やって来たように、思わず岸本はそれを聞いて震えた。思い余って途方に暮れてしまって言わずにいられなくなって出て来たようなその声は極く小さかったけれども、実に恐ろしい力で岸本の耳の底に徹(こた)えた。それを聞くと、岸本は悄(しお)れた姪(めい)の側にも居られなかった。彼は節子を言い宥(なだ)めて置いて、彼女の側を離れたが、胸の震えは如何(いかん)ともすることが出来なかった。すごすごと暗い楼梯(はしごだん)を上って、自分の部屋へ行ってから両手で頭を押えて見た。
島崎藤村「新生(上)」(新潮文庫)
娘ほど年齢の離れた女性の妊娠を知って、大の大人がこんなに動揺するものでしょうか。