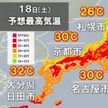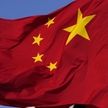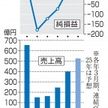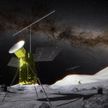1994年の5月1日に行なわれたF1サンマリノGPの決勝。このレースで、ウイリアムズのマシンをドライブしていたアイルトン・セナがタンブレロでクラッシュし、その命を落とした。
事故の原因については今も様々な意見が存在するが、その中のひとつに、セーフティカーがあまりにも遅すぎたため、その間にF1マシンのタイヤの内圧が下がり、それがセナの事故に繋がったという論調もあった。
この時セーフティカードライバーを務めていたマックス・アンジェレリは当時のことを振り返り、パフォーマンスが著しく劣るセーフティカーから100%のパフォーマンスを引き出したと自信を持っているものの、事故が起きたことについては、長きにわたって自責の念に捉われ続けたという。
セーフティカーがF1に正式に採用されたのは、1993年のことだった。今でもF1ドライバーたちは、「セーフティカーが遅すぎる」と苦言を呈することが多いが、当時のセーフティカーは今以上にF1マシンとのパフォーマンス差が大きく、セーフティカードライバーのアンジェレリにとっては、まさに悪夢のような状況だったようだ。
このアンジェレリの助手席に座っていたのが、後にF1のレースディレクターを務めることになるチャーリー・ホワイティングだった。ホワイティングは2019年に急逝してしまったため、その時の体験を今改めて訊くことはできないが、数年前に公開されたマックス・モズレーの動画の中で、セナの事故を振り返る際に、ホワイティングは当時のセーフティカーの状況を語っていた。
「私は当時、セーフティカーのオブザーバーだった」
FIAのテクニカルデレゲートを務めていたホワイティングはそう言う。
「それは私の義務のうちの、小さなモノのひとつだった」
「レース中には、やるべきことがあまりなかった。だから私は、当時セーフティカーに乗っていたんだ」
「メインストレートで事故があった。ペドロ・ラミーが関係する事故だったと思う(スタートでストールしたベネトンのJ.J.レートのマシンに、後方スタートだったロータスのラミーが追突。コース上に多くのデブリが散乱した。またこのデブリは、観客席にも飛び込んでしまい、負傷者を出すことになった)。それでセーフティカー出動が宣言され、我々はコースに出ていった」
「レースをリードしていたのはセナだった。それは、昨日のことのように覚えている」
「我々がシケインを通過しようとしていた時、セナはマシンを横付けしてきたんだ」
「彼はまさに隣にいて、バイザーを上げて『もっと速く! もっと速く!』と言っていた。私は『無理だ。これ以上速くは走れない。不可能だ』と言った」
「ブレーキは熱くなっていて、匂いもしていた。そして気の毒なドライバーは、このクルマで最善を尽くしていた。その周の終わりに我々はピットに戻ったが、その1周後に彼(セナ)が事故を起こしたんだ」
■パワー不足の上、重過ぎた
当時セーフティカーとして使われていたのは、オペル・ベクトラであった。この車両は重量が1350kgもあり、しかもパワーは204馬力しかなかった。しかもほぼノーマルの状態だったようだ。
そんなマシンでF1マシンを先導するのは、セーフティカードライバーのアンジェレリとしては、イモラに到着したその瞬間から懸念していたものだった。
書籍『セナ:真実』の中でアンジェレリは、セーフティカー出動の時の恐怖について、次のように回顧している。
「クルマを見せてもらった時、背筋が寒くなったよ」
そうアンジェレリは語った。彼は当時ドイツF3にも参戦しており、その2年前にはイタリアF3でタイトルを獲得していた人物。イモラのコース特性も熟知していた。
「F1マシンの集団の前を走るのには、適していなかったんだ」
「僕はチャーリーのところを訪れ、自分の疑問を説明した。クルマには十分なパワーがなく、そしてサーキットで使うのに適切なブレーキシステムも備わっていなかったんだ」
アンジェレリは、オペルで練習走行を行なったが、その懸念は劇的に高まっていった。
「それは本当に災害とも言えるモノだったんだ」
「2回の下り(アクア・ミネラリとリヴァッツァ)では、減速するために錨が必要だったね」
「わずか2周走っただけで、ブレーキが過熱しすぎてしまい、ペダルがスポンジみたいな踏み心地になってしまった。制動距離が長くなってしまった。とても心配したんだが、私が恐怖を抱いていたとしても、何も変わらなかったんだ」
■代替の手段を見つけたのに……
オペルではF1のセーフティカーとしては十分ではないと真面目に懸念を深めたアンジェレリは、他に適切なマシンがないか、それを探し始めた。それで行き着いたのが、ポルシェ・スーパーカップのパドックだった。
「僕は自分の選択を誇りに思ったね。それで、セーフティカーのカッティングシートとカメラを、ポルシェのコクピットに移し始めたんだ」
「土曜日の朝には全ての準備が整っていた。でも彼らは、911は使えないと僕に言ったんだ」
「僕はまだ若かったから、F1における色んな力関係を理解しきっていなかった。僕が知らなかった、商業的な契約があったみたいなんだ」
「僕としては、オペル・ベクトラはセーフティカーには適していなかった。それでより適したクルマがポルシェだった」
「でも何も説明されず、全て分解してベクトラに組み立て直すように言われたんだ。楽しいはずのことが、悪夢に変わる可能性があることに気付いたね」
■ヘルメットを被る余裕もないまま、急遽出動
結局アンジェレリには、オペルを走らせ続けるしか選択肢はなかった。しかしスタート直後にいきなりクラッシュが起き、セーフティカー出動が宣言された。まさに急遽の出動……アンジェレリにはヘルメットを被る時間も、レーシングスーツを着る時間もなかったのだ。写真を見ると、ヘルメットを被らずにオペルを走らせるアンジェレリの姿が写っている。
「全て突然起こったことなんだ」
そうアンジェレリは回顧する。
「上半身はまだ防火服を着ていなかったし、ヘルメットも後部座席に置かれたままだだった」
「事故には驚いたけど、それは完全の僕のせいだった。チャーリー・ホワイティングは無線で指示を受け、すぐに出発するように私に言った。コースに入るには、ピットボックスを通過する必要があったんだ」
「チャーリーはコントロールを維持し、落ち着いた口調で命令を話した。彼は僕が数回レースしていたマカオのレースディレクターを務めていた人だから、僕は彼のことをよく知っていた。
「彼は右側のシートに座っており、指示を実行するためにレースコントロールと繋がった無線のヘッドセットを装着していたため、ヘルメットを着用していなかった」
「我々はコースに入って減速し、後ろにマシンが追いつくのを待った。そしてバックミラーを見ると、首位を走るセナのウイリアムズが近付いてくるのが見えた」
「スピードは上がったけど、クルマの限界は十分に承知していたので、100%のパフォーマンスを発揮するつもりはなかった。レースが再開されるまで、どれだけ走らなければいけないか分からなかったからね」
「ブレーキが効くのは、せいぜい2〜3周だろうと分かっていた。だから慎重にブレーキをかけるようにしていた。一方加速する時には、スロットルペダルを強く踏み過ぎてしまって、床に穴が開きそうだったよ」
■クルマが止まっているように感じた
F1マシンの隊列を率いている時の恐怖と言ったら、練習走行中のそれとは比べ物にならないほどだったと、アンジェレリは振り返る。
「加速という面では、イモラはベクトラにとって挑戦じゃなかった。少なくとも、ふたつの登り以外はね。最も重要なのは、アクア・ミネラリの出口だったんだ」
「バリアンテ・アルタに向けて加速している時には、オペルは限界に見えたよ。時速130kmを超えることはできなかった」
「隊列をリードしていたセナが、何度か横に並びかけてきて、拳を振り上げて『もっと速く行け!』と言っていた。記憶から消してしまいたかった記憶が蘇りつつあるね。最後にアイルトンの目を見たのは、チャーリーと僕だったと思う」
「アイルトンは激怒していたけど、それは当然だった。彼のウイリアムズにとってはスピードが遅すぎて、タイヤの内圧と温度は下がっていただろうからね」
「ホワイティングは黙っていた。僕にもっと速く走れとは言わなかったんだ。彼はベクトラのパワーが十分ではないことに気づいていたし、ダッシュボードの全ての警告灯が点灯している状況だった」
「リヴァッツァに向けての下り坂でブレーキをかける時、優しくペダルを踏まなければいけなかった……だからスピードはとんでもないモノだった。3周した後、あらゆる予防をしたにも関わらず、ラインがワイドになって縁石を越え、芝生の上に2輪が出てしまった」
「この時点で僕は心配になった。そしてチャーリーにこう言ったんだ。『ほら、もうブレーキがないんだ。あと1周は走れるけど、それ以上は無理だから、ピットに戻ろう。危険だ。セーフティカーがコースアウトしたら、僕らは一体どうなるんだい?』とね」
ホワイティングは、レースコントロールにそのメッセージを伝えた。しかし、セーフティカーはステイアウトするようにという指示が戻ってきたという。
「走り続けたけど、ペースはどんどん遅くなっていった」
アンジェレリはそう語った。
「恥ずかしくなってしまったよ。ベクトラが悪いわけじゃないよ。でもあのクルマは、F1マシンを率いるには適していなかった」
「4周目が終わり、ついにレースコントロールは、レースを再開するために僕らにピットに戻るよう指示してきた。そしてピットに入り、オペルを止めてエンジンを切った。そのエンジンは、もう二度とかからなかったんだ。つまり、クルマは完全に死んでいたんだ」
「その2周後、アイルトンの事故が起きた。そしてレースコントロールは、すぐに赤旗を出してレースを中断した。そうしなければ、僕らは動けなかっただろう」
■セナの怒りが、頭から離れない
セナがセーフティカーに向かって何度も拳を振り上げ、スピードを上げるように訴える姿は、後に起きる悲劇的な事故とリンクして語られるようになった。そのことは、アンジェレリを悩ませることになったという。
「僕が経験したことを話すよ。僕は何年もの間、あの事故に関して自責の念を感じていたんだ」
そうアンジェレリは語る。
「彼のタイヤの内圧が下がり、それによってマシンがタンブレロのバンプで底打ちしてしまったのではないかと思ったんだ。あるいは、コースアウトする前に何かを壊したのかもしれない」
「事故は再スタートが切られてから3周目の前半、つまりレースの7周目に起きた。その時点で、タイヤが適切なグリップを発揮するために必要な内圧と温度に戻っていたかどうか、僕には正確なことは分からなかった」
「疑問を払拭するために、僕はレース後に、そのレースでフットワークのマシンをドライブしていたジャンニ・モルビデリに電話をかけた。すると彼は、『心配しなくていい』と言ったんだ。そして『タンブレロはすぐに全開で走ったけど、路面にぶつかってもマシンのコントロールに大きな問題は発生しなかったよ』と教えてくれた」
しかしアンジェレリは、セナの死に関する裁判の中で、法的な捜査の対象となってしまうことになった。
「何も反応がないと思っていたんだけど、僕は自分自身のことを守らなければならなかった」
そうアンジェレリは語った。
「僕はウイリアムズの弁護士に呼び出された」
「それは、実際に起きたことから、セーフティカーの役割に注意を逸らす試みであるように感じた。つまりセーフティカーが遅すぎてタイヤの内圧が下がり、それがウイリアムズをコースアウトさせる原因になったということにしたいのではないかと思った」
「でも僕に言えるのは、難しい状況の中で、クルマのポテンシャルを100%引き出したということだけだった。まずはブレーキを労り、そして車両が許容できるペースを維持しようとした」
■心の傷を癒す日々
セーフティカーが遅かったことが、セナの事故の一因となった可能性は、後に正式に除外されることになった。しかしその日の感情は、アンジェレリにその後何年にもわたって影響を及ぼしたという。
IMSAでレースをした時には、1994年にウイリアムズでセナのレースエンジニアを務めていたデビッド・ブラウンと共に仕事をしたが、事故のことについて話し合うことはなかった。
「これは、僕らがこれまで扱ったことのないテーマだ」
そうアンジェレリは言う。
「あれから30年が経った。あの呪われた日の細かい全てを、覚えているわけではない。でも、深い感情とそれが僕に残した傷跡のことは、今でも覚えている」
「歴史上最も偉大なドライバーが、僕の横にやってきて、もっと速く行けと拳を突き上げるのを見た。僕が自分がとてもちっぽけなモノになったように感じた。消えたかったし、生まれてきたくなかったとすら感じたよ」
「僕にとってそれは酷いことだった。彼がウイリアムズのコクピットから、僕に話しかけているのが見えた。彼が僕に送ってくるメッセージは、実に明白だったんだ」
「僕は罪悪感を感じながら、サーキットを後にした。酷い感情だった。モルビデリの言葉は慰めにはなったけど、僕の良心が静まったわけではなかったんだ」
「でもそれから30年が経って、心の傷はゆっくりと癒されてきたんだ」
セナの事故死から30年……ずっと苦しみ続けてきたセーフティカードライバーの話「僕は100%で走ったけど、F1の前を走る適切なクルマじゃなかった」

関連記事
あわせて読む
-

イモラの悲劇を忘れるな! ベッテル、F1での安全対策の迅速化を求める。GP開催前にはドライバーらとセナ追悼ラン
motorsport.com 日本版5/17(金)19:10
-

没後30年の英雄セナに現役ドライバーたちが語った思い…角田裕毅は「この人は明らかに違う」と感銘、ガスリーはアイドルの車を駆って感激
THE DIGEST5/17(金)18:48
-

FIA F3に参戦するダンとステンスホーンがマクラーレンの若手ドライバー育成プログラムに加入
オートスポーツweb5/17(金)16:36
-

バレーボール女子日本代表がブルガリア下し開幕2連勝、古賀と林が最多13得点【ネーションズリーグ】
SPAIA5/17(金)11:19
-

ベッテルがセナ&ラッツェンバーガー追悼イベントを主催。ドライバーたちがイエローのTシャツでイモラを1周
オートスポーツweb5/17(金)8:20
-

世界1位トルコ撃破&女子バレー2連勝でも油断できない? 荒木絵里香が語る“パリ五輪までの過酷な道のり”「警戒すべき3つの国は…」
Number Web5/17(金)6:00
-

バレー日本女子 世界1位の“最強”トルコ撃破で五輪切符へ大金星発進!古賀アウェーで大暴れ「勝ち切ることができてよかった」
デイリースポーツ5/17(金)5:00
-

栗原恵さん「ブロックをいかにしのいでいくか」眞鍋ジャパン次戦の相手はブルガリア【ネーションズリーグ】
TBS NEWS DIG5/16(木)17:00
-

【バレーボールネーションズリーグ】女子日本代表が世界1位トルコ撃破、パリ五輪へ好スタート
SPAIA5/16(木)11:13
-
-

ニュルのタイムはすでに先代超え『ポルシェ911』初のハイブリッドモデル、5月28日に世界初公開へ
オートスポーツweb5/15(水)22:27
-

誕生日の石川真佑「24歳は結果を出せる年に」 ネーションズリーグは「攻めていきたい」【眞鍋ジャパン】
TBS NEWS DIG5/15(水)12:00
-

モナコ・ヒストリック・グランプリでセナ追悼イベントを実施。カートを含む複数のカテゴリーのマシンでデモラン
オートスポーツweb5/14(火)18:18
-

眞鍋ジャパン、ネーションズリーグ第1週トルコラウンド登録メンバー発表 古賀紗理那、石川真佑ら14人選出【一覧】
TBS NEWS DIG5/14(火)11:14
-

【バレー】VNLがパリ五輪切符ラストチャンス 7枠決定し残り「5」 日本女子の獲得条件は?
日刊スポーツ5/14(火)6:00
-

ポルシェ・ペンスキー、キャデラックの牙城を崩しIMSAラグナ・セカを制す。恐竜カラーの911がGTDプロ初優勝
オートスポーツweb5/13(月)17:15
-

【京王杯SC】戦い終えて
スポニチアネックス5/12(日)4:30
-

【京王杯SC】松山「しぶとく差し返してくれた」ウインマーベルが重賞4勝目
競馬のおはなし5/11(土)20:40
-

【京王杯スプリングC】トウシンマカオは伸び欠いて6着 菅原明良騎手「右回りの1200メートルがベストかも」
スポーツ報知5/11(土)17:01
-
スポーツ アクセスランキング
-
1

5月17日が「大谷翔平の日」に LAが制定…グレースーツで市庁舎訪問、球団発表
Full-Count5/18(土)3:45
-
2

世界ランク1位シェフラー緊急事態 警察に拘束、手錠かけられ囚人服姿に 全米プロゴルフ選手権
日刊スポーツ5/17(金)22:10
-
3

【阪神】青柳晃洋3敗目 岡田監督辛口「目も当てられんわな。ボール、ボールなる」
日刊スポーツ5/17(金)23:04
-
4

大谷翔平が米ファンを泣かせる行動 突然現れたと思いきや…「よくやった。本当に…」と米感動
THE ANSWER5/17(金)21:03
-
5

眞鍋ジャパン、パリ五輪切符争うドイツにストレート勝ちで開幕から3連勝!エース・古賀紗理那が両チーム最多20得点【ネーションズリーグ】
TBS NEWS DIG5/17(金)21:25
-
6

今季絶望の日本代表DF中山雄太 英3部降格ハダースフィールド退団決定 ネット嘆き「怪我さえなければ」
スポニチアネックス5/18(土)2:12
-
7

「ドジャースで現役を続ける限りは…」なんとロサンゼルス市が5月17日を“大谷翔平の日”に公式制定! 大谷本人が市庁舎を訪れて感謝の意
THE DIGEST5/18(土)5:33
-
8

カブス・鈴木誠也 パイレーツ戦で今季2度目のスタメン落ち 死球による故障か、前日守備のミスが影響か
スポニチアネックス5/18(土)3:24
-
9

「真美子さんと決めたってマジか…」大谷翔平が明かした“始球式辞退の真意”にネット上は感動の嵐!「人間性も神」「ヒーローすぎる」
THE DIGEST5/18(土)5:15
-
10

【日本ハム】新庄監督 佐々木朗希を相手に死力ドロー「勝てるチャンス、あったんですけどね」
東スポWEB5/17(金)23:45
スポーツ 新着ニュース
-

【Mリーグ総括】2位・ドリブンズ 鈴木たろう「最高スコア賞で図に乗った」園田賢「増長はできない」
スポーツ報知5/18(土)7:13
-

【Mリーグ総括】優勝・パイレーツ 鈴木優「リベンジ果たせた」小林剛「連覇でぶっちぎってやりたい」
スポーツ報知5/18(土)7:13
-

【Mリーグ総括】3位・サクラナイツ 岡田紗佳「大きな一歩を踏み出せた1年」
スポーツ報知5/18(土)7:12
-

【Mリーグ総括】5位・ABEMAS 白鳥翔「負けで身が引き締まった」松本吉弘「責任感じた32戦」
スポーツ報知5/18(土)7:11
-

【Mリーグ総括】4位・風林火山 二階堂亜樹「勝てる時にいかに勝つか」松ヶ瀬隆弥「変化への対応遅れた」
スポーツ報知5/18(土)7:11
-

決勝ラウンドがいよいよスタート…好調維持する2人の“黄金世代”が首位奪還をもくろむ【ブリヂストンレディス】
e!Golf5/18(土)7:10
-

HR打って病院直行「ヒビが入っていた」 苦悶→苦悶→股間に笑顔…助っ人襲った“壮絶珍事”
Full-Count5/18(土)7:10
-

ブライトン三笘薫、日本で実戦復帰か デゼルビ監督が可能性示唆
Qoly5/18(土)7:10
-

【Mリーグ総括】6位・麻雀格闘倶楽部 佐々木寿人「来期はトップ量産」伊達朱里紗「成長できている」
スポーツ報知5/18(土)7:10
-

【Mリーグ総括】8位・雷電 萩原聖人「ファンの期待に応えられないままでは悔いが残る」
スポーツ報知5/18(土)7:09
総合 アクセスランキング
-
1

木村拓哉『Believe』“人気女優”演じるキャラがまさかの豹変…「期待外れ感」に視聴者ガッカリ「マジで怖い」
女性自身5/17(金)20:10
-
2

滝沢秀明氏「TOBE」6人組新グループ「DeePals」結成発表、いきなり有明デビューも決定
日刊スポーツ5/17(金)22:34
-
3

5月17日が「大谷翔平の日」に LAが制定…グレースーツで市庁舎訪問、球団発表
Full-Count5/18(土)3:45
-
4

「ビリギャル」小林さやかさん「コロンビア大学教育大学院を卒業しました!」美しいガウン姿…12日に離婚公表
スポーツ報知5/17(金)20:30
-
5

世界ランク1位シェフラー緊急事態 警察に拘束、手錠かけられ囚人服姿に 全米プロゴルフ選手権
日刊スポーツ5/17(金)22:10
-
6

【阪神】青柳晃洋3敗目 岡田監督辛口「目も当てられんわな。ボール、ボールなる」
日刊スポーツ5/17(金)23:04
-
7

84歳志茂田景樹氏「要介護5」告白 17年に関節リウマチ発症、車椅子生活も励ましの声相次ぐ
日刊スポーツ5/17(金)20:39
-
8

大谷翔平が米ファンを泣かせる行動 突然現れたと思いきや…「よくやった。本当に…」と米感動
THE ANSWER5/17(金)21:03
-
9

博多大吉 相方・華丸にも35年間黙っていた秘密を告白 五輪表彰台の夢も
デイリースポーツ5/17(金)23:01
-
10
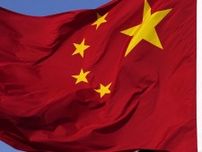
中国、日本水産施設を停止 5月から税関当局の登録
共同通信5/17(金)23:41
東京 新着ニュース
-

つばさの党の行為は「表現の自由」? 逮捕に踏み切った警視庁はどう判断したか 候補者ら立件の前例はなく
東京新聞5/18(土)6:00
-

選挙カー囲み「出てこい、クズが」 「米国の犬、ばばあ」とまで…各陣営が訴えた「つばさの党」妨害の内容
東京新聞5/18(土)6:00
-

重要人物が異論!「井上尚弥VS“最狂”デービスは現実離れし過ぎている」“モンスター”陣営のアラムCEOがサウジ王族提言のドリームプランを疑問視
RONSPO5/17(金)21:41
-

旧岩淵水門が「重要文化財」指定へ 荒川と隅田川の分岐点で水害防ぎ100年 「誇りだ」住民ら喜び
東京新聞5/17(金)21:15
-

シラサギの群れが舞った 浅草・三社祭が開幕「まるで別世界」 「宮出し」は最終日の19日
東京新聞5/17(金)20:42
東京 コラム・街ネタ
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
©2024motorsport.com Japan