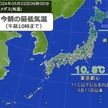2023年の東京大学入学式祝辞で「夢に関わる、心震える仕事を」と述べたことが話題の馬渕俊介氏。現在は、グローバルファンド(世界エイズ・結核・マラリア対策基金)でヘルスシステムのトップを務める。途上国での感染症対策にリーダーシップをとってきた馬渕氏が、グローバルヘルスの現在地とこれからを語った。
聞き手:編集部(田口佳歩)
※本稿は、『Voice』(2024年5月号)より、内容を編集したものです。
地域のニーズをつかむ重要性
――馬渕さんは、2023年度の東京大学入学式で祝辞を贈り、ご自身の体験を交えながら「日本人は世界で良いリーダーになれる」などとお話しされた内容が大きな話題を集めました。世界銀行に勤めていた2014年、エボラ出血熱流行を受けて、大流行を止めるべくつくられた緊急対策チームのリーダーとしてした経験もお話しされていました。当時、通常1年半かかるプロセスを45日間で終えたということですが、背景にはどんな工夫があったのでしょうか。
【馬渕】感染症対策はスピードが命ですが、当時、感染が爆発した3カ国にはお金がなく、海外からの援助も遅れていました。すると、世界銀行からの資金援助が頼みの綱になるのですが、通常のプロセスでは200億円近い資金を効果的なかたちで届けるには、1年半くらいかかります。
公的資金を動かすには、世界銀行内でも内容を精査したうえでの合意が必要ですし、国によっては、加盟国の国家予算の一部として国会承認される必要もある。すると国会のタイミングにも左右されますから、普通に進めると1年半はかかりました。
それまでの世界銀行は、このようなケースでも緊急対策を行なう組織ではないと言われてきました。しかし、圧倒的な危機的状況を前に、当時のジム・ヨン・キム総裁が「エボラ対策は世界銀行の仕事」と主張し、銀行のナンバーワンプライオリティに掲げたのです。じつは、彼は世界銀行の長い歴史のなかで唯一のヘルス領域の出身者で、自らNGOも設立、運営したアクティビストでした。私も「どんな対策を講じてもいい。その代わり30日でやれ」と指示を受けました。
――まさしくアクティビストですね。
【馬渕】でも、そんな「無茶」な指示を受けたからこそ、私たちのチームは「どうすれば30日でできるか」を考え抜いて、プロセスを大きく組み直すとともに今どこにいるかを可視化して、同時並行であらゆる仕事を進めていきました。
本気で30日での対策をめざしていましたから、チームのメンバーの1人は、ある財務大臣の家に押しかけてサインをもらってきたこともあったくらいです(笑)。その結果、チーム結成から30日でプロジェクト承認、45日で200億円弱のすべての資金を支出して対策を加速することができたのです。
――そこまでしたからこそ、多くの命が救われたのですね。そうした経験をふまえて、感染症対策でもっとも大切な点はどこにあると感じますか。
【馬渕】地域の人びとのニーズをよく理解することでしょう。たとえば、効果的なワクチンが開発されても、人びとがそれを信じて接種してくれなければ効果は見込めません。
世界銀行にいたころ、ナイジェリアでポリオという脊髄性小児麻痺の撲滅に向けたプロジェクトを担当したことがあります。ポリオは国際社会全体で撲滅に向けて対策を進めていて、現在残っているのはパキスタンとアフガニスタンのみです。ナイジェリアでもかつては蔓延していましたが、いまでは撲滅宣言が出ています。
対策を講じる過程で非常に大きかったのは、ポリオワクチンに対する不信感が強い地方に対して、彼らのニーズをふまえたうえで、包括的に対応できたことです。たとえば、ナイジェリアの北部の人びとには、ポリオワクチンを受けるよりも、子どもや妊婦の栄養が足りていないなど、より切迫した保健課題がありました。
そこで、政府とともに「ヘルスキャンプ」を開いて、ポリオワクチンの接種だけでなく、ビタミンAの摂取や子どもの成育状況のモニタリングなど、人びとのニーズに合わせて包括的に対応できる場所をつくったのです。すると、現地の人たちは一緒にポリオワクチンも接種してくれるようになり、状況が劇的に改善したのです。
それまでポリオ対策では、とにかくワクチンの接種率をあげるために、家に何度も押しかけて予防接種をすることもありました。それでは不信感が増すばかりであり、そこで必要になるのが、現地の人びとのニーズや感情をふまえた対策なのです。
世界の感染症対策はアップデートできるか
――感染症対策では、それぞれの地域にいかに寄り添うかが重要だとよくわかるお話です。
【馬渕】さらに言うならば、地域のキーパーソンと意思疎通することも大切です。ナイジェリアで基本的なヘルスサービスの改善に取り組んでいたとき、同じような対策を講じても、効果が目に見える地域と、あまり状況が変わらない地域に分かれました。
その原因を探っていくと二つ見つかって、一つはヘルスセンターを回す人たちのマネジメント力。単純に言えば、「いい店長がいると店が儲かる」という話と同じです。私はかつてマッキンゼーで働いていたころ、スーパーマーケットの改善を担当した経験もありますが、お客さんといちばん近い場所で働く従業員に、どのような仕事をしてもらうかを考えることが改善のレバーになりました。
もう一つは、たとえばナイジェリアの地方では村長や宗教的リーダーが尊敬され、「彼らの言うことならば聞こう」という習慣や空気があります。そうしたコミュニティリーダーに対して、ヘルスサービスを充実して人びとの生活を改善することの効果や意味を見せて、活動をサポートしてくれるように働きかけることが重要です。
――今後、世界が感染症対策を進めていくうえで課題は何でしょうか。
【馬渕】一つの大きな心配は、新型コロナ以降、高まり続けていたグローバルヘルスへの関心が、次第に薄れてきていることです。致し方ないこととはいえ、先進国の関心や資金は紛争や気候変動などの課題解決にシフトしています。もちろんすべて大事な問題ですが、感染症対策に使えるお金や人的資源が減っているのは懸念材料です。
世界の感染症対策は本来、国家の安全保障に関わる問題ですし、経済や社会へのインパクトも大きい。各国が「国防」という観点からお金を出すべきという主張もありますが、そうした流れにはなっていません。限られる資金では感染症の課題は解決できず、ウイルスとのいたちごっこが続きます。
2000年代以降、病気ごとに世界的な対策を講じて、感染拡大を制御する手法が効果を出してきました。これからは不規則な変化に備えて、また限られた資金をより効率的、効果的に活用するために、三大感染症や新型コロナなど、あらゆる問題に対応できる統合的なシステムを作る必要があります。例えばラボラトリーも、結核とHIVで分けるのではなく、統合されたシステムで新型感染症の検知なども含めたあらゆる検査を行なえるようにするべきでしょう。
その流れを推進するための鍵は、途上国のヘルスシステムを充実させることで、三大感染症およびパンデミック対策のそれぞれに対処してきたグローバルファンドの役割が大きいと自覚しています。ある意味では、グローバルファンド自身もアップデートして、生まれ変わる時期がきているのでしょう。
――最後に、馬渕さん個人のこれからの目標についてお聞かせ下さい。
【馬渕】かねてから目標としてきたのは、途上国の人たちの「理不尽な死」をなくして、人びとが自分たちの夢に向かって生きていけるような世界をつくりたいということです。また、日本人がこれからますます国際的に活動していく必要があるなかで、日本人が世界でリーダーシップを発揮できる姿を見せたいとも思って色々な挑戦をしてきました。
そのうえでいま目標としているのは、今回お話ししたように、業界の方向性の変化を担っていくことです。グローバルファンドは、グローバルヘルスの領域では世界最大規模ですが、そんな巨大な国際機関が生まれ変わり、変わりゆく世界的なヘルス課題に対して大きな結果を出し続けることができれば、非常に大きなインパクトになるはずです。
私生活では3人の子どもたちが大きくなってきているのですが、家族の選択と上手くバランスをとりながら、グローバルヘルスの将来を担う仕事に関わり続けていきたいと思います。
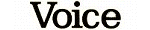









![[深層NEWS]米国のウクライナ支援「反転攻勢には不十分との見方」…防衛研究所・兵頭慎治氏](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/yomiuri/s_20240426-567-OYT1T50120.jpg)