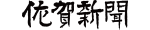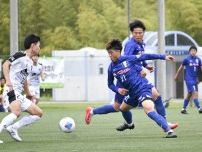第一章「怪談ラジオ局」(2)
午後十時になった瞬間、ラジオのスピーカーはオフになり、ラジオ局前に設置された幅四メートルの大型ビジョンも音声が途切れる。画面には、駅前広場のエチケット向上を呼び掛ける広告などが、静かに繰り返し流れ続けるのだった。
まるでそれが合図であるかのように、だんだん人影が少なくなっていく。
午後十一時半を過ぎると、南口広場にいるのは、いよいよ昇太ひとりになった。
今夜は満月なので、大屋根の照明や駅前ビジョンに加え、広場もいつもより少し明るい感じである。
昇太は周囲に誰もいないことを確かめ、チタンフレームの眼鏡をかけ直すと、ガラス張りのラジオスタジオにちらりと目を遣った。やがて体ごとラジオ局の方を向いて、まじまじと観察する。
「……」
何事も無いことを確認して、机に向き直る。
駅前のラジオ局には、ある噂(うわさ)があった。満月の深夜になると『怪奇現象が起こる』というのだ。
昇太の彼女、花音(かのん)もよく言っていた。
「満月の夜はね……駅前のラジオ局、出るらしいよ……」
あれは去年の冬のことだったか。
マンション十一階にある昇太の部屋で花音は、
「例のラジオ局の話なんだけどね。大学でも結構、見た子がいるみたいだよ」
怖い話が大好きな彼女は、目をキラキラ輝かせながら夢中になって話していた。
「バカだなあ。幽霊なんか、いないってば。『おばけなんてないさ』って歌もあったろ」
昇太はコタツの上のみかんに手を伸ばしながら、呆(あき)れ顔で返した。
「大体、満月の夜ってなんだよ。狼(おおかみ)男じゃあるまいし」
「でもほら、月の光ってさ、なんか神秘的な感じあるじゃない?」
昇太はみかんのヘタの方を上向きにして持った。みかんの皮を窪(くぼ)んだヘソ側から剥(む)く人が多いが、実はヘタから剥いた方が上手に剥けるのだ。
――ヘタだけど上手に、とか。
自分の思いつきに笑いそうになるが、わざとしかめっ面を作って話し続ける。