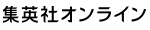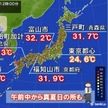2018年5月16日に亡くなった歌手の西城秀樹さん。『傷だらけのローラ』『ヤングマン(Y.M.C.A.)』など数々のメガヒット曲を送り出した彼だが、デビュー曲には隠された秘話があった。
夜逃げ同然の形で上京した西城秀樹
2015年4月13日。この日還暦を迎えた西城秀樹は、それを記念したアルバム『心響 -KODOU-』をリリースした。
それまでに2度の脳梗塞を乗り越えて復活した西城は、過去のヒット作のセルフカバーに加えて、新曲『蜃気楼』にもトライしている。
この作品は結果的に最後のアルバムになってしまったが、どの曲からもポジティブなチャレンジ精神が感じられて、実に力強い内容に仕上がっている。
意外なことに『心響 -KODOU-』は、1972年3月に発売されたデビュー曲の『恋する季節』から始まっていた……。
まだ少年だった木本龍雄(西城秀樹の本名)が、歌手として成功することを夢見て広島から上京したのは1971年の秋、15歳の高校1年生の時だった。
同郷の出身でロカビリー歌手だった藤本好一にスカウトされた木本少年は、父親の強い反対を振り切るようにして、夜逃げ同然の形で上京してきた。
そこからはヴォイス・トレーナーの先駆者、大本恭敬に師事して厳しい歌のレッスンを受ける一方で、縄跳びなどの運動による体力づくりにも励んだ。
そうした日課が終わったら、3畳にも満たない狭い部屋で寝るだけの日々が続く。
そんな木本少年のもとに、念願のデビュー曲が届いた。
「うれしくて楽譜を神棚にささげ、それこそ一日中歌っていた」
曲名は『恋する季節』。
作詞が麻生たかし、編曲は高田弘、そして作曲を手掛けたのが筒美京平だった。1968年にいしだあゆみの『ブルーライト・ヨコハマ』が大ヒットしたのを機に、筒美京平は歌謡曲の第一線で活躍する、最も勢いのあるヒットメーカーになっていた。
特に1971年に尾崎紀世彦が歌って大ヒットした『また逢う日まで』(作詞/阿久悠、作曲/筒美京平)は、ロックバンドの一員としてドラムを叩いていた木本少年にとって、歌謡曲のイメージを一変させた作品だった。
「うれしくて楽譜を神棚にささげ、それこそ一日中歌っていた。部屋の中より響きが良いので、マンションの階段で大声で歌っていたら、あちこちの部屋のドアが開き、『バカヤロー、メシがまずくなる!』と怒鳴られた。
仕方ないから、屋上で練習を繰り返したが、響かないからつい大声になる。気がつくと、のどから血が出ていた。でも、メロディーは最高だったし、ヒットすることを祈りながら毎日歌い続けた」
しかし、12月の半ばに譜面をもらったのに、1月が過ぎてもレコーディングの日が決まらなかった。
その頃の不安な思いが、著書『誰も知らなかった西城秀樹。』(青志社)にはこのように記されていた。
「だから本当にレコーディングされるとわかったときは、もう天にものぼるような気持だった。1回目はあがってNG。OKが出たときも、『もう一度、歌わせてください』といって歌った」
その後、雑誌の公募で芸名が「西城秀樹」に決まり、キャッチフレーズは「ワイルドな17歳」になった。
こうして1972年3月25日。念願のデビューシングル『恋する季節』が、日本ビクターのRCAレーベルからリリースされた。
「あの歌ね、ホントはぼくのところにきたんだけど…」
身長が高くてルックスがよかったこともあり、業界内での評判は上々だったので、テレビの音楽番組への出演もすぐに決まった。
ところがその収録スタジオでのこと。
元カーナビーツのドラムで、ボーカルを担当していたアイ高野に声を掛けられた。そこで『恋する季節』に関して、思ってもみなかった事実を伝えられたのである。
「あの歌ね、ホントはぼくのところにきたんだけど、気に入らなくてボツにしちゃったんだよ。ハハハ!!」
デビュー曲が先輩バンドマンの”お下がり”だったなんて。少年はポカンと口を開けたままだった。それだけでなく、アイ高野が唄うことを想定して、ファンに喜んでもらえるようにと、粋なアレンジが施されていたことを知る。
サビの終わりで「つぼみなら柔らかく抱きしめよう」と唄った後に、ホーンセクションがメロディーを追いかけるところで、カーナビーツのヒット曲『好きさ好きさ好きさ』の中の一節が流れるのだ。
アレンジも含めて、アイ高野の面影を感じさせるデビュー曲に、西城は一人で悔しさを噛み締めるしかなかった。
さらに『恋する季節』は、ヒットチャートでは最高42位という結果に終わり、新人・西城秀樹にとっては苦い思い出となってしまった。
それから間もなくして、派手な振り付けを取り入れたことで、ヒット曲に恵まれ始めた西城は、一気にトップアイドルの仲間入りを果たしていく。
しかし筒美京平の曲を再び歌う機会はしばらく訪れず、1979年の『勇気があれば』まで待たなければならなかった。
西城はそこから30年以上もの時を経て、病で2度も倒れながら、懸命のリハビリで立ち直り、現役に復帰した。
そして還暦を記念するアルバムを制作する時に、どこか不本意な思いが消えなかったデビュー曲を、「自分の作品」として完成させることに挑んだ。
微かな心の傷痕を、新しいサウンドと歌唱によって、乗り越えるためだったのだろう。
デビュー当時からさまざまな洋楽をカバーして、音楽面で自分の世界を切り拓いてきた実績、大人のシンガーとして重ねた経験、そしてこの曲に対する愛情が、それを可能にしたのだと思う。
西城秀樹は最初から最後まで、歌手であると同時に表現者であったのだ。
文/佐藤剛 編集/TAP the POP サムネイル画像/1972年3月15日発売『恋する季節』(RCA/日本ビクター)より
引用:「のどもと過ぎれば」(産経新聞)、『誰も知らなかった西城秀樹。』(青志社)