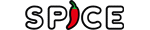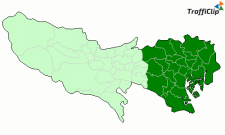nishina tour 2024 Feeling
2024.4.28 NHKホール
フィーリング――何かが生まれる発端だったり、人やモノに恋するきっかけだったり、感覚は自分に嘘をつかない。全国11ヵ所をめぐるツアータイトルに、かっちりしたコンセプトではなく“Feeling”と銘打ったことは今のにしながミュージシャンとして新たなフェーズにいることを示唆していたのではないか。その事実はボーカル表現や演奏、ファンとのコミュニケーションの全てで明らかだったからだ。ここではファイナルとなった初のNHKホール公演を振り返る。

白いクロスで覆われたステージはライトの色をそのまま映すキャンバスのよう。楽器スタッフも白い衣装という徹底ぶりが面白い。ごくさりげなくサポートメンバー、にしなが登場し日常の続きのようだったのが、にしなの“青い春に”という第一声のパワーに驚き、一瞬にしてホールに熱量がみなぎる。真田徹(Gt)のシューゲイズなギターがまさに風を思わせる「春一番」で幕を開けた後、短く挨拶をして、バブルマシンを手にシャボン玉を振り撒きながら、ステージ前方を自由に闊歩しアクションする「東京マーブル」。ネオソウルテイストの望月敬史(Dr)のドラミングとTomi(Ba)のリズムが心地よい「夜間飛行」で会場がビビッドに揺れ始める。若手敏腕のサポート陣はもちろん、アンサンブルのバランスの良さでにしなの声の魅力がストレートに伝わってくる。立て続けに「ケダモノのフレンズ」でNHKホールの空間をにしなとオーディエンスの自由な遊び場に変えていくような音楽の魔法が展開する。この曲にちなんだグッズであるケダモノの尻尾をにしなが振れば、フロアはタオル回しで応える。跳ねるビートも相まって、にしなが小動物のように見えたのは自分だけじゃないだろう。


テンポよく“どこにもない国”に迷い込ませてくれたあと、最初のMCで序盤にも関わらず、「ファイナル終わっちゃうなあ。思い残すことなく燃え尽きてもらえれば!」と意気込みを伝える。

にしなのコードストロークがグルーヴを生み出し、ツインギターの旨みも味わわせる「真白」、再びハンドマイクでの「夜になって」ではそれまでの無邪気さや明るさが影を潜め、いたたまれないような孤独な状態を醸し出す。胸苦しい恋を歌う幼さの残る声は彼女にしかないものだと改めて確信し、ストロボの演出も慟哭を表すようで秀逸だった。夜の情景のひと連なりとしてシームレスに「FRIDAY KIDS CHINA TOWN」に繋げたのもいい。Lo-Fiヒップホップ以降のフロウといえばそれまでだが、ダンサブルな曲での彼女のメロディと言葉の閃きたるや。音源よりフィジカルなラガマフィン調のビートも歌を転がしていく。

夜をモチーフにしたナンバーは「透明な黒と鉄分のある赤」に続き、自分自身を“白紙でいられない”と紙に喩え《握って破ってを繰り返して》と歌う独特の言語感覚と、それをキャッチーに伝える声の魅力に瞠目。かと思えば彼女の語りで始まり、彼の視点で歌われる日常感溢れる「ワンルーム」の、眼前に映像が浮かぶようなリアリティ。たくさんのアウトプットを持つにしなの中でも、一瞬、痛みの記憶が蘇るような彼女の真髄と言えるセクションだったと思う。

1曲ごとの世界に没入させながら、MCになると素の表情を見せ、サポートメンバーにツアーの感想を聞くにしな。全員が手応えを感じて、すでに名残惜しそうだ。今回のツアーでは「箸休めタイム」として、ツアーの最中にリリースされたニューシングル「It's a piece of cake」をファンのシンガロングも交えたラフなスタイルで演奏する、それこそ「Feeling」を体現するコーナーがあった。作品作りを共にする仲間と真夜中の公園で過ごした記憶から作られたこの曲。音楽を作るという目的を同じくする仲間とのうっすらとした未来への不安などがドキュメント的だが、この感覚は同世代のファンにとってもすごく身近なテーマだろう。綺麗に揃ったシンガロングというより、自然と参加する声が大きくなっていくのがこの曲のシーンともリンクしていた。

続くセクションはダンスチューンやアトモスフェリックな音像が続く。にしなが爪弾くリフとバンマスの松本ジュン(Key)のピアノリフから始まり丹念に音のレイヤーが編まれていく「ダーリン」、これもまた歌詞の独自性とフロウが冴える「U+」。元々彼女なりの多様性を曲にしてほしいというCMサイドからのテーマがあった曲ではあるが、フェイクだらけの今の時代に胸にしっかり抱いておきたいアンセムに成長した印象もある。サビでは客席にマイクを向けていた気持ちもわかる。さらにエレクトロスウィングな「クランベリージャムをかけて」でフロアをバウンスさせ、イーブンキックで踊らせる「bugs」でさらにダンスに拍車をかける。ミニマムな演奏の上でR&B寄りのメロディとハイトーンを駆使するにしなの表現の幅も鮮烈だった。


繰り返しになるが、1曲ごとにその世界に没入させることが可能なのは、やはりツアー11本目のバンドとの練度なのだろう。ジャンルに拘束されない彼女の楽曲をライブの最適解でアレンジし、深めてきた5人で共通したビジョンが見えているのだと感じた。終盤に向け、「心残りなく燃え尽きていってください」と自身にも言っているようなにしな。グッとヘヴィかつ厚く、グランジと言っていいようなアンサンブルと切実な発声が刺さる「スローモーション」、フルアコースティックギターからストラトに持ち替えてのトレブリーな響きで曲の人格を表すような「ヘビースモーク」と、サイドギタリストとしての音作りも念入り。今も彼女の人気曲筆頭だが、いい意味で慣れることはないのだろう。苦しい想いはずっと切実な声のままこちらの感情も締め付けてくる。本編ラストに向けてどんどん内面の深いところへダイブしていく構成は彼女らしいと言えばそうだし、ステージパフォーマーとしてタフになってきたからこそできることでもあるのだろう。ただ歌うことに集中して心を込めていくピアノバラード「青藍遊泳」では聴いているこちらも体に力が入る。清冽な決意のこの曲に続いて、世界の滅亡が訪れなかった年、1999年もテーマの一つである「1999」が終わりの始まりのマーチのように奏でられた。誰にも終わりがあることを《地球が滅亡する素敵な夜のこと》と表現する彼女の、これはある種の死生観でもあり、同時に生き方の指針なのだろう。潔くステージを後にし、暗転したステージの背景には映画のエンドロールのようにクレジットが投影された。


アンコールでは歌声を堪能させた「ホットミルク」に続き、ツアータイトルの「Feeling」に絡めた感覚や無邪気さの大切さについて話してくれたが、何より「音楽って宗教みたいなところがあるけど、(自分は)神にも仏にもなれないそこら辺に転がってる人間なんで、また道中“どう、元気?”って言えたら」というくだりににしなのスタンスが明らかだった。この場所から“道中”に送り出してくれるようにアッパーでポップな「シュガースポット」を演奏し、驚くほどサラッと11月からのZeppツアーも発表していた。正真正銘のラストは、撮影がOKになったファンはスマホを持つ手と掲げる手とシンガロングで忙しい(!?)「アイニコイ」。ステージ上のにしなとメンバーも、ファンも余力を残すことなくツアーを走り切った。
取材・文=石角友香 撮影=renzo masuda

>>すべての画像を見る