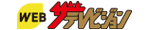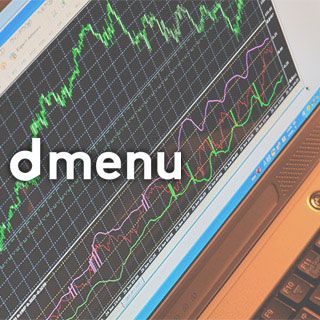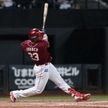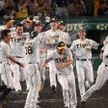■これぞアイドルという二宮の一言
「バグってたんだと思う、設定が。最後の年、51公演ドームでやった。たぶんヤクルト(スワローズ)よりいたよ」(「午前0時の森」2024年3月12日日本テレビ系)
二宮和也は、嵐休止前の1年間をそう笑って振り返った。そんなライブでの二宮は、バラエティでは決して見られないようなセクシーな表情やカッコいい表情をしてくれると嵐ファンの男性が熱弁すると、二宮はこれぞアイドルという一言を返した。
「我々にとっても“夢の時間”なんだ、あれは」(「ニノさん」2019年6月9日日本テレビ系)
アイドルとしてのステージではキラキラ、バラエティ番組では飄々とふざけ、そしてドラマや映画では地に足のついた実在感たっぷりの人物を演じ、まったく異なる顔を見せてくれている。
■与えられるチャンスの裏で重ねた何倍もの努力
役者としてのキャリアをスタートさせたのは嵐結成前。ドラマには1998年の松本清張原作「天城越え」(TBS系)でデビュー。嵐結成後もコンスタントにドラマ出演していた。この頃は「照明さんが一番怖かった時代」(「午前0時の森」2024年3月19日)。撮影では、照明をなかなかあててもらえないような厳しさを味わった。
そんな経験をしたからだろうか。「嵐やってなかったら(俳優として)呼ばれてないです。それは忘れちゃいけないこと」(「あさイチ」2017年10月27日NHK総合)といった話を事あるごとに語っている。当時の彼ら男性アイドルは、他の若手俳優と比べて何倍もチャンスが与えられた。だがその分、実力を認めてもらうには、その何倍もの努力が必要だったのだ。
「なんでも器用にこなすように見えているかもしれないけど、本来は、人とコミュニケーションを取ったり集団行動をしたりするのは苦手」(「ぴあ」2022年8月8日)だという二宮。「ゲームのように操作性が利かないのが現実で、その中で仕事をしてきて、少しずつだけど、人の考えが想像できるようになってきたんです。苦手だからこそ、仕事や人に向き合ってきた」(同)
■ドラマや映画の主演、そしてハリウッドへ
彼がいわゆる“実力派”などと評されるようになったのは、蜷川幸雄監督の映画「青の炎」(2003年)に主演した頃だっただろうか。この頃から「Stand Up!!」(2003年TBS系)を始め連続ドラマでも主演を務めるようになっていった。
決定的だったのは2006年、ハリウッド映画「硫黄島からの手紙」に出演したことだろう。嵐という看板を超えてその名を轟かせた。そんな中でも前年に放送された倉本聰脚本のドラマ「優しい時間」(2005年フジテレビ系)が印象的だ。陶芸職人を目指す寡黙でナイーブな若者を繊細に演じ、役者・二宮和也のイメージを決定づけた。
このとき二宮は役作りのために専門家から陶芸を習っている。その時に言われたことが「心に残っている」と後に語っている。「これは他の誰にも真似できない、俺にしかつくれない皿だというものは、1枚なら誰でもつくれる。それよりももっと難しいのが、どこにでもある、割れたらすぐに替えが利くような、平凡な皿をつくることだって」(「ぴあ」2023年10月3日)
二宮は芝居もまったく同じだと思った。「大見得切って、発狂して、泣いて、人を刺して殺してみたいなのは誰にもできる」と。「それよりも、ただ普通に座って、飯食って、友達と話して、人の話を聞いて、泣いている人に寄り添って、そういうお芝居の方がずっと難しい。すごく地味だし、正直そういう平凡なシーンってやっていても日々の達成感はあまりないのかもしれないけど、そういうことがちゃんとできるようにならなきゃいけないんだって」(同)
■瞬間の感情を汲み取り、表現する
その後は、宮藤官九郎脚本の「流星の絆」(2008年TBS系)、「フリーター、家を買う。」(2010年フジテレビ系)、立川談春を演じた「赤めだか」(2015年TBS系)、そして「赤めだか」と同じタカハタ秀太監督による、同作で共演したビートたけし原作の映画「アナログ」(2023年)など、次々と話題作で主役を張り、それを体現してきた。
彼は自分が演じてきた役に「共感」したことは少ないという。なぜならその人物の性格を「たった2〜3個の言葉で表現するのはウソくさい」(「ぴあ」2022年8月8日)と感じるからだ。逆に「その瞬間の感情だけ」を丁寧に汲み取って演じるからこそ、実在感のあるリアルな人物を表現することができるのだ。
文=てれびのスキマ
1978年生まれ。テレビっ子。ライター。雑誌やWEBでテレビに関する連載多数。著書に「1989年のテレビっ子」、「タモリ学」など。近著に「全部やれ。日本テレビえげつない勝ち方」
※『月刊ザテレビジョン』2024年6月号
二宮和也「その瞬間の感情だけ」を丁寧に汲み取り、演じる【てれびのスキマ】

関連記事
おすすめ情報
WEBザテレビジョンの他の記事もみるあわせて読む
-

Snow Manと櫻井翔が“マネキンナイン”でコーディネート対決 「ひみつの嵐ちゃん!」「学校へ行こう!」と2週連続コラボ<それスノSP>
WEBザテレビジョン6/21(金)22:00
-

『それスノ』でTBS伝説の企画が復活 Snow Man&櫻井翔が「マネキンナイン」でガチコーディネート対決
ORICON NEWS6/21(金)22:00
-

「ひみつの嵐ちゃん!」「学校へ行こう!」復活 櫻井翔「それスノ」サプライズ初登場でSnow Manとコーデ対決
モデルプレス6/21(金)22:00
-

「ひみつの嵐ちゃん!」と「学校へ行こう!」が「それスノ」で復活! 6月28日から2週連続コラボSP、1週目は嵐・櫻井翔とコーデ対決
iza!6/21(金)22:00
-

『それSnow Manにやらせて下さいSP』、『ひみつの嵐ちゃん!』&『学校へ行こう!』と2週連続コラボ
クランクイン!6/21(金)22:00
-

『それスノ』2時間SPに嵐・櫻井翔が初登場 『ひみつの嵐ちゃん!』人気企画が復活
ENCOUNT6/21(金)22:00
-

菊池風磨、“身バレ防止”先輩2人のコードネーム発表「センス流石」「最高」と反響
モデルプレス6/21(金)18:47
-

二宮和也 独立後初主演!「この6年で物事をより客観的に見られるようになったかな」
女性自身6/21(金)15:50
-

ギャルたちのギャップあふれる“すっぴん”姿 モデルから芸人まで「美人すぎる」「肌綺麗すぎんか?」
クランクイン!6/21(金)6:30
-
-

放送前から批判続出のクドカン脚本ドラマ 公式サイトからひっそり「削除された言葉」
女性自身6/21(金)6:00
-

ヒカル、ビートたけしに「会いたい」と宣言 東国原英夫氏が可能性についてコメント
スポニチアネックス6/20(木)16:48
-

「低予算ドラマ“量産”は淘汰される」…TBS電撃退社の“ふてほどP”が訴えた、局内の根深すぎる問題
デイリー新潮6/20(木)10:57
-

Xの使い方がうまいSTARTO所属タレントランキング! 2位「二宮和也」、1位は?
All About NEWS6/20(木)10:50
-

新日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』、二宮和成&石坂浩二の誕生日を祝福
DailyNewsOnline6/19(水)15:00
-

北野武監督 長編新作はAmazon MGM スタジオとタッグ「新たな挑戦でワクワク」
テレ朝news6/19(水)13:39
-

北野武監督・脚本・主演の長編映画をAmazon MGMスタジオが製作
CINRA6/19(水)11:16
-

北野武監督「新たな挑戦でわくわく」 Amazon MGM スタジオと長編映画制作
産経新聞6/19(水)10:11
-

東国原英夫氏、格差婚と言われた大女優の元妻を“恋に落とした”初デート秘話「かっこよかったらしい」
スポニチアネックス6/19(水)9:51
-
エンタメ アクセスランキング
-
1

橋本志穂 全身に謎の湿疹が現れ「かゆくて眠れず」病院へ… まさかの診察結果に「え?」
スポニチアネックス6/21(金)18:30
-
2

水卜麻美アナの24時間テレビ〝はしご謝罪〟は「禁じ手」 元放送作家「日テレは崩壊寸前」
東スポWEB6/21(金)22:02
-
3

TBS「東大王」9月末で終了 赤門スター輩出も最近は視聴率低下 開始から7年「一定の役割を終えた」
スポニチアネックス6/22(土)3:00
-
4

野村義男がマッチと付かず離れずの友情を告白「お互い連絡しないで1年とか2年、それでも…」
サンケイスポーツ6/21(金)22:58
-
5

渋谷すばる 自身の体調について「酷いHSPとトゥレット出まくり」と明かすも「自分らしくて愛おしい日」
スポニチアネックス6/21(金)20:04
-
6

女王蜂アヴちゃん体調不良のため休養「医師の診断を踏まえ今回の判断」全国ツアーも中止
日刊スポーツ6/21(金)21:23
-
7

千鳥・大悟「フジテレビで言うのは申し訳ないけど…」 「すぽると!」を受けたまさかの理由にスタジオ騒然
スポニチアネックス6/21(金)23:25
-
8

いじめ被害受けたタレント、元いじめっ子からかけられた言葉に絶句
クランクイン!6/21(金)20:25
-
9

元人気子役、引退後にホームレス生活 「“普通”を教えてくれる環境が必要」と訴え
クランクイン!6/21(金)20:01
-
10

「死んだみたいなので」ティモンディ前田、突然の“戒名募集”に励ましの声「冗談にしてもひどい」
All About NEWS6/21(金)19:40
エンタメ 新着ニュース
-

渡部建 キー局復帰は…関係者「起用したいテレビマン一定数いるが、スポンサーが難色」
スポニチアネックス6/22(土)5:10
-

倉木麻衣 夢かなった水族館コラボ「胸がいっぱい」
スポニチアネックス6/22(土)5:09
-

吉沢亮 主演作を上海で世界初上映「アクターを始めて15周年という記念すべき日に…凄く幸せ」
スポニチアネックス6/22(土)5:07
-

吉田鋼太郎「ハンサム漬けの1年 感無量」
スポニチアネックス6/22(土)5:06
-

伊藤新叡王 「25歳まで酒とギャンブル禁止」師の鉄の掟守り藤井撃破 21歳8カ月 誘惑に「関心なし」
スポニチアネックス6/22(土)5:05
-

伊藤新叡王の師匠・宮田八段 一門初のタイトルに「国宝級の盤」贈呈へ
スポニチアネックス6/22(土)5:04
-

元力士の米俳優テイラ・トゥリさんが死去 56歳 人気ドラマ「HAWAII FIVE‐0」で活躍
スポーツ報知6/22(土)5:03
-

横浜流星「めちゃくちゃ『べらぼう』でした」炎天下での火事シーン 25年大河 京都ロケ取材会
デイリースポーツ6/22(土)5:00
-

倉木麻衣 水族館愛全開でプロデュース「自分もクラゲになった気持ちで」
デイリースポーツ6/22(土)5:00
-

吉田鋼太郎パパ リモート参加でも家族の絆バッチリ! MEGUMIが「お父さん大丈夫?」
デイリースポーツ6/22(土)5:00
総合 アクセスランキング
-
1

橋本志穂 全身に謎の湿疹が現れ「かゆくて眠れず」病院へ… まさかの診察結果に「え?」
スポニチアネックス6/21(金)18:30
-
2

渋野日向子が大逆転で五輪出場の可能性も 現状国内11番手から2枠に滑り込む条件とは
スポーツ報知6/22(土)1:15
-
3
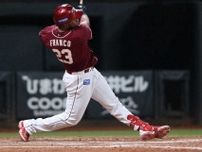
記録ずくめの日本ハム―楽天 4時間22分の死闘…史上初外国人の満塁弾返しなど
スポニチアネックス6/21(金)23:04
-
4

山上被告「こんな状況なるとは」 安倍氏銃撃事件、接見で述べる
共同通信6/21(金)23:20
-
5

水卜麻美アナの24時間テレビ〝はしご謝罪〟は「禁じ手」 元放送作家「日テレは崩壊寸前」
東スポWEB6/21(金)22:02
-
6

TBS「東大王」9月末で終了 赤門スター輩出も最近は視聴率低下 開始から7年「一定の役割を終えた」
スポニチアネックス6/22(土)3:00
-
7

野村義男がマッチと付かず離れずの友情を告白「お互い連絡しないで1年とか2年、それでも…」
サンケイスポーツ6/21(金)22:58
-
8

渋谷すばる 自身の体調について「酷いHSPとトゥレット出まくり」と明かすも「自分らしくて愛おしい日」
スポニチアネックス6/21(金)20:04
-
9

なぜ?巨人が76日ぶりBクラス転落 4位・DeNAもサヨナラ負けで順位が入れ替わる珍現象
デイリースポーツ6/21(金)22:54
-
10

「タラップから墜落した」作業の男性1人死亡 3人が重軽傷 大型船に取り付けた約10mのタラップごと地面に落ちたか 広島の造船所
広島・RCCニュース6/21(金)21:28
いまトピランキング

東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-

炎が復活!日本代表、2024新ユニフォームを発表 「ヨウジヤマモト×adidas」のY-3と歴史的なコラボが実現
Qoly6/22(土)5:00
-

サガン鳥栖のリトアニア追加!「Jリーグで1名しかプレーしていないレア国籍選手」
Qoly6/22(土)0:00
-

Jリーグ、AIによるスポーツファンエンゲージメントの再構築〜「HALF TIMEカンファレンス2024」レポート
Qoly6/21(金)22:30
-

バイエルンが「国内のライバル」から無慈悲に引き抜いた外国人5名
Qoly6/21(金)22:05
-

「いたばし選挙割」始まる 都知事選投票済証書提示で割引・おまけ
みんなの経済新聞ネットワーク6/21(金)21:01
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright (c) 2024 KADOKAWA. All Rights Reserved.