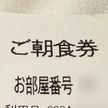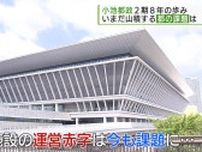ワイドショーへの思いも告白
90歳を迎えた事件リポーターの東海林のり子さん(90)。40歳の頃から本格的に事件取材を始め、足を運んだ現場は4000件以上に及ぶ。印象に残っている事件、今は少なくなってしまったワイドショー番組への思いを語ってもらった。(インタビュー第3回・全3回)
***
これまでで、一番印象に残っている取材現場は、1980年に起きた「金属バット両親殺人事件」です。現場は神奈川県川崎市の新興住宅地でした。
大学受験で二浪した息子がいるエリート家族だったんですが、お母さんとお父さんの夫婦仲が、あんまりよくありませんでした。
ある時、お父さん が酔っ払って帰ってきたところ、息子が勉強せずテレビをみていた。お父さんが「お前、勉強しないのか」と怒って、その子が座っていた椅子を蹴ったら、バタンと倒れてしまった。
たぶん、その時にお父さんに対する殺意を抱いたんでしょう。その後、お父さんとお母さんが寝静まってから、金属バットで殴って殺害した。
裁判も傍聴に行きましたが、大人しい男の子だったんです。事件が起きた時はぽっちゃりしていましたが、裁判ではガリガリになっていました。
その姿を見たら、大学なんか行かなくてもいいじゃないかと思いましたね。ただ、その頃は、“受験戦争”全盛の時です。だから、何が何でも大学に行かなければいけない、それが正しい生き方だと思っていたから、しょうがないんですが……。時代が起こした事件かもしれません。
事件をたくさん取材していると、だんだん、勘が良くなってくるんです。実際の事件現場を2回ぐらい当てたことがあります。
例えば、お母さんが子どもの教師と不倫していたんですが、喧嘩して、その教師を刺し殺したという事件があったんです。
事件現場は「あの部屋だと思う」
事件現場は3階建ての団地ということだけがわかっていましたが、どこの部屋かわからなかった。その時、私、ベランダを見たんです。すると、3階の一番端の部屋のベランダで、アロエが枯れていた。あんなに強い植物がなぜ、枯れているんだろうと思いました。
そのベランダをよく見ると、男の子のタンクトップが干してあって、何日も取り込んでいない様子でした。これを見て、「あの部屋だと思う」と言ったら、その部屋が事件現場だったんです。
毎日毎日いろんな現場に行っていたので、感覚が研ぎ澄まされたのかもしれません。私、刑事になればよかったかな(笑)。何か嗅覚みたいなものがあるんです。だから、他のテレビ局よりも先に現場に到着したり、先にインタビューできたんだと思います。
ただ、納得のいかない現場もありました。1986年6月に海洋調査船が沈没したという事件があり、記者会見に行きました。会見場で、新聞社や週刊誌の記者が名刺を渡していたので、私も「東海林です」と言って渡したら、「ワイドショーには話さない」と言われて……。「わかりました」と言って、すぐに帰りました。
誇りを持って仕事をやってきましたが、そういう風な目で見られるのが悔しかったですね。どんな人よりもたくさん取材したし、どんな人よりもたくさんインタビューして、事件を伝えてきた自負はあります。仕事のモチベーションになったのは、深く取材しようという思いと、他局に負けちゃいけないという思いです。
ある時、子どもの誘拐事件があって、私がその子どもの親御さんと信頼関係ができて、単独でインタビューを取れそうだったんです。でも、後から、「報道の代表が話を聞きます」と言われました。その代表が、私が当時リポーターを務めた番組を制作しているフジテレビでした。
それで、フジテレビの報道部長のところに行って、「私が取り付けたのに、何で私がインタビューできないんですか」と抗議しました。「ごめんなさい」と謝っていましたが……。そういう悔しい思いがあるから、余計に頑張れるんです。
自分がやらなければいけないという責任感もあったと思います。会社からは、いつでも現場に行けるように、前もって1週間分の拘束料をもらっていました。他のリポーターさんたちも、何か起きると、「どうせ、東海林さんが行くわよ」と いう感じでしたね。
「誇りと自信を持ってやっています」
事件現場ってあまりみんな行きたがらないんです。ただ、私の場合、人に任せたくない。やっているうちに、だんだん競争心も芽生えてきますしね。視聴率も朝の番組なのに、8%くらいいった時もありました。「負けたくない」という思いが、数字に表れていたんだと思っています。
ただ、世間からは「ワイドショーは低俗」と言われることもありました。どこかの週刊誌の女性記者がインタビューに来た時に、「毎日毎日、事件の取材をして、お子さんは嫌がりませんか」と言ってきたんです。
私は「あなた、子ども たちが嫌がったら、私はやりませんよ。それだけ、誇りと自信を持ってやっています」と答えました。
2人の子どもは私の仕事について、これまで何か言ってきたことはありません。朝方帰ってきたと思ったら、すぐにまた出て行って……。それでも、「ママ、何やっているの?」と聞いてきたこともありません。
こういう人なんだ、こういう親なんだと思っているのでしょう。もしかしたら、学校で「お前のお母さんは……」と言われていたかもしれませんが、そういうことは一切言いませんでした。命懸けでやっていたことが伝わって、もう宿命だと思って受け入れていたのかもしれません。
デイリー新潮編集部