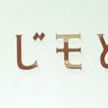ここは地下闘技場か。
『RIZIN.46』(4月29日・有明アリーナ)で行われた篠塚辰樹とJ.マルチネスによるベアナックル・ボクシングマッチを目の当たりにして、そんな思いにかられた。
篠塚のジャブでマルチネスの顔は変形し…
もともと、素手によるボクシングは欧米で非合法で行われていたものであり、表立ったところでやれるものではなかったのだから無理もない。警察の追跡から逃れに逃れ、会場変更を繰り返してようやく開催にこぎつけていた。会場は世間の目が届きにくい地下や倉庫などのスペースに落ち着く。アメリカならアスレチック・コミッションの権力が行き届かないインディアン居留地が多かった。
ベアナックル・ボクシングの別名はプライズファイティング。イギリスを中心に行われ、近代ボクシングの原型となった立ち技格闘技である。時代が進むにつれ、近代ボクシングの興隆に押されるかのようにボクシング界の裏側に追いやられたのは“あまりにも残酷なファイト”と見なされたからだろう。
時間が経つにつれ、劣勢に立たされた選手の目は潰れ、頬や鼻はあらぬ方向に膨れ上がり、顔面は血まみれ。まるで「ストリートファイトでボコボコにされたら、こうなるだろう」という見本のようだ。
ボクシンググローブを着用していたら、こうはならない。中に入っている緩衝材のおかげで、ベアナックルに比べれば裂傷や内出血などの外傷を負うリスクは極端に低くなるからだ。
案の定、篠塚のジャブを食らい続けたマルチネスの顔面はどんどん変形していった。アンコの部分が薄いオープンフィンガーグローブで殴られてもベアナックルに近いダメージがあるが、むき出しの裸拳の外傷リスクとはやはり比べ物にならない。
有明アリーナに駆けつけた観客の声援もすさまじいものが感じられた。篠塚の当てさせずに打つ戦法がハマればハマるほど、声援のボルテージは大きくなっていく。まるでアクション映画の格闘シーンを見ているかのように。これは公開のストリートファイトではないか。そんな印象さえ受けた。このとき会場はMMAでもキックボクシングでも味わえない、新しい興奮に満ちていた。
ベアナックル・ファイトの歴史「初期UFCも素手だった」
この一戦は世界で拡大の一途をたどっているアメリカの「ベア・ナックル・ファイティング・チャンピオンシップ」(以下、BKFC)の提供試合として行われた。もともと篠塚はBKFCの北米大会に出場する予定だったが、諸事情で試合が流れたため、その話をスライドさせる形でRIZIN初のベアナックル・ボクシングマッチを実現させたのだ。
BKFC公認以外だと、日本初のベアナックル・ボクシングは、2020年1月19日に元キックボクサーで現在は俳優として活躍する小林さとしが主催する「野良犬祭」で実現している。開催時期は新型コロナウイルスが猛威を振るう直前で、出場選手が無名ということも手伝い大きな話題になることはなかった。
ボクシングに限定しなければ、ベアナックルの歴史はさらにさかのぼり、1992年に総合武道を標榜する大道塾主催のワンマッチ大会『THE WARS』で、日本初のラウェイの試合が組まれている。ラウェイとはムエカッチュアともいわれる、ミャンマーの格闘技だ。バンデージだけを巻いた拳で殴り合うだけではなく、ヒジ、ヒザ、足、さらには頭突きでの攻撃も許されているため、“世界で最も過酷な格闘技”とも呼ばれている。
出場したのはふたりのミャンマー人選手だったが、我々が想像したような激しい打ち合いにはならず、拍子抜けした記憶がある。翌93年にK-1がスタートすると、ラウェイが日本で初めて披露されたという事実は人々の記憶から失われ、歴史に埋もれていった。Wikipediaの「ラウェイ」の項目にも、『THE WARS』で同試合が行われたことは記されていない。
いや、歴史に埋もれたベアナックルの格闘技はラウェイだけにとどまらない。PRO-KARATEDO、全日本格闘技選手権など、素手による顔面殴打を認めた格闘技はほかにもある。埋もれた歴史から学べること──それは公衆の目につくところで、知名度のある選手が出てやらなければ記憶には残りにくいということだ。
ベアナックルといえば、もうひとつ忘れてはならない大会がある。いまや世界最大規模のMMAプロモーションとなったUFCだ。この団体も胎動期にはバンデージも巻かないベアナックルの状態でオクタゴンの中に入っていた。ホイス・グレイシーも、ウェイン・シャムロックも、そして日本人として初めてオクタゴンの中に入った市原海樹も、みな素手で殴り合っていたのだ。
「ボクシングやMMAよりダメージは少ない」は真実か
しかしながら、当時のUFCに対しても、そして現在のベアナックル・ボクシングに対しても、素手による殴り合いには「見た目が野蛮」「スポーツとはかけ離れている」といった批判や、「なぜ時代に逆行したことをするのか?」という疑問が投げかけられる。
そうした意見に敏感に反応するように、UFCは1997年7月27日の『UFC 14』からオープンフィンガーグローブの着用を義務づけた。そして2000年11月17日の『UFC 28』からは現行のユニファイド・ルールが採用され、出場選手の健康チェックがより厳格化されるようになった。
そんなUFCの流れと逆行するように、なぜ21世紀になってベアナックル・ボクシングは再び台頭してきたのか。そもそも近代ボクシングは合法スポーツとしての権利を勝ち取るため、ベアナックルによる殴り合いを禁止しボクシンググローブの着用を義務づけることで世の中に認められた経緯がある。
BKFCの創設者で元プロボクサーのデイヴィッド・フェルドマンは「ベアナックル・ボクシングで多いのは顔の裂傷だけで、実はボクシングやMMAより外傷性脳損傷や拳の骨折は少ない」と主張する。そうした医学的データが2018年にワイオミング州で認められたことで、BKFCは合法スポーツとして大会を重ねられるようになったという。
すでに日本で有名なブアカーオ・バンチャメークもBKFCに出場しており、今春からはあのコナー・マクレガーが運営する「マクレガー・スポーツ・アンド・エンターテイメント」がBKFCの共同運営会社に名を連ねるようになった。
時代に逆行するように見えながらも医学的データを基に再び世に出てきたベアナックル・ボクシング。何が危険で、何が安全なのか。ベアナックルで殴打されたことによるダメージについては、さらに研究されるべきだと思うのは筆者だけではあるまい。
しかし、賽は投げられた。新しい興奮を味わった我々はもう後戻りできないのか。
文=布施鋼治
photograph by RIZIN FF Susumu Nagao