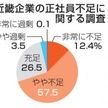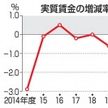ミュージカル『ビリー ・エリオット〜リトル・ダンサー〜』(原題:Billy Elliot)日本プロダクションの魅力を色々な角度から解明していくシリーズ。今回は、バレエ&ダンスの角度から専門家(高橋森彦氏)に解説をしていただく。
ミュージカル『ビリー・エリオット 〜リトル・ダンサー〜』が、2024年7月〜11月、 東京・大阪にて上演される。エルトン・ジョン(音楽)×リー・ホール(脚本・歌詞)×スティーヴン・ダルドリー(演出)ら偉才によって生み出された傑作の日本プロダクション3度目の公演だ。ここでは、世界各地で多くの観客に感動をもたらし、トニー賞やローレンス・オリヴィエ賞などを受賞している名舞台に関して、バレエ&ダンスの話題に触れながらその魅力を紹介する。
■炭鉱町の夢見る少年にも、スターへのチャンスは拓かれている!
舞台は1984年、不況にあえぐ英国北部の炭鉱町。早くに母を失くした少年ビリーは、炭鉱夫の父と兄、祖母と暮らしている。父が工面したお金でボクシングを習っていたビリーは、バレエ教室のレッスンを目にして密かにバレエを習う。ビリーの素質を見抜いたウィルキンソン先生は、ロンドンの名門バレエ学校のオーディションを受けるように勧める。父は最初反対するが、ビリーのバレエへの深い愛、ダンサーになるという夢に心打たれ、息子を応援するようになる――。
映画「BILLY ELLIOT」(邦題「リトル・ダンサー」)を原作とする『ビリー・エリオット 〜リトル・ダンサー〜』のストーリーは基本的に映画同様で、ビリーを主人公に青春と家族愛を描く。ビリーの父や兄はストライキに参加するが、これは、当時のサッチャー政権による新自由主義に基づく改革に対する炭鉱労働者の抗議活動である。彼らは、家族・仲間たちの生活の基盤であり生きがいである炭鉱を守るために闘う。鬱屈とした炭鉱町の空気感と、軽やかにステップを踏むビリーの踊りは対照的だ。ビリーは家族の、炭鉱町の人々の希望となっていくのである。
ビリーがウィルキンソン先生の薦めによって受験しようとするのは、ロイヤル・バレエ・スクールである。英国を代表するこのバレエ学校は1926年、英国バレエの祖であるニネット・ド・ヴァロワにより設立されたスクールを前身としており、1956年にロイヤルの名を冠することが許された。卒業生はロイヤル・バレエ、サドラーズウェルズ・ロイヤル・バレエ(のちのバーミンガム・ロイヤル・バレエ)をはじめとするカンパニーで踊る。11歳から16歳までが学ぶロウアー・スクールと16歳から19歳が学ぶアッパー・スクールに分かれている。卒業生にスターが多く、ウィルキンソン先生がビリーとの初対面時に「私はマーゴよ」とジョークを飛ばした20世紀最高峰の名花マーゴ・フォンテインをはじめ、アンソニー・ダウエル、モニカ・メイソン、アレッサンドラ・フェリ、ダーシー・バッセル、吉田都、熊川哲也ら大物ぞろいである。
その名門校に、炭鉱町の貧しい家庭の少年が入ることができるのか?と思われるかもしれない。しかし、才能あふれる生徒を選抜するため、学費や寮費を免除されたり、一部が支給されたりするシステムがある。したがって、受験に合格し優秀な成績を収めれば、未来のスターへの道が拓かれる。ウィルキンソン先生は、そういったことを分かっているので素質を感じたビリーに受験を薦め、個人レッスンまでやったのだ。ビリーは受験の最後に、審査員のひとりから踊っているときの気分を聞かれ、こう答える。「僕は自由になる」と。踊ることで救われるのである。
■ダンスで大事なのは「基本テクニック」と「自己表現」
ビリーにモデルはいるのか? 原作の脚本そしてミュージカルの脚本・作詞を手がけたリー・ホールは、映画の脚本執筆に際しロイヤル・バレエに問い合わせ、炭鉱町バーンズリー出身のダンサーであるフィリップ・モーズリーを紹介され取材した。モーズリーの両祖父は炭鉱労働者で、兄はストライキを闘った。モーズリーを特定のモデルにしていないにせよ、ビリーと似た境遇にあったようだ。また、ホールは、英国バレエの名振付家ケネス・マクミランを思い出したという。スコットランド出身で父親が炭鉱労働者であったマクミランの身の上は、ビリーと重なる。(註1)
ビリーのイメージと重なるといえば、往年の名舞踊手として知られるウェイン・スリープも挙げられる。ウエストエンド版では、ビリーは女の子たちと一緒にバレエをやっていることが父にばれると「ウェイン・スリープだってやっている!」というふうに訴える。スリープは1948年生まれ。ロイヤル・バレエ・スクールを経てロイヤル・バレエで活動するだけでなく、テレビ、映画、演劇などで多彩に活躍する大スターとして一世を風靡した。ミュージカル『キャッツ』のミストフェリーズ役を初演したことでも有名だ。タップダンスの達人でもあり、小気味よくタップを踊るビリーの憧れともいえる。なお、日本プロダクションではルドルフ・ヌレエフ(1938〜1993年)に変えられている。ソ連で生まれたヌレエフは、マリインスキー・バレエの若き俊英だったが、1961年に西側に亡命した。20世紀後半の男性バレエ・ダンサー躍進期の立役者で、パリ・オペラ座バレエ団の芸術監督も務めた。
ウィルキンソン先生は、ダンスのポイントは「基本テクニック」と「自己表現」だと説く。すると、バレエ教室のピアノ弾きのブレイスウェイトが「ロシア・バレエのディアギレフがバレエに革命を起こし、原始的な表現と優雅な表現を融合した」というふうに通信教育で得た知識を披露する。バレエ芸術を極めるために必要な技術と表現の関係性、20世紀初頭のバレエ・リュスによって総合芸術として高められた歴史背景の本質を、軽妙なやり取りで伝えるのは秀逸だ。
ビリーに負けず劣らず注目される役柄が、オールダー・ビリーである。大きくなったビリーであり、憧れの存在でもある。映画とミュージカルの最大の違いは、このオールダー・ビリーの扱い方である。映画版では、14年後、ビリーは成人しプロのダンサーとなって、マシュー・ボーンの『白鳥の湖〜スワン・レイク〜』の主役ザ・スワンを踊ろうとして飛び出す場面で終わる。このオールダー・ビリーを当時ロイヤル・バレエのプリンシパルだったアダム・クーパーが演じて話題をさらった。いっぽう、ミュージカルでは、二幕後半でビリーとともに踊る「Dream Ballet」が見どころだ。ふたりが並んでそれぞれ椅子を回しながらのユニゾン(同じ振付での踊り)、それにワイヤーワークもあるタフな振付だが、ビリーの未来の姿として登場し、ともに踊り、まさに夢のように甘美な場面が現出する。
註1)参照元:「The Guardian」紙 2000年10月1日記事「It is like electricity, like magic」。(https://www.theguardian.com/film/2000/oct/01/features.review1)
■四者四様、それぞれの色に期待したいビリー役
ミュージカル『ビリー・エリオット〜リトル・ダンサー〜』は2005年にウエストエンドで幕を開け、2008年にはブロードウェイでも上演される。その後は、オーストラリアやアメリカ、韓国、ノルウェー、オランダなどで現地キャストによるバージョンが制作され、2017年に待望の日本プロダクションが初演されたのは周知のとおりだ。上演までにさまざまな難関があったはずだが、最大のハードルは、ビリー役にふさわしい出演者に恵まれるか否かに尽きるだろう。
ビリー役に求められる条件はいくつもある。まずは、少年役にふさわしい11歳前後であること。そして、歌、バレエ、タップダンスやアクトバットなどの技能も求められる。それこそロイヤル・バレエ・スクールの入学試験ではないが素質を見極められる。難関であるオーディションを突破し、その後長期にわたる育成期間を経て、ようやく舞台に立てるのだ。
ビリー役を務めた少年のなかからは、バレエやショービジネスの世界で活躍する人が出ている。2017年公開の映画「スパイダーマン:ホームカミング」でスパイダーマン役を演じるなどスターダムに登り詰めた俳優のトム・ホランドは、2008年〜2010年にウエストエンド公演でビリーを演じた。また、ロイヤル・バレエのプリンシパルを務めるセザール・コラレスは、2010〜2011年にアメリカのシカゴとカナダのトロントの公演でビリーを踊っている。日本版では、2017年と2020年の公演時に合計9名のビリー役が生まれ、それぞれの夢に向かって邁進している。最近の話題を挙げれば、今年2月、2020年にビリーを踊った利田太一が、若手バレエダンサーの登竜門と称されるローザンヌ国際バレエコンクールにおいて第9位入賞を果たし、大きく報じられた。
3度目の上演となる日本版でビリーに挑むのは、浅田良舞、石黒瑛土、井上宇一郎、春山嘉夢一の4人。彼らは国内外のバレエコンクールで上位入賞を果たすなど、それぞれのポテンシャルが高い。そのうえで切磋琢磨して、おのおののビリーを創り上げるだろう。いま一度ウィルキンソン先生の言葉を思い起こそう。ダンスのポイントとして「技術」だけでなく「自己表現」が大事。四者四様の色を帯びた表現が日々進化して物語られるステージの開幕が待ちきれない。
文=高橋森彦

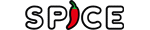

















![ゲスの極み乙女がカバーに登場、Omoinotakeの『ヒロアカ』EDやミスチルの映画主題歌など、『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』が今週話題の新作11曲を紹介](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/spice/s_spice-328587.jpg)