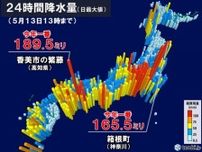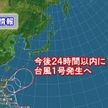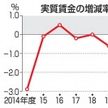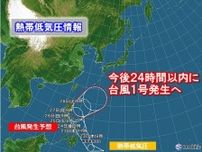前編【元皇族の庶子を自称、17歳で宮様と熱愛、元首相と勝手に入籍…皇族詐欺の元祖「増田きぬ」の波乱万丈人生】からのつづき
皇室の出自であると偽って詐欺をはたらく「皇族詐欺」。その“元祖”と見られていた「増田きぬ」は、終戦直後から元皇族・北白川宮(きたしらかわのみや)のご落胤および久邇宮朝融(くにのみや・あさあきら)王の愛人を自称していた。昭和53年には元皇族・東久邇稔彦(ひがしくに・なるひこ)氏の“戸籍妻”として注目され、その後も数々の訴訟や詐欺スレスレの行為でマスコミに登場する。ノンフィクションライター・上條昌史氏が増田きぬを追ったのは2005年のこと。きぬが電話取材で語った“過去と残りの人生“とは。
(前後編記事の前編・「新潮45」2005年8月号特集「昭和史七大『猛女怪女』列伝 元祖偽皇族『東久邇きぬ』という謎」をもとに再構成しました。文中の年齢、肩書、年代表記等は執筆当時のものです)
***
再度マスコミに登場
「婚姻無効」の確定後、増田きぬが、再びマスコミに登場したのは、平成7年11月。“旧皇族”の肩書きで、健康食品会社ジャパンヘルスサミットという会社から、2000万円もの金を、ちゃっかり“騙し取って”いたことが判明した。
この会社、万病に効くという触れ込みで、蟹の甲羅が原料の「カニトップハイゴールド」という製品を売りまくり、急成長を果たした会社だったが、マルチ商法すれすれの業態で、オーナーが訪販法違反で逮捕。彼女はその会社のパーティーに、「東久邇紫香」という名で来賓となって出席し、見返りに2000万円もの貸付けを受けていたのである。
平成12年には、今度は怪しげな「M資金詐欺」の話に関連して、再び世間に登場した。もとは皇室の財産で、今は台湾にある宮家の所有になっているドイツのマルク債券(時価2000億円以上)の約半分が、もうすぐ日本に返還される予定で、その保管料を支払うために出資すると「倍返し」になるという、わけのわからないM資金話である。彼女はこの怪しげな出資話を口コミで募り、借用書をばら撒いていた。
もっとも本人はこの2つの“事件”について、「私が人を騙すはずがありません」と全面否定。ゆえに真実は定かではない。
そして彼女は、このM資金話を最後に、世間から忽然と姿を消してしまうのだ。
元華族が取締役の「謎の企業」
その後の彼女の活動で、判明していることといえば、平成14年に「公照院紫香」と改名したこと。また自身が取締役であった「久邇ウエルネス」という会社を、同年解散していることくらいである。
ちなみに、「久邇ウエルネス」の取締役には、元華族(これは本物の)二條恭仁子(くにこ)氏らが名を連ねている。「李方子王妃碑」の建設委員長としても名が出てい恭仁子氏は、すでに亡くなっており、ご子息の基敬(もとゆき)氏(彼自身も取締役として登記に記載)に、同社の活動内容を尋ねると、「そんな会社のことは全く知らない」という、戸惑い気味の答えが返ってきた。
「増田きぬは、亡くなった母が知っていたかもしれないが、私自身は面識もない。久邇ウエルネスなんて会社は知らないし、もちろん取締役になっていた事実もない。なにか報酬が発生したこともないし、とにかくそんな会社の名前は聞いたこともない」
彼女は元華族の名を勝手に借りて、その会社で何かをやろうとしていたのだろうか。いずれにしても、その試みはうまくいかなかったようだ。
あながち信憑性がないとはいえない
彼女とは古くからの知り合いであるという皇室ジャーナリストの河原敏明氏は、彼女の人間性やご落胤説について、次のように語る。
「はっきり言いまして、皇族関係では彼女の評判は悪く、相手にされていないというのが実情です。でも、私は彼女が若い頃からよく知っていますが、人間としてそれほど悪党には見えないんです。一言でいえば、女実業家ぶって、名を顕したいという面が多分にあって、失敗して抜き差しならないことになってしまった人間、という感じがします。
詐欺まがいのこともずいぶんやっていますが、最初から詐欺をするつもりだったことは少ないのではないでしょうか。むしろそんな彼女を利用して金儲けをしようとする連中に、うまく騙されてしまっているケースが多いように思います。
北白川のご落胤説については、否定的な見解が多いですが、私はあながち信憑性がないとはいえないと思うんです。小さい頃から姉妹と違う待遇を受けていたのは事実ですし、強羅の地所にしても、昔は隣が北白川の土地だったんです。また彼女は顔がよく、若い頃から非常に色が白いのですが、北白川の系統は皆、色が真っ白という特徴があるのです。ただし、ご落胤説が本当だとしたら、東久邇の名を騙ることなく、ずっと北白川で通したほうが人間として立派だったという気はしますが……」
モダンなお婆ちゃんという感じ
その昔、4000坪あったという土地は切り売りされ、現在、電鉄系のリゾートマンションが立ち並び、残された“金閣寺”の土地と家屋は、現在箱根町に差し押さえられている。箱根町に事情を聞くと、「個人的な情報は明かせませんが、一般的に税金を滞納し、返済の見込みがないと判断した場合に差し押さえを行います」(箱根町税務課)とのこと。
木立の中の“金閣寺”は、確かに落日のうらぶれた感がある。付近の住人によれば、「東麗寺」の社には賽銭箱があるものの、参詣する人の姿は殆どなく、地元の自治会にも顔を出さないため、彼女が日々どのような暮らしをしているのか、皆目わからないという。
「1、2年前までは、時々近所の園芸店に花を買いに来ていました。華奢な体で、ピンク色の服を着て、モダンなお婆ちゃんという感じでした。でも1000円、2000円の買い物を、いつも100円玉で払うので、お寺のお賽銭で買い物をしているのかな、と思ったりもしました」(近隣の女性)
世間から半ば隠遁し、地元ではすでに伝説の人物になっているようだった。
“金閣寺”の裏手には勝手口があり、結局そこで、お手伝いさんが応対してくれた。
彼女の話によると、“椿姫”はこの冬に体調を崩し、いまは、起き上がることもままならない状態だという。ただし直通の電話があるので、そこに電話をしてくれたら、もしかしたら取材に応じるかもしれない、と教えてくれた。
“椿姫”が語った強羅での生活
そこで後日、教えられた番号に電話をすると、消え入るような小さな声の“椿姫”が、受話器をとった。
「私、生まれて初めて、足と手が痛くなって、救急車で病院に運ばれて、先日まで、3日間ほど入院していたんです。左の腰に激痛が走るので、まだモノにつかまらないと歩けない状態で……」
体調のことを除けば、現在の強羅での生活は、静かで穏やかなものだ、と言う。
数年前、京都の醍醐寺で得度をし、仏門に入った。高野山や遠い地へ出かけ、滝に打たれるなどの厳しい修行を積んできた。今は朝晩にお経をあげ、“お隠れ”になった皇族の知り合いや、戦死した財閥の子息たちの冥福を祈る毎日だという。
そんな彼女の心の慰めになっているのが、“一緒に住んでいる”猫たちである。
「私は、父も母もなく孤独に育ちましたから、捨てられた動物をかわいそうに思いまして、いま野良猫ちゃんを十数匹飼っているんです。洋間を2つ、猫のために使っていて、餌の缶詰を東京から月に2、3回送ってもらい、お刺身やらお肉やら、好きなものを食べさせてあげているんです」
増田きぬには、実父母も姉妹もいたはずだが、彼女の中では、やはり今も、北白川のご落胤、という事実があるだけのようだった。
いいえ、裁判には勝ちましたから
今回、皇族詐称(疑惑)に関する彼女への具体的な質問は、ことごとく、やんわりと、はぐらかされてしまった。記憶も、ところどころ曖昧になっているようで、事実関係を訊き始めると、話はわき道にそれ“迷宮”の中に入ってしまう。
たとえば、東久邇稔彦氏との入籍問題を問うと、彼女は次のように答えた。
「ええ裁判には勝ちました。最高裁の判決で私が負けた? いいえ、裁判には勝ちましたから。婚姻の事実があるということが、きちんと認められたんです。そもそも稔彦と籍を入れたきっかけは――生前、稔彦の奥様の聡子さんが、紅葉狩りと称して、強羅の私の家に泊まりに来たことがあったんです。南米に養子に出されていた、3番目のご子息の方とご一緒に。『ロマンスカーに乗ったことがないから』と言って、ロマンスカーでいらしたんです。私は小田原まで迎えに行きました。そのとき聰子さんに、『自分は病気なので、もしものことがあったら(稔彦氏を)お願いします』と、頼まれたのです……」
愛人の噂があった久邇朝融については、「私の17歳のころの『リーベ(恋人)』でしたの」と、説明してくれた。
「私たち、お互いに好きになったんですが、当時朝融は宮様でしたから、離婚することができません。それでも本人は離婚すると騒いで……。そんなことがあったので、戦後、私は単身でアメリカに渡ったんです。以来、いろいろな財閥の方とか、公爵とか伯爵の方々から、結婚の話をいただいたものです。でも、みな丁重にお断りしました。一緒になれなくても、やはり私は朝融が好きだったからです……」
若い頃の話になると、老女の声は、心なしか艶やかな声になった。
残りの人生、美しい華を咲かせていきたい
ところで、現在の生活費はどのように賄っているのだろうか?
「アメリカに留学していた頃、デパートを経営しており、そのときの貯金で、なんとか暮らしています。もう歳ですから、少し食べるだけで、生活はできるんです。以前はお手伝いさんが、5人くらいいましたが、経費削減のため、2年前から2人にしました。
それに、お寺の社に、存じ上げない方たちが、通りがかりにお賽銭を入れてくれるのです。月の初めに、そのお賽銭箱を開けて、お手伝いさんたちと3人で、平等に分けるようにしています。ほんのわずかな金額ですけれど……」
“椿姫”は今年で88歳。しかしまだ人生にはやり残したことがある、と言う。この話になると、急に声のトーンが変わり、力が漲ってきた。
「もう財産はありませんが、美術品をたくさん持っているので、それを処分して、ちょっとメイク・マネーしまして、慈善事業的なことをしようと計画しているんです。ひとつでもいいことをしておかないと、“お前は何をやってきたんだ!”と、閻魔様に叱られますから。舌を抜かれて、地獄に落ちますからね。
これからの残りの人生、美しい華を咲かせていきたいと思います。見ていてください。近いうちに、必ずやりますから。そのときには、またご報告しますよ」
受話器から流れてくる声は、いつしか奇妙な活気に満ち溢れていた。そして最後には、「元気になったら、おいしいご馳走でもご一緒しながら、ゆっくりお話しましょう。これを機に親しくなれるといいですね――」と、楽しげに宣言した。
昭和の時代を生き抜いた怪女は、いまだ健在で、未来だけを眺めているようだった。
上條昌史(かみじょうまさし)
ノンフィクション・ライター。1961年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部中退。編集プロダクションを経てフリーに。事件、政治、ビジネスなど幅広い分野で執筆活動を行う。共著に『殺人者はそこにいる』など。
デイリー新潮編集部