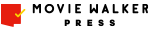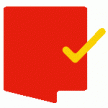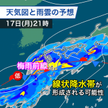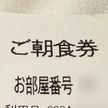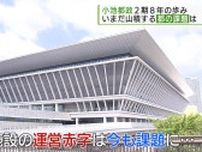ジャマイカが生んだレゲエミュージックの伝説ボブ・マーリーの半生を描く伝記映画『ボブ・マーリー:ONE LOVE』(公開中)。1億7千万ドルに迫る世界興収を記録した話題作の舞台裏には、どんなエピソードがあったのか?故ボブ・マーリーの長男で自身もアーティストであり、本作ではプロデューサーを務めたジギー・マーリーと、主人公ボブを演じたキングズリー・ベン=アディルに聞いた。
■「キングズリーには父の姿と重なるものがあった」(ジギー・マーリー)
まず気になるのは、ジギーが製作名義で、どんな仕事をしたのか。プロデューサーの仕事は多岐にわたるが、彼は「必要なことがあれば出てきた、という感じですね。例えば自分が見た光景にどこまで近いか?とか、言葉の訛りとか。相談役のようなものです。もっとも重要な役割は、父を正しく描くことでした」と語る。
それを聞いたベン=アディルは「謙虚に話してらっしゃいますが、ジギーはとてつもなく大きな貢献をしてくれました。私も監督もジャマイカ人ではありませんから、多くのことを知る必要があった。ジギーは毎日セットを訪れて、僕らが助言を求めた時、つねにヒントをくれました。映画全体の流れを導いたんですよ」と称賛する。
没後40年以上を経たボブ・マーリーという伝説を演じるうえで、ベン=アディルはどうしたのだろう?「オーディション前に、様々なボブの映像を見ましたが、インタビューではお茶目で笑ってしまうような部分がありました。一方で、彼のライブパフォーマンスには驚かされましたね。もちろん彼の名は知っていたし、有名な曲も聴いたことがありますが、このような側面に触れたのは初めてでした。彼はつねに、自分の本心を口にしていました。そこが魅力的な部分です。物事を曖昧にせず、はっきり言う。そして、圧倒的なカリスマ性がありました。そんな人物像を深めていくことを考えて、演技に臨みました」。
ジギーも彼の演技を賞賛する。「彼はオーディションの映像の段階で群を抜いていました。カリスマ性を持っていたし、なにより他人をリスペクトする姿勢がすばらしい。現場での彼は欲しいものが明快だった。そういう意味では、父の姿と重なるものがあったのです。私自身、彼のそのような姿勢を見て、改めて真剣に取り組まなければならないと思ったのです」 クリエイター同士の高め合う姿勢が、本作をおもしろくしたと言えるだろう。
コンサートにおけるボブ・マーリーの動きは独自のものがあり、ダンスにも個性がある。ベン=アディルは、その特徴をつかみ、完全に自分のものにしている。「肝心なのは、自分の動き方とどう違うのか、どうしてそういう動きになるのかを理解することでした。ステージ上のボブは全身全霊で動いていて、疲弊するほどそれを続けていたんです。あれだけ動けるということは肉体が健康だったのでしょう。また、彼は周りのミュージシャンがとんな音を出し、どう動いているのかも把握していた。私はミュージシャンではないので、その姿勢はわかりませんが、だからこそ興味を惹かれました」。
■「脚本にはなかった口論のシーンは何か月もかけて、ジギーと語り合いました」(キングズリー・ベン=アディル)
映画は1976年から1978年にかけてのボブの生をたどるもの。冒頭、ボブが子どもたちと一緒にサッカーをしている際に銃声が響き、彼はジギーら息子たちを避難させる。当時のジャマイカは政治的内紛が深刻化しており、緊張に包まれていたのだ。「大人の目から見れば、それはかなり危険な状況だったでしょう。ただ、当時の私は8歳だったから、危険であるとは認識していませんでしたし、そういう状況に置かれていることにも抵抗はなかった。確かに、子どもがいるべき環境ではなかったかもしれません。しかし、父はそのような状況から、私に学んでほしかったのでしょう。まあ、子どもにしたら大冒険ですね(笑)」。ベン=アディルは、こう付け加えた「それを知ると、ボブ・マーリーという人物がさらによく理解できるんです」。
程なくして、コンサートに出演するためにリハーサルを行なっていたボブ・マーリーはスタジオで銃撃される。民衆に対して政治的な影響力を持つ彼の存在を疎ましく思う人間が、当時のジャマイカには存在していたのだ。ジギーは語る。「おそらく、当時の父は自分が撃たれるとは思っていなかったのでしょう。私もそうでした」。ベン=アディルがフォローする。「ボブは“皆、仲間だから”という姿勢を持っていて、映画はそこからスタートするんです」。この時、ボブの平和主義は過酷な現実に打ち砕かれるのだ。
銃弾を受けるも一命をとりとめたボブ・マーリーはコンサートをやり遂げた直後、命の危険を察してロンドンへと渡り、ジャマイカを約1年半、離れる。そこには、祖国の混乱をもはや楽観視できないいらだちもあったのだろう。彼のバンド、ザ・ウェイラーズのメンバーでもあった妻リタも、遅れて到着し、ボブの新天地での音楽活動をサポートする。つまり、当時8歳のジギーは長きにわたり、両親と離れて暮らすことになったのだ。「もともと両親は音楽活動に忙しく、私は大叔母や親戚と暮らしているのが当たり前だったので、感傷的にはなりませんでした。映画の中で、父がジャマイカに戻ってきた時、空港で群衆に揉みくちゃにされながら車に乗り込み、私もスタッフにそこに押し込められる場面がありますが、あれは事実です。久しぶりに会ったのに、感動の再会とは程遠い状況でした(笑)」。
ロンドンでレコーディングした名盤「エクソダス」は世界的なヒット作となり、ヨーロッパツアーも好評。しかし成功のなかで人間関係が軋みだし、ボブと妻リタの関係も悪化。ツアー中のパリでの口論は、この映画でボブの人間的な弱さが出てしまうシーンだろう。「口論のシーンについては、もともとの脚本にはなかった。ジギーが考えて、つくり出した場面です。ご両親の口論の流れをよく理解していたので、この場面については何か月もかけて、彼と語り合いました」とベン=アディルは語る。
世界中の紛争が絶えない世の中に、一つの愛=“ワン・ラヴ”で人々は結ばれるべきである、というテーマを持った本作はタイムリーでもある。「この映画がヒットしていることはうれしいし、そこには“愛”というテーマが関係していると思います」とベン=アディルは言う。またジギーは「アートを発表した時、往々にして世の中では予想していないことが同時発生的に起こります。映画を作っている時には、公開時にこんな世の中になっているとは思っていませんでした。我々はなにかに導かれて、この映画をつくり、一方では我々の見えない力によっていまの世の中がこうなった。我々がやっていることは、ひょっとしたら我々が思っている以上に重要なことかもしれません」と語った。本作が混沌の現代に、どんな音を打ち鳴らしているのか?まずは、体感してみほしい。
取材・文/相馬学
あの名シーンは当初の脚本になかった!? ジギー・マーリー&キングズリー・ベン=アディルが明かす『ボブ・マーリー:ONE LOVE』製作秘話

関連記事
おすすめ情報
MOVIE WALKER PRESSの他の記事もみるあわせて読む
-

外国人が日本の恩人に“アリガト!” ハートフルな姿をSnow Man佐久間大介、桜田ひより、馬爪エブリンが見守る
ORICON NEWS6/17(月)12:00
-

『鬼滅の刃』柱稽古編あと2話でファン驚き 迫る決戦に「ついに無限城編が」「続きは劇場版かな」
ORICON NEWS6/17(月)11:45
-

<鬼滅の刃>玄弥の鎹鴉役は中尾隆聖 EDクレジットで発表
ORICON NEWS6/17(月)7:10
-

「芥見下々『呪術廻戦』展」榎木淳弥&諏訪部順一が音声ガイドに登場! 渋谷ヒカリエコラボ情報も
アニメ!アニメ!6/17(月)0:00
-

『鬼滅の刃』柱稽古編は第8話で最終回!60分放送 第7話も放送枠拡大の特別放送に
ORICON NEWS6/16(日)23:51
-

『鬼滅の刃』柱稽古編の第7話あらすじ&場面カット公開 涙を流す悲鳴嶼さん
ORICON NEWS6/16(日)23:45
-

懐かしの妖艶美女キャラに挑んだ女優たちへの反応は? 「ハマり役」「実写化は無理」
マグミクス6/16(日)19:10
-

「鬼太郎 ゲゲゲの謎」公式上映 フランスの国際アニメ映画祭で独創的作品集う「コントルシャン部門」出品
スポニチアネックス6/16(日)15:41
-

「機動戦士ガンダム」白馬に跨るシャアをフィギュア化! 馬の筋肉や血管まで圧巻の造型と絵画のような彩色は必見
アニメ!アニメ!6/16(日)13:00
-
-

梅雨のジメジメを吹き飛ばす!いまこそ観たいアカデミー賞受賞映画13選
MOVIE WALKER PRESS6/16(日)12:30
-

<鬼滅の刃>蜜璃ちゃん大胆開脚に大反響「目のやり場に困る!」「えぐかったなぁ」
ORICON NEWS6/16(日)11:10
-

サンドラ・ブロックとN・キッドマン 『プラクティカル・マジック』98年以来の続編に向け交渉中
よろず~ニュース6/16(日)7:50
-

死ぬまで焼き付いているのは、夫婦げんか後の母が山頂で歌った童謡…長渕剛「つらい時に心を癒やすのが歌」
読売新聞6/16(日)7:02
-

『鬼滅の刃』柱稽古編、第6話が本日放送 鬼殺隊最強…悲鳴嶼さん登場!あらすじ&場面カット公開
ORICON NEWS6/16(日)0:00
-

『バッドボーイズ RIDE OR DIE』が北米No. 1の好発進でさらなる続編の可能性も!?「LOTR」3部作がイベント上映で存在感
MOVIE WALKER PRESS6/15(土)19:30
-

限定ガンプラも!『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』Blu-ray&4K UHD-BD&DVDは全5形態で発売
MOVIE WALKER PRESS6/15(土)18:30
-

「4人でもう1回歌うんや」結成25周年のET-KINGが仲間と繋ぐ想いと感謝ーーツアーファイナルは思い出の大阪城音楽堂で開催
SPICE6/15(土)18:00
-

「まだまだ現役なのに…」「降板の裏に複雑な胸中」 物議を醸したアニメの声優交代
マグミクス6/15(土)17:55
-
エンタメ アクセスランキング
-
1

日テレ・水卜麻美アナ 管理職として「ポスト水卜育成」の初任務も…局内で危惧される重大リスク
東スポWEB6/17(月)5:00
-
2

TBS渡部峻アナ 泥酔で民家上がり込み放尿 通報されていた 日曜「Nスタ」は出演見合わせ
スポニチアネックス6/17(月)4:50
-
3

鶴光ラジオ番組めぐる「不適切」謝罪にSNSで様々な声「鶴光に適切さを求めるなよ」
日刊スポーツ6/17(月)12:34
-
4

「うちの息子の嫁に!」の声が殺到も 高橋里華 ひと目ぼれで結婚して芸能界引退、直後に介護を迎えた怒涛の人生
CHANTO WEB6/17(月)6:30
-
5

鈴木奈穂子アナがあさイチ欠席、大吉は「悪い魔法使いに魔法を…」と説明 近藤泰郎アナが代打
日刊スポーツ6/17(月)8:47
-
6

「普通のアラサー女はもっと盛る」志田未来、SNSで見せた“素”がありのまま過ぎて波紋
週刊女性PRIME6/17(月)11:45
-
7

オードリー若林、“因縁の相手”と収録中に乱闘騒ぎ!弘中綾香アナも悲鳴上げる非常事態
テレ朝POST6/17(月)7:30
-
8

『あさイチ』鈴木奈穂子アナの欠席理由にネットざわつく ゲストも便乗「キムタクってww」「明日はどうすんだ?」
中日スポーツ6/17(月)11:13
-
9

伊藤沙莉 『虎に翼』愛娘役で姪っ子が極秘出演!地元焼肉店の店員が見た「伊藤家の絆」
女性自身6/17(月)6:00
-
10

高嶋ちさ子 家族ぐるみの付き合いの超人気タレントのパパぶり明かす 「本当に謙虚」「4時半に…」
スポニチアネックス6/17(月)11:51
エンタメ 新着ニュース
-

織田信成 大ヒット歌手との“もらい泣きコラボ”で2ショ披露 ファンのツッコミに「大正解です」
スポニチアネックス6/17(月)15:31
-

ツモって笑い、振り込んで泣いた……マージャン漫画の半世紀
読売新聞6/17(月)15:30
-

「アンチヒーロー」近藤華、“親子”再会ショットが大反響!「パパとの2ショット泣ける」「感動的」
スポーツ報知6/17(月)15:30
-

ヒカル、今度は霜降り・せいやにかみ付く!「歌モノマネしてるだけ」長時間トークでは「俺が勝つ」
スポニチアネックス6/17(月)15:30
-

「コンパ行かない」麒麟川島が女性お笑いファンと“飲み会の練習” カラオケ店で受けた手ほどき
スポニチアネックス6/17(月)15:29
-

森口博子 中学の先輩だった大物タレント明かす 40代の悩み相談し授かった“金言”「すごく気が楽に」
スポニチアネックス6/17(月)15:29
-

48歳・神崎恵、若い=美しいの“定義”変えたい「減点方式ではなく、気楽に年を老いたい」
ORICON NEWS6/17(月)15:27
-

今田美桜「花咲舞が黙ってない!」最終話8・1% 昇仙峡は相馬にこれまでの非礼をわびつつ…
日刊スポーツ6/17(月)15:27
-

高嶋ちさ子「土下座して…」 最大の武器不調に「一応ヴァイオリニストなので、キャンセルはないかなと…」
中日スポーツ6/17(月)15:25
-

【訃報】女優の山田昌さん 大河ドラマ「真田丸」で秀吉の母役
テレ朝news6/17(月)15:25
総合 アクセスランキング
-
1

大谷HRでNHK中継に映り「なんで??」 早朝の視聴者が大注目、珍光景が話題「何やこの集団」
THE ANSWER6/17(月)10:43
-
2

「ストップ!」と叫び バスと電柱に挟まれバスガイドの女性死亡か 69歳運転手現行犯逮捕 誘導中に事故 状況から女性は救急搬送されず(山形・上山市)
テレビユー山形6/17(月)9:42
-
3

日テレ・水卜麻美アナ 管理職として「ポスト水卜育成」の初任務も…局内で危惧される重大リスク
東スポWEB6/17(月)5:00
-
4

「表情が暗い…」日本は米国にストレート負け!主将・古賀紗理那が試合後のインタビューで“声を詰まらせる姿”にファン心配「泣きかけてたよね」「声、大丈夫?」
THE DIGEST6/17(月)8:54
-
5

大谷翔平、特大18号で“記録樹立” 球場騒然の137m弾…米記者紹介「初めての選手」
Full-Count6/17(月)6:24
-
6

TBS渡部峻アナ 泥酔で民家上がり込み放尿 通報されていた 日曜「Nスタ」は出演見合わせ
スポニチアネックス6/17(月)4:50
-
7

鶴光ラジオ番組めぐる「不適切」謝罪にSNSで様々な声「鶴光に適切さを求めるなよ」
日刊スポーツ6/17(月)12:34
-
8

高校生、店員に助け求める 容疑者ら「取り合うな」 旭川17歳殺害
毎日新聞6/17(月)12:21
-
9

「うちの息子の嫁に!」の声が殺到も 高橋里華 ひと目ぼれで結婚して芸能界引退、直後に介護を迎えた怒涛の人生
CHANTO WEB6/17(月)6:30
-
10

鈴木奈穂子アナがあさイチ欠席、大吉は「悪い魔法使いに魔法を…」と説明 近藤泰郎アナが代打
日刊スポーツ6/17(月)8:47
いまトピランキング
 いまトピランキングの続きを見る
いまトピランキングの続きを見る
東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-

EUROオランダ代表クーマン監督の“衝撃鼻ほじり”がトレンド入りしたワケ…「世界中を駆け巡る不快な仕草」
Qoly6/17(月)15:00
-

板橋区文化会館大ホールがプラネタリウムに 小学生向けワークショップも
みんなの経済新聞ネットワーク6/17(月)14:44
-

速報!広島サッカー次の100年へ大変革!サンフレッチェ広島に続く県内第2のJクラブや皇后杯決勝のエディオンピースウイング広島開催も…
ひろスポ!6/17(月)14:03
-

二子玉川ライズで「フードドライブ」開催へ 子ども食堂などに寄贈
みんなの経済新聞ネットワーク6/17(月)12:40
-

文京で「共生社会」テーマに公開講座 広瀬浩二郎さん迎えて
みんなの経済新聞ネットワーク6/17(月)12:30
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright (c) MOVIE WALKER Co., Ltd.