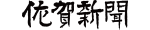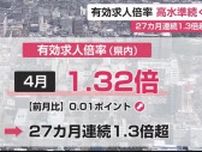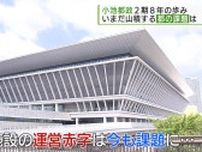第一章「怪談ラジオ局」(3)
「毎日、日本中で何千人も死んでんだよ? 病気とか事故とか、老衰とかでさ。ホントに幽霊がいるなら、わざわざ心霊スポットなんか行かなくても、どこもかしこも幽霊だらけだろ。でも俺、一回も見たことないよ」
「そりゃ、私だって見たことなんてないけどさあ……だけど、ひょっとしてもしかしてホントにいるなら、見てみたいじゃん」
昇太の理屈は至極もっともだったが、小柄でショートカットの花音は食い下がった。
「なんかきっとさあ、普段は見えなくても、見えてしまう条件的なものが揃(そろ)うと見える、みたいなことがあるんじゃない?」
「条件的なもの?」
昇太はみかんを剥く手を休めて花音を見た。
「幽霊側に、どうしても生きている人に伝えたい的なことがあるとか。ほら、怨霊的な存在とかってさ、なんか物凄(ものすご)く怒ったり憎んだり恨んだりしてる訳でしょ……それこそ、あちらの世界からこちらの世界に飛び越えて来るほどの、超絶的なマイナス的パワーっていうの? それをさらに、満月の神秘的パワーが後押しする的な感じ?」
「さっきからすんごい『的』が被(かぶ)ってるよ」
「細かいことは気にしないの。日本語なんて、通じたら良い的な感じで」
「いや、花音さん、将来は一応アナウンサー志望でいらっしゃるんですよね。それでしたら、普段から正しい日本語をお使いになった方が……」
昇太が慇懃(いんぎん)に突っ込む。
花音は高校時代、アナウンスのコンクールで度々全国大会に出場した経歴があり、女子アナ志望者としてはなかなかの有望株と言われている。華やかでよく響く声質は、仲間内で『噂話が出来ない声』などとからかわれることもあるが、天性の明るい性格も含めて、これほどアナウンサーに向いている人はいないんじゃないかと昇太も思っている。
ちなみに昇太自身は花音の影響で、マスコミ業界全般、特に放送局に憧れを抱きつつ、将来の夢はまだ模索中だ。
――放送局に入れたらいいけど、花音ほどの才能も熱意も無いし……。
彼女とは付き合い始めてまだそれほど経っていないけれど、もしも就職先が離れてしまったら、二人の仲はどうなるのだろうか。そもそも、いかにも異性にモテそうな花音が、自分のような引っ込み思案なキャラ……陰キャと付き合ってくれていること自体が、不思議なのだけれど。