 インタビューに応える自然エネルギー財団事業局長の大林ミカ氏(5月16日。撮影/今井康一)
インタビューに応える自然エネルギー財団事業局長の大林ミカ氏(5月16日。撮影/今井康一)
国の中長期的なエネルギー政策の方向性を示す「エネルギー基本計画(第7次)」の議論が始まった。経済産業省は5月15日、総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長・隅修三東京海上日動火災保険相談役、委員15人)を開き、議論をスタートさせた。
現在のエネルギー基本計画(第6次)は、菅義偉前首相の「2050年カーボンニュートラル宣言」に呼応し、2030年度の電源構成に占める脱炭素電源比率を約6割と想定している。内訳は「再生可能エネルギー36〜38%、原子力20〜22%、水素・アンモニア1%」。
今回の見直しでは、2035年度以降の削減目標と脱炭素電源の構成比率をどこまで上げるかが注目されている。ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化などで化石燃料の地政学的リスクは高まっており、いかに純国産の再エネでエネルギー安全保障を確保するかも問われる。
ところが、である。これまでの同基本計画の改定過程で、再エネ普及の観点から専門的なシナリオを報告してきた自然エネルギー財団が、議論の輪からはずされている。理由は、内閣府の「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(以下、TF)」の3月23日会合で、財団の事業局長・大林ミカ構成員が提出した資料に中国の国家電網公司のロゴが混入したことに端を発する政府の「調査」が長びいているからだ。
事務的ミス以外の要因は浮上せず
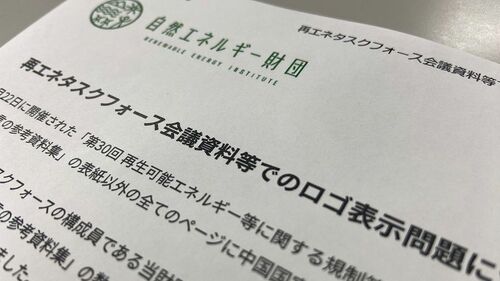 自然エネルギー財団が3月26日に公表したロゴ表示問題についてのリリース(編集部撮影)
自然エネルギー財団が3月26日に公表したロゴ表示問題についてのリリース(編集部撮影)
各省庁は、調査によって財団が中国政府や中国企業の影響を受けていないことが明らかになるまでは、財団を意見聴取の対象にしないという。もちろん日本のエネルギー政策が他国の影響で捻じ曲げられるようなことは許されない。政府は検証をしなくてはなるまいが、問題発覚から2ヶ月が経ってもロゴ混入の要因は大林氏の事務的ミスのほかに浮上していない。
はたして国内で他に類のない再エネ系シンクタンクを除外して、幅広い知見を集めたエネルギー論議ができるのだろうか。
当事者である大林氏に、ロゴ混入の経緯と自然エネルギー財団が外されている背景を聞いてみた。
「そのロゴは、2016年5月に韓国で国際送電ネットワークをテーマに開催したワークショップの資料の中にありました。当時、私たちの財団以外にも、日本創成会議(増田寛也座長)や韓国電力公社、中国国家電網などさまざまな機関が国際送電網の提案をしていました。2016年の12月、諸提案を比較検討する資料を作成するため、中国国家電網の構想地図のスライドのバーを削除して日本語に翻訳する作業をおこないましたが、白地に白いロゴがなじんで見えず、削除されないまま残ってしまった。空白と表示されるスライドにロゴが入っていることに気づかず、『白地スライド』から他の資料作成を行ったため、他にも含まれてしまったのです。それが、私のプレゼンの最後の空白スライドを利用したページにロゴが入っている理由です。まったくの事務的ミスでした。タスクフォースで公表した資料の一部は私が作成したものですが、もちろんそれにはまったく国家電網の資料を使っていませんし、出典も明記しています。詳しい経緯については3月26日に『再エネタスクフォース会議資料等でのロゴ表示問題について』をリリースし、27日の記者会見でもご説明しました。総理や大臣、国会議員を含む多くの方々を混乱させましたので、私はTFの構成員を辞めました。その後、内閣府など国の省庁には4月5日付で『自然エネルギー財団へのご質問に対する報告書』を送り、その概要を8日に公表するとともに、4月16日には2回目の記者説明会を開催し、私たちが中国政府や中国の企業と人的、資金的に一切関係がないことを重ねて報告しました」
大林氏は実際にパソコンで操作をしてみせながらロゴ混入の経緯を筆者に説明した。筆者はそれで混入の原因が理解できたし、3月27日の記者会見でもマスコミの記者たちは納得していたという。事実、それ以降この問題は大手メディアではほとんど扱われなくなっている。













































































































































