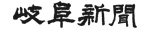三重県桑名市の長良川河口堰(ぜき)が来年7月で運用開始から30年を迎えるのを前に、東京大学大学院農学生命科学研究科の蔵治光一郎教授(58)が編著を務めた新刊「長良川のアユと河口堰−川と人の関係を結びなおす」が出版された。鵜匠や漁師、研究者ら18人が、それぞれの立場から鮎や長良川と人とのつながりをつづり、人口減社会を踏まえ環境とも調和したこれからの河口堰のあり方を論じている。
「まさか長良川にこんなに長く関わることになるとは」。蔵治さんは、開門調査を公約に掲げて2011年に当選した大村秀章愛知県知事が翌年設けた「長良川河口堰最適運用検討委員会」の設立時からの委員。声がかかったのは、同県瀬戸市の演習林に勤務しながら矢作川流域の住民と一緒に「森の健康診断」に取り組んでいた頃だった。
今回の書籍は、国と対話のテーブルに着けないまま議論を重ねた検討委の10年間をまとめた22年の報告書がベースで、検討委員以外にも執筆を依頼して論考の幅を広げている。
冒頭で「自分たちの川は、自分の手のひらと一緒」(小瀬鵜飼の岩佐昌秋鵜匠)など川をなりわいの場にする人たちの声を紹介し、「ばばちい(汚い)川になってまった」と話す羽島市のサツキマス漁師の故大橋亮一さんの講演録も掲載する。
次いで、河口堰による鮎の仔魚(しぎょ)の降海への影響、海と川を行き来する鮎以外の「通し回遊魚」の激減、温暖化で1カ月遅くなった鮎の降海などの今の姿を研究者が報告。河口堰の開発水量のうち実際に使っている水が16%にとどまる利水の現状を踏まえ、「過剰な水資源開発、県民の過剰な負担」(小島敏郎元青山学院大教授)とも指摘する。
その上で、生態系再生や水質改善のため、塩水遡上(そじょう)を考慮しながら開門に取り組むオランダと韓国の河口堰の事例を紹介する。
流域での一体的な水管理や治水対策を提言する蔵治さんは「対立から対話へ」の移行で、新しい未来図が描かれることに期待する。「人口が減り、生物多様性が失われてきた中で、過剰な利便性、渇水への過剰なリスク対応を求めるのではなく、『足るを知る』ことが必要」
書籍化を働き掛けた出版社「農文協」(埼玉県戸田市)の編集者、馬場裕一さん(46)=岐阜市出身=は「過去の対立を乗り越えられるような本にしたいと思った。しっかりとした議論の土台になるのではないか」と出版の意義を説いた。
表紙は岐阜県出身の絵本作家、村上康成さんが描き、帯にはロックバンド「サカナクション」の山口一郎さんと父で木彫家の山口保さんが一文を寄せる。A5変型判、232ページ、2420円。