契約している電気料金のメニュー次第ですが、電気料金は4月から少なくとも7月までは毎月上がりそうです。燃料費が下がれば、値上がりしないかもしれませんが、その可能性はあまりありません。
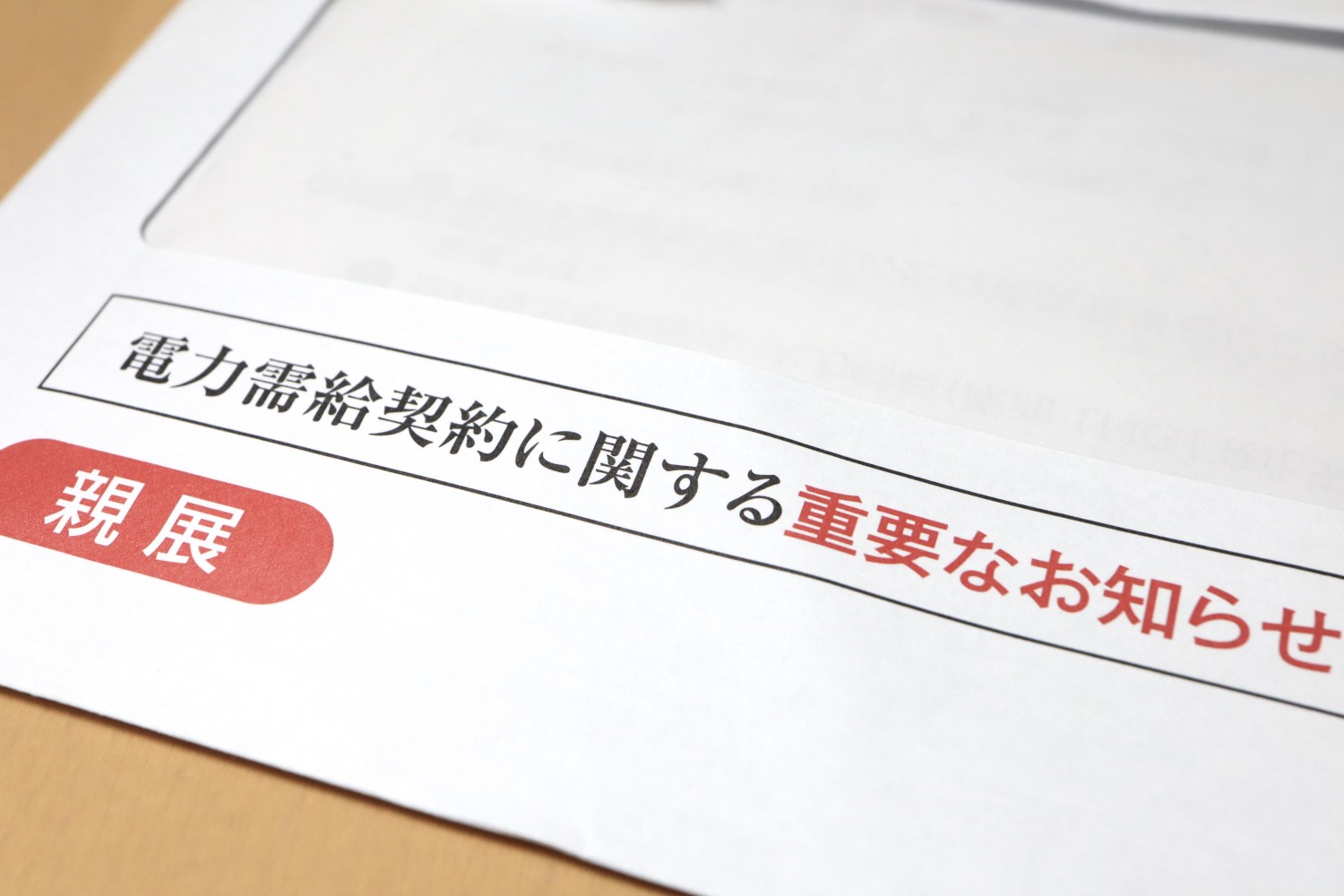 再エネ賦課金の負担増に補助金終了。さらなる電気料金の値上げが国民を待ち受けている( Yusuke Ide/gettyimages)
再エネ賦課金の負担増に補助金終了。さらなる電気料金の値上げが国民を待ち受けている( Yusuke Ide/gettyimages)ロシアがエネルギー危機を引き起こし、天然ガス価格と石炭価格は2022年秋に大きく上昇し、日本でも電気料金を引き上げました。
その後、燃料価格が下落に転じ、燃料費の調整制度を持つ電気料金は下がりましたが、年度が替わり一転、引き上げる要素が相次いで登場しています。
一つは、容量市場と呼ばれる新たに導入された制度に基づく容量拠出金と呼ばれる電気の小売り会社の負担です。4月から適用されています。
この負担を求めるか求めないかは、小売り会社により異なりますので、読者の方が電気を購入している会社によっては、値上がりはなかったかもしれません。
二番目は、再生可能エネルギー(再エネ)発電促進賦課金の上昇です。12年の7月から固定価格買取制度(FIT)に基づき、再エネ設備導入のため電気料金で賦課金が負担されています。年度ごとに見直されます。24年度は値上がりし、5月の料金から適用されています。
三番目は、激変緩和措置の終了です。23年1月(2月支払い料金)から家庭用電気料金では最大1キロワット時(kWh)7円(高圧の電気料金では3.5円)が支援されていましたが、徐々に減額されて5月の1.8円を最後に終了します。6月支払いの料金までの支援になり、段階的な減額により、6月、7月と料金は上昇します。
電気料金が決まる仕組み
16年に電力市場は完全に自由化され、消費者はそれまでの北海道から沖縄までの地域ごとの大手電力会社に加え、新たに小売りを始めた「新電力」と呼ばれる会社からの電気の購入も可能になりました。
20年には、電気を発電所から消費者に送る送配電を担う会社も大手電力から法的に分離され、大手電力の傘下に新たに東京電力パワーグリッド、関西電力送配電、東北電力ネットワークなどの会社が設立されました。
電気料金の内訳は、発電に係る費用、送配電の費用(託送料金と呼ばれます)、小売り・販売に係る費用で構成されています。
発電を行う事業者は、小売りの会社と相対取引と呼ばれる契約を結び電気を販売するか、あるいは卸電力市場で売却します。
発電部門のない小売りの会社は、発電事業者から相対取引に基づき電気を購入するか、卸電力市場で調達します。
送電線を複数敷設することは無駄ですので、送配電の会社は独占が認められますが、規制下にあり政府が査定した料金に基づき託送料金を受け取ります。
消費者は電気料金を支払う時に、発電、送配電、小売りの費用を別々に支払うわけではありません。小売り会社が、自社が発電事業者から購入した電気の費用、託送の費用を合わせて電気料金として請求します。









































































































































