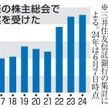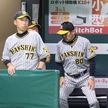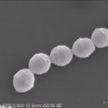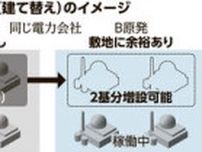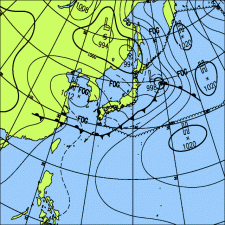<前編のあらすじ>
香世(43歳)は、ゴールデンウィークに夫と息子の勇太(11歳)を連れて義実家に帰省していた。毎年、義母と会わないといけないこの時期が嫌で仕方がなかった。義母は、太っている香世に対して「見てるだけで暑苦しいね」、「でかいのは身体だけかい?」など、執拗に容姿イジリをしてくるのだ。夕食の席ではなんと、すき焼きの肉を香世にだけ取り分けなかった。その時、勇太が突然自分の肉を「お母さんにあげる」と香世の皿に入れてきたが……。
香世さんは痩せないといけないから
「勇太が食べなさい。お母さんは気にしなくていいから」
隆子の機嫌をとろうと、香世は勇太に言った。しかし勇太はそんな香世の言葉を無視して、別の肉も小皿に放り込んだ。
見かねた隆子が話に割り込んできて、
「1度取り分けたものを、そうやって人さまのところに移すんじゃないよ」
「何で?」
「勇太に食べてほしくて、買ってきたお肉なんだよ。それね、けっこう良い値段する高級なお肉なんだよ」
それはまるで香世に高い肉はもったないないと言っているようにも聞こえ、忍ばせられた悪意はまた香世を傷つける。
「俺、たくさん食べたから。別にもういいよ。残ってる分はお母さんにあげてもいいでしょ? さっきから、お母さんは肉を1つも食べてないし」
「なんだい、そうだったの? それなら言ってくれればいいのにね」
隆子はわざとらしく驚いて、香世の小皿を取り上げると、鍋のなかで小さくちぎれて取り残されていた肉を入れた。
「香世さんは痩せないといけないから小さめでいいね」
「なんで?」
「だってって、見てごらんよ。お母さん、暑そうだろ?」
隆子の言葉に香世は唇をかんだ。
「母さん、なんてことを言うんだよ」
さすがに我慢できなかったのか充人が割って入ってくる。しかしそんなものに意味はない。
「母親がだらしない見た目で恥をかくのは、子供なんだよ。授業参観もPTAも、パツパツのジーパンで来られたんじゃ、悪い意味で注目の的じゃないか。ねえ、勇太」
「別に、誰もお母さんのことなんて見てないよ。授業参観は、お母さんたちが俺たちを見に来るんだから」
勇太の語気が強まっているのが分かった。
円満に今回の帰省を終えるなら、きっと香世は勇太を止めるべきだと思った。けれど止めたくないと思った。
「お母さんの見た目のこと言うのなんて、おばあちゃんくらい」
「おばあちゃんはね、心配してるんだよ。太ってると病気のリスクだってあるんだから」
「でも病気なのはおばあちゃんだよ」
勇太が返す刀で発した言葉に香世は顔を上げた。隆子も驚いて目を見開いていた。
「え……?」
「だっておばあちゃん、お母さんのこと、いつもばかにしていじめてるじゃん。いじめって、アメリカとかだといじめるほうが病気なんだってYoutubeで言ってたよ」
勇太にはっきりと言われて、隆子は言葉が出ないようだった。
ごちそうさま。勇太はそれだけ言ってソファへ移動し、かばんから取り出したゲームを始める。
静まり返った居間では、勇太のゲームの効果音だけがやけに陽気に響いている。
香世は勇太が小皿に入れてくれた肉を頰張った。
ほろほろに柔らかいお肉が甘いだしとともに口のなかで溶ける。今まで食べたどのすき焼きよりもおいしいと香世は思ったのは、単に高級な肉だからではなかった。
勇太の価値観
その日、隆子はもうほとんど口を開くことはなく、置物のように座っているか、機械のように食器を洗っているかのどちらかだった。
長居する理由もなく、食事と片づけを終えた香世たちは早々に義実家から帰ることにした。
香世は勇太と並んで後部座席に乗り込む。勇太はさっそくゲームを取り出す。
「車のなかでやると酔わない?」
「別に」
切り出すための言葉を探す。もちろん言いたいのは、そんなことではなかった。
「勇太、さっきはありがとね。お肉、とってもおいしかったよ」
「そう。よかったね」
「でも、おばあちゃんにあんなことを言うなんて思わなかったからびっくりしちゃった」
「……別にいいだろ、何でも」
やっぱりゲームの画面を見たままの、素っ気ない返事だが、かすかにゆがめられた横顔からは照れているのが伝わってくる。
「何でもよくないよ。かっこよかったよ。お母さん、すごく助かったし、うれしかった」
これ以上やると嫌がられそうだなと思ったが、勇太は続けて口を開いた。
「……クラスにさ、山本ってやつがいるんだ」
「ふーん、山本さん」
「そいつね、ランドセルとかリコーダーとか全部、お下がりを使ってるんだって。だから持ってるもの、どれもちょっとボロいんだよ」
香世は山本という児童の事情を察した。いや、克明に想像できた。香世自身、ひとり親の家庭で育っており、決して裕福とは言えない環境で育ったからだ。
「洋服も、ちょっと汚くて、そのことをイジられていたんだ」
子供たちの残酷さは、香世も身をもって知っている。いや、その残酷さには子供も大人も関係ないのかもしれない。人は差異に厳しく、一度自分よりも下だと思った相手にはどこまでも冷たく、酷薄になれる。
「でもね、俺、山本と席が近くなって、最近よく話すようになったんだ。すげえ優しくて面白いんだよ。ゲームの話とかやったことないから全然できないんだけど、キャラクターの絵とかめっちゃうまいんだ」
勇太の口から学校の話を聞くのは久しぶりだった。
「仲良しなんだね」
「別に、そんなんじゃないよ。でもみんなに山本の絵見せたらさ、すげえってなって、見た目のことをからかうのとかなくなったんだ。だから、もう別に俺と仲いいわけじゃない」
「お母さんみたいに、その子のことも助けてあげたんだ」
「見た目でばかにすんのとかダサいって思うだけ。そういうんじゃないから」
素直じゃないなぁ、とは思ったが言わないでおいた。というより言えなかった。
勇太の言葉を聞いた香世は思わず泣きそうになってしまって、顔を窓の外に向けたからだ。
勇太はとても優しい子に育ってくれている。
涙をなんとか奥に引っ込めて、香世は勇太を抱きしめる。勇太は邪魔すんなよと身じろぎをする。
「ありがとう。そんな風に思ってくれて、お母さん、うれしい」
「いや、別に……。普通のことだから。離して―—あ、死んだ。お母さんのせいで死んだ!」
「ごめん、ごめん」
照れている勇太がなおいとおしい。
「なあ、明日、3人でどっか遊びにいかないか?」
見ると、充人がバックミラーでこちらにほほ笑みかけていた。
「そうだね。勇太は行きたいところある?」
「じゃあ俺、新しいゲーム買ってほしい!」
「それはダメ」
「ちぇーっ」
勇太は唇をとがらせながらも上機嫌だ。
これからもずっとこの笑顔を見続けていきたい。
心からそう思った。
※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。