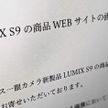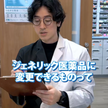◆これまでのあらすじ
夫との離婚に向け、弁護士に依頼をした楓。しかしあるとき帰宅すると、自宅の様子がいつもと違うことに気づいた。
なにが違うのか分からないけど、きっと夫が帰ってきたに違いない。
離婚を切り出してからの夫の変貌ぶりを思い出した楓は、夫が留守中に家にやってきて“何か”をしていたことに身震いするのだった。
▶前回:「離婚したら、娘を私立に入れるのはムリ?」34歳主婦が、経営者夫との離婚を決めて知った事実
Vol.6 調停が始まった
地下鉄の出口を出た楓は、降り注ぐ初夏らしい日差しに目を細めた。
バッグから日傘を出し、柳がそよそよと揺れる歩道を歩き始める。
「あっつ…」
5月下旬、午前11時の丸の内。
弁護士・真壁に呼び出され楓が向かうのは、マリキータ法律事務所だ。
呼び出しの理由はほかでもない。
今後の離婚までの筋道を立て直すためだ。
昨日真壁からかかってきたのは、「協議離婚は無理そうです」という、失意の電話だった。
調停や裁判をせずに、財産分与や養育費の金額を取り決めて離婚できれば、それほど楽なことはない。
そのため楓は、最短の近道ともいえる協議離婚で決着がつくことを心の底から祈っていた。
だが、真壁から光朗に連絡をとってもらったところ…やはり現実はそう甘くはないようだ。
― やっぱり、一筋縄ではいきそうもないのね…。
落胆とも緊張ともつかない気持ちを抱えたままマリキータに着くと、いつものように満面の笑みを浮かべた真壁が楓を出迎える。
「楓さん!お待ちしてました!まだ夏本番には早いのに、暑かったでしょう?冷たいお茶をご用意しますね」
真壁は秘書にお茶を持ってくるよう指示をすると、会議室の窓際の席に座るよう楓を促した。
「結論から言うと、私がご主人に直接連絡させていただいたら、『弁護士を通してください』とおっしゃられました…」
そして、電話を切って数分後。光朗の依頼した弁護士より連絡をもらい、「話し合いは調停で」と言われたそうだ。
「不思議よね。離婚したいと離婚届を送りつけて来たのはご主人の方なのに、わざわざ時間とお金がかかる調停で離婚の条件を決めたいなんて」
確かに、今回真壁が光朗に直接連絡を取ったことで、楓の離婚の意思は伝わったはず。
「私たちが動くよりも前から、ご主人は用意周到に弁護士を雇って離婚への筋道を立てていたんじゃないかしら?ちなみに、ご主人の会社の顧問弁護士について聞いたことはありますか?」
会社経営にはこれまでまったくタッチしてこなかった楓には、光朗の会社に顧問弁護士がいたかどうかなど、知るよしもない。
「まったくわからないです。すみません」
申し訳なさそうに答えながらも、内心、真壁の言ったことが引っかかる。
「用意周到に…って、先生はなぜそう思ったんでしょう?」
「それはね…。弁護士にも得意分野、不得意分野があるんです。私はご存じのとおり、離婚案件を得意としています。
でも、今回光朗さんが雇っている弁護士も、離婚の分野では有名な事務所の方なんですよ」
「そうなると、確かに会社の顧問弁護士ってことはないですよね」
楓は、真壁から聞いた光朗側の法律事務所の名前を、自身のスマホに打ち込んで検索してみた。
「なるほど。男性の離婚に詳しい、って書いてありますね」
ホームページには大きなフォントで、「男性の離婚について経験豊富な弁護士がお力になります」とある。
さらにはそれを補足するように、次のような事務所のポリシーが書き連ねてあった。
一般的に、離婚は女性に有利に働く場合が多いこと。
しかし、男女平等の時代である今、家事や育児も分担している夫婦が多いなかで、女性ばかりが有利というのはおかしいということ。
親権、財産分与、慰謝料の相場などを、男性の視点に立って解決に導くということ…。
スマホの画面を食い入るように見つめていると、そんな楓を現実に引き戻すように、真壁がはつらつとした声を上げた。
「そうなんです。だから、きっとわざわざ探して依頼したんですね。ってことは、向こうはやる気満々ってこと。
そうとわかったら気合入れて頑張らなくちゃ!」
真壁がガッツポーズをして見せる。
「はい!よろしくお願いします」
楓も、真壁に習って小さくガッツポーズをする。真壁という、法を武器に持つ味方がいるだけで、1人で悶々と悩んでいた時に比べれば格段に心強い。
しかし真壁は、PCに打ち込んだメモを見ながら、怪訝な顔で楓に尋ねた。
「でも、ご主人に関しては、わからないことがたくさんありますね。離婚理由も曖昧だし、いきなり人格が変わってしまったことも。何か心当たりはありますか?」
「いえ、コレといった心当たりがないんです。ただ…私の思い違いかもしれないんですが…」
そう答えながら楓は、先日帰宅した時の違和感を思い出した。あの違和感は、楓の中ですでに確信に変わっている。
「主人に家で遭遇したのは一度だけなんですが、そのあとにもう一度、主人は家に帰ってきたような気がします。
先日、幼稚園から家に帰ってきたら、いつもは開けっぱなしにしているリビングのドアがあの日は閉まっていて…。絶対に開けっぱなしで家を出たはずなのに」
そう言って真壁の方を見ると、真壁はPCの画面を見つめながらぶつぶつと小さく呟いている。
「妻の留守、夫が帰宅…その理由…。妻の留守、夫の帰宅…」
「あの…先生?」
眉間に皺を寄せながら呟く真壁の様子を前に、おかしさを堪えながら楓は声をかける。真壁はハッとして顔を上げた。
「あら、ごめんなさいね。ご主人、何か忘れ物を取りに来たんじゃないですか」
それは、楓も一度は考えた。そして、何を取りに来たのかを知るため、居室の物の配置やクローゼットの中を確認したりした。
「それが先生、何も持ち帰った形跡がないんです。でも、何かを探しに帰ってきたのだと私も思います。私の留守を狙って来るほど、どうしても必要な何かを」
「だとすると、楓さんに見つかると彼にとって不利に働く何かかもしれませんね」
夫にとっての不利とは何か?楓は考えてみるが、すぐに思い浮かぶものはない。
「世間一般的には、不倫の証拠になるものとかですが…。それは人それぞれだから、一概にこうとは言えません。
とりあえず、ここで立ち止まっていても進まないので、こちらから調停を申し立てましょう」
「はい…なんか、どきどきしますね」
不安そうな楓に真壁は「大丈夫、大丈夫」と胸を張る。そして、光朗から申し立てても、楓から申し立てても、調停の結果には影響はない、と付け加えた。
真壁がこれまで扱った案件でも、双方が離婚に合意しているのに、女性から離婚調停を申し立てたケースは多いという。
「女性からの申し立てが多い理由は、やはり財産についての主導権を夫が握っている場合が多いからだと思います」
調停という場なら夫の持つ財産を明らかにできるし、特に子どもがいる家庭なら、離婚後の面会交流や養育費などもきっちり決めることができる。
「なるほどー。私みたいな人、ほかにもいるんですね。がんばります」
◆
7月。
梅雨明けにはまだ早く、ここ数日ジメジメした日が続いている。
今日は、第1回の調停だ。
家庭裁判所の最寄り駅・霞ケ関の改札を出て地上に上がると、どんよりとした空とビル群が視界いっぱいに広がり、楓の気持ちは重くなった。
朝から不安と緊張が入り交じり、落ち着かないまま霞ケ関までやってきた。
いつものように花奈を幼稚園に送ったまではよかったが、1人になると家に戻ってもそわそわと落ち着かない。だから、早めに行って周辺のカフェでランチでもしようと考えたのだった。
しかし、調停の2時間以上前に霞ケ関に到着したものの、あたりにはコーヒーショップのひとつも見当たらない。
「早く着きすぎちゃったけど、何にもないのね…」
地上にはコンビニやコーヒーショップの類が見当たらず、灰色のビルが立ち並ぶばかり。
楓は仕方なく、スマホで一息つける場所を探す。
近くのビルの地下に飲食店があることがわかり、再度地下に下りる入り口へと向かった。
飲食店が並ぶ地下街は、束の間の昼休みにランチを求めるサラリーマンたちで賑わっている。
日頃あまり目にすることのない光景を、楓は思わずきょろきょろと物珍しく眺めた。
その時だった。
「楓さん!!」
不意にどこからか名前を呼ぶ声が聞こえて、楓はあたりを見まわした。
すると『よかろう』と書かれたラーメン屋の中から、ひょっこりと知っている顔が現れる。よく見てみると、まさに今から会うはずの真壁だった。
「先生!何してらっしゃるんですか?」
驚く楓に、真壁が手招きをする。
「ここ、辛いラーメン美味しいのよ。一緒に食べましょうよ。腹が減っては戦はできぬって言うじゃない」
真壁に隣の席を勧められ、2人でカウンターに並び座る。そして、これまた真壁の言われるがままに坦々麺を注文した。
「先生、美味しいです。にしても辛いー」
「でしょ?週に何度か霞ケ関に来るんだけど、たまーに食べたくなるのよね。
ところで楓さん、見違えたわ。今日の服装、完璧ね!」
真壁は箸を置いたかと思うと、楓の服装を上から下までじろじろと眺めた上で、にっこりと太鼓判を押す。
「ありがとうございます。先生に言われたとおりに、用意しました」
この日の楓の服装は、なんの変哲もない白い開襟の半袖ブラウスに、ベージュのスラックス、靴は黒の3センチヒールだ。
バッグも同様に、特段飾りもこだわったディテールもないレザーのトートバッグ。髪は黒いゴムで後ろでひとつにまとめて来た。
実は先日、調停の日の服装と持ち物については、真壁に細かく忠告されていた。
「楓さん、調停の日の服装のことだけど…。今みたいな感じでは、ちょっと…」
もともと楓は、華美な服装は好まない。この日は、マックスマーラで買ったサマーワンピースに、プラダのヒールの靴、ホワイトのピコタンにミニウォレットとスマホを入れ携えていた。
「見た目は上品だけど、お金がかかっているっていうのがよくわかるのよ。ほら、時計だってカルティエでしょ?」
「ええ、まあ。でも、なぜこれじゃダメなんですか?」
調停は、調停員と裁判官を通じて、話し合いをする場所だ。
申立人である自分の服装にお金がかかっていたからといって、一体なにがいけないというのか?
楓はまったくわからなかった。
「うん、ダメだわ。これは、戦略でもあるのですが。まず、堅実な良い妻アピールをしてください」
つまり、真壁はこう言いたいのだ。
ある日突然、夫が家を出て行ってしまった。理由もわからずひたすら途方に暮れていたが、数ヶ月後に帰ってきた夫は、別人のように人が変わっていた。そしてそんな辛いことがあったにもかかわらず、これまでの間、不安のなか1人で必死に子育てをしてきた──。
そんな、健気で打ちひしがれた妻に見えるよう、印象を調整してほしい…と。
「堅実な良い妻に…見えませんか?」
「うーん、そうね。もっとお金をかけてないお洋服でお願いします。ファストファッションなどでそろえられては?メイクも薄めでね」
これから調停の回数が進めば、もしかしたら、楓に不利な事実をつきつけられる可能性だってある。
だから初回のうちから、「真面目ないい奥さん」のイメージを作っておくことは大事なのだと真壁は言った。
そんな助言を得た上で、今日の「調停ファッション」は仕上がった。コーディネートの総額は、全身1万円以下だ。
明るいブラウンでカラーリングしていた髪も、真っ黒に染め直した。
まるで就活中の女子大生のようでもあるが、真壁が「いい」というのならこれが正解なのだろう。
「なんか落ち着きませんが…頑張ります!」
楓はこのあと控えている調停に緊張しながらも、目の前に出されたばかりの坦々麺をすすって気合を入れた。
ランチを終えると、2人は地上に上がり家庭裁判所に向かう。真壁は勝手知ったる様子で入り口を入っていく。
「楓さんは、そちらで所持品のチェックを受けて」
家庭裁判所の入り口は、まるで空港の保安検査場ようだ。赤外線を利用した装置で持ち物のチェックを受けると、所定の階までエレベーターで上がる。
家庭裁判所の中は、楓が想像していた通り、実務的で簡素な場所だった。
「待合室で呼ばれるまで待ちましょう」
真壁の後について、長椅子が並ぶ小部屋に入る。すでに数人が部屋にいて、それぞれ別々の長椅子に腰掛け、何かを待っていた。
「あの…ここには夫もくるんですか?」
恐る恐る聞くと、真壁がクスッと笑い答えた。
「まさかー!さっき廊下の案内図にも書いてあったと思いますが、ここは申立人専用待合室。ご主人は、相手方の待合室を利用するんです。
でもきっと今日はいらっしゃいませんよ」
初回の調停は、相手方の都合を確認せずに裁判所から日時を指定されることが多い。そのため、事前に欠席の連絡があれば、申立人のみの聞き取りを行う。相手が来るのは、ようやく2回目になってから…というのは、よくあることなのだそうだ。
「よかった。光朗さんと会ったらどんな顔すればいいんだろうって、実はすごく緊張してました」
「緊張することなんかないですよ。調停員からの聞き取りも、鉢合わせないようになってるから」
調停では、申立人と相手は会わないような配慮がされているらしい。
まずは申告人の話を先に30分ほど聞いたあと、今度は相手側の話を同じように聞く。そのようにして代わりばんこの聞き取りを、計2回行う。
そんな真壁の説明を聞き、光朗に会わずに済むと知った楓は、ほっと胸を撫で下ろした。
すると、その時だった。
「18番の方はいらっしゃいますか?」
18番──それは、楓の離婚についての“事件番号”だ。どうやらここでは、名前ではなく番号で呼ばれる配慮がされているようだ。
家庭裁判所の職員らしき人物からいよいよ呼び出され、楓の体に緊張が走る。
「はい、おります」
真壁が代わって返事をし、「行きますよ」と楓を促した。立ち上がり、真っすぐに続く廊下を真壁に続いて歩いていく。
調停室の前で真壁が立ち止まり、楓は思わず真壁と目を合わせる。
「よし…」
お互いに目で合図すると、楓は深く深呼吸をして…調停室に足を踏み入れた。
▶前回:「離婚したら、娘を私立に入れるのはムリ?」34歳主婦が、経営者夫との離婚を決めて知った事実
▶1話目はこちら:結婚5年。ある日突然、夫が突然家を出たワケ
▶NEXT:5月23日 木曜更新予定
ある日、見知らぬ番号から電話が。電話の主の女性の正体は…
エルメスのバッグも、カルティエの時計も封印。34歳セレブ妻が、全身1万円以下の服を着る理由

関連記事
あわせて読む
-

JR東など首都圏鉄道8社、磁気乗車券を廃止へ 26年以降QR乗車券に
Impress Watch5/29(水)14:37
-

【注意】「そんな怖い虫だったとは!」ヤケドみたいな水ぶくれ「学校の校庭にめちゃくちゃいました」
まいどなニュース5/29(水)7:55
-

【怪我をした息子】を心配するも「うるせぇ!ほっとけ!」→ 私「じゃあそうします」家出を決断!そして?
ftn-fashion trend news-5/29(水)13:01
-
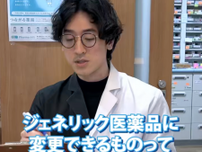
薬局で「ジェネリックに変更しますか?」どう答えるのが正解?→「知らなきゃ損する」「2024年10月からは注意」
まいどなニュース5/29(水)7:25
-

夫「パート主婦はお気楽でいいね」【収入差を馬鹿にした夫】だが → 妻が『無言で見せたもの』に真っ青!
ftn-fashion trend news-5/29(水)11:01
-

「ワシの楽しみを取り上げるのか!」免許返納を認めない79歳父親が自家用車を手放した“まさかのワケ”
日刊SPA!5/29(水)8:53
-

大渋滞エリア「津田沼」の「南北分断」解消近し!? 念願の「JRと京成またぐ道路」が完成間近 橋脚も見えてきた!
くるまのニュース5/29(水)7:40
-

ダイソーマニアが今探し回ってる…!見つけたらラッキーな入手困難アイテム4連発
michill byGMO5/29(水)11:00
-

「育ちの悪いバカ嫁だねぇ」→「嫁ちゃん助けてぇえ」【嫌な姑からSOS】の電話が突然かかり!?
ftn-fashion trend news-5/29(水)12:31
-
-

【男子学生、ありがとう(泣)】電車で【妊婦の私に暴言】を吐く女性。困り果てていると──?
ftn-fashion trend news-5/29(水)7:11
-

DVで妻子が家出しても「俺は間違ってない」と怒る夫。ある日“上司の言葉”で目が覚めた<漫画>
女子SPA!5/29(水)8:46
-

忙しい店員さんを手伝ったつもりが「それ、しない方がいいよ」友人に指摘された【ありがた迷惑】って?
ftn-fashion trend news-5/29(水)12:01
-

妊婦の嫁に、義父が「女なんだから家事ぐらい出来ないとね」【男女差別発言】→ 救世主が成敗!
ftn-fashion trend news-5/29(水)9:01
-

「あれ?首にしこりがある、、、」気づくも放置した結果 → 病院でゾッとする診断結果が──!
ftn-fashion trend news-5/29(水)8:01
-

や〜っとセリアでみつけた!髪には使わない?!使い方が変わってる話題のシュシュ
michill byGMO5/29(水)8:00
-

世界で一番〝ネコ〟ですわ... あまりにも見事なネコに、ネット民大はしゃぎ「神かと思った」
Jタウンネット5/29(水)11:00
-

会議中に5分で作った!「職人の再現度、さすが」 虚無感ある〝サカバンバスピス〟が和菓子になった経緯は
withnews5/29(水)7:10
-

<子ども嫌いの隣人ママ>うちの玄関前で【隣人の子どもからお願い】が!→ 衝撃の事実に「呆れた」
ftn-fashion trend news-5/29(水)7:01
-
トレンド アクセスランキング
-
1

JR東など首都圏鉄道8社、磁気乗車券を廃止へ 26年以降QR乗車券に
Impress Watch5/29(水)14:37
-
2

【注意】「そんな怖い虫だったとは!」ヤケドみたいな水ぶくれ「学校の校庭にめちゃくちゃいました」
まいどなニュース5/29(水)7:55
-
3

【怪我をした息子】を心配するも「うるせぇ!ほっとけ!」→ 私「じゃあそうします」家出を決断!そして?
ftn-fashion trend news-5/29(水)13:01
-
4
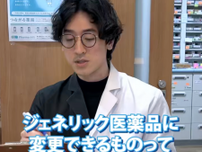
薬局で「ジェネリックに変更しますか?」どう答えるのが正解?→「知らなきゃ損する」「2024年10月からは注意」
まいどなニュース5/29(水)7:25
-
5

夫「パート主婦はお気楽でいいね」【収入差を馬鹿にした夫】だが → 妻が『無言で見せたもの』に真っ青!
ftn-fashion trend news-5/29(水)11:01
-
6

「ワシの楽しみを取り上げるのか!」免許返納を認めない79歳父親が自家用車を手放した“まさかのワケ”
日刊SPA!5/29(水)8:53
-
7

大渋滞エリア「津田沼」の「南北分断」解消近し!? 念願の「JRと京成またぐ道路」が完成間近 橋脚も見えてきた!
くるまのニュース5/29(水)7:40
-
8

ダイソーマニアが今探し回ってる…!見つけたらラッキーな入手困難アイテム4連発
michill byGMO5/29(水)11:00
-
9

「育ちの悪いバカ嫁だねぇ」→「嫁ちゃん助けてぇえ」【嫌な姑からSOS】の電話が突然かかり!?
ftn-fashion trend news-5/29(水)12:31
-
10

【男子学生、ありがとう(泣)】電車で【妊婦の私に暴言】を吐く女性。困り果てていると──?
ftn-fashion trend news-5/29(水)7:11
トレンド 新着ニュース
-

テクノロジーで家族の時間をつくり出す。ファミリーコンシェルジュ・Yohana代表 松岡陽子インタビュー
ライフハッカー[日本版]5/29(水)18:17
-

「ロシアが誇る防空兵器」米国製ミサイルから自身を守り切れず爆発
乗りものニュース5/29(水)18:12
-

発売から1か月 トヨタ新型「ランドクルーザー250」注目の “丸目”限定車はまだ買える!? 販売店に聞いてみた
VAGUE5/29(水)18:10
-

日産 新型「ノートSUV」世界初公開! 3年ぶり”顔面刷新”に反響大! タフ感増した新型「ノート“クロスオーバー”」発表
くるまのニュース5/29(水)18:10
-

かねこ統がアニメプロジェクトとコラボ 地球再生がテーマ「AGRIBEAR MARCO」
J-CASTトレンド5/29(水)18:02
-

<ご祝儀の額でランク付け!?>「3万しかくれなかった子は、縁切ろうかな」セコ新婦に、ブチ切れ!
ftn-fashion trend news-5/29(水)18:01
-

これぞまさしく「シンクロナイズド睡眠グ」 ソックリすぎる母子の寝姿が超尊い
Jタウンネット5/29(水)18:00
-

夏の定番・シースルーアイテムは【クロエ・セヴィニー】のヘルシーマインドがお手本!
オトナミューズウェブ5/29(水)18:00
-

夏の下着悩みを解決! 洒落見えする、ランジェリーの着こなし術
オトナミューズウェブ5/29(水)18:00
-

ドッグランのプールを爆走するシベリアンハスキー 怖……楽しそうな顔に爆笑
おたくま経済新聞5/29(水)18:00
総合 アクセスランキング
-
1

「『自衛隊辞めてしまえ!』などとひたすら罵倒されました…」“大ブレイク芸人”やす子の後輩が“深夜の指導トラブル”を告発!
文春オンライン5/29(水)16:00
-
2

トータス松本、週刊誌報道に「事実を全く認識しておりませんでした」 代表取締役を辞任&事務所謝罪
ORICON NEWS5/29(水)12:50
-
3

一時閉鎖の宮城野部屋から転籍の4力士が引退 日本相撲協会が計12人の引退を発表
デイリースポーツ5/29(水)10:24
-
4

金子恵美氏の〝蓮舫批判〟に米山隆一氏が痛烈皮肉 過去の話持ち出し「片腹痛い」
東スポWEB5/29(水)14:51
-
5

「暴露します」松本人志飲み会参加セクシー女優「衝撃作」発売「言えなくてずっと溜めてた」
日刊スポーツ5/29(水)12:58
-
6

佳子さまのお相手候補「旧華族の御曹司」が直撃取材に漏らした“本音” 「まあ仕方がないかな」
デイリー新潮5/29(水)11:41
-
7

北朝鮮、韓国に汚物入った風船 ビラ散布に対抗か
共同通信5/29(水)12:12
-
8

松本潤の独立で…強まる「嵐」“事実上の解散”の見方と気になるSTARTO社の今後
日刊ゲンダイDIGITAL5/29(水)9:26
-
9

中山秀征 人気芸人との“確執”告白 「楽屋真っ暗…風切る音しか聞こえない」 かみ合わず番組半年で終了
スポニチアネックス5/29(水)11:54
-
10

女子大学生が運転する車が追突…トラックから絵画を下ろす作業していた画家の男性が死亡 2台の間に挟まれる
東海テレビ5/29(水)11:35
東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-

世界で唯一!セサミストリートのオフィシャルストアでワークショップがスタート
Walkerplus5/29(水)17:00
-

早大で「体育各部新入部員パレード・宣誓式」 早稲田通りや早大周辺を行進
みんなの経済新聞ネットワーク5/29(水)17:00
-

仕事、結婚、子育てなどのライフイベントをネットでシミュレーションできる「東京ライフデザインシミュレーター」公開
TOKYO MX+(プラス)5/29(水)17:00
-

U-19日本代表、モーリスレベロに臨む26名を発表!ロス五輪世代のガチメンバー バルサの髙橋仁胡も招集
Qoly5/29(水)16:45
-

長谷部渋谷区長、協定結ぶLINEのイベントに登壇 協力体制「モチベに」
みんなの経済新聞ネットワーク5/29(水)15:45
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright © 2024 TOKYO CALENDAR INC. All rights reserved.