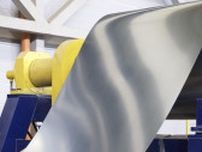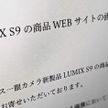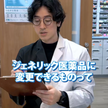もう20年あまりになるだろうか。民藝(みんげい)に対する関心がやまない。来たる2025年には言葉の誕生から100年を迎えることもあり、関連の展覧会が開催されるなど、ここへ来てさらに盛り上がってもいる。
「民藝」は、1925年に考案された造語である。それまで蔑(さげす)むように「下手(げて)もの」などと呼ばれていた日常使いの器物に、特有の美的価値を見出(みいだ)した柳宗悦らによって創出された。「民衆的工藝」を略したとされるが、器物に留(とど)まらず、社会の趨勢(すうせい)に抗(あらが)うカウンターカルチャーを体現するコンセプトでもあった。そうした意味もあってか、近年の関心はたんに民藝だけに向けられているわけではない。民藝を糸口にしながら、食や農、地方移住やエコロジーと、さらに周辺へと関心は向かう。あるいはその逆のパターンの方が多いかもしれない。右肩上がりの経済成長ありきの20世紀的な社会システムやライフスタイルの崩壊がジワジワと明らかになり、それらのオルタナティブ(別の道)が求められるなかで、「民藝」というワードを繰り返し耳にするようになった。何なの、民藝って?といったふうに、よくわからないけど、気になる存在としての民藝に関心が寄せられてきた二十数年だったともいえるだろう。
「逆接」が本領
それこそ民藝って何なのかを知りたい人には、『わかりやすい民藝』(高木崇雄著、D&DEPARTMENT PROJECT・2200円)をお薦めしたい。様々な文脈で語られ、わかりにくくもなった民藝をとり巻く現状を丁寧に解き分け、タイトル通り明快に論じる。とりわけ民藝にひそむ「逆接の論理」を明らかにした点は本書の卓見とすべきだろう。既存の基準に即して「〜だから」素晴らしいのではなく、まるで評価しようがない「にもかかわらず」、美しいと判断する。世間からは馬鹿にさえされる「にもかかわらず」、ひるむことなく肯定する。そんな姿勢にこそ民藝の本領は存する。
情愛と寛容さ
ブームとなり、民藝自体がブランド化・権威化し、民藝「だから」よいと受けとめられかねない状況をふまえると、「にもかかわらず」という視点の意義はますます高まっている。『アウト・オブ・民藝』(軸原ヨウスケ・中村裕太著、誠光社・1650円)は、まさにこの視点から民藝にまつわる言説そのものに切り込む。糸口となるのは、こけしなど、民藝として扱われてこなかった「にもかかわらず」、無視できない存在。それら民藝の「周縁」が有する豊かさを明らかにすることが、民藝のポテンシャルを窺(うかが)う上でも不可欠であることを教えてくれる良書だ。
「にもかかわらず」という民藝の視点は単に世評への反発を目的とするものではない。弱く小さく儚(はかな)く、ともすると世間から排除されかねない生命の営みに寄り添い、そのかけがえのなさを守りぬこうとする、深い情愛を伴ったまなざしである。早くから民藝と福祉との接点を見出し、知的障がい者支援施設を運営してきた著者ならではの知見にあふれた、『ありのままがあるところ』(福森伸著、晶文社・1760円)は、そんな民藝の可能性をおおいに示唆する。
考えてみると、二十数年にわたって民藝に関心が寄せられてきた背景には、人生すら勝ち負けで論じられる社会の生きづらさ、息苦しさがあるといってもよいだろう。こうした社会をただちに変革することはできなくても、ささやかながらも確実に風通しよくする何かが民藝にはある。
「不完全を厭(いと)う美しさよりも、不完全をも容(い)れる美しさの方が深い」(柳宗悦『美の法門』)
「にもかかわらず」の眼目はこの寛容さにある。民藝の関心が少しでもこうしたおおらかさの共有につながることを願ってやまない。=朝日新聞2024年5月11日掲載