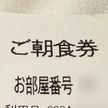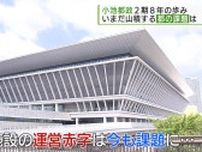ノンフィクションライター・長谷川晶一氏が、異業種の世界に飛び込み、新たな人生をスタートさせた元プロ野球選手の現在の姿を描く連載「異業種で生きる元プロ野球選手たち」。第11回は、現在、代官山でパティシエとしてお店を構える小林敦司さん(51)です。前編では広島東洋カープへ入団、ケガや不調に悩みながらもプロ初勝利を挙げた試合などを振り返りました。後編ではプロ引退後、飲食の道に進み、現在のお店をオープンするまでの苦労を伺います。(前後編の後編)
20代の女性たちに叱られながら修業する日々
それまで一度も故障したことのない右肩を痛めたことで、現役生活への未練は完全に吹っ切れた。31歳を迎え、第二の人生を考えたときに、小林敦司の頭に真っ先に浮かんだのが、東京・赤坂で料亭を営む父の姿だった。
「《甘え》と言ったら、完全な甘えなんですけど、当時の自分としては“他にできることもないし、やりたいこともないし、もう実家を継ぐしかないだろう”という思いでした。一応、カープからは“スコアラーをやらないか?”という誘いはあったんですけど、迷うことなく家業を継ぐことに決めました」
それまで、まったく料理の経験はなかった。小林にできることは、皿洗いや魚のうろこをはがしたり、内臓を取ったりする下処理だけだった。そんな生活が2002(平成14)年1月から始まった。
「店はオーナーで板前の父と、それを支える二番手の人がいて、僕はその下の役割でした。料理の世界は中学卒業後、すぐに始める人も多い中で、自分はすでに30歳を過ぎていたので、調理や料理ではなく、仕入れや経営面で力になりたい。そんな思いを持っていました。だから築地には毎日通ったし、魚屋さんなど関わりのある人たちに顔を覚えてもらうことを意識していました」
それから約2年後、母が新たにカフェをオープンする計画が持ち上がった。
「母は赤羽で小料理屋っぽいスナックをやっていたんです。でも、体力的に夜の仕事がきつくなってきたということで、“昼間のカフェをオープンしたい”と。母はとても料理が上手なんですけど、ケーキは作れなかった。それで、“じゃあ、僕がケーキを作れば一緒にお店ができるな”と考えて、ケーキ屋さんでアルバイトをすることにしました」
父親の庇護の下にいることに対する甘えや、マンネリズムを打破する目的もあった。いろいろと修業のための店舗を探し、小林が選んだのが人気洋菓子店「キルフェボン」だった。さまざまなフルーツをあしらったタルトが有名なこの名店で、小林は基礎の基礎から学ぶ機会を得た。
「周りは20歳ぐらいの女性ばかりでした。始発から終電間際まで、若い女の子たちに叱られながら、一から学びました。初めは土台の生地作りを1年半、次はオーブンで生地を焼く工程を2年、ムースを作る工程を半年、毎日、一生懸命でした」
地道な日々が続く。それでも、すでに30代半ばに差し掛かっていた小林にとって、愚直な日々を過ごす以外に他に道はなかったのだ。
「元プロ野球選手」という肩書きは、何の役にも立たない
キルフェボンでの修業時代について、小林が振り返る。
「おそらく多くの人が誤解していると思うんですけど、タルトに関して言えば、まず土台作りを覚えてしまえば、あとは上に載せるフルーツを変えるだけで何種類も作れるようになるって思うじゃないですか。でも、キルフェボンのタルトはフルーツによって土台となる層が一つ、一つ違うんです。生地も違えば、クリームも違う。だから覚えることはたくさんありました」
それでも、小林は前向きだった。「せっかくの機会だから、学べるものはすべて学ぼう」という貪欲さがあった。
「キルフェボンのいいところは、3年働いている人も、今日入ったばかりの人も同じ作業を任せられるんです。もちろん、ベテランならば1時間で20個作れるけど、新人は1時間で2個かもしれない。それでも同じ作業を経験できる。でも、僕にとっては、とにかく頑張れば身につくのは早いわけで、とにかくやってやろうという気持ちになりました」
プロ野球の世界では年齢が立場に大きく影響した。自分よりも年長か、それとも年少なのか? それで上下関係が決まっていた。けれども、一般社会ではその常識は通じなかった。
「当時、20歳そこそこの女性たちと仕事をしていたけど、若い子に普通に怒られていました(笑)。野球時代の感覚からすると、“オレの方が年上だぞ”って思うんですけど、もちろん、そんなことは通用しません。会社の人は、僕が元プロ野球選手だということは知っていました。でも、別にボールを投げるわけじゃないんだから、この場ではそれは何も役に立たない。とにかく、早いうちに学べたのはよかったと思います」
時給850円。経済的には決して恵まれていたわけではなかったけれど、この期間に小林は多くのことを学んだ。キルフェボンでの修業期間は5年近く続いた。仕事に慣れてくると、「パスタ作りも学びたい」という意欲が芽生え、イタリアンカフェでのアルバイトを掛け持ちすることに決めた。こうして、少しずつ、少しずつ、自分の店をスタートさせるための足がかりが築かれていった。
清原和博の突然の来店が起爆剤に
そして、2011年4月、東京・代官山に「2−3Cafe」をオープンした。「2−3」とはもちろん、野球のストライク、ボールカウントである。現在はアメリカに倣いボールカウントを先に呼ぶスタイルが定着し「3−2」と呼ばれているが、当時は「2−3」表記が一般的だった。ボールカウント・ツースリー。フルカウント、次の1球で勝負が決まる。
「まずは、“数字を入れた店名にしたい”と考えていました。ツースリーというのは、ピッチャーからすれば、“追い詰められている”というよりは、“バッターを追い込んでいる”という感覚になります。僕のようなコントロールが悪いピッチャーなら、“ツースリーなら、多少のボール球でも振ってもらえる”って、気持ちの余裕ができます。そんな思いもありつつ、《2−3Cafe》と名づけました。……まぁ、後づけの理由ですけど(笑)」
オープンから2年ほど経過した頃のことだった。ある日、身体の大きな男性が店にやってきた。清原和博である。扉を開ける前から、「あっ、清原さんだ」と小林は気づいた。
「本当に何の前触れもなく、清原さんがふらっとお店にやってきました。それですぐにあいさつしました。すると、回りのお客さんたちの様子がおかしい。それぞれが手元に小さなカメラを持っていて、その後すぐに大きなカメラが現れました。テレビのドッキリ企画だったんです(笑)」
小林の経歴を知った制作者が、「何の前触れもなく清原が店にやってきたら……」というドッキリ企画を小林に試みたのだという。
「この番組のおかげで、お客さんがかなり増えたんです。また、うちのオープン後、すぐ近くに蔦屋書店が誕生したことも大きかった。それまでの売り上げを1だとしたら、蔦屋のおかげで4ぐらいになり、清原さんのおかげで8、9、10くらいになりました。それまでは、自分が《元プロ野球選手》だということは積極的に口にしていなかったけど、テレビで取り上げられてからは、野球ファンの方もいらしてくれるようになって」
オープン以来、すでに13年のときが流れた。コロナ禍による苦しい時期を乗り越え、今は「世界一のチーズケーキ」と銘打っているベイクドチーズケーキを主力商品としてガトーショコラやシフォンケーキをすべて一人で作っている。すでに50代を迎え、新たな思いも芽生えつつある。
「仕入れから仕込みから接客まで、何から何まで一人でやってきました。今まで元日以外はまったく休みなく働いてきました。でも、“これからはチーズケーキとドリンクだけにしたい”という思いもあります。いつも週末は忙しいんですけど、週明けの月曜日にはかなり疲れが残るようになって(苦笑)。だから、今後は少しは休みが取れるようにしたいんですけどね」
そう言った後、小林は自身の発言をすぐに撤回した。
「でも、休みがないことには何も抵抗がないんです。カープの二軍もまったく休みがなく猛練習の日々でしたから(笑)。たまに、“ホントにオレはプロ野球選手だったのかな?”って思うことがあるんですけど、野球で学んだ《忍耐》は、今でも自分の中に息づいているのかもしれないですね」
プロ野球選手として11年。パティシエとして13年。すでに現在の暮らしの方が長くなった。第二の人生を堅実に歩んでいる小林が丹精込めて作る「世界一のチーズケーキ」は、本当に美味しい――。
長谷川 晶一
1970年5月13日生まれ。早稲田大学商学部卒。出版社勤務を経て2003年にノンフィクションライターに。05年よりプロ野球12球団すべてのファンクラブに入会し続ける、世界でただひとりの「12球団ファンクラブ評論家(R)」。著書に『いつも、気づけば神宮に東京ヤクルトスワローズ「9つの系譜」』(集英社)、『詰むや、詰まざるや 森・西武 vs 野村・ヤクルトの2年間』(双葉文庫)、『基本は、真っ直ぐ――石川雅規42歳の肖像』(ベースボール・マガジン社)、『大阪偕星学園キムチ部 素人高校生が漬物で全国制覇した成長の記録』(KADOKAWA)ほか多数。
デイリー新潮編集部