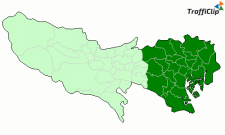8月1日に甲子園球場は開場100年を迎える。「甲子園100年物語」と題した連載で、“聖地”の歴史や名物の秘話などを紹介する。(井之川 昇平)
「土は1日で治せるが、芝は1週間かかる」。これは元グラウンドキーパー長、辻啓之介(79)の言葉だ。甲子園の土の仕上げの美しさは知られるところだが、実は、芝生の手入れの方が大変だという。
外野に芝生が張られたのは1928年12月。だが、太平洋戦争中、日本陸軍の木炭トラックが球場内に物資を搬入し、その際に木炭の灰が落ちて芝生がダメになった。1947年、米軍による接収が解除されると、球場を急ピッチで修復。鳥取県から芝生を取り寄せ、6年ぶりに春の選抜中等学校野球大会を開催。甲子園に野球が戻ってきた。
当時は野芝。蔓(つる)がよく出て、スパイクにからむ恐れがあった。そのため、55年頃、高麗芝に替えた。これは蔓はあまり出ない。だが、回復力が弱かった。オフに張り付けるが、センバツの大会が進むと、外野手の守備位置などにハゲができた。75年に洋芝に切り替えたが、センバツ中にハゲができることに改善はみられなかった。しかも、現在と違って芝は茶色。ハゲと茶色…。見るからに寒々しかった。
当時はそれが当たり前だったのだが、初代グラウンドキーパー長の米田長次は愛着ある甲子園に夢を持っていた。80年に亡くなるのを前に「甲子園が年中、青々としてたらええのになあ」という言葉を残した。後継者の藤本治一郎が恩師の言葉をきっかけに革命に乗り出す。ゴルフ場の芝生が冬も青いことをヒントに、関係者に教えを請うた。82年、芝生の二重方式、二毛作と言えるオーバーシーティングに乗り出した。従来の洋芝に加え、冬型の牧草をまくことにしたのだ。
1年の周期は以下のようになっている。9〜10月に冬型の牧草をまく。それがセンバツや春のプロ野球での芝生となる。その牧草の根を5月頃にカット。すると6月頃、夏用の洋芝の芽が吹き出す。夏の高校野球はその洋芝が活躍する。そして、洋芝が枯れる前に牧草をまく。こうしたサイクルで、甲子園の芝生は1年を通して青々としている。
その二毛作の導入時、藤本の命を受けて実務に当たった若手数人のうちの1人が冒頭の辻だった。「最初の数年は試行錯誤だった。気温を測定し、芝の発育状況をデータにとったりして、水をまく量などを研究した。手探りで、手入れの方法のノウハウを蓄積していった」。甲子園の芝を生まれ変わらせた辻は、その後も我が子のように大事に芝をはぐくんだ。こだわりたっぷりの“芝の育成方針”を次回。(敬称略)
※参考 藤本治一郎著「甲子園球児 一勝の“土”」(講談社)