低価格戦略と市民権獲得
機内食や手荷物などの有料化、座席数の増加などで、LCCは大手航空会社の半額以下に迫る圧倒的な低価格を実現し、市民権を得た。
1980年代以降、航空業界の自由化が進むにつれ、LCCは世界中でシェアを拡大してきた。現在では、
・サウスウエスト航空(米国)
・ライアンエアー、イージージェット(欧州)
・エアアジア、ライオンエア(東南アジア)
など、ある程度の航空インフラが整っている国ではすでに大きなシェアを獲得しているところもある。しかし、日本を含む東アジアでは、その普及率は世界標準を下回り続けている。
大都市が多く、国土も広く、航空インフラも一定水準あるにもかかわらず、なぜLCCが伸び悩んでいるのか。その理由を本稿で説明しよう。
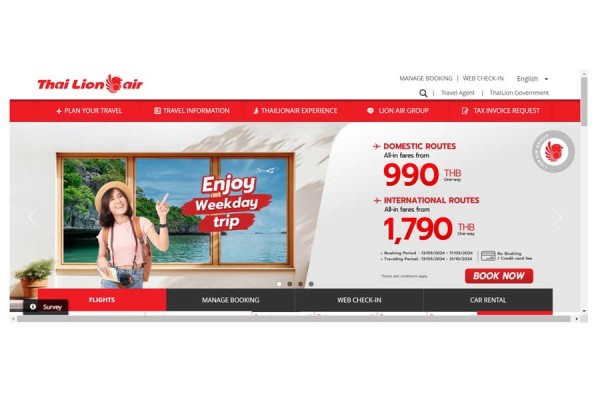
東アジア諸国の普及状況
はじめに、東アジア諸国におけるLCCの普及状況について説明する。前提として使用したデータはコロナ禍以前のもの(2018年集計)であるが、東アジア諸国ではシェアが劇的に動いていないため、現在も状況は変わらないと思われる。
一般に、2018年時点の世界平均におけるLCCの占有率は、国内線で33%、国際線で13%であり、短距離路線でLCCが市民権を得ていることがわかる。特に、エアアジア、ライオンエア、セブパシフィック航空、ベトジェットなどの大手LCCが盛んな東南アジアの主要国では、国内外ともに高いシェアを誇っている。
・インドネシア:国内線70%、国際線40%
・マレーシア:国内線57%、国際線51%
・タイ:国内線72%、国際線32%
・フィリピン:国内線64%、国際線31%
・ベトナム:国内線56%、国際線33%
・シンガポール:国際線31%
また欧州の場合、域内路線に占めるLCCの割合は33%(2018年)、米国内路線は30%(2020年)とほぼ平均的である。
一方、東アジアの主要国・地域は次のとおりである。
・中国:国内線10%、国際線14%
・日本:国内線17%、国際線26%
・韓国:国内線50%、国際線35%
・香港:国際線11%
・台湾:国際線18%
韓国と台湾を除き、LCCは世界平均を下回っており、特に中国と日本の国内線における独占率の低さが目立つ。香港の国際線も平均を下回っており、同じような立場で国際競争力を争うライバルであるシンガポールの半分以下であることは注目に値する。
中国、日本、台湾における国際線シェアは世界平均を上回っているが、東南アジア諸国や韓国からの乗り入れの影響が大きく、自国に本社を置く就航路線は非常に限られている。このことは、東アジアでは韓国を除き、
「LCCが自国産業として浸透・発展していない」
ことを示唆している。

東アジアの普及率が低い四つの理由
LCCが韓国以外の東アジア諸国、特に経済規模も大きいはずの中華圏(中国本土、香港、台湾)や日本で存在感を示すのが難しいのはなぜか。以下、その理由を四つ説明する。
●国内に発達した高速鉄道網がある
第一の理由は、国内の高速鉄道網が発達しており、鉄道は大都市間の主要な競争相手であるということである。特に、中国の高速鉄道網は2023年までに約43万7000kmに達し、世界最大規模となるが、日本、韓国、台湾も主要都市のほとんどを鉄道網で結んでいる。500km以内、所要時間2〜3時間以内の移動では、低価格と高頻度のため、LCCの有力な代替手段となっている。
実際、台湾は2001年の高速鉄道開業以来、澎湖(ほうこ)諸島などの離島路線を除き、国内線はほぼ壊滅状態となっている。日本では、最も収益性の高い首都圏〜関西圏の需要の7〜8割を新幹線が占めている。
インドネシア以外に高速鉄道網が存在しない東南アジア諸国や、アセラエクスプレス以外に高速鉄道網が存在しない米国とは、全く異なる問題である。しかし、日本や中国の場合、国土が広く、東京から福岡・札幌、北京から上海・広州など、1000km以上離れた大都市間にも需要がある。にもかかわらず、LCCのシェアが小さいのはなぜか。その理由は残りの3点にあると思われる。

羽田・成田の制約
以下、3点の理由である。
●主要空港の発着枠がとれない
ふたつめの理由は、主要都市の空港で発着枠を獲得するハードルが高いことだ。特に日本と中国でその傾向が強い。都心に近い羽田空港では、深夜早朝便を除き、国内線・国際線ともに発着枠に厳しい制限が課せられている。その結果、羽田を発着するLCCは、深夜時間帯にエアアジアがクアラルンプールへ、ピーチが台北へ就航するなど、ごく一部に限られている。
東京のもうひとつの空港である成田空港も、24時から翌朝6時までは着陸できず、遅れの許されないシビアな運航を要求される。このような遅れによる損失は莫大(ばくだい)であり、便数を増やすことは困難である。このような発着枠の制限は、東アジア全域に共通している。
例えば、中国の首都である北京や中国最大の経済都市である上海は、航空自由化の対象から外されることが多く、ほとんどの路線が自由に開設できない。実際、中国の研究者によると、上海を拠点とする中国最大のLCC、春秋航空は航空当局としばしばもめており、収益性の高い路線や時間帯のよい発着枠の確保に苦労しているという。
LCCはまた、高頻度運航をビジネスの重要な要素と考えており、空港での着陸から次の離陸までの間隔を狭めている。しかし、日本や中国の主要空港のように発着枠に余裕がない場合、米国のサウスウエスト航空などが実現している上記のような仕組みを運用することは難しく、非常に不便である。
●空域の制限が厳しい
LCCに限らず、フルサービス企業に共通することだが、東アジア諸国は旅客機が運航できる空域が狭い。首都圏に近く、カバー範囲が広いにもかかわらず、米軍の管理下にあり、自由な運航が難しい“横田空域”をご存じの読者も多いだろう。
実際、他の国でも同じような状況があり、特に中国では空域のほとんどを軍が支配しているため、民間旅客機は飛行空域が狭く、遅延が発生しやすい。また、中国の軍事訓練は台湾海峡など周辺地域で行われることが多く、中国だけでなく日本や台湾にも影響を及ぼす可能性がある。前述したように、LCCにとっても空港滞在時間を短くすることは利益確保のために重要であり、遅延リスクのある空域制限は大きな制約要因となっているのだ。
●独立系LCCが少なく、路線網が増えにくい
最後に、日本、中国、台湾、香港で独立系のLCCが少ないことが、LCCの普及に影響していると思われる。特に日本と台湾では、次のように各社とも各国・地域の大手航空会社の傘下に入っている。
・ANA傘下:ピーチ、エアジャパン
・JAL傘下:ジェットスター・ジャパン、春秋航空日本、ジップエアトーキョー
・チャイナエアライン傘下:タイガーエア台湾
香港もふたつあるLCCのうち、香港エクスプレス航空は現地最大手・キャセイパシフィック航空の子会社である。中国にはいくつかのLCCがあるが、企業として成功しているのは上場企業でもある春秋航空だけである。大手航空会社の傘下に入ると、限られた発着枠を利益率の高いフルサービス路線に使う傾向がある。そのため、ネットワークを拡大し、市場シェアを拡大することが難しくなる。
一方、東アジアで唯一LCCのシェアが高い韓国では、エア・プレミア、ティーウェイ航空、イースター航空、チェジュ航空など独立系の航空会社も多く、長距離路線も含めて多くの会社が競合している。先行してきた欧米では、路線網が拡大しており、最近では米国東海岸と西欧各地を結ぶ大西洋路線にもLCCが登場している。こうした競争力のある国々と、発着枠が限られているため収益性の高い路線に集中しがちなフルサービスエアラインの中華圏や日本との差は大きい。

規制次第の成長余地
東アジア、特に日本や中華圏でLCCが普及しない理由は、こうしたところにある。
特に発着枠の制限や空域の制限が大きく影響しており、地域の規模に対して航空会社の選択肢が少ないことが原因と思われる。
しかし、2022年就航予定のグレーターベイ香港航空や、2024年就航予定のトキエアなど、新しい会社も徐々に出てきている。
もともと国土が広く、経済基盤も巨大な国や地域が多いため、他の地域同様、規制次第ではまだまだ成長の余地がある。今後の発展に期待したい。
なお、コロナ後の状況については、筆者(前林広樹、乗り物ライター)の調査ではカバーしきれなかった部分もある。新たな進展があり次第、報告したい。






































































































































