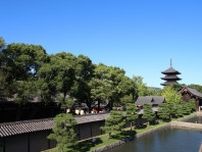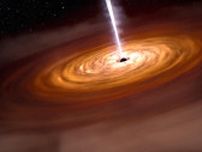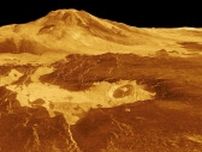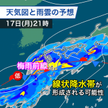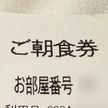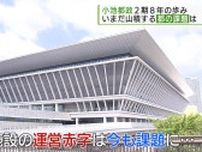全国の劇場で公開中の最新作『猿の惑星/キングダム』(2024年/監督:ウェス・ボール)を映画館で観てから、実に56年前のシリーズ原点、1968年の第1作『猿の惑星』(監督:フランクリン・J・シャフナー)を観直すと、VFX映像からほど遠い露骨なアナログぶりに最初は脱力してなごんでしまう。だが、ほのぼのしていられるのも束の間だ。ケネディ宇宙センターから旅立ったNASAならぬ“ANSA”の宇宙飛行士であるテイラー船長(チャールトン・ヘストン)率いるチームは、長い人工冬眠などを経て地球時間における3978年、とある惑星に到着する。しかし、この謎の新天地を支配していたのは、高度な知性を持った猿人たち(なぜか“英語”を喋る)。対して人間たちは言語も持たず原始的な状態のまま、猿人の奴隷や家畜として虐げられていた……といった恐ろしい物語が展開。第41回アカデミー賞名誉賞を受賞したジョン・チェンバースによる猿人の特殊メイクは簡素ながら今の目で観ても意外にクールで、容赦なき人間狩りのシーンはドキュメンタリーのような生々しさ。例えばイタリアの奇才、グァルティエロ・ヤコペッティ監督が世界各地の野蛮な風習を紹介した『世界残酷物語』(1962年)などに通じる禍々しさと言えるだろうか。やがて“映画本編を観たことのない人でも知っているラストシーン”として有名な、朽ち果てた自由の女神像の半身が海辺の砂浜から突き出している画に背筋が凍る――(撮影されたのはL.A.のズマビーチ・ポイントデュム)。やはりこれは人類への警句という永久的な射程のツメアトを刻んだ偉大なクラシックだ。

1960年代から擦られ続けている『猿の惑星』だが、もともとの第1作は『戦場にかける橋』(1957年/監督:デヴィッド・リーン)の原作でもよく知られるフランスの作家、ピエール・ブールが1963年に発表したSF小説をベースにしたもの。脚色を担当したのは、テレビシリーズ『トワイライト・ゾーン』(1959年〜1964年)で原案・メイン脚本とホスト役を務めたロッド・サーリングたち。監督にはテレビ業界出身で、このあと『パットン大戦車軍団』(1970年)で第43回アカデミー賞作品賞・監督賞など7冠に輝くフランクリン・J・シャフナーが当たった。
そこから独自に展開・派生し、テレビシリーズも含めて相当な数の続編やフランチャイズが製作されているが、劇場映画に限ると現時点では計10本。オリジナルシリーズは計5本。そこにティム・バートン監督による番外編的なリ・イマジネーション版『PLANETS OF THE APES 猿の惑星』(2001年)を挟んで、第1作の起源を解き明かす前史を描いたリブート版が3本。まだ人間が地球に君臨していた時代――現代のサンフランシスコを舞台にした『猿の惑星:創世記(ジェネシス)』(2011年/監督:ルパート・ワイアット)からはじまるこのトリロジーはいずれもレベルが高い。そのラストから300年後を描いたのが今回の新作『猿の惑星/キングダム』だ。時期としては1970年代までと、21世紀に入ってからに集中している。また粗製濫造というわけでもなく、シリーズの中に比較的佳作が多いのも特徴だ。例えば旧シリーズでも第4作『猿の惑星 征服』(1972年/監督:J・リー・トンプソン)は人間語を解する知的な猿のシーザー(過去の地球に亡命した考古学者コーネリアス博士と動物心理学者ジーラ博士の間に産まれた息子で、元々の名前はマイロ)を主人公とする物語の起源の革命を描いたもので、先述の『猿の惑星:創世記(ジェネシス)』のベースとなった必見作である。
この長きに渡る成果もやはり、最初に土台として設計された風刺劇としての強度がとんでもなく高かったためだろう。そんな『猿の惑星』シリーズの物語構造を把握するに辺り、ざっくりつかんでおきたいのは次のポイントである。
●人間と猿の立場(権力関係・社会階層)が逆転。
●支配層になった猿だが、やはり人間と同じ愚かな道を辿っていく。
こうして猿と人間の戦争や分断が複雑化し、シャレにならない泥沼へと突き進んでいく中で、「異人種・異文化の平和な共存は可能なのか?」という3つめの重要な主題がせり上がってくる。この問題意識の根幹自体は、どのシリーズ/フランチャイズを通しても基本的に変わらない。

ちなみに以前、『猿の惑星』の猿人のモデルは日本人ではないか?という説が有力となっていた。というのも、原作者のピエール・ブールは第二次世界大戦中、ナチス・ドイツとの抗戦を訴える自由フランス軍のレジスタンスの一員として従軍し、日本軍の捕虜になっていた時期があったとされていたからだ。しかしこの経歴は誤りだとする説もある。もし本当であれば、ブール自身が体験した「白人とアジア人の逆転」が『猿の惑星』の物語に結実したわけで、むしろ今の時代のアジアンヘイト問題にぶっ刺さるものとして興味深い。
ただ『猿の惑星』が発表された当時はアフリカ系アメリカ人の公民権運動の沸騰期であり、白人と黒人の立場が逆転した風刺劇、つまり今で言うブラック・ライヴス・マターの問題系として解釈されることが多かった。また当時はヴェトナム戦争の渦中にあり、米兵へのヴェトコンの逆襲といった構図も投影できる。ともあれ現実社会の軋轢を寓話として抽象化したおかげで、あらゆる支配・差別構造に置き換え可能な普遍性を獲得したわけだ。そしてラストシーンは米ソ冷戦の成れの果てをイメージしたと言われており(つまり核戦争後の世界――ポストアポカリプスの情景だ)、全体としては争いばかりを繰り返す人類の歴史そのものへの刃を突きつけたわけだ。
『猿の惑星』という企画自体はハリウッドの伝統的な大作路線を踏襲したものだが、このお先真っ暗な結末といい、やはりアメリカン・ニューシネマの反体制的な時代の刻印を強く感じる。当然にも直接のフランチャイズ企画だけでなく、様々な後続のカルチャーへの影響も絶大である。例えば日本でも、ファッションブランドのア・ベイシング・エイプ(A BATHING APE)は、デザイナーのNIGOやスケートシングこと中村晋一郎が、テレビ放送で観た『猿の惑星』シリーズから着想を受けて立ち上げられたもの。またミュージシャンの小山田圭吾がソロユニット名として採用しているコーネリアスは、もちろん『猿の惑星』の重要キャラクターであるチンパンジーのコーネリアス博士から取られている。

『猿の惑星』には科学vs宗教の歴史体系も組み込まれており、考古学者の見地から「猿の繁栄の前には人間の高度に発達した文明があった」と主張するのがコーネリアス博士。その彼と婚約者のジーラ博士を危険思想の持ち主として異端審問に掛けるのが、神が猿の世界を作ったとする信仰の力によりコミュニティを統治しているオランウータンのザイアス博士である。当初、テイラー船長たち人間をゴリゴリズタズタに虐め倒すザイアスは鬼畜な悪役のボスにしか見えないのだが、だんだん一筋縄ではないかない複雑な猿人像を顕わにしていく。「人間がそんなに優秀ならなぜ滅亡したのだ?」と鋭く問いかける彼は、人間の罪に対する批判者の急先鋒なのだ。
そしてザイアスは猿人の聖書から、第29章第6節に記されているという痛烈な一節を読み上げる。そのゾッとする台詞=テキストを以下に引用して本稿を締めよう。
「人間という獣は悪魔の手先だ。
霊長類の中で人間だけが娯楽や欲望のために命を奪う。
土地を奪うために兄弟を殺すのだ。
人間を繁栄させるな。
さもなければすべてが荒廃する。
人間を遠ざけ、砂漠の彼方へと追い込め。
人間は万物に死をもらたすのだ」
『猿の惑星』
製作年/1968年 原作/ピエール・ブール 監督/フランクリン・J・シャフナー 脚本/マイケル・ウィルソン、ロッド・サーリング 出演/チャールトン・ヘストン、キム・ハンター、モーリス・エバンス、ロディ・マクドウォール
●こちらの記事もオススメ!
ツメアト映画〜エポックメイキングとなった名作たち〜 Vol.25『許されざる者』が映画界に残したものとは?(1)
文=森直人 text:Naoto Mori
photo by AFLO